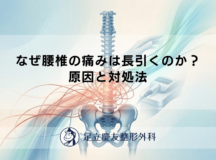股関節が右だけ痛むときの症状チェックと受診判断
「歩き始めに、なぜか右の股関節だけが痛む」「椅子から立ち上がるとき、右足の付け根に違和感がある」など、片側だけの股関節の痛みに悩んでいませんか。
多くの場合、痛みは体からの重要なサインです。その原因は、無意識の生活習慣や体の使い方にあるかもしれませんし、何らかの病気が隠れている可能性も考えられます。
この記事では、右の股関節だけに痛みが生じる背景から、考えられる原因、ご自身でできる症状のチェック方法、そして医療機関を受診するべきかどうかの判断目安まで、詳しく解説していきます。
目次
なぜ股関節の痛みは右だけに出やすいのか
体の左右どちらか一方だけに痛みが出るのには、多くの場合、理由が存在します。特に股関節は、立つ、歩く、座るといった日常のあらゆる動作の基盤となる重要な関節です。
そのため、わずかなバランスの崩れが、片側への負担の集中につながることがあります。
ここでは、右の股関節に痛みが集中しやすい背景と、日常生活に潜むその原因について掘り下げていきます。
日常生活の癖と体のゆがみ
私たちは毎日、無意識のうちにさまざまな動作を繰り返しています。
例えば、いつも同じ側の足で脚を組む、電車を待つときに片方の足に体重をかけて立つ、ショルダーバッグを常に同じ方の肩にかけるといった行動です。
これらの些細な癖の積み重ねは、骨盤の高さや傾きに左右差を生じさせ、体のゆがみを引き起こす一因となります。
骨盤がゆがむと、股関節にかかる体重の分散がうまくいかなくなり、特定の一方、この場合は右の股関節に過剰な負担がかかり続け、痛みを引き起こすことがあります。
体のゆがみにつながる生活習慣
| 項目 | チェック内容 | 考えられる影響 |
|---|---|---|
| 脚を組む | いつも右足を上にして組んでいないか | 骨盤のねじれや傾き |
| 立ち方 | 無意識に右足に重心を置いていないか | 右股関節への過剰な負荷 |
| カバンの持ち方 | 常に右手や右肩で荷物を持っていないか | 体の左右の筋力バランスの崩れ |
利き足と体重のかかり方
多くの人には利き手があるように、利き足も存在します。例えば、サッカーでボールを蹴る足、階段を上り始めるときの足など、力を入れたり、体を支えたりする際に無意識に使う方の足です。
日本人は右利きの人が多いため、それに伴い右足を軸足として使う傾向があります。
物を持ち上げるときに右足で踏ん張る、方向転換の際に右足を軸にするなど、日常の動作の中で右足、ひいては右の股関節にかかる負担は、知らず知らずのうちに大きくなっているのです。
この長年にわたる負荷の蓄積が、右股関節の痛みの原因となることがあります。
スポーツや仕事での特定の動作
特定のスポーツや職業は、体を一方向にひねったり、片側に負荷をかけたりする動作を反復することが多くあります。
例えば、ゴルフや野球の右打ちの選手は、スイングの際に右の股関節を軸として体を回転させます。この動作は、右の股関節に大きな回旋力と圧迫力を繰り返し加えることになります。
また、工場でのライン作業や特定の機械操作などで、常に体を右側に向けて作業するような場合も同様です。
このような特定の動作の繰り返しは、右の股関節周辺の筋肉や軟骨、その他の組織に微細な損傷を蓄積させ、やがて痛みを引き起こす原因となり得ます。
特定の動作と股関節への影響
| スポーツ・仕事の例 | 主な動作 | 股関節への影響 |
|---|---|---|
| ゴルフ(右打ち) | 右股関節を軸にした回転 | 回旋ストレス、軟骨への負荷 |
| 野球(右打ち・右投げ) | 踏み込みと体重移動 | 衝撃吸収とねじれの負荷 |
| 特定の立ち仕事 | 片側への体重負荷 | 持続的な圧迫ストレス |
右の股関節痛で考えられる主な病気
股関節の痛みが続く場合、それは単なる体の使いすぎや癖だけが原因ではなく、何らかの病気が背景にある可能性を考える必要があります。
特に股関節は消耗しやすい関節の一つであり、さまざまな病気が起こり得ます。ここでは、右の股関節に痛みを引き起こす代表的な病気について、その特徴と症状を解説します。
変形性股関節症
変形性股関節症は、股関節の痛みを引き起こす最も一般的な病気の一つです。
関節のクッションの役割を果たす軟骨が、加齢や体重の負荷などによってすり減り、骨が変形することで痛みや動きの制限が生じます。
初期の段階では、立ち上がりや歩き始めなど、動きの開始時に足の付け根に痛みを感じる程度ですが、進行するにつれて痛みが強くなり、安静にしていても痛んだり、夜間に痛みで目が覚めたりすることもあります。
また、関節の動きが悪くなるため、靴下が履きにくい、足の爪が切りにくい、あぐらがかけないといった日常生活での支障も現れます。特に女性に多く見られる傾向があります。
変形性股関節症の進行度と症状
| 進行度 | 主な症状 | 特徴 |
|---|---|---|
| 初期 | 動き始めの痛み、違和感 | 休むと痛みは和らぐ |
| 進行期 | 持続的な痛み、安静時痛 | 可動域の制限が顕著になる |
| 末期 | 強い痛み、歩行困難 | 関節の変形が著しい |
臼蓋形成不全
臼蓋形成不全は、生まれつき股関節の骨盤側にある受け皿(臼蓋)のかぶりが浅い状態を指します。
受け皿が小さいため、大腿骨頭(太ももの骨の先端)を十分に覆うことができず、関節が不安定になります。
このため、軟骨の狭い範囲に体重が集中してかかり、通常よりも早く軟骨がすり減りやすくなります。
若い頃は無症状で過ごせることも多いですが、体重の増加や加齢、スポーツなどをきっかけに痛みが出現することがあります。
この臼蓋形成不全が、将来的に変形性股関節症へと進行する主な原因の一つと考えられています。
大腿骨頭壊死症
大腿骨頭壊死症は、大腿骨の先端部分である大腿骨頭への血液の供給が何らかの原因で滞り、骨の組織が死んでしまう(壊死する)病気です。
骨が壊死するとその部分の強度が低下し、体重の負荷によって潰れてしまうことがあります。この骨の圧潰が生じると、急激に強い痛みが出現するのが特徴です。
原因が特定できない特発性のものがほとんどですが、アルコールの多量摂取や、他の病気の治療で使われるステロイド剤の大量使用などが、発症のリスクを高めることが知られています。
比較的若い世代にも発症することがある病気です。
股関節唇損傷
股関節唇とは、臼蓋の縁を取り囲むように付着している線維軟骨のことで、関節の安定性を高める役割を持っています。
この股関節唇が、スポーツや日常生活での繰り返される動作によって損傷したり、断裂したりすることがあります。
股関節を深く曲げたり、ひねったりする動作で、鋭い痛みや「ゴリッ」というような引っかかり感が生じるのが特徴です。
特に、サッカーやラグビー、バレエ、ヨガなど、股関節を大きく動かすスポーツを行う若年層や活動的な人に多く見られます。
病気以外の原因で起こる右股関節の痛み
股関節の痛みの原因は、必ずしも骨や軟骨の病気だけとは限りません。関節を支え、動かしている筋肉や、その周辺の組織に問題が生じることでも痛みは発生します。
これらの原因は、レントゲンなどの画像検査では異常が見つからないことも少なくありません。ここでは、病気以外の一般的な痛みの原因について解説します。
筋肉の疲労や炎症(股関節周囲炎)
股関節の周りには、お尻の中殿筋や、上半身と下半身をつなぐ腸腰筋など、多くの筋肉が存在し、歩行や姿勢の維持に重要な役割を果たしています。
普段あまり運動しない人が急に長距離を歩いたり、スポーツで特定の筋肉を使いすぎたりすると、これらの筋肉に疲労がたまり、炎症を起こして痛みを生じることがあります。
これを総称して股関節周囲炎と呼ぶこともあります。痛みは、原因となっている筋肉によって、股関節の前側、外側、後ろ側など、さまざまな場所に現れます。
ストレッチ不足や準備運動なしでの運動も、筋肉性の痛みを引き起こす誘因となります。
股関節周りの主な筋肉と役割
| 筋肉名 | 場所 | 主な役割 |
|---|---|---|
| 腸腰筋 | 股関節の前面 | ももを上げる、姿勢を保つ |
| 中殿筋 | 股関節の外側(お尻) | 歩行時の骨盤の安定 |
| 内転筋群 | 太ももの内側 | 脚を閉じる、骨盤の安定 |
滑液包炎
滑液包とは、筋肉や腱、骨などがこすれ合う部分にある、潤滑液を含んだ小さな袋状の組織です。関節の動きを滑らかにするクッションの役割を果たしています。
この滑液包が、繰り返しの摩擦や圧迫によって炎症を起こすのが滑液包炎です。
股関節の周辺では、太ももの外側の出っ張った骨(大転子)の上にある大転子滑液包で炎症が起こりやすく、この場所に圧痛や、歩行時の痛みが生じます。
横向きに寝ると痛い方の股関節が下になったときに痛みを感じることも特徴の一つです。
腰からの関連痛
痛みの原因が、痛む場所そのものにあるとは限りません。腰に問題がある場合でも、股関節周辺に痛みを感じることがあります。これは「関連痛」と呼ばれます。
例えば、腰椎椎間板ヘルニアや腰部脊柱管狭窄症などによって、腰のあたりで神経が圧迫されると、その神経が支配しているお尻や太もも、足の付け根といった領域に痛みやしびれが放散します。
患者さん自身は股関節が痛いと感じていても、詳しく調べると原因は腰にあった、というケースは少なくありません。
特に、しびれを伴うような痛みの場合には、この可能性を考慮する必要があります。
自分でできる症状チェックリスト
ご自身の痛みがどのような性質を持ち、どのような状況で起こるのかを客観的に把握することは、原因を探り、専門家に相談する際に非常に重要な情報となります。
漠然とした不安を解消するためにも、まずは以下の項目に沿って、ご自身の状態を整理してみましょう。
痛みの種類を確認する
痛みと一言でいっても、その感じ方はさまざまです。どのような種類の痛みかを意識することで、原因となっている組織を推測する手がかりになることがあります。
例えば、炎症が強い場合は「ズキズキ」と脈打つような痛み、神経が関わっている場合は「ジンジン」「ピリピリ」としびれるような痛み、筋肉性の場合は「重だるい」痛みなど、表現は多岐にわたります。
ご自身の痛みがどの表現に近いか、考えてみてください。
- ズキズキする
- ジンジン、ピリピリする
- 重だるい
- 電気が走るよう
痛むタイミングを把握する
痛みが「いつ」現れるのかも、重要なチェックポイントです。特定の動作のときにだけ痛むのか、それともじっとしていても痛むのかで、重症度や原因が異なります。
例えば、動き始めの痛みは変形性股関節症の初期によく見られます。長時間歩いた後に痛むのは、筋肉の疲労や関節への負荷が原因かもしれません。
夜間や安静時に痛みが強い場合は、炎症が強かったり、他の病気が隠れていたりする可能性も考えます。
痛むタイミングと考えられる原因の傾向
| 痛むタイミング | 考えられる状態の例 |
|---|---|
| 動き始め(立ち上がりなど) | 変形性股関節症(初期) |
| 長時間歩いた後 | 筋肉疲労、軟骨の摩耗 |
| 安静時・夜間 | 強い炎症、大腿骨頭壊死症など |
股関節の動きをチェックする
痛みに加えて、股関節の動きに制限が出ていないかを確認することも大切です。関節の動きが悪くなることを「可動域制限」と呼びます。
日常生活の中で、以前は問題なくできていたことが、やりにくくなっていないかチェックしてみましょう。
特に、左右の足で動きを比べてみると、異常に気づきやすくなります。
「靴下を履く」「足の爪を切る」「あぐらをかく」「椅子に座って脚を組む」といった動作が、右足だけやりにくい場合は、股関節に何らかの問題が起きているサインかもしれません。
痛み以外の症状の有無
痛みだけでなく、他にどのような症状があるかにも注意を向けましょう。
例えば、股関節の周りが腫れている、触ると熱を持っている(熱感)といった症状は、強い炎症が起きていることを示唆します。
また、特定の動きで「ゴリッ」「カクッ」といった引っかかり感がある場合は、股関節唇損傷などが疑われます。
腰からの関連痛の可能性を考える上では、お尻から足にかけてのしびれの有無が重要な情報となります。これらの付随する症状は、診断の大きな手がかりとなります。
こんな症状は要注意!受診を判断する目安
痛みが続くと「このまま様子を見ていていいのだろうか」「病院に行くべきだろうか」と悩むものです。自己判断で放置した結果、症状が悪化してしまうこともあります。
ここでは、どのような場合に医療機関を受診すべきか、具体的な判断の目安について解説します。
すぐに受診を検討すべき症状
以下のような症状が見られる場合は、骨折や脱臼、重度の炎症、あるいは急速に進行する病気の可能性も考えられるため、自己判断で様子を見るのではなく、できるだけ早く整形外科を受診することを推奨します。
我慢することが、かえって状態を悪化させることにつながりかねません。
- 転倒などの明らかな原因の後に、激しい痛みが生じた
- 痛くて体重をかけることができず、歩けない
- じっとしていても痛みが非常に強い
- 股関節の周辺が赤く腫れていて、熱を持っている
2週間以上痛みが続く場合
急激な痛みではなくても、日常生活の中で感じる痛みが2週間以上続いている場合は、一度専門医に相談することをお勧めします。
安静にしたり、湿布を貼ったりといったセルフケアを試みても改善が見られない、あるいは徐々に痛みが強くなっているようなケースでは、一時的な筋肉の疲れなどではなく、治療が必要な何らかの原因が隠れている可能性が高いと考えます。
日常生活に支障が出ている場合
痛みの強さそのものだけでなく、その痛みによって「生活の質(QOL)」が低下しているかどうかも、受診の重要な判断基準です。
「痛みで仕事に集中できない」「趣味の散歩やスポーツが楽しめない」「痛みなく眠れない」など、痛みがあなたの日常生活に影を落としているのであれば、それは我慢すべきではありません。
専門家による適切な診断と治療を受けることで、快適な日常を取り戻せる可能性があります。
何科を受診すればよいか
股関節の痛みで医療機関を受診する場合、基本的には「整形外科」が専門となります。整形外科は、骨、関節、筋肉、神経といった運動器の専門家です。
問診や身体診察、レントゲンなどの画像検査を通して、痛みの原因を総合的に診断します。
診断の結果、リウマチ性の病気が疑われる場合にはリウマチ科へ、あるいは他の内科的な病気が関連している場合には適切な診療科へと紹介されることもあります。
まずは、お近くの整形外科クリニックや病院に相談することから始めましょう。
受診する診療科の目安
| 主な症状 | 推奨される診療科 | 理由 |
|---|---|---|
| 足の付け根の痛み、動きの悪さ | 整形外科 | 骨、関節、筋肉の専門家のため |
| 複数の関節の腫れや痛み | 整形外科またはリウマチ科 | 関節リウマチなどの可能性を考慮 |
| 原因不明の発熱を伴う痛み | 整形外科または内科 | 感染症などの可能性を鑑別 |
痛みを和らげるためのセルフケア
医療機関で診断を受けるまでの間や、医師から指示された治療と並行して、ご自身で痛みを管理し、和らげるためにできることもあります。
ただし、これらのセルフケアは、あくまで補助的なものです。痛みが強くなる、あるいは新たな症状が出るような場合は、すぐに中止して専門家に相談してください。
安静とアイシング
痛みが急に出てきた直後や、運動後などに痛みが強くなった場合は、まず股関節を休ませることが重要です。
無理に動かしたり、マッサージをしたりすると、かえって炎症を悪化させることがあります。特に、痛む部分に熱っぽさ(熱感)を感じる場合は、炎症が起きているサインです。
このようなときは、氷のうや保冷剤をタオルで包み、1回15分から20分程度、痛む部分を冷やす(アイシング)と、炎症と痛みを抑えるのに有効です。
股関節に負担をかけない生活の工夫
日常生活の動作を見直すことで、右の股関節にかかる負担を軽減できます。床に座る、布団で寝起きするといった和式の生活は、股関節を深く曲げる動作が多く、負担が大きくなります。
できるだけ椅子やテーブル、ベッドを使用する洋式の生活スタイルに切り替えることを検討しましょう。また、痛みが強いときは、杖を使うことも有効です。
痛い方の右足と反対の左手で杖を持つと、歩行時の右股関節への負荷を大きく減らすことができます。さらに、体重の管理も重要です。
体重が1kg増えると、歩行時には股関節にその3倍の負荷がかかるといわれています。適正体重を維持することは、長期的な股関節の健康につながります。
股関節への負担を減らす生活の工夫
| 場面 | 工夫の例 | 期待できること |
|---|---|---|
| 室内生活 | 椅子・ベッドの使用 | 深くかがむ動作の減少 |
| 歩行時 | 杖の使用(痛い側と反対の手で) | 患側への荷重の軽減 |
| 全般 | 適正体重の維持 | 関節にかかる全体的な負荷の軽減 |
専門家の指導のもとで行う運動
痛みが少し落ち着いてきたら、股関節を支える周りの筋肉を鍛える運動や、硬くなった筋肉をほぐすストレッチが有効です。
ただし、自己流でやみくもに運動をすると、症状を悪化させる危険性があります。特に、痛みを感じるような運動は禁物です。
どのような運動が今のあなたの状態に適しているかは、医師や理学療法士などの専門家が的確に判断します。
医療機関で指導された運動療法を、指示された回数や強度を守って正しく続けることが、機能の回復と痛みの再発予防にとって非常に重要です。
よくある質問
右の股関節痛について、多くの方が疑問に思う点や不安に感じる点について、質問と回答の形式でまとめました。ご自身の状況と照らし合わせながら、参考にしてください。
Q. 湿布を貼っても大丈夫ですか?
A. 痛みを一時的に和らげる目的で湿布を使用することは問題ありません。特に、筋肉の使いすぎによる炎症などが原因の場合、消炎鎮痛成分が含まれた湿布は有効な場合があります。
しかし、湿布はあくまで対症療法であり、痛みの根本的な原因を治すものではありません。
湿布を使っても痛みが改善しない、あるいは痛みが続く場合は、原因を特定するために医療機関を受診してください。
Q. サプリメントは効果がありますか?
A. グルコサミンやコンドロイチン、ヒアルロン酸といった成分を含むサプリメントは、関節の健康をサポートするものとして広く知られています。
しかし、これらのサプリメントが変形性股関節症の進行を抑制したり、すり減った軟骨を再生させたりする効果については、現時点で科学的に明確な証拠は確立されていません。
健康食品の一つとして摂取することは個人の判断ですが、過度な期待はせず、まずは適切な診断に基づいた治療や、生活習慣の改善、運動療法に取り組むことが大切です。
Q. 妊娠中に右の股関節が痛むのはなぜですか?
A. 妊娠中は、出産に備えて「リラキシン」というホルモンが分泌されます。このホルモンは骨盤周りの靭帯を緩める働きがあるため、関節が不安定になりがちです。
また、お腹が大きくなるにつれて体重が増加し、体の重心が前に移動するため、姿勢を保とうとして腰を反らせるような姿勢になり、股関節への負担が増加します。
これらの要因が組み合わさることで、片側の股関節に痛みが出やすくなります。
多くの場合、出産後にホルモンバランスや体型が元に戻るにつれて痛みは改善しますが、痛みが強く日常生活に支障がある場合は、我慢せずに産婦人科医や整形外科医に相談しましょう。
Q. 痛いときは温めるべきですか、冷やすべきですか?
A. 温めるべきか冷やすべきかは、痛みの時期や状態によって異なります。一般的に、急な痛みで腫れや熱感を伴う「急性期」の場合は、炎症を抑えるために冷やす(アイシング)のが適切です。
一方、慢性的な鈍い痛みで、動かすと少し楽になるような「慢性期」の場合は、血行を良くして筋肉の緊張を和らげるために温める(温熱療法)のが効果的なことがあります。
ただし、どちらが適切か自己判断に迷う場合は、まず専門家に相談するのが最も安全です。
温める場合と冷やす場合の判断目安
| 状態 | 対処法 | 目的 |
|---|---|---|
| 急な痛み、腫れ、熱感がある | 冷やす(アイシング) | 炎症を抑える、痛みを鎮める |
| 慢性的な痛み、こわばり | 温める(入浴など) | 血行促進、筋肉の弛緩 |
| 判断に迷う場合 | 専門家に相談 | 適切な対処法の確認 |
以上
参考文献
LOUW, J. A. The differential diagnosis of neurogenic and referred leg pain. SA Orthopaedic Journal, 2014, 13.2: 52-56.
MENGIARDI, Bernard; PFIRRMANN, Christian WA; HODLER, Juerg. Hip pain in adults: MR imaging appearance of common causes. European Radiology, 2007, 17.7: 1746-1762.
LUNGU, Eugen; MICHAUD, Johan; BUREAU, Nathalie J. US assessment of sports-related hip injuries. Radiographics, 2018, 38.3: 867-889.
THEIN-NISSENBAUM, Jill; BOISSONNAULT, William G. Differential diagnosis of spondylolysis in a patient with chronic low back pain. Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy, 2005, 35.5: 319-326.
HUNTOON, Elizabeth; HUNTOON, Marc. Differential diagnosis of low back pain. In: Seminars in Pain Medicine. WB Saunders, 2004. p. 138-144.
FLASAR, Mark H.; CROSS, Raymond; GOLDBERG, Eric. Acute abdominal pain. Primary Care: Clinics in Office Practice, 2006, 33.3: 659-684.
LUKAC, Stefan, et al. Extragenital endometriosis in the differential diagnosis of non-gynecological diseases. Deutsches Ärzteblatt International, 2022, 119.20: 361.
PATEL, Reeya; MONEM, Mohammed; SHERIEF, Tamer. Unilateral infective sacroiliitis in a boy presenting with a limp. Case Reports, 2017, 2017: bcr-2017-219279.
RAMOS, John. Abdominal pain: the differential diagnosis, classic histories, and diagnosis. Physician Assistant Clinics, 2023, 8.1: 33-48.
Symptoms 症状から探す