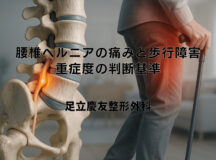膝の関節炎の原因と症状|早期発見のポイント
「最近、膝が痛む」「立ち上がる時に違和感がある」と感じていませんか。その不調、もしかすると膝の関節炎のサインかもしれません。
膝の関節炎は、初期段階では自覚症状が少ないこともありますが、放置すると徐々に進行し、日常生活に大きな影響を及ぼす可能性があります。
この記事では、膝の関節炎がなぜ起こるのか、その主な原因と種類、そして見逃してはならない初期症状について詳しく解説します。
早期発見がなぜ重要なのか、ご自身でできるチェックポイントもご紹介しますので、膝の健康を守るための第一歩として、正しい知識を身につけましょう。
目次
膝の関節炎とは?(基本的な理解)
膝の関節炎と聞くと、多くの方が「年配の方の病気」というイメージを持つかもしれません。しかし、実際には様々な原因で幅広い年齢層に起こり得ます。
まずは、膝の関節炎がどのような状態なのか、基本的なところから理解を深めていきましょう。
膝の関節の仕組み
膝関節は、太ももの骨(大腿骨)、すねの骨(脛骨)、そしてお皿(膝蓋骨)という3つの骨で構成されています。
これらの骨の表面は、弾力性のある「関節軟骨」という滑らかな組織で覆われています。この軟骨が、歩いたりジャンプしたりする際の衝撃を吸収するクッションの役割を果たしています。
また、関節全体は「関節包」という袋に包まれており、その内側にある「滑膜」から分泌される「関節液」が、軟骨に栄養を与えたり、関節の動きを滑らかにする潤滑油の働きをしたりしています。
この精巧な仕組みが、私たちのスムーズな膝の曲げ伸ばしを支えています。
関節炎が起こる状態
「関節炎」とは、文字通り「関節に炎症が起きている状態」を指します。
膝関節の場合、何らかの原因で関節軟骨がすり減ったり、傷ついたりすると、その破片が滑膜を刺激し、炎症が起こります。
炎症が起こると、滑膜が腫れて関節液が過剰に分泌され、いわゆる「膝に水がたまる」状態になり、痛みや腫れを引き起こします。
この炎症が長期間続くと、軟骨の破壊がさらに進み、最終的には骨同士が直接こすれ合うようになり、強い痛みや関節の変形につながります。
膝の関節炎の主な種類
膝の関節炎にはいくつかの種類がありますが、最も多いのが「変形性膝関節症」です。これは主に加齢や体重の増加、過去の怪我などによって軟骨がすり減ることで起こります。
次に多いのが「関節リウマチ」で、これは免疫システムの異常により、自分自身の関節を攻撃してしまう自己免疫疾患の一つです。
その他にも、血液中の尿酸値が高くなることで起こる「痛風」や、ピロリン酸カルシウムという結晶が関節に沈着する「偽痛風」、細菌感染による「化膿性関節炎」などがあります。
膝の関節炎の種類と特徴
| 種類 | 主な原因・要因 | 特徴 |
|---|---|---|
| 変形性膝関節症 | 加齢、体重増加、O脚、過去の怪我 | 軟骨がすり減る。初期は動き始めに痛む。 |
| 関節リウマチ | 自己免疫疾患 | 滑膜の炎症。朝のこわばり。複数の関節に発症。 |
| 痛風・偽痛風 | 結晶(尿酸など)の沈着 | 突然の激痛発作。赤く腫れて熱を持つ。 |
なぜ起こる?膝の関節炎の主な原因
膝の痛みを引き起こす関節炎は、決して一つの原因だけで発症するわけではありません。加齢によるものから、生活習慣、さらには体質的な要因まで、複数の要素が複雑に関係しています。
ここでは、膝の関節炎を引き起こす代表的な原因を見ていきましょう。
最も多い「変形性膝関節症」の原因
日本の膝関節炎の中で最も患者数が多い「変形性膝関節症」は、いくつかの要因が重なって発症することが知られています。
加齢による軟骨の変化
関節軟骨は、年齢とともにその主成分である水分やコラーゲンが減少し、弾力性が失われていきます。
このことにより、長年の使用による摩耗や、わずかな衝撃でも傷つきやすく、すり減りやすくなります。これが、高齢になるほど変形性膝関節症を発症しやすい大きな理由です。
体重(肥満)の影響
膝関節には、立っているだけでも体重がかかりますが、歩行時にはその約3倍、階段の上り下りでは約6〜7倍もの負荷がかかると言われています。
体重が増加すると、その分だけ膝への負担が常にかかり続け、軟骨のすり減りを早める強力な要因となります。体重管理は、膝の健康を守る上で非常に重要です。
過去の怪我や膝への負担
スポーツや事故などで膝の半月板や靭帯を損傷した経験がある人は、関節の安定性が損なわれ、将来的に変形性膝関節症になりやすいことがわかっています。
また、O脚やX脚といった脚のアライメント(骨の配列)の異常も、膝の内側または外側に偏った負担をかけ続けるため、軟骨のすり減りを助長する原因となります。
自己免疫が関わる「関節リウマチ」
関節リウマチは、本来自らを守るはずの免疫システムが異常をきたし、自分自身の関節を包む「滑膜」を異物とみなして攻撃してしまう病気です。
この攻撃により滑膜に慢性的な炎症が起こり、炎症が続くと軟骨や骨の破壊が進行します。
原因はまだ完全には解明されていませんが、遺伝的な要因や、喫煙、歯周病などが発症に関係していると考えられています。
膝だけでなく、手足の指の関節など、複数の関節に左右対称に症状が出やすいのが特徴です。
その他の原因(痛風・感染症など)
痛風は、プリン体という物質の代謝産物である「尿酸」が血液中で増えすぎ(高尿酸血症)、関節内で結晶化することで急性の関節炎を引き起こします。
足の親指の付け根が有名ですが、膝関節に激痛と腫れが起こることもあります。
また、怪我や他の部位からの感染により、細菌が関節内に入り込んで炎症を起こす「化膿性関節炎」は、急速に関節破壊が進行するため、緊急の対応が必要です。
見逃さないで!膝の関節炎の代表的な症状
膝の関節炎は、初期段階では見過ごしやすいサインしか出さないこともあります。しかし、症状が進行すると日常生活に大きな支障をきたすことにもなりかねません。
どのような症状に注意すればよいか、具体的に確認しましょう。
主な症状「痛み」の特徴
関節炎の最も代表的な症状は「痛み」です。特に変形性膝関節症の場合、初期の痛みは「動き始め」に現れることが多いのが特徴です。
例えば、朝起きて最初の一歩を踏み出す時、椅子から立ち上がる時、車から降りる時などに、こわばるような、あるいはズキッとした痛みを感じます。
しばらく動いていると痛みが和らぐことも多いため、「年のせい」と見過ごされがちです。
しかし、進行するにつれて、階段の上り下り(特に下り)や長時間の歩行、正座やしゃがみ込みといった動作でも痛みを感じるようになります。
さらに悪化すると、安静にしていても痛む(安静時痛)、夜間に痛みで目が覚める(夜間痛)といった状態になることもあります。
痛みの進行度の目安
| 進行度 | 痛みの特徴 | 痛む主な場面 |
|---|---|---|
| 初期 | こわばるような痛み、重だるさ | 立ち上がり、歩き始め |
| 中期 | はっきりとした痛み | 階段、長時間の歩行、正座 |
| 末期 | 強い痛み、持続的な痛み | 安静時、夜間 |
「腫れ」「熱感」「水がたまる」
関節内部で炎症が起こると、関節を包む滑膜が刺激され、関節液が過剰に分泌されます。
これが「膝に水がたまる」(関節水腫)状態です。膝が腫れぼったく感じ、重だるさや動かしにくさを伴います。
炎症が強い場合は、膝全体が熱っぽく感じる「熱感」や、赤みを帯びることもあります。特に、関節リウマチや痛風発作では、強い腫れと熱感が現れやすい特徴があります。
関節の「動きにくさ」
関節炎が進行すると、痛みや腫れ、あるいは関節自体の変形によって、膝の動きが制限されていきます。
関節可動域の制限
健康な膝は、かかとがお尻につくくらい深く曲がり、まっすぐ(あるいは少し反るくらい)伸びます。しかし、関節炎が進行すると、まず膝がまっすぐに伸びにくくなります(伸展制限)。
これは痛みを避けるために無意識に膝を曲げた姿勢をとることや、関節の後ろ側が硬くなることが原因です。
さらに進行すると、深く曲げることも困難になり(屈曲制限)、正座ができない、和式トイレが使えない、しゃがんで靴下を履けないなど、日常生活の動作に大きな支障が出てきます。
朝のこわばり
朝起きた時や、長時間同じ姿勢でいた後、関節が固まって動かしにくい感じを「こわばり」と呼びます。
特に関節リウマチでは、この朝のこわばりが1時間以上続くこともあり、重要なサインの一つとされています。
変形性膝関節症でもこわばりを感じることはありますが、関節リウマチに比べると短時間(通常30分以内)で改善することが多いです。
関節の変形
変形性膝関節症が進行すると、体重のかかりやすい膝の内側の軟骨が主にする減るため、脚がO脚に変形してくることが多く見られます。
見た目で「O脚がひどくなった」と感じる場合は、関節炎がかなり進行している可能性があります。
また、関節の縁に「骨棘(こつきょく)」と呼ばれるトゲのような骨の変形ができることもあり、これが動きを妨げたり、痛みの原因になったりします。
早期発見が重要な理由
「そのうち治るだろう」「年のせいだから仕方ない」と膝の痛みを放置していませんか?
膝の関節炎、特に変形性膝関節症は、早期に対処を始めることが、将来の膝の健康を大きく左右します。なぜ早く気づくことが大切なのか、その理由を解説します。
軟骨は再生しにくい
膝の関節炎、特に変形性膝関節症の進行において知っておくべき最も重要な事実は、「関節軟骨には血管が通っておらず、一度すり減ったり傷ついたりすると、自然に元の状態に再生することはほとんどない」ということです。
皮膚が擦りむけても自然に治るのとは根本的に異なります。
だからこそ、軟骨がまだ多く残っている初期の段階で関節炎に気づき、それ以上すり減るのを防ぐための対策を講じることが非常に重要になります。
進行を遅らせる選択肢
関節炎は、早期であればあるほど、対処法の選択肢が多く残されています。
初期の段階であれば、手術を必要とせず、運動療法で膝周りの筋力を強化したり、体重管理を徹底したり、日常生活の動作を見直したりする「保存療法」によって、症状の悪化を防ぎ、痛みを十分にコントロールできる可能性が高いです。
しかし、進行して軟骨のすり減りがひどくなり、骨の変形が進んでしまうと、これらの保存療法の効果も限定的になり、最終的には人工関節置換術などの手術的な対応を検討する必要が出てくるかもしれません。
悪循環を断ち切る
膝の関節炎は「痛み → 痛いから動かさない → 筋力が低下する → 関節が不安定になり、さらに負担がかかる → 痛みが増す」という悪循環に陥りやすい特徴があります。
また、膝の痛みのために外出が億劫になると、活動量が全体的に低下し、体重増加や、心肺機能、他の部位の筋力低下にもつながりかねません。
早期に痛みに対処し、適切な運動を続けることで、この負の連鎖を断ち切り、活動的な生活を長く維持することを目指せます。
進行による生活への影響
| 進行度 | 主な症状 | 生活への影響例 |
|---|---|---|
| 初期 | 動き始めの痛み、こわばり | 長距離の歩行や運動を避けるようになる。 |
| 中期 | 階段昇降痛、正座困難 | 外出が億劫になる。和式の生活が難しくなる。 |
| 末期 | 安静時痛、O脚変形 | 杖や手すりが必要。自分の身の回りのことが困難になる。 |
自分でできる?膝の関節炎セルフチェック
病院に行くほどではないかもしれない、でも最近膝が気になる…という方のために、日常生活で注意したいポイントをまとめました。
これらはあくまで目安であり、関節炎の診断を下すものではありません。しかし、ご自身の状態を知り、医療機関を受診すべきかどうかの判断材料として役立ててください。
日常動作でのチェックポイント
以下のリストに当てはまる項目が複数ある場合、あるいは一つの症状でも続く場合は、膝の関節炎が始まっている可能性があります。
膝の痛みのチェックリスト
- 椅子から立ち上がる時や、歩き始めに膝が痛む。
- 階段の上り下り、特に下りる時に膝が痛む、または不安感がある。
- 長時間歩くと膝が痛くなってくる。
- 膝が重だるい、または腫れぼったい感じがする。
膝の動きのチェックリスト
- 正座や深くしゃがみ込むことが難しい。
- 膝が以前よりまっすぐ伸びにくくなったと感じる。
- 朝起きた時に膝がこわばり、動かしにくい(通常30分以内に治まる)。
- 和式トイレの使用や、床からの立ち座りが辛い。
膝の状態の視覚的チェック
お風呂上がりなどに、鏡の前でご自身の膝を左右見比べながら観察してみましょう。客観的に見ることで、変化に気づきやすくなります。
視覚的チェックポイント
| チェック項目 | 確認する内容 | 考えられる状態 |
|---|---|---|
| 腫れ | 左右の膝の太さや、お皿の周りの輪郭を比べる。 | 関節に水がたまっている(関節水腫)。 |
| 熱感・赤み | 手の甲で左右の膝を触り比べ、熱っぽくないか。 | 関節内で炎症が起きている。 |
| 変形 | 両足をそろえてまっすぐ立った時、O脚やX脚になっていないか。 | 軟骨のすり減りによる変形(O脚が多い)。 |
症状の変化を記録する
もし膝に違和感や痛みを感じ始めたら、「いつから」「どんな時に(動作)」「どの程度(我慢できる、辛い)」「どれくらい続くか」といった症状の変化を簡単なメモでもよいので記録しておくことをお勧めします。
この記録は、後に医療機関を受診した際、状態を正確に伝え、適切な判断をしてもらうための重要な情報となります。
膝の関節炎が疑われる時の検査と対処法
セルフチェックで気になる点があり、症状が続くようなら、自己判断で放置せずに一度、整形外科などの医療機関を受診することを推奨します。
関節炎の診断を受けた場合、どのような検査や対処法があるのか、一般的な流れをご紹介します。
医療機関で行う主な検査
医療機関では、症状や膝の状態を総合的に評価するために、いくつかの検査を行います。
検査の種類と目的
| 検査 | 主な目的 | わかること |
|---|---|---|
| 問診・視診・触診 | 症状の把握、膝の状態の確認 | 痛みの程度、腫れ、熱感、可動域、O脚変形 |
| X線(レントゲン)検査 | 骨の状態の確認(基本検査) | 軟骨のすり減り(関節の隙間)、骨棘(骨のトゲ)、変形 |
| MRI検査 | 軟骨や周辺組織の詳細な確認 | 初期の軟骨損傷、半月板や靭帯の損傷、骨の変化 |
| 血液検査・関節液検査 | 他の疾患(リウマチなど)との鑑別 | 炎症反応、リウマチ因子、尿酸値、細菌の有無 |
特にX線(レントゲン)検査は、変形性膝関節症の診断と進行度の判定における基本となります。関節の隙間が狭くなっていれば、軟骨がすり減っている証拠と判断します。
基本となる「保存療法」
関節炎の治療の基本は、手術をしない「保存療法」です。これは、病気の進行を遅らせ、痛みを和らげ、日常生活の質を維持することを目的としています。
保存療法の主な内容
| 療法の種類 | 主な内容 | 目的 |
|---|---|---|
| 運動療法 | 筋力訓練(大腿四頭筋など)、ストレッチ | 関節の安定化、可動域の維持、負担軽減 |
| 生活指導 | 体重管理、動作指導(正座を避けるなど) | 膝への負担軽減 |
| 装具療法 | サポーター、足底挿板(インソール) | 関節の安定化、衝撃吸収、O脚矯正 |
| 物理療法 | 温熱療法、低周波治療など | 痛みの緩和、血行改善 |
運動療法の重要性
保存療法の中でも特に重要なのが「運動療法」です。膝が痛いと動きたくなくなるものですが、安静にしすぎると膝周りの筋力(特に太ももの前の筋肉である大腿四頭筋)が衰え、関節を支える力が弱まり、膝が不安定になります。
この不安定さが、さらなる軟骨のすり減りや痛みを引き起こす悪循環を生みます。痛みが出ない範囲で適切に筋力を維持・強化することが、関節炎の進行予防に非常に大切です。
自宅でできる簡単な筋力訓練
| 運動名 | 方法 | ポイント |
|---|---|---|
| 大腿四頭筋訓練(座位) | 椅子に深く座り、片脚の膝をまっすぐ伸ばし、5秒程保持してゆっくり下ろす。 | 太ももの前に力が入るのを意識する。痛みが出ない範囲で。 |
| 大腿四頭筋訓練(臥位) | 仰向けに寝て、片方の膝を立てる。もう片方の脚は伸ばしたまま、床から10cm程上げて5秒保持。 | 腰が反らないように注意する。 |
薬物療法について
痛みが強く、日常生活や運動療法に支障が出る場合には、薬物療法を併用します。外用薬(貼り薬、塗り薬)や内服の消炎鎮痛薬(NSAIDsなど)で炎症と痛みを抑えます。
また、関節の潤滑油の役割を補う「ヒアルロン酸」を関節内に注射したり、炎症が非常に強い場合には「ステロイド」を注射して強力に炎症を抑えたりすることもあります。
ただし、これらは根本的に関節炎を治すものではなく、症状を緩和するための対症療法であることを理解しておく必要があります。
日常生活でできる予防とセルフケア
関節炎の進行予防や症状緩和には、医療機関での対処と並行して、日々の生活習慣を見直すことが非常に重要です。
膝に優しい生活を心がけ、ご自身でできるケアを継続していきましょう。
体重管理の徹底
前述の通り、体重の増加は膝関節への負担を飛躍的に増大させます。もし体重が標準を上回っている場合、減量に取り組むことは最も効果的なセルフケアの一つです。
体重を1kg減らすだけでも、膝への負担は歩行時で約3kg、階段昇降時では約6〜7kgも軽減されるとされています。
無理なダイエットは必要ありませんが、食事内容を見直し、適度な運動(膝に負担の少ない水中ウォーキングや自転車など)を取り入れ、体重をコントロールすることが大切です。
膝に負担をかけない動作の習得
日常生活の中で、無意識に膝に負担をかけている動作は多くあります。これらの動作を避け、膝に優しい動作を習慣づけることが進行予防につながります。
膝に優しい動作の工夫
| 負担のかかる動作 | 工夫・代替案 | 理由 |
|---|---|---|
| 床に座る(正座・あぐら) | 椅子やソファ、ベッドでの生活を基本にする。 | 膝を深く曲げる動作は関節への圧力を高める。 |
| 床からの立ち座り | 近くのテーブルや手すりにつかまって立ち上がる。 | 膝への急激な負荷とねじれを防ぐ。 |
| 重い荷物を持つ | 台車(カート)を利用する。荷物を小分けにする。 | 体重+荷物の重さが直接膝にかかるのを防ぐ。 |
食生活で気をつけること
特定の食品が関節炎を治すということはありませんが、バランスの取れた食事は健康な体づくりの基本であり、関節の健康維持にも寄与します。
特に、骨の材料となるカルシウム(乳製品、小魚、大豆製品など)や、その吸収を助けるビタミンD(きのこ類、魚類など)、筋肉の材料となるタンパク質(肉、魚、卵、大豆製品など)を意識して摂取しましょう。
また、肥満予防の観点から、高カロリー・高脂肪な食事は控えることが賢明です。
関節リウマチの場合は、炎症を促進する可能性のある特定の脂肪酸(リノール酸など)の過剰摂取を避け、抗炎症作用が期待されるオメガ3系脂肪酸(青魚など)を適度に取り入れることが勧められる場合もあります。
靴選びとインソール(足底挿板)
足元からの衝撃は、直接膝に伝わります。クッション性が高く、かかとが安定する、ご自身の足に合った靴を選ぶことが大切です。
特に女性は、膝に負担のかかるハイヒールの常用は避ける方が無難です。また、O脚が目立つ場合には、靴底の外側がすり減りやすくなっています。
この場合、足底挿板(インソール)を使用して足のアライメントを補正し、膝の内側にかかる負担を軽減する方法も有効です。
市販のものもありますが、個々の足に合わせて作成することも可能です。
膝の関節炎に関するよくある質問
最後に、膝の関節炎に関して多く寄せられる疑問点についてお答えします。
Q. 膝がポキポキ鳴るのは関節炎のサインですか?
A. 膝を曲げ伸ばしした時に「ポキポキ」「パキパキ」と音が鳴ることがあります。
この音(クラッキング音)は、多くの場合、関節内の圧力の変化で関節液の中の気泡が弾ける音など、生理的な現象です。
痛みや腫れ、引っかかり感などを伴わなければ、特に心配する必要はありません。
ただし、音とともに痛みを感じたり、何かが引っかかるような感覚があったりする場合は、軟骨や半月板が傷ついている可能性も考えられるため、一度医療機関に相談することをお勧めします。
Q. 痛い時は温めるべきですか?冷やすべきですか?
A. これは症状の時期によって使い分けるのが基本です。膝が急に強く痛みだした、赤く腫れて熱を持っているような「急性期」は、炎症を抑えるために冷やす(アイシング)のが適切です。
一方、激しい痛みや熱感はなく、動かし始めに痛む、こわばるような慢性的な痛み(慢性期)の場合は、温めて血行を良くすることで、筋肉の緊張がほぐれ、痛みが和らぐことがあります。
お風呂でゆっくり温まる、ホットパックを使うなどが良いでしょう。
どちらが適切か迷う場合は、ご自身が「気持ち良い」と感じる方を選んでも構いませんが、原則は「急な炎症は冷やす、慢性的な痛みは温める」と覚えておくと良いでしょう。
Q. サプリメントは効果がありますか?
A. 膝の健康維持をうたったサプリメント(健康食品)として、グルコサミンやコンドロイチン、ヒアルロン酸、コラーゲンなどが広く知られています。
これらの成分が膝の痛みを和らげるのに役立ったという研究報告もありますが、その効果については医学的にまだ明確な結論が出ていないのが現状です。
医薬品とは異なり、すり減った軟骨を再生させたり、関節炎の進行を確実に止めたりする効果は証明されていません。
摂取する場合は、あくまで食事の補助として位置づけ、過度な期待はせず、基本となる運動療法や体重管理を疎かにしないことが重要です。
Q. O脚は治せますか?
A. O脚の原因が、長年の生活習慣によるものではなく、関節炎の進行による骨の変形(軟骨のすり減りによるもの)である場合、ストレッチや体操だけでO脚を完全にまっすぐに治すことは困難です。
しかし、前述の足底挿板(インソール)の使用や、膝周りの筋力バランスを整える運動療法によって、膝の内側にかかる負担を軽減し、痛みを和らげたり、変形の進行を遅らせたりすることは期待できます。
変形が非常に高度で、痛みが強い場合には、骨の角度を矯正する手術(高位脛骨骨切り術)や、人工関節置換術などが選択肢となる場合もあります。
参考文献
FAVERO, Marta, et al. Early knee osteoarthritis. RMD open, 2015, 1.Suppl 1.
HEIDARI, Behzad. Knee osteoarthritis prevalence, risk factors, pathogenesis and features: Part I. Caspian journal of internal medicine, 2011, 2.2: 205.
DRIBAN, Jeffrey B., et al. Risk factors and the natural history of accelerated knee osteoarthritis: a narrative review. BMC musculoskeletal disorders, 2020, 21.1: 332.
MAHMOUDIAN, Armaghan, et al. Early-stage symptomatic osteoarthritis of the knee—time for action. Nature Reviews Rheumatology, 2021, 17.10: 621-632.
DOHERTY, Michael. Risk factors for progression of knee osteoarthritis. The Lancet, 2001, 358.9284: 775-776.
HEIDARI, Behzad. Knee osteoarthritis diagnosis, treatment and associated factors of progression: part II. Caspian journal of internal medicine, 2011, 2.3: 249.
ZHANG, Weiya, et al. EULAR evidence-based recommendations for the diagnosis of knee osteoarthritis. Annals of the rheumatic diseases, 2010, 69.3: 483-489.
MADRY, Henning, et al. Early osteoarthritis of the knee. Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy, 2016, 24.6: 1753-1762.
SALEHI-ABARI, Iraj. 2016 ACR revised criteria for early diagnosis of knee osteoarthritis. Autoimmune Dis Ther Approaches, 2016, 3.1: 118.
CHU, Constance R., et al. Early diagnosis to enable early treatment of pre-osteoarthritis. Arthritis research & therapy, 2012, 14.3: 212.
Symptoms 症状から探す