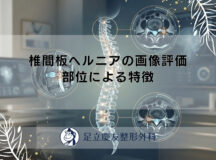股関節の痛みで歩行困難なときの対処方法
股関節に強い痛みが生じ、「痛くて歩けない」という状態は、日常生活に深刻な影響を及ぼします。
突然の激痛であれ、徐々に悪化してきた痛みであれ、歩行が困難になるほどの症状は、何らかの異常が起きている重要なサインです。
この状態は、単なる筋肉痛や一時的な不調とは異なり、股関節そのものや周辺組織に問題が発生している可能性を示唆しています。
この記事では、股関節の痛みで歩行が困難になった場合に考えられる原因、ご自身でできる応急処置、そして医療機関を受診する目安について、詳しく解説します。
目次
「股関節 痛くて 歩けない」状態の緊急度と深刻さ
股関節が痛くて歩けないという症状は、非常に切実な問題です。この症状を経験している方は、強い不安を感じていることでしょう。
まずは、その痛みがどのような状態を示しているのか、そしてなぜ迅速な対応が求められるのかを理解することが大切です。
強い痛みで歩けない状態とは
「歩けない」と一言でいっても、その程度は様々です。
足を着くたびに激痛が走る、体重を全くかけられない、安静にしていてもズキズキと痛む、特定の角度に動かすと電気が走るように痛むなど、症状の現れ方は異なります。
歩行困難なほどの痛みは、股関節の構造(骨、軟骨、靭帯など)が何らかのダメージを受けているか、強い炎症が起きていることを示しています。
なぜ歩行困難なほどの痛みが出るのか
股関節は、体重を支え、歩く、立つ、座るといった基本的な動作を可能にする人体のかなめとなる関節です。
この重要な関節に問題が生じると、体重がかかる(荷重時)だけで強い痛みが出ることがあります。また、炎症が強い場合は、動かさなくても痛み(安静時痛)が生じることがあります。
痛みのために無意識に股関節をかばうようになり、結果として正常な歩行ができなくなります。
放置するリスクと早期対応の重要性
強い痛みを我慢し続けることは、いくつかのリスクを伴います。痛みをかばうことで、反対側の股関節や膝、腰など他の部位に過度な負担がかかり、新たな痛みの原因となることがあります。
また、原因となっている疾患が進行し、関節の変形が進んだり、治療がより困難になったりする可能性もあります。
放置した場合に考えられる影響
- 症状の慢性化
- 関節の変形の進行
- 他の部位(腰、膝など)への負担増加
- 日常生活動作(ADL)の低下
歩行困難なほどの痛みは、体が発する危険信号です。この信号を無視せず、早期に適切な対応をとることが、将来的な機能維持のために重要です。
歩けないほどの股関節痛を引き起こす主な原因
股関節が痛くて歩けないほどの症状を引き起こす原因は一つではありません。加齢に伴うものから、急性の外傷、あるいは他の病気が関連するものまで、多岐にわたります。
原因を特定することが、適切な対処への第一歩です。
加齢による変形性股関節症
中高年以降の方で、特に女性に多い原因の一つが「変形性股関節症」です。
これは、長年の使用により股関節の軟骨がすり減り、骨が変形することで痛みや動かしにくさ(可動域制限)が生じる疾患です。
初期は立ち上がりや歩き始めに痛む程度ですが、進行すると安静時にも痛むようになり、歩行が困難になることがあります。
関節の炎症や感染症
「関節リウマチ」などの自己免疫疾患は、股関節を含む全身の関節に炎症を引き起こし、痛みや腫れ、こわばりの原因となります。
また、まれですが、細菌が関節内に入り込む「化膿性股関節炎」は、急激な激痛、発熱、腫れを伴い、歩行不能となることがあります。この状態は緊急の治療を必要とします。
骨折や脱臼などの外傷
転倒や事故など、明確なきっかけがある場合の激痛は、骨折を疑う必要があります。
特に高齢者の場合、骨粗しょう症の影響で、わずかな衝撃でも「大腿骨近位部骨折(太ももの付け根の骨折)」を起こしやすい傾向があります。
この骨折は、発症と同時に強い痛みで立てなくなり、歩行が不可能になることがほとんどです。
主な股関節痛の原因と特徴
| 主な原因 | 典型的な症状 | 主な対象者 |
|---|---|---|
| 変形性股関節症 | 動作開始時の痛み、可動域制限(徐々に悪化) | 中高年(特に女性) |
| 大腿骨近位部骨折 | 転倒直後からの激痛、起立・歩行不能 | 高齢者(特に女性) |
| 化膿性股関節炎 | 急激な激痛、発熱、腫れ、歩行不能 | 全年齢(緊急対応が必要) |
その他の疾患(大腿骨頭壊死症など)
「特発性大腿骨頭壊死症」という疾患も、強い股関節痛の原因となります。これは、大腿骨の先端部分(大腿骨頭)への血流が途絶え、骨の組織が壊死(死んでしまうこと)する病気です。
ステロイド薬の多用やアルコールの多飲が関連するといわれますが、原因不明(特発性)の場合も多くあります。
骨壊死が進行し、骨頭が潰れる(圧潰)と、急激な痛みが生じ、歩行が困難になります。
すぐに医療機関を受診すべき危険な兆候
股関節が痛くて歩けない場合、多くは医療機関での診断が必要ですが、中には一刻も早い対応が求められる「危険な兆候」があります。
ご自身の症状と照らし合わせて確認してください。
激しい痛みで全く動けない
体重をかけるどころか、ベッドの上で少し体勢を変えるだけでも激痛が走る、痛む方の足を全く動かせない、といった場合は、骨折や重度の関節炎、感染症の可能性があります。
このような状態では、無理に動こうとせず、救急車の要請も検討する必要があります。
転倒などの明確なきっかけがある
「転んだ」「強くひねった」といった明らかな原因の直後から歩けなくなった場合は、骨折や脱臼、靭帯の重度な損傷が強く疑われます。
特に高齢者の場合は、大腿骨近位部骨折の可能性を考慮し、速やかに整形外科を受診してください。
痛み以外の症状(発熱、腫れ、しびれ)
股関節の痛みと同時に、全身の発熱、股関節の著しい腫れや熱感がある場合は、「化膿性股関節炎」などの感染症が疑われます。
この場合、迅速な治療を行わないと関節が破壊される危険があるため、夜間や休日であっても救急外来の受診が必要です。
また、足にしびれや麻痺が伴う場合は、腰の神経(腰椎)に問題がある可能性も考えられます。
緊急受診を検討すべき症状
| 症状 | 疑われる状態 | 対応 |
|---|---|---|
| 転倒後に立てない・動かせない | 骨折(大腿骨近位部骨折など) | 速やかに整形外科を受診(救急車も検討) |
| 急激な激痛、発熱、著しい腫れ | 化膿性股関節炎(感染症) | 緊急受診(夜間・休日でも) |
| 安静時も続く激痛、全く動けない | 骨折、重度の炎症、大腿骨頭壊死症など | 速やかに整形外科を受診 |
安静にしていても痛みが続く
通常、筋肉や腱の軽い炎症(いわゆる股関節痛)であれば、安静にすることで痛みは和らぐことが多いです。
しかし、楽な姿勢をとっても痛みが全く軽減しない、あるいは夜間に痛みで目が覚める(夜間痛)場合は、炎症が非常に強いか、骨や軟骨に深刻な問題が生じている可能性が高いです。
これも早期受診のサインです。
痛みが強いときの応急処置と安静の保ち方
歩行困難なほどの痛みがある場合、医療機関を受診するまでの間、ご自身でできる応急処置があります。
無理をせず、症状を悪化させないための対処法を知っておきましょう。
痛む動作を避ける(安静の基本)
最も重要なのは、痛みを感じる動作を無理に行わないことです。「歩けない」と感じるなら、無理に歩こうとしないでください。
家の中の移動も最小限にし、体重をかけないようにすることが第一です。痛みを我慢して動くと、炎症を悪化させたり、損傷部位をさらに傷つけたりする恐れがあります。
冷却(アイシング)と温熱(温め)の使い分け
痛みの性質によって、冷やすべきか温めるべきかが異なります。転倒などの直後で、股関節が腫れて熱を持っているような「急性期」の痛みには、冷却(アイシング)が適しています。
一方、動かすと痛いが腫れや熱感はそれほどでもない、慢性的な痛み(変形性股関節症など)の場合は、温熱(温める)ことで血流が良くなり、痛みが和らぐことがあります。
冷却と温熱の判断基準
| 対処法 | 適した状態 | 目的 |
|---|---|---|
| 冷却(アイシング) | 急性の痛み(転倒直後など)、腫れ、熱感がある | 炎症と腫れを抑える |
| 温熱(温める) | 慢性の痛み、こわばり感、腫れや熱感がない | 血流促進、筋肉の緊張緩和 |
判断に迷う場合は、無理に温めず、安静を優先してください。
杖や歩行器の使用
どうしても移動が必要な場合は、杖や歩行器を使用し、痛む股関節への負担を減らすことが重要です。杖は、痛む足と反対側の手で持ちます。
例えば、右の股関節が痛い場合は、左手で杖をつきます。これにより、痛む足にかかる体重を分散させることができます。
歩行器は、より安定性が高いため、両側の股関節が痛む場合や、杖では不安な場合に有効です。
楽な姿勢の見つけ方
安静にしているときの姿勢も大切です。痛みが最も和らぐ姿勢を探しましょう。
一般的に、股関節の痛みが強いときは、仰向けで膝の下にクッションや丸めたタオルを入れ、股関節と膝を軽く曲げた状態にすると楽になることが多いです。
横向きになる場合は、痛い方を上にし、足の間にクッションを挟むと安定します。
安静時の楽な姿勢の例
| 姿勢 | 工夫 |
|---|---|
| 仰向け | 膝の下にクッションを入れ、股関節と膝を軽く曲げる |
| 横向き | 痛い方を上にする。両足の間にクッションや枕を挟む |
医療機関での一般的な検査と診断
歩行困難なほどの股関節痛で医療機関(主に整形外科)を受診すると、痛みの原因を正確に突き止めるために、いくつかの検査を行います。
どのような検査が行われるのかを知っておくと、安心して受診できるでしょう。
医師による問診と身体診察
診察室では、まず医師が患者さんから詳しくお話を聞きます(問診)。
いつから痛むのか、どのようなきっかけがあったか、どんな時に痛みが強くなるか、痛み以外の症状はあるか、といった情報が診断の手がかりとなります。
問診でよく尋ねられる内容
- 痛みの発生時期ときっかけ
- 痛みの場所と性質(ズキズキ、チクチクなど)
- 痛みが強くなる動作(歩行時、安静時など)
- 過去の病気や怪我、現在治療中の病気
その後、医師が股関節を動かしたり、押したりして痛みの場所や可動域を確認する「身体診察」を行います。
これにより、痛みの原因が関節の中にあるのか、外の筋肉や腱にあるのかをある程度推測します。
レントゲン(X線)検査の役割
股関節痛の診断において、レントゲン検査は基本となる重要な検査です。骨の形状や、関節の隙間(軟骨の厚み)、骨折の有無などを確認します。
変形性股関節症の進行度や、大腿骨近位部骨折の診断は、主にレントゲン検査で行います。比較的短時間で簡便に行える検査です。
MRIやCT検査でわかること
レントゲン検査だけでは診断が難しい場合、さらに詳しい検査を行います。
MRI検査は、磁気を利用して体の断面を撮影する検査で、レントゲンでは映らない軟骨、靭帯、筋肉などの「柔らかい組織」の状態や、骨の中の変化(大腿骨頭壊死症の早期診断など)を詳細に調べるのに優れています。
CT検査は、X線を多方向から当てて体の断面を撮影する検査で、骨折の複雑な状態や、骨の微細な変化を立体的に把握するのに役立ちます。
画像検査の比較
| 検査方法 | 主な目的 | 特徴 |
|---|---|---|
| レントゲン (X線) | 骨の形状、骨折の有無、関節の隙間 | 基本的、迅速、簡便 |
| MRI検査 | 軟骨、靭帯、骨の内部(壊死など) | 軟部組織や早期病変の描出に優れる |
| CT検査 | 複雑な骨折、骨の立体的な評価 | 骨の詳細な構造把握に優れる |
血液検査が必要な場合
発熱を伴う場合や、関節リウマチなどの全身性疾患が疑われる場合は、血液検査を行います。
血液検査では、体内の炎症の程度(CRP値や赤沈)や、特定の疾患に関連する項目(リウマトイド因子など)を調べ、感染症や炎症性疾患の診断に役立てます。
歩行困難な股関節痛に対する治療の選択肢
検査によって痛みの原因が特定されたら、その診断に基づいて治療が開始されます。治療法は、原因や症状の重症度、年齢、活動レベルなどに応じて選択されます。
大きく分けて、手術をしない「保存的治療」と、手術を行う「手術的治療」があります。
保存的治療(薬物療法・リハビリテーション)
多くの股関節痛は、まず保存的治療から開始します。これは、手術以外の方法で痛みや症状の改善を目指す治療法です。
安静指導、薬物療法、そしてリハビリテーション(運動療法や物理療法)が中心となります。特に変形性股関節症の初期から中期では、保存的治療が主体となります。
保存的治療の主な内容
| 治療法 | 目的 |
|---|---|
| 安静・生活指導 | 股関節への負担軽減、症状の悪化防止 |
| 薬物療法 | 痛みと炎症のコントロール |
| リハビリテーション | 筋力維持・強化、可動域の改善 |
薬物療法(痛み止め・注射)の種類と目的
痛みが強い場合、まずは痛みと炎症を抑えるために薬物療法が行われます。一般的には、非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)の飲み薬や貼り薬、塗り薬が使用されます。
これらで効果が不十分な場合や、痛みが極端に強い場合は、股関節内にヒアルロン酸やステロイドの注射を行うこともあります。
これらの薬物療法は、痛みを和らげる対症療法であり、根本的な原因を治すものではありませんが、痛みを軽減してリハビリテーションをスムーズに進めるために重要です。
運動療法(リハビリ)の重要性
痛いからといって動かさないでいると、股関節周囲の筋力が低下し、関節が硬くなり(拘縮)、ますます股関節が不安定になって痛みが悪化するという悪循環に陥りがちです。
理学療法士などの専門家の指導のもと、股関節に負担をかけない方法で筋力(特に中殿筋などの股関節を支える筋肉)を強化したり、関節の柔軟性を保つストレッチを行ったりする運動療法は、股関節痛の治療において非常に重要です。
ただし、自己流で行うと症状を悪化させることもあるため、必ず専門家の指導を受けてください。
手術的治療(人工股関節置換術など)が検討される場合
保存的治療を続けても痛みが改善しない場合、歩行困難が続き日常生活に大きな支障が出ている場合、あるいは変形性股関節症が末期まで進行している場合、大腿骨頭壊死症で骨頭の圧潰が進んだ場合、そして大腿骨近位部骨折などでは、手術的治療が検討されます。
代表的な手術には、傷んだ関節を金属やポリエチレンなどでできた人工の関節に置き換える「人工股関節置換術」があります。
この手術は、痛みの除去と関節機能の再獲得に大きな効果が期待できる方法です。
股関節の負担を減らす日常生活の工夫
医療機関での治療と並行して、日々の生活の中で股関節への負担を意識的に減らす工夫をすることも、痛みの管理と悪化の予防に役立ちます。
歩行困難なほどの痛みを経験した後は、特に注意が必要です。
体重管理の重要性
股関節には、歩行時に体重の数倍の負荷がかかるといわれています。体重が増加すると、それだけ股関節への負担も増大します。
もし体重が標準よりも多い場合は、適正な体重に近づけることで、股関節への負担を大幅に減らすことができます。
痛みのために運動が難しい場合でも、食事内容の見直しによる体重管理は可能です。
体重管理が股関節にもたらす利点
- 股関節にかかる負荷の直接的な軽減
- 痛みの緩和
- 疾患の進行予防
動作の工夫(立ち座り・階段昇降)
日常生活の何気ない動作も、股関節に負担をかけていることがあります。例えば、低い椅子や床からの立ち上がりは、股関節を深く曲げる必要があり、大きな負担となります。
できるだけ高さのある椅子を使用する、トイレに補高便座を設置するなどの工夫が有効です。
階段の上り下りも負担が大きいため、手すりを必ず使用し、痛くない方の足から昇り、痛い方の足から降りるようにすると負担が軽減されます。
股関節に負担をかける動作と軽減する工夫
| 負担のかかる動作 | 軽減する工夫 |
|---|---|
| 床に座る(あぐら、横座り) | 椅子やベッドでの生活を心がける |
| 低い位置からの立ち座り | 高さのある椅子を使う、手すりを設置する |
| 重い物を持つ | 荷物を小分けにする、キャリーカートを使う |
靴選びとインソール(中敷き)の活用
歩行時の衝撃は、足の裏から股関節に伝わります。クッション性の高い靴を選ぶことで、この衝撃を和らげることができます。
ハイヒールや底の硬い靴は避け、スニーカーやウォーキングシューズなど、足に合った安定感のある靴を選びましょう。
また、足の形(扁平足や外反母趾など)に合わせてインソール(中敷き)を作成し、靴に入れることで、足元のバランスが整い、股関節への負担が軽減される場合もあります。
和式から洋式への生活スタイルの変更
日本の伝統的な生活様式である、床に座る、和式トイレを使用する、布団で寝起きするといった動作は、股関節を深く曲げ伸ばしするため、股関節に大きな負担をかけます。
可能であれば、椅子やソファ、ベッドを使用する洋式の生活スタイルに変更することを検討してください。
特に和式トイレは股関節への負担が非常に大きいため、洋式トイレへの改修が望ましいです。これらの小さな変更が、長期的な股関節の保護につながります。
股関節の痛みで歩行困難なときの対処方法に関するよくある質問
ここでは、股関節の痛みに関して多く寄せられる疑問にお答えします。歩行が困難になるほどの痛みを経験すると、様々な不安や疑問が生じるものです。
Q. 痛みが少し和らいだら、運動を再開してもよいですか?
A. 痛みが強い「急性期」は安静が第一です。痛みが少し和らいできたからといって、自己判断で急に運動を再開するのは危険です。
特に、ランニングやジャンプ、長距離のウォーキングなど、股関節に衝撃がかかる運動は避けるべきです。
運動を再開する場合は、必ず医師の許可を得てから、まずは水中ウォーキングやエアロバイクなど、股関節への負担が少ない運動から、専門家の指導のもとで徐々に始めるようにしてください。
Q. 杖を使うことに抵抗があります。
A. 「杖を使うと年寄りに見える」といった理由で、杖の使用に抵抗を感じる方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、杖は歩行困難なほどの痛みがある場合に、股関節を守るための非常に有効な道具です。
痛む股関節への負担を軽減し、痛みをかばうことで生じる他の部位への悪影響を防ぐ役割があります。
また、杖を使うことでバランスが取りやすくなり、転倒を予防する効果もあります。
一時的に使用するだけでも、股関節の回復に役立ちますので、医師や理学療法士から勧められた場合は、前向きに活用を検討してください。
Q. どのような病院(何科)を受診すればよいですか?
A. 股関節の痛みで歩行が困難な場合は、「整形外科」を受診してください。整形外科は、骨、関節、筋肉、靭帯、神経といった運動器の疾患を専門とする診療科です。
レントゲンやMRIなどの画像検査設備が整っており、股関節痛の原因を正確に診断し、専門的な治療(薬物療法、リハビリテーション、手術など)を受けることができます。
特に転倒などの外傷がきっかけである場合は、迷わず整形外科を受診しましょう。
Q. 痛みを我慢し続けるとどうなりますか?
A. 歩行困難なほどの痛みを我慢し続けることは、多くの不利益をもたらします。
痛みの原因となっている疾患(例えば変形性股関節症や大腿骨頭壊死症)が進行し、関節の変形が進んでしまう可能性があります。
また、痛みをかばう歩き方(跛行)が続くことで、反対側の股関節や膝、腰に二次的な障害を引き起こすことも少なくありません。
さらに、痛みによる活動量の低下が筋力低下を招き、ますます歩行が困難になるという悪循環に陥ることもあります。
適切な時期に治療を開始するためにも、強い痛みは我慢しないでください。
参考文献
MCGOVERN, Ryan P., et al. Non-operative management of individuals with non-arthritic hip pain: a literature review. International journal of sports physical therapy, 2019, 14.1: 135.
HOSSAIN, Mounier; NEELAPALA, V.; ANDREW, J. G. Results of non-operative treatment following hip fracture compared to surgical intervention. Injury, 2009, 40.4: 418-421.
OOI, L. H., et al. Hip fractures in nonagenarians—a study on operative and non-operative management. Injury, 2005, 36.1: 142-147.
AMSELLEM, Delphine, et al. Non-operative treatment is a reliable option in over two thirds of patients with Garden I hip fractures. Rates and risk factors for failure in 298 patients. Orthopaedics & Traumatology: Surgery & Research, 2019, 105.5: 985-990.
LOGGERS, Sverre AI, et al. Prognosis of nonoperative treatment in elderly patients with a hip fracture: a systematic review and meta-analysis. Injury, 2020, 51.11: 2407-2413.
ENSEKI, Keelan R., et al. Hip pain and movement dysfunction associated with nonarthritic hip joint pain: A revision: clinical practice guidelines linked to the international classification of functioning, disability, and health from the academy of orthopaedic physical therapy and American academy of sports physical therapy of the American physical therapy association. Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy, 2023, 53.7: CPG1-CPG70.
WALLEY, Kempland C.; APPLETON, P. T.; RODRIGUEZ, E. K. Comparison of outcomes of operative versus non-operative treatment of acetabular fractures in the elderly and severely comorbid patient. European Journal of Orthopaedic Surgery & Traumatology, 2017, 27.5: 689-694.
POLLOCK, Noel; HULSE, David. The Non-operative Management of Hip Disease in Young Adults. In: The Young Adult Hip in Sport. London: Springer London, 2013. p. 135-148.
NAKAMURA, Keisuke, et al. Factors associated with functional rehabilitation outcomes of non-operative treatment for hip fractures: a retrospective study. Journal of Physical Therapy Science, 2019, 31.5: 453-456.
Symptoms 症状から探す