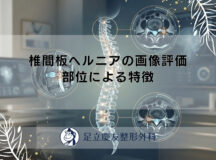太ももから股関節にかけての痛み|原因と治療法
太ももから股関節にかけての痛みに悩んでいませんか。歩き始めや立ち上がる時に痛む、太ももの外側や付け根がズキズキするなど、症状は様々です。
その痛みは、股関節自体に問題がある場合もあれば、腰や周囲の筋肉が原因となっている場合もあります。放置すると痛みが悪化し、日常生活に支障をきたすこともあります。
この記事では、太ももから股関節にかけての痛みの原因として考えられること、代表的な疾患、ご自宅でできる対処法、医療機関での検査や専門的な治療法について詳しく解説します。
ご自身の状態を理解し、適切な対応を見つけるための一助となれば幸いです。
目次
太ももから股関節にかけての痛みの特徴
痛みを感じる場所、痛みの性質、どのような時に痛むかといった情報は、原因を探る上で重要な手がかりとなります。
まずは、ご自身の症状がどのように現れているかを詳しく観察してみましょう。
痛みの具体的な場所
痛みが出ている場所によって、考えられる原因が異なります。股関節は体の深い部分にあるため、痛みの場所が特定しにくいこともありますが、おおよその傾向があります。
- 股関節(脚の付け根)の前側
- 太ももの外側
- お尻(股関節の後ろ側)
- 太ももの内側
例えば、股関節の前側(脚の付け根)が痛む場合は股関節自体の問題、お尻や太ももの裏側が痛む場合は腰からの神経の影響も考えます。
太ももの外側に痛みやしびれが出る場合は、特定の神経が圧迫されている可能性もあります。
痛みの種類
痛みの感じ方も人によって様々です。「ズキズキする」「ジンジンする」「ピリピリとしびれる」「重だるい」など、表現は多岐にわたります。
鋭い痛みは炎症や損傷を、しびれを伴う痛みは神経の圧迫を示唆することがあります。どのような種類の痛みかを把握することも、診断の一助となります。
痛みが強まる状況
痛みがどのような動作や状況で強まるかにも注目します。
歩き始めや立ち上がり時に痛む、長時間歩くと痛くなる、階段の上り下りがつらい、あぐらをかくのが難しい、といった動作に関連する痛みは、股関節やその周囲の筋肉に負担がかかっているサインです。
一方で、じっとしていても痛む(安静時痛)や夜間に痛む(夜間痛)場合は、炎症が強い状態や、股関節以外の原因も考慮する必要があります。
痛み以外の伴う症状
痛みだけでなく、他の症状が出ていないかも確認が大切です。股関節の動きが悪くなる「可動域制限」は、変形性股関節症などでよく見られます。
また、太ももやふくらはぎにしびれや脱力感(力が入りにくい感じ)を伴う場合は、腰椎(腰の骨)の問題で神経が圧迫されている可能性も疑います。
関節周辺が腫れていたり、熱感を持っていたりする場合は、強い炎症や感染なども考えられます。
痛みを引き起こす股関節の主な原因
股関節や太ももが痛む背景には、様々な要因が複雑に関わっています。ここでは、痛みを引き起こす主な原因を分類し、どのような要因が影響するかを見ていきます。
筋肉や腱の問題
股関節は多くの筋肉や腱に囲まれています。
これらの組織の使いすぎ(オーバーユース)や、急な運動による損傷(肉離れなど)、あるいは運動不足による筋力低下や柔軟性の低下が、痛みの原因となることがあります。
特に股関節の周りにある中殿筋や梨状筋、腸腰筋といった筋肉が硬くなったり、炎症を起こしたりすると、股関節や太ももに関連する痛みが出ることがあります。
関節軟骨の摩耗や変形
股関節は、大腿骨(太ももの骨)の先端にある球状の「骨頭」と、骨盤側でそれを受ける「寛骨臼」というお皿状のくぼみで構成されています。
これらの表面は「関節軟骨」という滑らかな組織で覆われており、クッションの役割を果たしています。
加齢や体重の負荷、過去の怪我などによってこの軟骨がすり減ると、骨同士がこすれ合い、痛みや炎症、関節の変形を引き起こします。これが「変形性股関節症」です。
神経の圧迫や障害
太ももや股関節周辺の痛みは、必ずしも股関節自体が原因とは限りません。
腰椎(腰の骨)で神経が圧迫される「腰椎椎間板ヘルニア」や「腰部脊柱管狭窄症」などがあると、お尻から太もも、時にはすねや足先にかけて痛みやしびれ(坐骨神経痛など)が出ることがあります。
また、骨盤の出口で神経が圧迫される「梨状筋症候群」や、太ももの外側の皮膚感覚を支配する神経が圧迫される「外側大腿皮神経痛」なども、太ももの痛みの原因となります。
骨や関節の構造的な問題
生まれつき、あるいは成長の過程で、股関節の形状に特徴がある場合、将来的に痛みの原因となることがあります。代表的なものに「臼蓋形成不全」があります。
これは、骨盤側の寛骨臼の「かぶり」が浅く、大腿骨頭を十分に覆えていない状態です。
この状態だと、狭い範囲に体重が集中してかかるため軟骨が傷みやすく、若いうちから変形性股関節症に進行することがあります。
股関節痛に関連するリスク要因
| 要因カテゴリ | 具体的な要因 | 解説 |
|---|---|---|
| 年齢・性別 | 加齢、女性 | 加齢により軟骨は摩耗しやすくなります。女性は臼蓋形成不全の割合が高く、筋力も男性より弱い傾向があります。 |
| 体重・活動 | 肥満、激しいスポーツ | 体重が重いと股関節への負荷が増大します。激しい運動は関節や筋肉を痛める原因となり得ます。 |
| 既往歴・構造 | 過去の怪我、臼蓋形成不全 | 股関節周辺の骨折や脱臼の経験、先天的な関節の形状は、将来の痛みに影響することがあります。 |
股関節や太ももの痛みを伴う代表的な疾患
股関節周辺の痛みを引き起こす疾患は多岐にわたります。ここでは、医療機関で診断されることの多い、代表的な疾患とその特徴を紹介します。
変形性股関節症
日本において股関節の痛みの原因として最も多い疾患の一つです。関節軟骨がすり減り、骨が変形することで痛みが生じます。
初期は立ち上がりや歩き始めに脚の付け根に痛みを感じる程度ですが、進行すると安静時や夜間にも痛むようになり、可動域制限によって靴下の着脱や爪切りが困難になるなど、日常生活に大きな支障が出ます。
特に臼蓋形成不全が背景にある場合、若年でも発症することがあります。
大腿骨寛骨臼インピンジメント(FAI)
股関節を深く曲げた時などに、大腿骨の首部分と寛骨臼の縁が衝突(インピンジメント)することで、関節唇(寛骨臼の縁にある軟骨組織)や関節軟骨を損傷し、痛みを引き起こす状態です。
特にスポーツ選手や若年層で股関節の前側に痛みが出る場合、この疾患を疑うことがあります。放置すると変形性股関節症に移行するリスクがあると考えられています。
大腿骨頭壊死症
大腿骨頭の一部が、血流の障害によって壊死(組織が死んでしまうこと)する疾患です。
アルコールの多飲やステロイド薬の大量使用と関連がある場合と、原因が特定できない特発性の場合があります。
初期は症状がないこともありますが、壊死した部分が潰れる(圧潰)と急激に強い痛みが出現し、歩行が困難になることもあります。
変形性股関節症と異なり、比較的急速に進行することが特徴です。
筋肉・腱の炎症(腱付着部炎、滑液包炎)
股関節の周囲には多くの筋肉が付着しており、その付着部(腱)や、筋肉と骨の間にある滑液包(摩擦を減らす袋状の組織)が炎症を起こすことがあります。
例えば、太ももの外側、大転子と呼ばれる骨の出っ張り部分が痛む場合は「大転子部痛症候群(滑液包炎など)」が考えられます。
使いすぎや柔軟性の低下が原因となることが多いです。
股関節疾患と痛みの特徴の比較
| 疾患名 | 主な痛みの場所 | 特徴的な症状 |
|---|---|---|
| 変形性股関節症 | 脚の付け根(前側)、お尻 | 歩き始めの痛み、可動域制限(あぐら、爪切り困難) |
| FAI | 脚の付け根(前側) | 股関節を深く曲げた時の詰まるような痛み |
| 大腿骨頭壊死症 | 脚の付け根、お尻、膝 | 急激に発症・悪化することがある、安静時痛 |
股関節以外の太ももの痛みの原因
太ももが痛む場合、股関節ではなく、腰や他の神経、筋肉が原因であることも少なくありません。
股関節の動き自体には問題がないのに痛む場合は、これらの原因も調べる必要があります。
腰椎(腰)由来の問題
腰椎椎間板ヘルニアや腰部脊柱管狭窄症など、腰椎で神経の根本が圧迫されると、その神経が支配する領域(お尻、太もも、すね、足)に痛みやしびれが出ます。
これは「関連痛」や「放散痛」と呼ばれます。
股関節を動かしても痛みはあまり変わらず、むしろ腰を反らしたり、前かがみになったり、長時間立っていたりすると症状が悪化することが特徴です。
一般に「坐骨神経痛」と呼ばれる症状の多くは、この腰椎由来です。
筋肉・筋膜性の痛み
特定の筋肉が硬くなったり、筋肉を包む「筋膜」がこわばったりすることで、痛みを引き起こすことがあります(筋膜性疼痛症候群)。
硬くなった筋肉の中に「トリガーポイント」と呼ばれるしこりのようなものができ、そこを押すと痛むだけでなく、離れた場所(関連痛領域)にも痛みが響くことがあります。
例えば、お尻の中殿筋や梨状筋のトリガーポイントが、太ももの外側や裏側に痛みを引き起こすことがあります。
末梢神経障害
腰椎の根本ではなく、神経が末梢(手足に近い部分)で圧迫されたり、障害されたりして痛むこともあります。
太ももの前側から外側にかけてピリピリとした痛みや感覚異常が出る場合は「外側大腿皮神経痛(がいそくだいたいひしんけいつう)」が考えられます。
これは、骨盤の前側で神経が圧迫されて生じることが多く、きつい下着やベルト、肥満などが誘因となることがあります。
股関節痛と腰椎由来の痛みの見分け方(目安)
| 項目 | 股関節由来が疑われる場合 | 腰椎由来が疑われる場合 |
|---|---|---|
| 痛みが強まる動作 | 歩行、階段、あぐら、靴下履き | 長時間の立位・座位、腰を反らす、前屈み |
| 主な症状の範囲 | 脚の付け根、太もも前面・内側 | お尻、太もも裏側、すね、足(しびれ伴う) |
| 股関節の動き | 動きが悪い(可動域制限) | 動きは正常なことが多い |
自宅でできる初期対処法とセルフケア
痛みが強い場合や続く場合は医療機関の受診が原則ですが、症状が比較的軽い場合や、慢性的な痛みと付き合っていく上では、ご自宅でのセルフケアも大切です。
ただし、自己判断で無理に行うと悪化することもあるため、注意して行いましょう。
安静と活動のバランス
痛みが出始めた初期や、炎症が強いと思われる時期(ズキズキ痛む、熱感がある)は、まず安静を心がけ、痛みの出る動作を避けることが重要です。
しかし、痛みが少し落ち着いてきたら、過度な安静は逆効果になることもあります。
関節が固まったり、筋力が低下したりするのを防ぐため、痛みのない範囲で股関節を動かしたり、軽い運動(プール歩行など)を取り入れたりするなど、活動とのバランスを取ることが大切です。
冷却(アイシング)と温熱(温め)の使い分け
急性期(痛めた直後、熱感や腫れがある)は、炎症を抑えるために冷却(アイシング)が有効です。氷のうなどをタオルで包み、1回15分から20分程度、痛む部分を冷やします。
一方、慢性的な痛み(痛みが長引いている、筋肉がこわばっている)の場合は、温める(温熱)ことで血流が良くなり、筋肉の緊張がほぐれて痛みが和らぐことがあります。
入浴やホットパックなどで心地よい程度に温めましょう。
冷却と温熱の使い分け目安
| 冷却(アイシング) | 温熱(温め) | |
|---|---|---|
| 適した時期 | 急性期(痛めた直後、腫れ・熱感がある) | 慢性期(痛みが長引いている、筋肉がこわばっている) |
| 主な目的 | 炎症を抑える、痛みを鎮める | 血流促進、筋肉の緊張緩和、痛みの緩和 |
| 注意点 | 冷やしすぎによる凍傷に注意 | 炎症が強い時は悪化させる可能性あり |
股関節周辺のストレッチ
股関節の痛みの原因が、周囲の筋肉の硬さにある場合、ストレッチが有効なことがあります。
特にお尻(中殿筋、梨状筋)、太ももの裏(ハムストリングス)、太ももの前(大腿四頭筋)などの筋肉を、痛みが出ない範囲でゆっくりと伸ばします。
ただし、変形性股関節症が進行している場合など、特定の動作が関節に負担をかけることもあります。ストレッチ中に痛みが増すようであれば、すぐに中止してください。
日常生活での注意点
日々の暮らしの中で、股関節に負担をかけない工夫をすることも重要です。意識を変えるだけで、痛みの予防や悪化防止につながります。
股関節に負担をかける動作と代替案
| 負担をかける動作 | 推奨される動作・工夫 |
|---|---|
| 床に座る(あぐら、正座、横座り) | 椅子やソファでの生活を基本にする。 |
| 深いソファや低い椅子からの立ち座り | 適切な高さの椅子を選び、手すりなどを使って立ち座りする。 |
| 重い物を持ち運ぶ | 荷物を小分けにする、カートを利用する。 |
また、体重管理も非常に重要です。体重が増えると、歩行時に股関節にかかる負担は何倍にもなります。
肥満傾向にある場合は、適度な運動と食生活の見直しによって体重をコントロールすることが、股関節の保護につながります。
医療機関を受診する目安
太ももや股関節の痛みが続く場合、自己判断での対処には限界があります。
適切な診断と治療を受けるためにも、以下のような症状が見られる場合は、早めに整形外科などの医療機関を受診することを推奨します。
急激な激しい痛みや腫れがある場合
転倒などの怪我の後に強い痛みが出た場合、骨折(大腿骨頸部骨折など)の可能性があります。
また、明らかな原因がなくとも、急に激しい痛みで動けなくなった場合、大腿骨頭壊死症の圧潰や、化膿性股関節炎(感染)などの重篤な状態も考えられます。
このような場合は、速やかな受診が必要です。
歩行が困難になった場合
痛みのために体重がかけられず、杖を使わないと歩けない、あるいは全く歩けなくなった場合は、関節の状態がかなり悪化している可能性があります。
日常生活に大きな支障が出ているため、専門家による診断が求められます。
安静にしていても痛みが続く場合
動作時だけでなく、じっとしていても痛む(安静時痛)や、夜間に痛みで目が覚める(夜間痛)場合は、関節内の炎症が強いことや、悪性腫瘍など他の疾患の可能性もゼロではありません。
痛みが持続する場合は、一度検査を受けることが賢明です。
しびれや脱力感を伴う場合
太ももや脚に力が入らない、感覚が鈍い、強いしびれが広範囲にあるといった症状は、腰椎での重度な神経圧迫などが考えられます。
神経障害が進行すると回復が難しくなることもあるため、早期の対応が大切です。
医療機関で行う検査と診断
医療機関では、痛みの原因を正確に突き止めるために、様々な検査を行います。問診から始まり、画像検査などを組み合わせて総合的に診断します。
問診と身体所見(視診・触診・徒手検査)
まず、医師が患者さんの話を詳しく聞きます(問診)。
いつから痛むか、どこが痛むか、どのような時に痛むか、過去の病歴や怪我、現在の生活習慣など、詳細な情報が診断の手がかりとなります。
その後、歩き方(視診)、痛む場所や筋肉の状態を押して確認(触診)、医師が患者さんの股関節を動かして可動域や痛みの出方を調べる(徒手検査)など、身体所見を取ります。
画像検査(レントゲン・MRI・CT)
痛みの原因を視覚的に評価するために、画像検査は非常に重要です。レントゲン(X線)検査は、骨の変形や関節の隙間(軟骨の厚み)を評価する基本的な検査です。
MRI検査は、レントゲンでは映らない軟骨、関節唇、筋肉、腱、神経などの軟部組織の状態や、大腿骨頭壊死の早期発見に優れています。
CT検査は、骨の立体的な形状や骨折の詳細な評価に用いられます。
主な画像検査の役割
| 検査方法 | 主な評価対象 | 特徴 |
|---|---|---|
| レントゲン (X線) | 骨の形状、関節の隙間 | 基本的な検査。骨の変形や軟骨のすり減り具合を大まかに把握。 |
| MRI | 軟骨、関節唇、筋肉、腱、神経、骨の内部 | 軟部組織の評価に優れる。初期の骨壊死や関節唇損傷の診断に有効。 |
| CT | 骨の立体構造、骨折 | 骨の詳細な形状把握や、複雑な骨折の評価に適している。 |
超音波(エコー)検査
超音波(エコー)検査は、リアルタイムで筋肉や腱、滑液包などの状態を観察できる検査です。炎症による腫れや水が溜まっている様子、腱の損傷などを評価するのに役立ちます。
診察室で簡単に行える利点があります。
血液検査や関節液検査
関節リウマチや他の膠原病、感染症などが疑われる場合には、血液検査を行います。
また、股関節に水(関節液)が溜まっている場合、注射で関節液を採取して調べる(関節液検査)ことで、感染の有無や結晶(痛風など)の存在を確認することがあります。
股関節の痛みに対する専門的な治療法
検査によって診断が確定したら、その原因と重症度、患者さんの年齢や活動レベルに応じて治療方針を決定します。
治療法は、大きく「保存療法」と「手術療法」に分けられます。
保存療法(薬物療法・リハビリテーション)
多くの場合、まずは手術を行わない保存療法から開始します。リハビリテーション(運動療法)は、保存療法の中心となります。
股関節周囲の筋力(特に中殿筋などの支える筋肉)を強化したり、硬くなった筋肉の柔軟性を改善したりすることで、股関節への負担を減らし、痛みの軽減と機能の改善を目指します。
専門家の指導のもと、正しい運動を継続することが重要です。
保存療法で用いる主な薬剤
| 薬剤の種類 | 主な目的 | 形態 |
|---|---|---|
| 非ステロイド性抗炎症薬 (NSAIDs) | 炎症を抑え、痛みを和らげる | 内服薬、外用薬(湿布・塗り薬) |
| アセトアミノフェン | 痛みを和らげる(鎮痛) | 内服薬 |
| 神経障害性疼痛治療薬 | 神経の圧迫などによるしびれや痛みを緩和 | 内服薬 |
薬物療法は、これらの痛みをコントロールするために補助的に用います。内服薬のほか、湿布や塗り薬などの外用薬も使用します。
注射療法
痛みが強い場合や、内服薬などでのコントロールが難しい場合、関節内に直接薬剤を注射する治療法も選択肢となります。
炎症を強力に抑える「ステロイド」や、関節の滑りを良くし炎症を抑える「ヒアルロン酸」などを注射することがあります。
ただし、これらの効果は一時的な場合もあり、根本的な解決にはならないことも理解しておく必要があります。
手術療法
保存療法を十分に行っても痛みが改善しない場合や、変形や損傷が進行し日常生活に著しい支障が出ている場合には、手術療法を検討します。
どのような手術を選択するかは、疾患の種類や進行度、年齢などによって異なります。
- 関節鏡視下手術
- 骨切り術
- 人工股関節置換術
関節鏡視下手術は、FAIや関節唇損傷などに対して行われる比較的負担の少ない手術です。
骨切り術は、臼蓋形成不全などで関節の形状を整え、軟骨への負担を減らす目的で、比較的若年層に行われることがあります。
人工股関節置換術は、変形性股関節症や大腿骨頭壊死症が進行し、関節が著しく損傷した場合に行われる手術で、痛みの除去と機能の回復に高い効果が期待できます。
よくある質問
ここでは、太ももや股関節の痛みに関して多く寄せられる質問にお答えします。
Q. 痛い時は歩かない方が良いですか?
痛みが非常に強い急性期や、腫れ・熱感がある場合は、安静にして痛む動作を避けることが優先されます。
しかし、痛みが慢性化している場合や、変形性股関節症の初期段階などでは、過度な安静は逆に関節を支える筋力を低下させ、関節を硬くしてしまう可能性があります。
痛みのない範囲、あるいは多少痛んでも後で悪化しない程度の軽い運動(水中ウォーキングやエアロバイクなど、関節に負担の少ないもの)は、筋力維持や血流改善のために推奨されることもあります。
痛みの程度に応じて、活動のバランスを取ることが大切です。
Q. どのような寝方が股関節に良いですか?
一般的に、股関節に最も負担が少ないのは仰向けで寝る姿勢とされます。膝の下にクッションや丸めたタオルを入れると、股関節や腰がリラックスしやすくなります。
横向きで寝る場合は、痛い方を上にするのが基本ですが、上にした脚が前に倒れて股関節がねじれないよう、膝の間にクッションや抱き枕を挟むと良いでしょう。
うつ伏せは腰や股関節に負担がかかることがあるため、避けた方が無難かもしれません。ご自身が最も楽に感じる姿勢を探してみてください。
Q. 自分でマッサージをしても大丈夫ですか?
お尻や太ももの筋肉が硬くなって痛みが出ている場合、セルフマッサージやストレッチで筋肉をほぐすことが症状緩和に役立つことがあります。
テニスボールなどを使って、お尻の外側などを心地よい強さで圧迫するのも一つの方法です。
ただし、関節自体に強い炎症がある場合や、神経を圧迫している可能性がある場合に、強く揉んだり押したりすると症状が悪化することがあります。
痛みが増すようであればすぐに中止し、専門家に相談してください。
Q. 痛みの予防のために何をすべきですか?
股関節の痛みを予防・悪化させないためには、日常生活での継続的なケアが重要です。
第一に、適正体重の維持です。体重が増えると股関節への負担が直接的に増加するため、体重管理は非常に効果的な予防策となります。
第二に、適度な運動習慣です。ウォーキングや水泳など、股関節に過度な負担をかけずに周囲の筋力を維持・強化する運動を続けることが大切です。
第三に、股関節に負担をかける生活習慣(床での生活、深い椅子からの立ち座りなど)を見直すことです。これらの地道な取り組みが、股関節の健康を長く保つことにつながります。
参考文献
TIBOR, Lisa M.; SEKIYA, Jon K. Differential diagnosis of pain around the hip joint. Arthroscopy: The Journal of Arthroscopic & Related Surgery, 2008, 24.12: 1407-1421.
CHAMBERLAIN, Rachel. Hip pain in adults: evaluation and differential diagnosis. American family physician, 2021, 103.2: 81-89.
BUSCONI, Brian D.; OWENS, Brett D. Differential diagnosis of the painful hip. In: Early Hip Disorders: Advances in Detection and Minimally Invasive Treatment. New York, NY: Springer New York, 2003. p. 7-15.
FEINBERG, Joseph H. Hip pain: differential diagnosis. Journal of Back and Musculoskeletal Rehabilitation, 1994, 4.3: 154-173.
GEHRET, Jeffrey A.; FREEDMAN, M. K.; SHER, L. Low back vs. hip pain: how to decide. Pract Neurol, 2008, 12-15.
SEALY, David. Additional Differential Diagnosis for Adult Hip Pain. American Family Physician, 2021, 104.1: 9-9.
BATTAGLIA, Patrick J.; D’ANGELO, Kevin; KETTNER, Norman W. Posterior, lateral, and anterior hip pain due to musculoskeletal origin: a narrative literature review of history, physical examination, and diagnostic imaging. Journal of chiropractic medicine, 2016, 15.4: 281-293.
HAMMER, Warren I. The hip and thigh. Functional Soft Tissue Examination and Treatment by Manual Methods: New Perspectives, 1999, 213.
PLANTE, Matthew; WALLACE, Roxanne; BUSCONI, Brian D. Clinical diagnosis of hip pain. Clinics in sports medicine, 2011, 30.2: 225-238.
BROWN, Mark D., et al. Differential diagnosis of hip disease versus spine disease. Clinical Orthopaedics and Related Research (1976-2007), 2004, 419: 280-284.
Symptoms 症状から探す