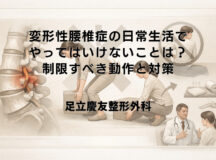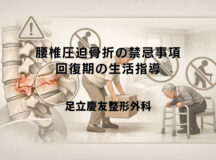膝が痛いと感じるときの原因や治療の流れ日常でできる対策を学ぶ
年齢を重ねると多いとされる膝の痛みは、日常生活に支障をきたすほど深刻になりやすい症状です。
スポーツによる急性のけがや慢性的な使いすぎでも痛みが生じ、原因は多岐にわたります。大切なのは痛みの原因を知り、適切な治療やケアを行うことです。
本記事では、膝が痛いと感じたときに考えられる主な原因や治療の流れ、日常で取り組める対策を解説し、痛みの進行を防ぐヒントをお伝えします。
目次
膝の痛みが起こるメカニズム
膝の痛みは、膝関節にかかる負担が大きいときや、軟骨・骨・筋肉・靭帯・腱などの組織に異常が生じたときに起こります。
人間は歩行や階段の上り下りなど日常的に膝関節を使用するため、日頃から適度な運動やケアを行わないと変形が進みやすいといわれています。
まずは膝が痛いときの基礎的なメカニズムを理解することが重要です。
膝関節の構造
膝関節は大腿骨、脛骨、膝蓋骨がかみ合って形成されています。これらの骨の間には軟骨があり、クッションの役割を果たしています。
さらに、大腿四頭筋や太ももの裏側の筋肉、足側の筋肉とのバランスによって膝の曲げ伸ばしがスムーズに行えるようになっています。
膝が痛いと感じるときは、関節そのものだけでなく周囲の筋肉や腱にも注意が必要です。
膝の構成要素一覧
| 骨の名称 | 位置や役割 |
|---|---|
| 大腿骨 | 太ももの部分。膝関節の上側を構成する主要な骨 |
| 脛骨 | すねの骨。膝関節の下側で体重を支える重要な骨 |
| 膝蓋骨 | いわゆる「お皿」と呼ばれる骨 |
膝関節には半月板などの組織もあり、関節を安定させる役割を担います。半月板損傷が起こると強い痛みや引っかかり感が出やすいので、膝が痛い場合はそのあたりも含め診断が必要です。
軟骨と骨の関係
膝関節の軟骨は、骨同士が直接こすれないようにするための柔らかい組織です。
運動や加齢によってすり減った軟骨が痛みの原因となりやすく、変形性膝関節症では軟骨の摩耗が進むことでさらに炎症や腫れが生じる場合があります。
適切な食事で軟骨に良い栄養を摂取し、適度な運動で筋力を維持することが重要です。
過度に負担をかけると軟骨が傷つきやすくなるので、膝が痛いと感じたら早めに専門の医師に相談するとよいでしょう。
筋肉や腱の役割
膝関節周りの筋肉(大腿四頭筋、ハムストリング、内転筋など)は、関節を支え、曲げ伸ばしの動作をサポートします。腱は筋肉の力を骨に伝達し、膝が安定して動くために欠かせない組織です。
筋力が低下すると膝関節への負担が増え、痛みが起こるリスクが高まります。
- ふだん運動不足の人
- 中高年で筋力低下が進んでいる人
- 長時間同じ姿勢をとる仕事が多い人
こういった方々は、筋力維持を心がけることが大切です。
痛みの信号が伝わる仕組み
膝関節や周囲の組織に炎症や損傷があると、痛みの信号は神経を通じて脳へと伝わります。痛みを感じるときは、炎症が強くなったり腫れを伴ったりすることも多いです。
特にランナーやスポーツ選手の中には、腸脛靭帯炎(ランナー膝)などによる外側の痛みに悩む人もいます。
膝が痛いときに考えられる原因
膝の痛みには、急性・慢性を問わず多彩な原因があります。
スポーツ中の外傷だけでなく、長期間の使いすぎによっても変形や炎症が起こりやすくなるため、何が原因なのか整理することが大切です。
急性のケガによる痛み
急性のケガによる痛みは、主に外部から大きな力が加わったときに生じることが多いです。代表例としては、骨折や靭帯断裂、半月板損傷などがあります。
- 転倒や衝突などで膝を強打
- スポーツで急な捻転や衝撃を受ける
- 階段から足を踏み外してしまう
こうした場合は痛みが急に生じ、腫れや内出血を伴うことも多いです。放置すると重症化の恐れがあるので、膝が痛いときは早めの受診を考えましょう。
慢性的な変形や疾患
変形性膝関節症のように、軟骨がすり減って変形が生じる病気は中高年に多い傾向があります。体重が膝関節にかかり続けると、骨同士が摩擦を起こしやすくなり痛みが増す可能性があります。
このような慢性疾患は、ある程度進行して初めて症状が出ることもあるため要注意です。
慢性的な変形の要因
| 要因 | 具体例 |
|---|---|
| 加齢 | 軟骨が自然にすり減り、関節が変形して痛みが出る |
| O脚やX脚などの脚のアライメント異常 | 膝の内側や外側に偏った負担がかかる |
| 過体重 | 膝関節にかかる負荷が大きくなる |
加齢による変形は誰にでも起こり得るため、早めの予防とケアが重要といえます。
スポーツによる負担
スポーツによる膝の痛みは、使いすぎ(オーバーユース)や繰り返しの動作によって引き起こされることが多いです。
ランナー膝(腸脛靭帯炎)やジャンパー膝(大腿四頭筋腱炎・膝蓋腱炎)、オスグッド病などは若い世代にも多くみられます。
- ランニングを長距離・長時間継続する
- ジャンプ動作の多いスポーツを頻繁に行う
- 急にトレーニングの負荷を上げる
こうした状況下で炎症や痛みが出る場合は、運動量や方法を見直すことが必要です。
老化による膝関節の変性
加齢で膝が痛いケースでは、関節周辺の組織が衰え、軟骨がすり減ることで慢性的な痛みにつながります。また、筋肉や腱の柔軟性が失われ、動きがぎこちなくなることも原因のひとつです。
一定の年齢を過ぎると腰や股関節の動きにも影響が及ぶことがあり、膝だけでなく全身のバランスを整える必要があります。
膝の痛みに関連する代表的な病気
膝が痛いときは、原因となる病気を正確に把握して適切な治療につなげることが大切です。多くの患者が抱える代表的な疾患を知り、早めに対処するよう心がけましょう。
変形性膝関節症
変形性膝関節症は、加齢や体重増加などによって軟骨がすり減り、関節に変形が生じる病気です。
初期は「朝起きると膝が痛い」「階段を下りるときに痛む」といった症状から始まり、進行すると常に痛みを感じるようになります。
ヒアルロン酸注射などの治療法があり、痛みが強いときは手術を検討することもあります。
変形性膝関節症の特徴
| 症状の段階 | 主な特徴 |
|---|---|
| 初期 | 動き始めに痛む、休むと症状が治まる |
| 中期 | 膝の内側や外側に強い痛み、腫れが出る |
| 進行した段階 | 軟骨が大きくすり減り、常時痛みを感じやすい |
痛みを軽減し、進行を抑えるためには早期の診断とケアが大切です。
半月板損傷
半月板は膝関節の大腿骨と脛骨の間にあり、衝撃を吸収するクッションの役割を持ちます。
スポーツ中のけがや加齢による変性によって損傷が起こりやすく、膝を曲げ伸ばしすると痛む、引っかかり感があるといった症状が特徴です。損傷の程度によっては手術が必要になる場合もあります。
靭帯損傷
膝には前十字靱帯や後十字靱帯など、関節を安定させる強力な靭帯があります。
靭帯損傷は急激に大きな力がかかったときなどに発生し、膝に激しい痛みや腫れが生じます。靱帯が伸ばされるだけで済む場合もあれば、断裂してしまうケースもあります。
診断と治療を適切に行わないと膝関節に長期的な不安定感が残るおそれがあります。
膝蓋骨周辺のトラブル
膝蓋骨(お皿)周辺には、膝蓋腱や膝蓋骨の軟骨などが存在し、ジャンパー膝(膝蓋腱炎)、膝蓋軟骨軟化症などの病気が生じることがあります。
膝の前部や周辺が痛いときには、膝蓋骨の位置や周囲の組織を整形外科でチェックしてもらうことが必要です。
受診の目安と検査方法
膝が痛いと感じても、「痛みがすぐ治まるから大丈夫」と放置していると、症状が悪化し、歩くのが困難になることもあります。
症状が長引いたり強くなったりした場合は、整形外科で診察を受け、原因をはっきりさせることが大切です。
病院を受診するタイミング
- 痛みが2週間以上続いている
- 腫れや熱感があり、安静にしても軽減しない
- 膝に違和感があり、歩行や階段の上り下りがつらい
- 関節がゴリゴリとした感じや音を伴う
このような状態がみられる場合は早めに病院に行うほうがよいでしょう。整形外科で診療を受けることで、レントゲンやMRIなどの検査を通して病気の有無や進行度をチェックできます。
レントゲン検査の意義
レントゲン検査では骨や関節の隙間の状態を見ることができます。変形性膝関節症や骨折、O脚・X脚などのアライメント異常があるかどうかを簡易的に確認できます。
しかし、靭帯や半月板などの軟部組織は写らないため、必要に応じてMRI検査などを追加します。
代表的な検査の特徴
| 検査方法 | 特徴 |
|---|---|
| レントゲン | 骨折や変形の有無がわかる |
| MRI | 軟骨・靭帯・半月板などの軟部組織を詳細に確認できる |
| 血液検査 | 関節リウマチや痛風など、炎症や代謝異常を調べる |
画像検査だけでは判断がつかないケースもあるため、医師の触診や問診も含め総合的に診断します。
MRIや血液検査の役割
MRIは靭帯や半月板、軟骨の状態を詳しく調べられます。半月板損傷や靭帯断裂など、レントゲンだけではわかりにくい膝の痛みの原因を特定するのに役立ちます。
血液検査ではリウマチや痛風など炎症が関わる病気を調べることができます。痛みが長引く場合や原因不明の腫れがある場合は、血液検査が必要になることも多いです。
整形外科での診察の流れ
整形外科では、問診・視診・触診を行いながら、必要に応じてレントゲンやMRIなどの検査を組み合わせて診断を進めます。
膝が痛い原因が特定できれば、病気の種類や状態に合わせた治療計画を立てられます。治療計画には注射や運動療法、手術が含まれる場合もあるため、不安な点はしっかり相談しましょう。
主な治療方法
膝の痛みを治療するためには、保存療法から手術療法までさまざまな方法があります。
痛みの程度や原因となっている疾患によって選択肢が異なるため、医師と相談しながら自分に合った治療を進めてください。
保存療法(安静・装具・注射)
保存療法では安静を保ち、炎症や腫れが治まるのを待ちながら装具で膝をサポートする方法がよく行われます。
変形性膝関節症ではヒアルロン酸やステロイド注射で関節の動きを滑らかにし、痛みや炎症を抑えることが期待できます。鵞足炎などの炎症の場合は局所注射で早期の改善を図ることもあります。
保存療法で用いられる手段
| 手段 | 目的 |
|---|---|
| 安静 | 膝への負担を減らし、炎症を落ち着かせる |
| サポーター装着 | 関節の安定を補助し、痛みを軽減する |
| 注射(薬剤注入) | ヒアルロン酸やステロイドで炎症や痛みを抑える |
炎症が強いときは安静期間を十分に設けることが重要です。
運動療法とリハビリ
膝を動かさずにいると筋力が低下し、かえって痛みが長引きやすくなる場合があります。
専門家の指導のもと、大腿四頭筋などの筋力を強化したり、柔軟性を高めたりする運動療法を行うと症状が軽減しやすいです。
リハビリでは痛みがある程度改善した段階で、階段をスムーズに昇降できるように練習するなど実践的なメニューを行うこともあります。
- 膝を大きく曲げ伸ばしする前に軽いストレッチをする
- 痛みが少しでも出たら、無理をせず動作を中断する
- 腰や股関節の動きも同時に改善を目指す
適度な運動を継続しながら、体重コントロールも意識すると効果を高められます。
手術療法が必要な場合
骨折や靭帯断裂、重度の変形性膝関節症などで保存療法では改善が難しい場合は手術が検討されます。
人工関節置換術、骨切り術、靭帯再建術など、病気の種類や進行度に応じて方法が異なります。手術後はリハビリを行い、正しく膝を動かしていくことが重要です。
薬物治療の選択肢
痛みが強いときや炎症がひどい場合は、消炎鎮痛剤(NSAIDs)や筋弛緩剤などの薬を使用することがあります。
整形外科医と相談しながら服用することで、膝の痛みを和らげて日常生活を送りやすくすることができます。
長期にわたる服用は副作用のリスクもあるため、定期的に受診しながら薬の調整を行うことが大切です。
日常生活でできるケアとストレッチ
膝が痛いときには、治療だけでなく日常でのケアが重要になります。普段の生活習慣を見直し、適度な運動やストレッチを取り入れることで、痛みの軽減や再発予防につながります。
膝にやさしい歩行や姿勢
膝への負担を減らすために、正しい姿勢と歩行を意識してください。背筋を伸ばし、足を真っ直ぐ前に出すように意識すると、膝が外側や内側に傾きにくくなります。
O脚やX脚がある場合は、インソールやサポーターなども役立ちます。
姿勢チェックのポイント
| チェック項目 | 注意点 |
|---|---|
| 立った時の足の向き | つま先が外や内に極端に向いていないか |
| 歩くときの重心 | 体が左右に揺れすぎていないか |
| 座るときの姿勢 | 膝をねじっていないか、深く座りすぎていないか |
歩くときには、痛みがある場合は杖を使用するのも選択肢です。
筋力維持のための運動
膝が痛いと感じる方こそ、適度な筋力トレーニングが必要です。大腿四頭筋を含めた下肢全体の筋力を高めることで、膝関節への負担を軽減できます。
水中ウォーキングや軽めのスクワットなど、衝撃が少ない運動がおすすめです。痛む範囲を無理に曲げず、少しずつ運動量を増やしてください。
- ウォーキングは平坦な道をゆっくり行う
- 筋力トレーニングは回数よりも正しいフォームを重視する
- 運動前後にはストレッチを行う
腰や足首の柔軟性も高めると動きに安定感が増します。
自宅で試せるストレッチ
ストレッチは膝周りの筋肉や腱を柔らかくし、血流を良くする方法として有効です。膝の内側が痛い、外側が痛いなど部位によって伸ばす場所を変えるとより効果的です。
座った状態や仰向けの状態でゆっくり行うと安全に取り組めます。
- 太ももの前側を伸ばす(大腿四頭筋ストレッチ)
- 太ももの後ろを伸ばす(ハムストリングストレッチ)
- すねやふくらはぎなど足首周りも意識する
痛みを感じるときは無理に引っ張りすぎないことが大切です。
自宅で行いやすい簡易ストレッチ
| 部位 | 方法 |
|---|---|
| 大腿前面 | 片脚を後ろに曲げ、足首を手でつかんで大腿四頭筋を伸ばす |
| 膝の内側 | 椅子に座り、片膝を外側に軽く開いてからゆっくり内転筋を伸ばす |
| 膝の外側 | 横向きに寝そべり、上側の脚を後ろに曲げながら腸脛靭帯や大腿外側を伸ばす |
痛みが強いときは医師や理学療法士に相談してください。
痛みを軽減するサポートグッズ
痛みが出ているときは、膝をサポートする道具を活用すると負担が減ります。たとえば、サポーターやテーピング、クッション性に優れたインソールなどです。
上手に利用して膝の不安定感を減らすと、日常生活でも活動しやすくなります。
膝痛が改善しにくいと感じたとき
治療やケアを続けていても症状がなかなか良くならない場合は、膝以外の要因や病気の進行度を考える必要があります。
気になる症状が続くなら、早めの再診やセカンドオピニオンを検討してください。
他の関節との関連
膝の痛みだけでなく、腰や股関節、足首の動きにも問題があると、膝関節に余計な負担がかかることがあります。
肩こりや腰痛を同時に抱えている人は、全身のバランスを整えることを意識してください。
- 長時間のパソコン作業で姿勢が悪くなっていないか
- 片脚に体重をかける癖はないか
- 普段の歩き方や立ち方で左右差が大きくないか
膝を含めた全身の動きを医師や理学療法士にチェックしてもらうのも有効です。
進行を防ぐ考え方
変形性膝関節症などは一度発症すると、放っておくと進行する可能性があります。軽度のうちに治療を始め、負担の少ない運動で筋力を維持することが重要です。
炎症を繰り返すほど関節組織がすり減りやすくなるので、痛みがあるときには早めのケアを心がけましょう。
痛みが長引く場合に考慮する点
| 可能性 | 具体例 |
|---|---|
| 病気が進行している | 軟骨の摩耗が進み、痛みが強くなる |
| 他の疾患が隠れている | 関節リウマチや痛風など、膝以外の病気が潜んでいる |
| リハビリが不十分 | 筋力強化や柔軟性向上の運動が継続できていない |
状態に合わせて適切なタイミングで再診を受けることが大切です。
早期受診が大切な理由
痛みが続くということは、何らかの炎症や軟骨の変性が進んでいるサインでもあります。
膝が痛い状態を無理して放置すると、日常生活に大きな支障をきたし、最終的には手術が必要になることもあります。
早めに受診すれば、比較的軽い負担の治療法で改善が見込めるケースが多いです。
セカンドオピニオンの活用
治療方針に迷いがある場合や、ほかに改善策がないか探りたいときは、別の医師の意見を聞くことも一つの方法です。
セカンドオピニオンを通じて新たなアプローチを見つけたり、自分の疾患についてより理解を深めたりできます。
変形が進行しているように見えても、運動療法で効果を上げる場合もあるため、柔軟に検討しましょう。
膝の痛みと向き合うために大切なこと
膝の痛みは人によって原因や症状、進行度が異なります。自分の状態をしっかり把握し、適切な治療やケアを続けることが痛みの軽減と再発予防につながります。
日頃からのチェックが必要
膝の痛みは突然始まることもあれば、長期的にじわじわと進むこともあります。気づかないうちに変形が進行しているケースもあるため、普段から身体の声に耳を傾けることが大切です。
- 朝起きたときに膝が痛むか
- 長時間座った後に立ち上がるときの痛みはどうか
- 同じ動作を繰り返したときに炎症が起きていないか
小さなサインを見逃さず、痛みが続くようなら早めに整形外科で診断を受けましょう。
適度な運動を続ける意義
膝が痛いと安静にしがちですが、まったく動かさないと筋力や柔軟性が低下して逆効果となる場合があります。
リハビリやトレーニングを通じて、大腿四頭筋や周囲の筋肉を鍛えたりストレッチしたりすることは、痛みの緩和だけでなく再発予防にもつながります。
ただし、無理をすると炎症が悪化するため、医師の指導のもと少しずつ行うと良いです。
運動を継続するための工夫
| 工夫 | 具体的な例 |
|---|---|
| スケジュール化 | 週に2~3回、決めた曜日と時間にトレーニングする |
| モチベーションを保つ | 一緒に運動する仲間をつくる |
| 小さな目標を設定 | 5分~10分の軽い運動から始めて達成感を得る |
運動を習慣化することで膝の痛みが改善するだけでなく、体重管理にも役立つことがあります。
痛みと上手につきあう工夫
膝の痛みをゼロにすることが難しい場合でも、上手につきあっていくことで日常生活の質を保てます。
サポーターやテーピングで補強しながら、痛みが少ない範囲で動作を行うなど、工夫を重ねてください。痛いと感じたら早めに休むことも大切です。
- 仕事や家事の合間に軽いストレッチを挟む
- こまめに体重をコントロールし、膝への負担を軽減する
- 立ち仕事が多い人は適度に休憩を取り、足腰をリラックスさせる
痛みを無理に我慢せず、上手にペース配分を考えながら生活しましょう。
病院との連携で適切な治療へ
継続的な治療やリハビリが必要な場合は、定期的に病院を訪れて経過を確認してもらうことが重要です。
症状に応じた注射や運動療法、あるいは手術など、多様な選択肢をタイミングよく適用することで改善が期待できます。
医師や理学療法士、看護師などと連携しながら、自分に合った治療計画を立てていきましょう。
参考文献
MURAKI, Shigeyuki, et al. Incidence and risk factors for radiographic knee osteoarthritis and knee pain in Japanese men and women: A longitudinal population‐based cohort study. Arthritis & Rheumatism, 2012, 64.5: 1447-1456.
MURAKI, S., et al. Prevalence of radiographic knee osteoarthritis and its association with knee pain in the elderly of Japanese population-based cohorts: the ROAD study. Osteoarthritis and cartilage, 2009, 17.9: 1137-1143.
FUJII, Tomoko, et al. Disability due to knee pain and somatising tendency in Japanese adults. BMC Musculoskeletal Disorders, 2018, 19: 1-8.
MURAKI, Shigeyuki, et al. Quadriceps muscle strength, radiographic knee osteoarthritis and knee pain: the ROAD study. BMC musculoskeletal disorders, 2015, 16: 1-10.
MURAKI, Shigeyuki, et al. Prevalence of falls and the association with knee osteoarthritis and lumbar spondylosis as well as knee and lower back pain in Japanese men and women. Arthritis care & research, 2011, 63.10: 1425-1431.
AKAI, Masami, et al. An outcome measure for Japanese people with knee osteoarthritis. The Journal of rheumatology, 2005, 32.8: 1524-1532.
MURAKI, S., et al. Association of radiographic and symptomatic knee osteoarthritis with health-related quality of life in a population-based cohort study in Japan: the ROAD study. Osteoarthritis and cartilage, 2010, 18.9: 1227-1234.
UCHIO, Yuji, et al. A randomized, double-blind, placebo-controlled Phase III trial of duloxetine in Japanese patients with knee pain due to osteoarthritis. Journal of pain research, 2018, 809-821.
SUDO, Akihiro, et al. Prevalence and risk factors for knee osteoarthritis in elderly Japanese men and women. Journal of Orthopaedic Science, 2008, 13.5: 413-418.
KITO, Nobuhiro, et al. Contribution of knee adduction moment impulse to pain and disability in Japanese women with medial knee osteoarthritis. Clinical Biomechanics, 2010, 25.9: 914-919.
Symptoms 症状から探す