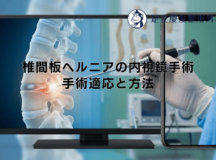なぜぎっくり腰は起こるのか?原因とメカニズム
突然腰に激痛が走り、その場から動けなくなるような経験をしたことはありませんか?それが俗に言う「ぎっくり腰」です。
ぎっくり腰は多くの人が経験する身近な腰痛ですが、その原因やメカニズムについては意外と知られていません。
本記事では、ぎっくり腰がなぜ起こるのかをわかりやすく解説し、主な原因や腰椎の構造上の仕組み、さらに予防策や対処法についてご紹介します。
腰痛に悩む方やぎっくり腰を予防したい方にとって役立つ情報が満載です。
目次
ぎっくり腰とは?
ぎっくり腰とは、一度は耳にしたことがある方も多いでしょう。まず初めに、その一般的な定義や腰椎との関わり、日本人における発症率について見ていきます。
ぎっくり腰の一般的な定義
ぎっくり腰とは、突然腰に激しい痛みが走る急性腰痛の総称です(医学的には「急性腰痛症」と言います)。
重い物を持ち上げた瞬間や体をひねったときなど、ある動作をきっかけに起こることが多く、そのあまりの痛みに思わず動けなくなることもあります。
欧米では「魔女の一撃」(Hexenschuss)という劇的な表現もあるほど、突然襲ってくる激痛が特徴です。
多くの場合、骨が折れたり神経が傷ついたりするわけではありませんが、筋肉や靭帯の損傷、椎間板のトラブルによって強い痛みが生じます。
症状は通常、数日から数週間で徐々に落ち着きますが、その間は日常生活に支障をきたすほどつらい状態となります。
腰椎との関連性
ぎっくり腰の痛みは、腰椎(腰の部分の背骨)やその周辺組織で起こります。
腰椎は5つの骨(第1腰椎〜第5腰椎)からなり、上半身の重さを支えつつ体を前後左右に曲げる可動性を持つ重要な部位です。
この腰椎を支える筋肉や靭帯、クッションの役割を果たす椎間板に急激な負荷がかかると、損傷や炎症が発生して激痛につながります。
つまり、ぎっくり腰は腰椎周辺の組織に生じた急性的なトラブル(腰の捻挫のようなもの)だと言えます。
腰椎は体を支える土台であるため、そこに問題が起これば体を動かすこと自体が困難になるのです。
日本人の発症率
日本人にとって腰痛は非常に身近な症状です。厚生労働省の調査でも、国民の訴える自覚症状として腰痛は常に上位に位置しています。
あるデータによれば、生涯で腰痛を経験する人は約8割にも上るという報告もあり、急に生じるぎっくり腰を経験する人も少なくありません。
特に30代以降になると椎間板や筋肉への負担が蓄積するため発症率が高くなる傾向がありますが、若い人でも無理な動作次第で起こる可能性があります。
つまり、ぎっくり腰は年齢や性別を問わず誰にでも起こりうる一般的な症状であり、あらかじめ原因や予防策を知っておくことが重要です。
以下に急性腰痛(ぎっくり腰)と慢性腰痛の違いを簡単にまとめます。
| 分類 | 特徴 |
|---|---|
| 急性腰痛(ぎっくり腰) | 突然発症する強い痛み。通常、数日〜数週間で改善します。原因は筋肉・靭帯の損傷や椎間板のトラブルなどです。 |
| 慢性腰痛 | 長期間続く鈍い痛み。3ヶ月以上持続する腰痛を指し、姿勢の悪化や筋力低下、慢性の疾患が関与します。 |
このように、ぎっくり腰は急性の腰痛であり、適切な対応によって回復が期待できます。では、ぎっくり腰はなぜ起こるのでしょうか。次に、その主な原因を見ていきましょう。
ぎっくり腰の主な原因
では、ぎっくり腰はなぜなるのでしょうか。その答えは一つではなく、いくつかの要因が重なって起こります。
ここでは、代表的な原因について見ていきましょう。急な動作や筋肉の疲労、腰椎の変性や姿勢の問題など、それぞれがぎっくり腰にどう関与するのかを解説します。
急な動作や無理な動き
ぎっくり腰は、何気ない一瞬の動作をきっかけに発症することがよくあります。
例えば、重い荷物を急に持ち上げたときや、中腰の姿勢から体をひねったときなど、急激で無理のある動きによって腰に大きな負担がかかります。
準備運動をせずにいきなり体を動かすと、筋肉や靭帯がその動きに対応しきれず捻挫のような状態になってしまうのです。
特に寒い朝や長時間同じ姿勢でいて筋肉が硬くなっているときに急に動くと、筋肉や関節がスムーズに伸縮できずぎっくり腰が起こりやすくなります。
よくぎっくり腰を起こしやすい動作の例として、次のようなものがあります。
- 床に置いた重い荷物を勢いよく持ち上げる
- 前かがみの姿勢から急に体をひねる
- 無理な姿勢でくしゃみや咳をする
- 硬い床で寝ていて朝起き上がるとき
- 中腰で長時間作業した後に体を伸ばす
筋肉疲労の蓄積
腰の筋肉に疲労が蓄積すると、ぎっくり腰を起こしやすくなります。
長時間の立ち仕事や重労働、あるいは逆に長時間のデスクワークで同じ姿勢を続けていると、腰の筋肉は休む暇がなく緊張が続きます。
そのような状態が続くと筋肉の柔軟性が失われ、疲労物質も蓄積して硬直状態になります。
限界まで疲れた筋肉は、些細な動作でも損傷しやすくなり、最後は小さな負荷でぷつんと筋繊維が断裂して激痛が走ることがあります。
いわば「疲労が限界に達したところに最後の一押し」が加わり、ぎっくり腰を引き起こすのです。
前日に重い作業をして翌朝に腰を痛めるケースなどは、この筋肉疲労の蓄積が原因の一つと言えるでしょう。
椎間板の変性による影響
背骨と背骨の間にある椎間板は、腰への衝撃を和らげるクッションの役割を果たしています。
しかし、加齢とともに椎間板の水分量が減って弾力が失われたり、繰り返しの負荷で微細な亀裂が入ったりすることがあります。
こうした椎間板の変性が進むと、ふとした動作でも椎間板の一部が飛び出したり(椎間板ヘルニアの一歩手前の状態)、神経を圧迫したりして強い痛みを引き起こすことがあります。
特に中高年以降でぎっくり腰を繰り返す方は、椎間板の変性が背景にある場合が少なくありません。
椎間板自体には痛覚がありませんが、変形することで周囲の靭帯や神経を刺激し、その結果、激しい痛みとして感じるのです。
不良姿勢や姿勢の問題
日常的な姿勢の悪さも、ぎっくり腰の大きな原因となります。猫背や反り腰など、不自然な姿勢を続けていると腰椎やその周りの筋肉・靭帯に常に偏った負担がかかります。
本来であれば分散されるはずの荷重が一部分に集中するため、組織が疲弊しやすくなります。
その状態でくしゃみをしたり重い物を持ったりといった何気ない動作をしたとき、蓄積した負荷により急に痛みが現れることがあります。
また、悪い姿勢の習慣が長年続くと筋力のアンバランスも招き、腰を支える力が弱まってしまいます。結果として、ちょっとした動作でも支えきれずぎっくり腰に陥りやすくなるのです。
ぎっくり腰の主な原因を表にまとめると次のようになります。
| 原因 | 具体例・解説 |
|---|---|
| 急な動作・無理な動き | 重い物を急に持ち上げたり、体をひねったりする動作が引き金になります。準備運動なしの急激な動きで腰の筋肉や靭帯に負荷が集中し、損傷が起こります。 |
| 筋肉疲労の蓄積 | 長時間の労働や同じ姿勢の維持で筋肉が疲労し硬直します。限界状態の筋肉にわずかな負荷が加わると、筋繊維が断裂して急激な痛みにつながります。 |
| 椎間板の変性 | 加齢などで椎間板が劣化するとクッション性が低下します。小さな衝撃でも椎間板が変形・突出して神経を刺激し、強い痛みを引き起こします。 |
| 悪い姿勢の習慣 | 猫背や反り腰など偏った姿勢を続けると腰に負担が蓄積します。その状態で何気ない動作をした際に蓄積ダメージが一気に現れて痛みが発生します。 |
以上のように、ぎっくり腰には様々な原因が関係しています。次の章では、腰椎の構造と実際に体内で何が起こっているのか、そのメカニズムを見ていきましょう。
腰椎の構造とぎっくり腰のメカニズム
ぎっくり腰が起きるとき、腰ではどのようなことが起こっているのでしょうか。この章では、腰椎の基本的な構造と、ぎっくり腰が発生するメカニズムについて解説します。
腰の骨(腰椎)や椎間板、周囲の筋肉・靭帯、そして神経がどのように関係しているのかを見ていきましょう。
腰椎の役割と負担
腰椎(腰の部分の背骨)は、人間の体を支える要(かなめ)です。5つの腰椎が連なって腰の部分の脊柱を構成し、その下に仙骨が続いて骨盤と連結しています。
腰椎は上半身の体重を支えながら、前後に体を曲げたり左右にひねったりといった可動性も確保しています。しかし、その分だけ負荷も大きく、日常生活の様々な動作で腰椎には大きな力がかかります。
例えば、物を持ち上げる動作では腰椎に体重の数倍もの圧力がかかります。無理な姿勢で行えば椎間板や関節に過剰なストレスが生じるでしょう。
特に下部の腰椎(第4腰椎〜第5腰椎、および第5腰椎〜仙骨の部分)は可動性が高い一方で負担も集中しやすく、ぎっくり腰の痛みの発生源となりやすい箇所です。
このように、腰椎は体を支え動かすうえで常に大きな役割と負担を担っているのです。
筋肉と靭帯の関係
腰椎の周囲には多くの筋肉と靭帯が存在し、背骨を支え安定させる働きをしています。
例えば、脊柱起立筋や腰方形筋などの筋肉は、上半身を起こしたり支えたりする役割を担い、腹筋群とともに体幹を安定させています。
靭帯は背骨と背骨を繋ぎ合わせる強靭な繊維組織で、脊椎の動きを制御し過度な可動を防いで関節を守っています。
ぎっくり腰では、これら筋肉や靭帯のいずれか(あるいは両方)に急激な負荷がかかり、損傷や炎症が起きています。
例えば、筋肉の筋繊維が部分的に断裂したり、靭帯が過度に引き伸ばされて繊維が切れたりすると、その部分から強い痛みが発生します。
体は損傷を受けると防御反応として周囲の筋肉を硬直させますが、これがいわゆる筋肉のけいれん(スパズム)で、ぎっくり腰のときに腰が固まってしまう原因です。
筋肉が硬直することで患部を動かないようにし、これ以上の損傷を防ごうとするわけですが、その緊張自体がさらなる痛みとなり悪循環に陥ることもあります。
神経への影響
腰椎の周囲には脊髄から分かれる神経根が走っており、腰や下肢の感覚や運動を司っています。
ぎっくり腰の際には、筋肉や靭帯の損傷に伴う炎症や椎間板の変形によって、近くを通る神経が刺激を受けることがあります。
神経が刺激を受けると、鋭い痛みとなって現れます。場合によっては太ももから脚にかけて痺れや痛みが放散する坐骨神経痛のような症状が出ることもあります。
特に椎間板ヘルニアを併発している場合には、飛び出した椎間板が神経根を圧迫し、足先にまで響く激痛や感覚麻痺を引き起こすことがあります。
ぎっくり腰の痛みそのものは腰周辺の筋肉や靭帯にある受容体からの信号ですが、それを脳が感じ取って「腰が痛い」と認識します。
このように、構造的な損傷と神経の痛み信号が組み合わさることで、私たちはぎっくり腰の激痛を経験するのです。
腰椎周辺の主な構造とその役割を以下にまとめます。
| 構造 | 役割・特徴 |
|---|---|
| 腰椎(背骨) | 腰の部分にある5つの椎骨です。上半身を支える柱となり、体を前後左右に曲げる動きを可能にします。常に大きな荷重を受け止めています。 |
| 椎間板 | 腰椎と腰椎の間に挟まっている軟骨組織で、クッションの役割を果たします。衝撃を吸収しますが、加齢で水分が減り弾力が低下します。 |
| 筋肉 | 脊柱起立筋や腹筋群など、腰椎を支え動かす筋肉です。腰の安定性を保ち、姿勢維持や動作を助けます。疲労や筋力低下で支える力が弱まります。 |
| 靭帯 | 椎骨同士をつなぐ強靭な繊維組織です。背骨の可動域を制限し、関節が外れないように支えます。無理な動きで過度に伸ばされると損傷します。 |
| 神経 | 脊髄から分岐し腰椎から下肢へ伸びる神経です。感覚や運動の信号を伝えます。圧迫や刺激を受けると痛みや痺れの原因になります。 |
腰椎の構造とメカニズムを理解したところで、次にぎっくり腰のリスク要因について見ていきましょう。どのような要素があるとぎっくり腰になりやすいのかを確認します。
ぎっくり腰のリスク要因
ぎっくり腰は誰にでも起こり得ますが、特に起こしやすい人には一定の傾向があります。この章では、ぎっくり腰のリスクを高める要因について解説します。
年齢や生活習慣、運動習慣など、どのような要素がぎっくり腰になりやすくするのかを見ていきましょう。
年齢と加齢による影響
一般的に、加齢とともにぎっくり腰のリスクは高まります。歳を重ねるにつれて腰椎や椎間板は摩耗し、水分が減って柔軟性が低下していきます。
その結果、若い頃には耐えられた動作でも、中高年になると腰に負担がかかりやすくなるのです。
例えば、椎間板の変性が進む40〜50代以降では、くしゃみや軽い物を持っただけでもぎっくり腰になることがあります。
また、筋力も加齢によって低下するため、腰を支える力が弱まり、急な動きに対する耐性が減ってしまいます。さらに、一度ぎっくり腰を経験すると、その後も再発しやすくなります。
これは損傷を受けた組織が完全に元通りになりにくいことや、根本的な原因(椎間板の変性や姿勢の癖など)が残っているためです。
生活習慣と職業
日々の生活習慣や職業も、ぎっくり腰のリスクに影響します。重い物を扱う肉体労働の現場や、介護職のように中腰で人を支える仕事では、常に腰に大きな負担がかかります。
また、長時間のデスクワークや車の運転など座りっぱなしの姿勢が続く職業も注意が必要です。
同じ姿勢を続けると血行が悪くなり筋肉が凝り固まるため、ちょっと動いた拍子にぎっくり腰が起こりやすくなります。
冷暖房の効いたオフィスで体が冷えることも筋肉のこわばりを招く一因です。さらに、肥満体型の方は常に腰にかかる負荷が大きく、ぎっくり腰になるリスクが高まります。
喫煙は椎間板の血流を低下させ変性を進める可能性があり、ぎっくり腰のリスク要因の一つです。
このように、仕事の内容や普段の生活習慣が腰に与える影響は大きく、それらが積み重なるとぎっくり腰の誘因となります。
運動不足と体幹筋の弱体化
普段あまり運動をしない人も、ぎっくり腰になりやすい傾向があります。運動不足だと腹筋や背筋など体幹の筋肉が弱くなり、腰椎を十分に支えられなくなります。
そのため、いざ重い物を持ったり急に動いたりしたとき、支えきれずに腰に過度な負担がかかってしまいます。また、ストレッチ不足で身体が硬い人は筋肉や関節の可動域が狭く、ちょっと無理な動きをしただけで筋肉や靭帯を痛めやすくなります。
普段から運動習慣がない状態で突然スポーツや力仕事をするのも危険です。準備ができていない筋肉に大きな負荷をかけると、やはりぎっくり腰を起こしやすくなります。
逆に、適度な運動で腰まわりの筋力や柔軟性を維持している人は、ぎっくり腰になりにくく、なっても軽症で済むことが多いです。
ぎっくり腰の主なリスク要因を以下にまとめます。自分に当てはまるものがないかチェックしてみましょう。
| リスク要因 | 内容・理由 |
|---|---|
| 加齢 | 年齢を重ねると腰椎や椎間板が劣化し、筋力も低下します。その結果、小さな負荷でも腰を痛めやすくなります。 |
| 職業・生活習慣 | 重労働や長時間のデスクワークなど、日常的な腰への負担が大きいとリスクが上がります。姿勢の癖や体の冷えも影響します。 |
| 運動不足 | 運動習慣がないと腹筋・背筋が弱くなり腰を支えきれません。柔軟性も低下し、急な動きに耐えられなくなります。 |
| 肥満 | 体重が増えると常に腰にかかる負担が増します。さらに運動不足にもつながり、ぎっくり腰を起こしやすくなります。 |
| 過去の腰痛歴 | 以前にぎっくり腰など腰痛を経験していると、その部分が弱くなり再発しやすくなります。 |
こうしたリスク要因を踏まえたうえで、次にぎっくり腰の予防策を見ていきましょう。日頃からどのような点に気をつければぎっくり腰を避けられるのか、具体的なポイントを解説します。
ぎっくり腰の予防策
ぎっくり腰は「起きてしまってから対処」するより、「起こさないように予防」することが大切です。日頃のちょっとした心がけで、ぎっくり腰になるリスクを大きく減らすことができます。
ここでは、ぎっくり腰を防ぐために有効な正しい姿勢や動作、ストレッチや筋力トレーニング、日常生活で気をつけたいポイントについて紹介します。
正しい姿勢と動作の心がけ
日常生活で常に正しい姿勢を保つことは、ぎっくり腰の予防に直結します。立っているときは、背筋を伸ばしお腹に軽く力を入れて骨盤が後ろに倒れすぎないよう意識しましょう。
座っているときは、深く腰掛けて背もたれを活用し、腰が丸まらないようにします。足は床にしっかりつけ、膝の角度は90度程度に保つのが理想です。
物を持ち上げる動作では、腰だけを曲げるのではなく膝を曲げて重心を落とし、物を体に近づけてからゆっくり持ち上げます。
急にひねる動作も避け、方向を変えるときは足ごと体全体で向きを変えるようにしましょう。こうした正しい姿勢や動作を習慣づけることで、腰椎への余計な負担を減らし、ぎっくり腰の発生を防ぐことができます。
正しい姿勢と悪い姿勢の例を以下の表に示します。
| シーン | 悪い姿勢の例 | 良い姿勢の例 |
|---|---|---|
| 立っているとき | 猫背で頭が前に出ている | 耳・肩・腰・膝・くるぶしが一直線になるよう背筋を伸ばす |
| 椅子に座るとき | 浅く腰掛けて背中が丸まっている | 深く腰掛けて背もたれに寄りかかり、背筋を伸ばす |
| 重い物を持つとき | 腰だけを曲げて持ち上げる | 膝を曲げ腰を落としてから持ち上げる(荷物は体に近づける) |
このように、常に良い姿勢を意識することで腰への負担を減らすことができます。
ストレッチやエクササイズの習慣
筋肉の柔軟性と筋力を高めておくことも、ぎっくり腰の予防にとって重要です。
特に腰回りや下半身のストレッチを日々行うことで、筋肉や靭帯の柔軟性が向上し、急な動きにも耐えやすくなります。
朝起きたときや長時間同じ姿勢でいた後などは、軽いストレッチで腰や太ももの筋肉をほぐす習慣をつけましょう。
また、腹筋や背筋など体幹の筋力トレーニングを定期的に行うことで、腰椎を支える筋肉が強化され、腰にかかる負担を軽減できます。
週に数回のエクササイズを継続するだけでも効果は大きいです。自宅で簡単にできる運動として、次のようなものがあります。
- 猫のポーズストレッチ:四つんばいになり背中を丸めたり反らせたりする。背骨周りの筋肉をほぐし柔軟性を高める。
- ハムストリングスのストレッチ:仰向けで片脚を上げて太ももの裏を伸ばす。骨盤の動きを良くし腰への負担を和らげる。
- プランク(体幹トレーニング):うつ伏せから肘とつま先で体を支える。腹筋・背筋をバランスよく鍛え腰を安定させる。
- バックエクステンション:うつ伏せで上半身を反らせる背筋運動。背中の筋力を強化し姿勢を支えやすくする。
日常生活で気をつけるポイント
普段の生活の中でも、ちょっとした工夫でぎっくり腰のリスクを下げることができます。
長時間同じ姿勢を取らないようにし、デスクワーク中でも1時間に一度は席を立って軽く体を動かすようにしましょう。腰を冷やさないことも大切です。
寒い時期には腹巻きやカイロで腰回りを保温し、筋肉がこわばらないようにします。
重い物を運ぶときは無理をせず台車を使う、家事でも中腰の姿勢が長く続く作業は適度に休憩を入れるなど、腰に負担をかけすぎない工夫を心がけましょう。
以下のようなポイントに気をつけると効果的です。
- 長時間同じ姿勢で過ごさない(定期的に立ち上がりストレッチをする)
- 腰を冷やさないよう腹巻きやカイロ等で保温する
- 重い荷物は可能な限り避け、持つ場合は正しいフォームで行う
- 必要に応じてコルセットやサポーターで腰をサポートする
- 適正体重を維持し、腰への負担を軽減する
ぎっくり腰になったときの対処法
万が一ぎっくり腰になってしまった場合でも、適切に対処すれば痛みを和らげ回復を早めることができます。
この章では、ぎっくり腰が起こった際に自宅でできる応急処置や痛みの緩和方法、そして病院に行くべきタイミングについて説明します。
痛みを緩和する方法
ぎっくり腰で強い痛みを感じたときは、まず無理に動かず安静にすることが基本です。可能であれば痛みが和らぐ姿勢を探し、その姿勢でしばらく休みましょう。
横向きに寝て膝を軽く曲げる姿勢や、椅子に座って背もたれにもたれかかる姿勢などが楽なことが多いです。痛み始めの48時間ほどは患部を冷やすと炎症を抑え、痛みを軽減できます。
氷嚢や冷却パックがあればタオル越しに15〜20分程度冷やし、1時間ほど間隔をあけて繰り返します。患部を温めるのは、急性期の炎症がおさまった後にしましょう。
痛みが少し引いてきたら入浴で温めたり、蒸しタオルやカイロで血行を良くしたりすると筋肉のこわばりが和らぎます。
市販の鎮痛薬(痛み止め)が手元にあれば服用して痛みを和らげても構いません。ただし、痛みが和らいだからといって無理に動くと悪化する恐れがあるため注意が必要です。
痛みが強い間は無理をせず安静にし、焦らずに経過を見守りましょう。痛みが少し落ち着くまで、数日は普段より静かに過ごすことが大切です。
自宅でできる応急処置
ぎっくり腰になった直後から自宅でできる応急的な対処を、順を追って見てみましょう。次のステップに沿って対応することで、症状を悪化させず回復を助けます。
- 楽な姿勢をとる:その場で無理に動こうとせず、痛みが少しでも和らぐ姿勢をとります。横向きに丸くなる、椅子にもたれて座るなど、自分が楽に感じる姿勢で安静にします。
- 患部を冷やす:痛み始めのうちは炎症を抑えるため患部を冷却します。ビニール袋に入れた氷や冷却パックをタオルで包み、痛む箇所に当てて15分程度冷やします。これを1時間おきに数回繰り返しましょう。
- 安静にする:強い痛みが治まるまでは安静が第一です。動くと痛む場合は無理に動かず、可能であれば仕事や家事を一時中断して休みます。必要に応じて市販の鎮痛剤を服用し、痛みを和らげます。
- 痛みが和らいだら軽い動きを:痛みのピークを過ぎて少し和らいできたら、ずっと横になったままにせず可能な範囲で体を動かし始めます。軽いストレッチをしたり、短時間の散歩をしたりして血行を促しましょう。長期間寝たきりでいると筋力が低下し、回復が遅れるため注意します。
- 症状に応じて医療機関へ:痛みがあまりにも強かったり、脚に痺れが出たりする場合は、早めに整形外科を受診します。無理に我慢せず専門医の診断を仰ぎましょう。
いつ病院に行くべきか
ぎっくり腰は安静にしていれば数日で和らぐケースが多いですが、場合によっては早めに医療機関を受診した方が良いこともあります。
次のような症状がある場合には、我慢せず整形外科を受診しましょう。
- 激痛でまったく動けない、日常生活に支障が出るほど痛みが強い場合
- 足や臀部に痺れや力が入らない感じがある場合
- 排尿・排便がうまくできない、会陰部(股のあたり)に感覚異常がある場合(緊急性があります)
- 数日安静にしても痛みがほとんど改善しない場合
- 時間の経過とともに痛みが悪化している場合や、発熱を伴っている場合
上記のような症状が見られたら、早めに専門医の診断を受けることが重要です。整形外科ではレントゲンやMRI検査で骨や椎間板の状態を確認し、必要な治療を行います。
無理をして症状を悪化させるよりも、専門家の判断を仰いだ方が安心です。
整形外科での治療方法
ぎっくり腰で整形外科を受診した場合、痛みを和らげ再発を防ぐために様々な治療が行われます。ここでは、整形外科で一般的に提供される治療方法について紹介します。
物理療法による痛みの軽減、薬による症状緩和、さらにリハビリテーションによる再発予防まで、専門的なアプローチで早期回復を目指しましょう。
物理療法(温熱・電気治療など)
整形外科では、痛みを軽減するために物理療法をよく用います。物理療法とは、熱や電気、力学的な刺激を使って症状を和らげる治療法の総称です。
ぎっくり腰の急性期を過ぎて炎症が落ち着いてきたら、腰を温める温熱療法や筋肉の緊張をほぐす電気治療などが効果的です。温熱療法ではホットパックや超音波装置を使って患部を温め、血行を促進して痛みを和らげます。
電気治療(低周波治療)では腰に電極を貼り、心地よい刺激を与えることで痛みの信号を和らげ、筋肉のこわばりを減らします。また、腰椎牽引(けんいん)といって、専用の装置で骨盤や胸部を固定し腰を引っ張る治療を行うこともあります。
牽引療法により椎間板や神経根への圧迫が軽減され、痛みが和らぐ効果が期待できます。そのほか、理学療法士によるマッサージやストレッチなどの手技療法で筋肉をほぐし、可動域を改善することもあります。
痛みが強い間は腰を固定するためにコルセットの着用を指示する場合もあります。腰を安定させることで、動作時の痛みを軽減し治癒を促進します。
整形外科で行われる主な物理療法の例を表にまとめます。
| 治療法 | 内容・効果 |
|---|---|
| 温熱療法 | ホットパックや超音波などで腰を温める治療です。血流を改善し痛みを和らげます。 |
| 電気治療 | 低周波などの電気刺激を与える治療です。痛みの信号を和らげ、筋肉の緊張を緩める効果があります。 |
| 牽引療法 | 専用ベッドで腰を引っ張る治療です。椎間板や神経の圧迫を軽減し、痛みの緩和が期待できます。 |
| 手技療法(マッサージ等) | 理学療法士が筋肉をほぐしたり関節を動かしたりする治療です。筋肉の凝りを解消し可動域を改善します。 |
| コルセット装着 | 腰部コルセットやサポーターで腰を固定します。患部を安定させて動きを制限し、痛みの軽減と治癒促進を助けます。 |
薬物療法(鎮痛剤・筋弛緩剤)
痛みが強い場合や筋肉の緊張が著しい場合には、医師が薬を使った治療を行います。まず一般的なのは消炎鎮痛剤(NSAIDsなど)の内服です。
炎症を抑えて痛みを和らげる効果があり、ぎっくり腰の急性期によく処方されます。内服薬に加えて、胃腸への負担が少ない湿布薬や塗り薬が処方されることもあります。
筋肉の緊張がひどい場合には、筋弛緩剤という筋肉を和らげる薬を併用することもあります。筋弛緩剤によって筋肉のけいれんが軽減し、痛みが楽になります。
それでも痛みが強い場合、医師が神経ブロック注射を行うこともあります。痛みの原因となっている神経周囲に局所麻酔薬や抗炎症薬を注射し、即効的に痛みを止める方法です。
これらの薬物療法により、ぎっくり腰の痛みをコントロールし、日常生活への早期復帰を目指します。
主な薬物療法とその効果を以下にまとめます。
| 治療法 | 内容・効果 |
|---|---|
| 内服鎮痛剤 | 消炎鎮痛剤(NSAIDsなど)を服用し痛みと炎症を抑えます。早期に痛みを和らげ、日常生活への復帰を助けます。 |
| 外用薬(湿布等) | 痛み止め成分を含む湿布や塗り薬を患部に使用します。局所的に炎症を抑え、痛みを軽減します。 |
| 筋弛緩剤 | 筋肉の緊張を和らげる薬を服用します。過度に収縮した筋肉をほぐし、痛みを軽減します。 |
| 神経ブロック注射 | 痛みの原因となる部位に局所麻酔やステロイド薬を注射します。炎症を抑え、即効的に痛みを止める効果があります。 |
リハビリテーションと再発予防
痛みが落ち着いてきた段階で重要になるのがリハビリテーションです。リハビリでは、理学療法士の指導のもとで腰周りの筋力強化や柔軟性向上のための運動を行います。
例えば、軽いストレッチや体幹トレーニング、姿勢矯正のためのエクササイズなどが段階的に実施されます。これにより、再発の防止につながるだけでなく、腰痛全般に対する抵抗力が高まります。
リハビリを通じて正しい体の動かし方や姿勢を身につけ、日常生活で腰に負担をかけにくい習慣を養うことができます。場合によっては、理学療法士が手技を用いて関節の動きを改善したり、筋肉のバランスを整えたりすることもあります。
リハビリテーションはぎっくり腰の再発予防にとても重要であり、医師や理学療法士の指導の下で計画的に取り組むことが大切です。
まとめ
ぎっくり腰は誰にでも起こり得る身近なトラブルですが、その原因とメカニズムを理解し対策を講じることで予防することが可能です。
急な動作や筋肉疲労、腰椎の構造上の問題など様々な要因が重なって発症するぎっくり腰も、日頃から正しい姿勢を心がけ、筋力を維持することで発生リスクを大きく減らせます。
万が一発症してしまっても、適切な応急処置と安静、そして必要に応じた整形外科での治療によって早期回復が期待できます。
繰り返す腰痛に悩んでいる方は、この機会に生活習慣を見直し、予防策を取り入れてみましょう。そして症状が改善しない場合や不安があるときは、早めに整形外科専門医に相談することが大切です。
正しい知識と専門的なケアで、つらいぎっくり腰を乗り越えていきましょう。
以上
参考文献
KNEZEVIC, Nebojsa Nick, et al. Low back pain. The Lancet, 2021, 398.10294: 78-92.
O’SULLIVAN, Peter. Diagnosis and classification of chronic low back pain disorders: maladaptive movement and motor control impairments as underlying mechanism. Manual therapy, 2005, 10.4: 242-255.
KELSEY, Jennifer L.; WHITE III, AUGUSTUS A. Epidemiology and impact of low-back pain. Spine, 1980, 5.2: 133-142.
RUBIN, Devon I. Epidemiology and risk factors for spine pain. Neurologic clinics, 2007, 25.2: 353-371.
FRYMOYER, John W., et al. Epidemiologic studies of low-back pain. Spine, 1980, 5.5: 419-423.
HEWETT, Timothy E.; MYER, Gregory D.; FORD, Kevin R. Anterior cruciate ligament injuries in female athletes: Part 1, mechanisms and risk factors. The American journal of sports medicine, 2006, 34.2: 299-311.
RADEBOLD, Andrea, et al. Muscle response pattern to sudden trunk loading in healthy individuals and in patients with chronic low back pain. Spine, 2000, 25.8: 947-954.
SATTAR, Naveed; MCINNES, Iain B.; MCMURRAY, John JV. Obesity is a risk factor for severe COVID-19 infection: multiple potential mechanisms. Circulation, 2020, 142.1: 4-6.
PINCUS, Tamar, et al. A systematic review of psychological factors as predictors of chronicity/disability in prospective cohorts of low back pain. Spine, 2002, 27.5: E109-E120.
BALAGUÉ, Federico, et al. Non-specific low back pain. The lancet, 2012, 379.9814: 482-491.
Symptoms 症状から探す