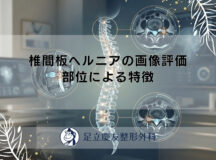DDH股関節における診断基準と治療計画
DDH股関節とは、発育期における股関節形成の異常を指し、将来的に変形性股関節症へ移行する可能性があると考えられています。
出生直後から乳幼児期にかけて気づかれることもありますが、青年期や成人期になって症状が目立つことも少なくありません。
本記事では、DDH股関節の診断基準や治療計画を丁寧に紹介し、受診のタイミングや日常生活での留意点を解説します。
見落とされやすい軽度の変形でも運動時の違和感や痛みが起こる場合もあるため、早期の診断と対応が大切です。
日頃の動作や姿勢の癖に関心を向け、気になる症状があれば専門医へ相談してみてください。
目次
DDH股関節とは何か
DDH股関節とは、英語でDevelopmentalDysplasiaoftheHipの略称を指します。
国内では発育性股関節形成不全とも呼ばれ、先天的または生後間もない時期に見られる股関節の形成異常を意味します。以下ではDDH股関節の概要と特徴を詳しくお伝えします。
DDH股関節の概要
DDH股関節の概要について、まずは一般的な股関節との違いを押さえることが大切です。正常な股関節は大腿骨頭が寛骨臼内にしっかりとはまり、体重を支える構造になっています。
しかしDDH股関節の場合、大腿骨頭が完全に収まらない、あるいは浅くしかはまっていない状態が見られます。その結果、歩行時や起立時の安定性が低下し、さまざまな症状を引き起こすおそれがあります。
乳児期の股関節脱臼や亜脱臼を放置すると、成長に伴って変形や痛みが強くなり、成人期以降に変形性股関節症へ移行することもあり、早めの診断と適切な対応が求められます。
また、近年では生後の股関節検診の普及に伴い、早期発見や早期治療の機会が広がりつつあります。
ただし、軽度の場合は見過ごされる例があり、違和感や痛みが出てから初めて発覚するケースも見受けられます。出生直後のチェックだけでなく、成長に合わせた定期的な観察が重要です。
DDH股関節と正常股関節の主な違い
| 項目 | 正常な股関節 | DDH股関節 |
|---|---|---|
| 大腿骨頭の位置関係 | 寛骨臼にしっかりはまる | 浅くしか収まらない、またはずれている |
| 可動域 | 安定して広範囲 | 不安定、または制限が生じる |
| 症状の出現 | 無症状が多い | 痛み、違和感、歩行異常などが出やすい |
| 将来リスク | 変形性股関節症のリスクは比較的低い | 変形性股関節症に移行しやすい |
DDH股関節の特徴
DDH股関節にはいくつかの特徴が存在します。まず、大腿骨頭の位置異常により、膝や足首の方向が偏ることがあります。そのため、歩行開始後に内股や外股が強調されるといった歩行異常が見られる場合があります。
また、乳幼児期にはおむつ替えの際に脚の開きに左右差を感じることや、股関節が硬く開きづらいといった所見が見られることがあります。
特徴が顕著な場合は家庭でも気付きやすいですが、軽度のDDH股関節でははっきりとした差が分かりにくく、医療機関でのチェックが欠かせません。
そのほか、股関節まわりの筋肉の緊張バランスや骨盤の傾きが影響を受け、姿勢や運動能力に影響することもあります。
いずれの場合も、成長期の骨や軟部組織の柔軟性が高いうちに治療へ取り組むと、より良い予後が期待できます。
DDH股関節が疑われるサイン
- 股のしわの左右差が目立つ
- 大腿を外転するときに違和感やクリックを感じる
- 歩き始めの時期が遅れたり、歩行バランスが不安定
- 立ち上がるときに痛みや引っかかり感がある
胎児期・乳児期の股関節形成とDDHとの関係
胎児期から乳児期にかけて、股関節はまだ軟骨が多く柔軟です。お母さんのお腹の中での姿勢や出産時の状況によっては、大腿骨頭が十分に寛骨臼に収まらないまま成長することがあります。
特に女児に多く見られ、骨盤位(逆子)で生まれた場合や、第一子で子宮内が狭い環境下の場合にリスクが高いといわれています。
また、出産後の抱っこの仕方やおむつの当て方によっても股関節に影響が及ぶ場合があります。例えば、股関節を強く伸展させるような姿勢が続くと、大腿骨頭が寛骨臼から逸脱しやすくなる可能性があります。
こうした初期の段階での影響が積み重なると、DDH股関節の発症につながるケースが少なくありません。産後の育児環境や赤ちゃんの姿勢にも目を向け、必要に応じて医療スタッフに正しいケア方法を教わることが望ましいです。
放置した場合のリスク
DDH股関節を放置した場合のリスクには、大きく分けて機能的な問題と痛みの問題があります。機能的な問題としては、歩行バランスの乱れや脚長差などが挙げられます。
股関節が不安定な状態で成長すると、骨盤が傾いて歩行時の負担が増大し、腰や膝といった他の関節にも影響が及びます。
また、痛みの問題としては、関節自体の負担が大きくなるため、将来的に変形性股関節症を発症するリスクが高まります。
歩行や日常生活動作に支障をきたし、通勤やスポーツなどの活動制限につながる場合もあります。
さらに、成人期以降に重度の症状が進行すると、人工股関節置換術などを検討しなければならない状況になることがあります。
早めに専門医を受診することで、軽症の段階で必要な対応を行い、将来のリスクを軽減することが期待できます。
放置による主なリスク分類
| リスク分類 | 具体的な影響例 | 対策 |
|---|---|---|
| 機能的リスク | 歩行バランスの乱れ、脚長差 | 早期診断とリハビリテーション |
| 痛みのリスク | 変形性股関節症、慢性的な疼痛 | 保存療法や手術療法の検討 |
| 二次的リスク | 膝や腰への負担、姿勢の崩れ | 全身的な運動指導と生活改善 |
病態と原因
DDH股関節は、単に先天的要因だけでなく、環境や生活習慣との相互作用によって成立すると考えられています。
大腿骨頭と寛骨臼の適切なかみ合わせが保たれない原因を知ることで、予防や早期対応がより具体的に見えてきます。
先天的要因と後天的要因
DDH股関節の発生には、遺伝的素因や胎児期の骨格形成異常など先天的要因が関係します。しかしすべてのケースが先天性ではありません。
出産時の骨盤位や、狭い子宮内での大腿骨頭の圧迫など、出生時の環境も大きく関与しています。また、産後の育児環境や赤ちゃんの股関節の使い方など、後天的な要因も深くかかわっています。
例えば、両脚をピンと伸ばしたまま長時間抱っこする習慣があると、大腿骨頭がうまくはまらずに発育が不十分になるかもしれません。
このようにDDH股関節は、先天的と後天的な要因が複雑に絡み合って発生します。
骨盤や股関節周囲組織との関連
大腿骨頭と寛骨臼だけでなく、それを支える靭帯や筋肉など周囲組織の状態もDDH股関節の発症や悪化に影響します。
股関節周囲の筋肉が柔軟性を欠いたり、骨盤の傾きが強かったりすると、関節に不均衡な負荷がかかります。その結果、大腿骨頭が安定しづらくなり、成長とともに変形や脱臼リスクが高まる場合があります。
また、運動不足や偏った姿勢によって周囲筋力が低下すると、よりいっそう不安定性が増し、痛みを伴う症状が出現することがあります。骨盤周囲のバランスを保つことはDDH股関節の管理において重要です。
生活習慣が与える影響
成長期における適度な運動や正しい姿勢は、股関節周囲の筋力や柔軟性を養ううえで大切です。
スマートフォンやタブレットの普及により、長時間の座位や前かがみ姿勢が増え、股関節周囲の筋力低下や骨盤の歪みが生じるケースも報告されています。
特に学童期や思春期の子どもは、運動習慣が減ると筋力バランスが崩れやすくなります。また、肥満や体重増加も股関節への負担を増大させ、DDH股関節の症状を悪化させる要因となる可能性があります。
適切な体重管理や運動習慣がDDH股関節のリスク軽減に役立ちます。
家族歴との関わり
DDH股関節は家族歴との関連が指摘されています。母親や祖父母が股関節脱臼や変形性股関節症を経験している場合、その子どもや孫世代にDDH股関節が出現する確率が高まると報告されています。
ただし、遺伝だけが決定的な要因ではありません。上記のように出生時の姿勢や育児環境、運動習慣など、複数の要因が絡み合うことによって発生リスクが変化します。
家族に股関節関連の疾患がある場合は、より注意して日常の観察を行い、異変を感じた時点で早めに受診することが望ましいです。
DDH股関節に影響する主な要因
- 骨格の遺伝的形態(先天的素因)
- 胎児期の子宮内環境(骨盤位など)
- 産後の育児習慣(抱っこの姿勢など)
- 生活習慣(運動不足、体重増加)
股関節周囲組織の主な役割
| 組織名 | 役割 | DDH股関節との関連 |
|---|---|---|
| 靭帯 | 関節の安定性確保 | 靭帯が緩むと股関節脱臼が起こりやすくなる |
| 軟骨 | 骨同士の衝撃を吸収 | 関節がずれていると軟骨磨耗が進行し痛みを生じる |
| 筋肉 | 関節を動かす・支える | 筋力低下があると骨頭が安定しにくくなる |
| 関節包 | 関節全体を包む袋状の組織 | 内圧変化によって関節の位置が不安定になる場合がある |
家族歴がある場合に注意したいこと
- 早期に股関節の検査を受ける
- 定期的に専門医に経過確認を依頼する
- 抱っこの姿勢やおむつの当て方を医療スタッフに相談する
- 運動や生活習慣の改善を積極的に取り入れる
診断基準のポイント
DDH股関節の診断には、視診・触診、画像検査、その他の検査結果など多角的な情報を組み合わせることが重要です。
正確な診断を行うことは、その後の治療計画を立てるうえで欠かせません。
触診と身体所見
医師はまず視診と触診によってDDH股関節を疑います。具体的には、股関節の開排制限や脚長差、太もものしわの非対称などを確認します。
乳幼児の場合は、大腿を外転させた際のクリック音(クリックサイン)や、脚を動かしたときの抵抗感から異常を察知することがあります。
大人の場合は、歩行の様子や姿勢、動かしたときの痛みの出方をチェックします。これらの身体所見はレントゲンなどの画像検査とあわせて評価され、診断の補助になります。
レントゲンやエコー検査による確認
DDH股関節の診断を確定するために、レントゲン検査やエコー検査を実施するケースが多いです。乳幼児に対しては、エコーが骨の状態を把握するうえで有用です。
成長段階の軟骨部分も描出しやすく、X線被ばくを避ける利点があります。一方、レントゲン検査は骨の位置関係や変形の程度を詳細に評価するのに役立ちます。
特に股関節周囲の骨構造や大腿骨頭の状態を確認し、関節の深さや脱臼の有無などを確認します。
レントゲン画像では、大腿骨頭中心と寛骨臼の位置関係を示すCE角(Center-Edge角)などの指標が診断や予後の評価に用いられます。
代表的な画像検査の特徴
| 検査方法 | 利点 | 注意点 |
|---|---|---|
| エコー | 被ばくがない、軟骨描出に適している | 骨が硬化する時期以降は評価が難しい場合がある |
| レントゲン | 骨の位置や変形を明確に捉える | X線被ばくがあり、軟骨の詳細は分かりにくい |
| MRI | 軟部組織や軟骨の状態を評価しやすい | 費用がかかる、撮影時間が長くなる |
DDH股関節の分類
診断されたDDH股関節は、脱臼の程度や骨の変形具合によっていくつかのカテゴリーに分類されます。軽度の亜脱臼から完全脱臼まで段階があり、治療方針や予後の見通しにも関わります。
レントゲン評価では、骨盤と大腿骨頭の位置関係を数値化する指標が活用され、その結果に応じて治療の選択肢を検討します。
例えば、CE角が20度以下であれば関節の被覆率が低いと判断され、将来的な変形や痛みのリスクが高いと考えられます。このような定量的な評価は、治療方針を定めるためにも重要です。
分類に用いられる主な指標
- CE角(Center-Edge角)
- Sharp角
- Tönnis分類
- AcetabularIndex(乳幼児期での指標)
治療方針の指標としての診断
DDH股関節の治療を考えるうえで、まずは脱臼や亜脱臼の程度を正確に判断する必要があります。
骨の変形が進んでいるか、軟骨部分のダメージがあるかどうかによって、保存療法か手術療法かを検討する指標になります。
軽度であれば装具やリハビリテーションによって改善が期待できるケースもありますが、すでに変形が進行している場合や痛みが強い場合は手術療法が検討されます。
診断はその後の方針を左右するため、専門医のもとで十分な検査を受けることが大切です。
保存療法の考え方
DDH股関節に対するアプローチとしては、状態に応じた保存的治療がまず候補に挙がることが多いです。
痛みの軽減や変形の進行を防ぐ目的で、装具やリハビリテーションを組み合わせる方法があります。
保存的治療の目的
保存的治療は、手術を避けつつ股関節の機能を保ち、痛みを抑えることを狙います。
発育期の子どもであれば、装具で股関節を適切な位置に保ちながら骨の成長を促し、正常に近い形へ導くことが期待できます。
成人の場合でも、リハビリテーションや日常生活での負荷軽減を工夫して関節の痛みを軽くし、変形の進行速度を遅らせる効果が期待できます。
保存的治療は身体に対する負担が比較的少なく、患者のライフスタイルに合わせやすい利点があります。
装具療法やリハビリテーション
装具療法では、乳児用のリーメンビューゲルなどの装具を使い、大腿骨頭を寛骨臼に正しく収める姿勢を保つ方法を選ぶことがあります。
大人の場合でも、必要に応じて股関節を安定させるサポーターを装着し、痛みの原因となる不安定性を和らげることがあります。
あわせてリハビリテーションでは、股関節周囲の筋力強化や柔軟性向上、正しい歩行パターンの獲得を目指します。
理学療法士による指導のもと、段階的に運動負荷を増やしながら安全に機能を高める方法を選びます。継続的な運動と装具の使用がポイントになり、根気強い取り組みが必要です。
装具やリハビリ方法の例
| 対象 | 使用する装具 | 代表的なリハビリ内容 |
|---|---|---|
| 乳幼児 | リーメンビューゲル | 脚の外転位を保つ姿勢指導、抱っこ方法の相談 |
| 学童期 | 簡易サポーター | 軽い筋力トレーニング、バランス練習 |
| 成人 | 股関節サポーター | 歩行指導、関節可動域を広げる運動、筋力強化 |
日常生活動作の工夫
DDH股関節の痛みを軽減したり、変形の進行を緩やかにしたりするために、日常生活の中で取り入れたい工夫があります。
例えば、立ち上がる際には股関節に過度なねじれや負荷がかからないよう、両脚に体重を分散させる姿勢を意識します。
また、椅子に座るときは股関節と膝をほぼ90度に保ち、深く座りすぎずに背筋を伸ばすと安定しやすくなります。
床に座る習慣がある場合は、長時間の正座やあぐらを避け、クッションや椅子を活用して股関節を圧迫しすぎないようにします。
このような小さな工夫が負担軽減につながり、痛みの出現を抑える助けになります。
日常生活で気をつけたい姿勢
- 立ち上がり時に両脚に体重を均等にかける
- 低い椅子や床生活を避けて股関節の曲げすぎを防ぐ
- 長時間同じ姿勢を続けず、定期的にストレッチを挟む
- 太もも裏を過度に引っ張らないよう脚を伸ばすときの角度に注意
経過観察の必要性
保存療法中でも、定期的な経過観察が欠かせません。成長期の子どもは骨の発育にともない、装具のサイズや調整が必要になることがあります。
成人であっても、リハビリテーションの効果や痛みの変化を見ながら、治療方針を微調整する必要があります。
レントゲン検査や医師の診察を定期的に受け、股関節の状態が良好に保たれているかを確認します。適切な時期に治療方針を見直すことで、より良い股関節の機能維持と将来的な変形予防を期待できます。
手術療法を考慮する場面
保存療法で十分な効果が得られない場合や、変形が進行して股関節の痛みや機能障害が顕著な場合、手術療法を選択することがあります。
患者の年齢や症状、骨の状態によって方法は多岐にわたります。
手術適応の目安
手術を検討する目安としては、股関節の痛みが強く日常生活に支障をきたすかどうか、レントゲンやMRIなどの検査で変形が進んでいるかなどが挙げられます。
特にCE角の低下や大腿骨頭の偏位が大きい場合は、将来的な関節症のリスクが高まるため、早めの対策をとることが検討されます。
年齢も考慮する必要があり、成長期の子どもならば骨切り術で股関節を矯正する可能性があり、成人では進行度に応じて骨切り術や人工股関節置換術が選択肢に含まれる場合があります。
骨切り術や骨盤修正術の概要
DDH股関節の手術では、大腿骨または骨盤を切り、その位置を調整して大腿骨頭が寛骨臼にしっかりはまるようにする方法がよく行われます。
代表的な方法として、大腿骨骨切り術や寛骨臼回転骨切り術などがあります。大腿骨骨切り術では、大腿骨の角度や向きを変えて股関節の適合性を高めることを目指します。
寛骨臼回転骨切り術は、寛骨臼自体を回転させて大腿骨頭の被覆率を改善します。これにより、股関節への負担を分散し、痛みや変形の進行を抑えることが期待できます。
骨を切る手術であるため回復までに時間がかかりますが、中長期的には関節の機能改善に寄与する可能性があります。
手術方法の比較
| 術式名 | 主な対象 | 目的 |
|---|---|---|
| 大腿骨骨切り術 | 骨の角度や向きに問題がある場合 | 大腿骨の向きを変え、関節適合性を向上させる |
| 寛骨臼回転骨切り術 | 寛骨臼が浅いなどの形態異常がある場合 | 寛骨臼を回転させて大腿骨頭の被覆率を高める |
| 人工股関節置換術 | 重度の変形や痛みがある高齢者など | 痛みの軽減と関節機能の回復 |
術後のリハビリテーション
手術後は関節の安定性を確保しつつ、徐々に股関節の可動域や筋力を回復させるリハビリテーションが必要になります。
骨切り術の場合、一定期間の免荷(足をつかずに過ごす期間)や装具使用が求められます。その後、理学療法士の指導のもと、股関節周囲の筋肉を中心にトレーニングを行い、歩行能力の回復を図ります。
日常生活動作をこなしながらリハビリテーションを進めるため、痛みや疲労に留意しながら無理のないメニューを実施します。
長期的にみると、術後のリハビリテーションの質と継続性が術後成績に大きく影響すると考えられています。
合併症と注意点
手術には一定のリスクがあり、感染や神経損傷などの合併症が起こる可能性があります。また、骨切り術の部位がきちんと癒合しない場合、再手術が必要になるケースもゼロではありません。
さらに、術後の固定やリハビリテーション期間が長引くと、関節周囲の筋力が低下しやすい点にも注意が必要です。
手術前には主治医から合併症のリスクや治療後の生活上の留意点について十分な説明を受け、患者自身も術後ケアに意欲的に取り組む姿勢が求められます。
医療スタッフとの連携を密にすることで、術後の合併症リスクを下げ、より良い機能回復を目指すことが重要です。
術後リハビリで注意したい点
- 手術創部の清潔保持と感染防止
- 痛み止めの服用と適度なアイシング
- 長時間の同じ姿勢を避けて適度に身体を動かす
- 医師の許可が出るまで無理な運動は控える
日常での管理と予防
DDH股関節を適切に管理し、合併症や変形の進行を防ぐためには、日々の暮らしの中でのちょっとした意識や工夫が欠かせません。
体重管理や筋力維持など、生活の基盤を見直す取り組みが大切です。
股関節周囲の筋力維持
股関節周囲の筋力が弱まると、関節への負担が増し、痛みを助長しやすくなります。スクワットやブリッジ運動など、股関節を支える大殿筋や中殿筋を強化するエクササイズが効果的です。
ウォーキングや軽いジョギングのような有酸素運動も、体重コントロールと筋力維持の両面で役立ちます。
運動を行う際は、痛みの程度に注意しながら無理のない回数や負荷を選ぶことが大切です。
日常の移動で階段を使うなど、ちょっとした場面でも股関節周囲の筋肉を意識的に活用し、活発に動かす習慣をつけると予防に結びつきます。
おすすめの運動習慣
- 週3回程度のウォーキング(20~30分)
- スクワットやブリッジ運動で殿筋を鍛える
- プールでのウォーキングやアクアエクササイズ
- ヨガやピラティスで体幹と股関節周囲の柔軟性を高める
体重管理と負担軽減
体重が増えると股関節への負担が増大し、DDH股関節の痛みや変形を悪化させる可能性があります。適正な体重を維持するためには、バランスの良い食事と適度な運動が必要です。
食事面では、タンパク質やビタミンD、カルシウムなど骨や筋肉の維持に役立つ栄養素を意識するとよいでしょう。
甘いものや脂質の多い食品を摂りすぎないよう注意し、適量を心がけることも大切です。
運動不足が続くとエネルギー消費が少なくなり体重が増加しやすくなるので、ウォーキングや軽いストレッチをこまめに取り入れながら体重コントロールを図ることが予防につながります。
骨や関節に良い栄養素の例
| 栄養素 | 主な食品例 | 期待される効果 |
|---|---|---|
| タンパク質 | 魚、肉、大豆製品 | 筋肉や軟骨の修復と維持 |
| カルシウム | 牛乳、小魚、小松菜 | 骨密度の維持 |
| ビタミンD | きのこ類、鮭、卵 | カルシウムの吸収を助ける |
| ビタミンC | 柑橘類、野菜 | コラーゲン合成を促進 |
| ビタミンK | 納豆、緑色野菜 | 骨の健康をサポート |
生活動線の改善
日常生活で股関節に負担がかからないようにするには、住環境や行動パターンの見直しも重要です。椅子やベッドの高さを適切なものに調整し、立ち座りがスムーズに行えるよう工夫します。
階段の昇降時に手すりを使いやすい位置に取り付けたり、段差を減らしたりすることで、不要な力をかけずに移動できます。
座る時間が長い人は、1時間ごとに軽く立ち上がってストレッチを行う習慣を付けると、血流もよくなり疲労が蓄積しにくくなります。
生活空間を見直すことで、股関節にかかる余計なストレスを減らせます。
早期発見のためのポイント
DDH股関節は初期段階では痛みが少なく、自覚症状が分かりにくいことがあります。そのため、違和感を覚えたら早めに医療機関を受診する習慣が大切です。
特に、歩くときに片脚が外や内に傾きがち、脚を開くときに左右差を感じる、長時間座ったあとに立ち上がりづらいなどの症状があれば注意が必要です。
成長期の子どもに対しては、定期健診だけでなく、歩行時の姿勢や動き方にも目を配り、わずかな異常を見逃さない姿勢を心がけましょう。
家族に股関節の疾患歴がある場合は、より積極的にチェックを行い、早期受診につなげることをおすすめします。
受診のタイミング目安
| タイミング | 症状例 | 推奨される対応 |
|---|---|---|
| 乳幼児期 | 股の開きの左右差、太もものしわの非対称 | 早めに小児科や整形外科で検査 |
| 学童期 | 運動時の膝や腰の痛み、姿勢の崩れ | 定期健診時に股関節をチェック |
| 成人初期 | 歩行時の違和感、長時間座位後の立ち上がり痛 | 専門医への相談、画像検査 |
| 高齢期 | 慢性的な痛み、変形性股関節症の悪化 | 手術療法を含む包括的な治療検討 |
当クリニックでの治療体制
DDH股関節の診療にあたっては、専門知識と経験を持つ医師やリハビリテーションスタッフの連携が欠かせません。当クリニックでは、患者さまが安心して治療に取り組める体制を整えています。
診療の流れ
初診時に問診と身体所見のチェックを行い、必要な画像検査(レントゲン、MRI、エコーなど)を組み合わせながら診断を行います。
その後、診断結果と患者さまの年齢、生活習慣、症状の程度などを総合的に評価し、保存療法か手術療法かを判断します。
保存的に対応できる場合は、装具療法やリハビリテーションの内容を提案し、定期的なフォローアップを行います。
手術が必要と判断される場合でも、ほかの医療機関と連携しながら適切なタイミングや術式を検討します。患者さまが納得のいく治療方針を共に考え、一人ひとりに合わせたサポートを提供するよう努めています。
専門スタッフのサポート
当クリニックでは、整形外科専門医だけでなく、理学療法士や看護師、リハビリテーション専門スタッフがチームを組んでDDH股関節の患者さまをサポートします。
リハビリテーションでは、姿勢や歩行の評価を丁寧に行い、日常生活動作を円滑にこなすための筋力強化や柔軟性トレーニングを指導します。また、栄養管理が必要な場合は管理栄養士と連携し、体重コントロールや食事の見直しを提案することもあります。
患者さまの症状やライフスタイルに合わせた総合的な支援を行うことで、治療効果の向上を目指しています。
装具やリハビリ機器の充実
DDH股関節の治療には、適切な装具の使用や各種リハビリ機器を活用することが効果的です。
当クリニックでは、乳幼児向けの装具から成人向けサポーターまで幅広く取りそろえ、個々の症例に応じてカスタマイズしています。
リハビリテーションでは、筋力トレーニングマシンや関節可動域を広げる装置などを用い、段階的に機能回復を進めます。
患者さまが日常生活にスムーズに復帰できるよう、院内だけでなく家庭でも継続しやすいメニューの提案を心がけています。
患者さまとの連携
DDH股関節の治療は、医療側の取り組みだけでなく、患者さま自身の理解と協力が必要です。そのため、当クリニックではコミュニケーションを大切にし、患者さまの疑問や不安に丁寧に答える体制を整えています。
治療方針やリハビリテーションの進め方について分かりやすく説明し、患者さまが納得したうえで治療を受けられるように配慮します。加えて、家庭でのケアや運動についてもアドバイスし、定期受診のタイミングを決めながら経過を追います。
相互の信頼関係を築くことで、より良い治療効果を目指し、患者さまのQOL向上に貢献したいと考えています。
まとめ
DDH股関節は、生まれつきや成長過程での環境要因が絡み合って発症し、進行すると日常生活に大きな支障をもたらします。
しかし、早期診断と適切な対応によって、症状の軽減や機能維持を図れる可能性があります。
早期治療の重要性
DDH股関節は、症状が軽度なうちに対処すれば装具療法やリハビリテーションなどの保存的治療で改善を期待できる場合が少なくありません。
特に乳幼児期の脱臼や亜脱臼は早めに装具を用いて正しい位置に誘導すると、正常に近い発育が期待できます。
成人になってからも、痛みが軽い段階でリハビリテーションや生活習慣の見直しを行うと、変形や痛みの進行を抑えられる可能性があります。何らかの異変を感じたら早期に医療機関へ相談することが大切です。
多角的なアプローチの必要性
DDH股関節の治療では、医師の診察や手術だけでなく、理学療法士による運動療法や看護師による日常生活指導、管理栄養士による食事管理など、多職種が協力する包括的なアプローチが求められます。
股関節への負担を軽減しつつ、筋力や可動域を徐々に改善する取り組みが継続的に求められます。患者さま自身が治療方針を理解し、日々の生活でのケアを積極的に実践することも重要です。
定期受診と相談のすすめ
DDH股関節は、経過とともに状態が変化する可能性があります。
保存療法中でも装具のサイズが合わなくなる、痛みが増すなどの変化が見られたときは、早めに受診することが大切です。
定期検査でレントゲンやエコーなどの検査を行い、股関節の位置や変形の進行度をチェックし、治療方針をこまめに見直すことで、症状の悪化を防ぎやすくなります。
小さな不調や疑問でも遠慮なく医療スタッフに相談し、適切な対策を講じてください。
これからの健康的な股関節生活
DDH股関節は、一度診断を受けたら一生付き合っていくイメージを持っている方もいますが、きちんとした治療とケアによって十分に快適な生活を送ることができます。
適度な運動や体重管理、姿勢の工夫などを取り入れながら、関節を守る意識を持ち続けることが大切です。
痛みや違和感があっても、専門家に相談しながら適切なリハビリテーションを続けることで、無理なく関節機能を保つことができます。
今の状態と向き合いながら、自分のペースで将来にわたって活発な日常生活を送りましょう。
以上
参考文献
SEWELL, Mathew D.; EASTWOOD, Deborah M. Screening and treatment in developmental dysplasia of the hip—where do we go from here?. International orthopaedics, 2011, 35: 1359-1367.
NGUYEN, Jie C., et al. ACR appropriateness criteria® developmental dysplasia of the hip-child. Journal of the American College of Radiology, 2019, 16.5: S94-S103.
SHIPMAN, Scott A., et al. Screening for developmental dysplasia of the hip: a systematic literature review for the US Preventive Services Task Force. Pediatrics, 2006, 117.3: e557-e576.
TERJESEN, Terje; HORN, Joachim. Prognostic value of severity of dislocation in late-detected developmental dysplasia of the hip. Journal of Children's Orthopaedics, 2020, 14.4: 266-272.
ALBINANA, J., et al. Acetabular dysplasia after treatment for developmental dysplasia of the hip: implications for secondary procedures. The Journal of Bone & Joint Surgery British Volume, 2004, 86.6: 876-886.
SCHMITZ, Matthew R., et al. Developmental dysplasia of the hip in adolescents and young adults. JAAOS-Journal of the American Academy of Orthopaedic Surgeons, 2020, 28.3: 91-101.
WEINSTEIN, Stuart L.; MUBARAK, Scott J.; WENGER, Dennis R. Developmental hip dysplasia and dislocation: Part I. JBJS, 2003, 85.9: 1824-1832.
AL-ESSA, Rakan S., et al. Diagnosis and treatment of developmental dysplasia of the hip: A current practice of paediatric orthopaedic surgeons. Journal of Orthopaedic Surgery, 2017, 25.2: 2309499017717197.
GAMBLING, Tina Samantha; LONG, Andrew. Psycho-social impact of developmental dysplasia of the hip and of differential access to early diagnosis and treatment: a narrative study of young adults. SAGE open medicine, 2019, 7: 2050312119836010.
GE, Yihua; CAI, Haiqing; WANG, Zhigang. Quality of reduction and prognosis of developmental dysplasia of the hip: a retrospective study. Hip International, 2016, 26.4: 355-359.
Symptoms 症状から探す