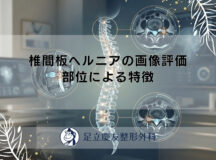レントゲンで確認する股間部の状態と異常所見
骨盤周辺の痛みや歩行時の違和感など、股間部にかかわる症状を感じる方は少なくありません。
レントゲン股間撮影によって骨の状態や関節の変化を早期にとらえ、適切な診断と治療につなげることが重要です。
痛みの原因がはっきりしない段階でも専門的な画像検査を行うと、将来的に大きなトラブルを回避できる可能性が高まります。
この文章では、レントゲン股間検査の目的や撮影方法、異常所見、さらによくみられる疾患や他の画像検査との違いについて詳しく解説します。
目次
股間部を撮影する目的
骨盤と大腿骨のつながりを正確に把握するためにレントゲン股間検査を活用することが多いです。腰や太もも、膝の痛みといった症状でも、股間部に異常が隠れている可能性があります。
痛みの原因を探るうえで、形態や隙間の状態を画像で捉えることは非常に大切です。
形状把握
骨盤と大腿骨の位置関係を可視化して、股関節が正しい角度でかみ合っているかどうかを調べます。ずれや変形が起きると動かしたときの衝撃が増え、軟骨がすり減ってしまう場合があります。
痛みや可動域の制限が生じる原因として、このような形状の異常は見落とせません。日常生活の動作に影響する要因が潜んでいるかどうかをチェックし、治療方針の検討に役立てることができます。
- 骨盤と大腿骨の密着度
- 両脚の長さの差
- 骨の変形や彎曲
- すり減った軟骨の有無
骨の形状に影響する主な要因
| 要因 | 内容 | 関連しやすい症状 |
|---|---|---|
| 加齢による変化 | 年齢とともに骨密度が低下し、形態異常が起こりやすくなる | 股関節のこわばり、疼痛 |
| 外傷 | 転倒や衝突などの強い衝撃で骨が変形する | 急性の激しい痛み、変形の進行 |
| 遺伝要素 | 先天的な骨格の問題が股関節に影響する | 幼少期からの運動機能の低下 |
変形性股関節症の疑い
中高年に多いとされる変形性股関節症では、レントゲン股間撮影で関節の隙間が狭くなっている状態や骨棘の有無を確認できます。
初期段階は軽い違和感だけの場合があるため、早期に撮影して把握すると進行を抑える対策を考えやすくなります。
立ったときや歩いたときに強く痛むようになってから受診するケースが多いですが、痛みが軽い段階で原因を突き止めることが重要です。
日常動作との関係
立ち上がったり階段を上り下りしたりといった日常動作の負担が、股間部に集中しすぎていないかも確認します。骨や軟骨の状態次第で負担が大きくなると、炎症が起こりやすくなります。
炎症が進むと痛みのために関節を動かしづらくなり、筋力低下を招くことにもつながります。生活の質を下げないために、原因を画像で把握して適切なアプローチを選ぶことが欠かせません。
レントゲン股間検査で確認できる主な構造
レントゲン股間撮影では、骨盤や大腿骨、関節面など複数の部位を一度に観察できます。これによって、わずかなずれや関節のすり減り具合、骨の変色なども確認できる可能性があります。
目視ではわからない変化を画像上で見極めることが、予防や治療のスタートになります。
骨盤の位置関係
骨盤は背骨と下半身をつなぎ、体重を支える土台として機能します。ねじれがあると、片側だけに大きな負荷がかかりやすくなります。
長い期間その状態が続くと、股関節や膝にも影響が及びます。レントゲン股間写真で骨盤全体の傾き具合を見て、腰椎からの影響も検討します。
骨盤の傾きが招きやすいトラブル
| 傾きのタイプ | 具体例 | 引き起こされる主な症状 |
|---|---|---|
| 前傾が強い | 腰を反らせた姿勢になりやすい | 腰痛、股関節の前側の張り |
| 後傾が強い | 猫背気味で背中が丸まる | お尻や太ももの裏側の痛み |
| 左右いずれかに傾く | 片脚重心で立つ癖がある | 骨盤まわりの筋力バランス崩れ、痛み |
大腿骨頭の形状
大腿骨の先端部にあたる大腿骨頭は、球状に近い形をした重要な要素です。関節軟骨が均一に保たれているかどうかで、動きのスムーズさが変わります。
摩耗や変形が強いと痛みが発生しやすくなり、進行すると歩行が難しくなる場合があります。丸みが失われているケースでは、関節の奥で余計な摩擦が起こるかもしれません。
- 先端部分の摩耗の度合い
- 関節と骨盤との接触範囲
- 骨頭の丸みの有無
関節腔の幅
股関節は骨と骨が接しているように見えて、実際には間に軟骨があり、適度な関節腔を保つ状態が理想的です。
レントゲン股間撮影で関節腔が狭くなっているときは、軟骨がすり減っている合図かもしれません。
左右の股間部を比較して片方だけ狭い状況なら、その側の骨に集中して負荷がかかっている可能性が高いです。
関節腔の状態
| 状態 | 考えられる原因 | 想定されるリスク |
|---|---|---|
| 正常な幅 | 軟骨がしっかり存在し負荷を均等に分散 | 痛みや炎症を起こしにくい |
| やや狭い | 過度の使用や軟骨の軽度損傷 | 運動後の痛みや違和感 |
| 極端に狭い | 軟骨の大幅な摩耗や変形 | 歩行困難や強い痛みが起こる可能性 |
よくみられる異常所見と特徴
股間部に生じる障害にはさまざまなパターンがありますが、レントゲン股間撮影で映りやすい代表的なものとして骨棘形成や関節裂隙の狭小化などが挙げられます。
これらの異常所見は、軽度のうちに発見すると大掛かりな治療を回避できるチャンスが高まります。
骨棘形成
関節の縁に飛び出すように骨が増殖した状態を骨棘と呼びます。
変形性股関節症の進行によって生じることが多く、動きが悪くなるだけでなく、他の組織を刺激して痛みを生じる要因にもなります。
骨棘によって骨どうしの当たり方が変わり、負担のかかる場所が偏りやすくなります。
骨棘があると起こりやすい症状
| 症状 | 具体的な例 |
|---|---|
| 動かし始めの痛み | 朝起きて体を動かし始めるときに感じる痛み |
| 外旋や内旋の制限 | 足を外にひねったり内側にひねったりしにくい |
| 鈍い違和感の持続 | 日常動作でじわじわと続く不快感 |
関節裂隙の狭小化
関節裂隙が狭くなると、軟骨の摩耗が進行している可能性が高いです。歩行や走行時の衝撃を吸収しづらくなるため、関節への直接的な負担が増します。
徐々に痛みを感じ始め、階段の昇降や正座といった動きに苦痛を覚えるケースがあります。骨と骨が近づきすぎると、軟骨以外の組織にも影響が及ぶかもしれません。
- 運動時の鋭い痛み
- 長時間座ってから立ち上がるときの違和感
- 深く曲げたときに生じる引っかかり感
骨の配列異常
先天的あるいは長い年月を経て形成された骨の配列異常が、股関節周りのトラブルを誘発しやすくなります。骨の配列が乱れていると、筋肉や腱、靭帯への負担も不均衡になります。
筋肉の張りや痛みを生じるばかりか、他の部位にも連鎖的に影響するので、画像をもとに配列の乱れを把握することが重要です。
レントゲン股間の撮影方法
レントゲン股間写真の撮り方には、複数のバリエーションがあります。患者の状態や症状にあわせて撮影体位を決めると、より詳細な情報を得られます。
撮影の仕方を工夫することで、どの角度から異常が目立つかもチェックできます。
仰向け撮影
最も一般的な撮影方法です。両足をまっすぐ伸ばし、床と平行な状態を保ったまま撮影します。骨盤の左右差や大腿骨頭の形状を見分けるのに向いています。
シンプルな姿勢なので、撮影時の負担が少ないこともメリットです。痛みが強い場合は脚の角度を調整しながら撮影し、できるだけ正確な画像を得ます。
仰向け撮影が有効なケース
| ケース | 特徴 | 確認しやすい事項 |
|---|---|---|
| 軽度から中程度の痛み | 強い苦痛がなく、通常の姿勢が保てる | 全体的な骨盤の角度や関節裂隙の幅 |
| 両側の比較が必要 | 左右の股間部を同じ条件で撮影 | 形状や骨の密度の左右差 |
| 初診時 | 基本的な情報を把握する段階で利用しやすい | 大まかな形状や初期の変形 |
体位変換撮影
仰向け以外にも横向きや、脚を開いたり閉じたりする姿勢で撮影する場合があります。大腿骨頭の前後のずれや微妙な角度変化を捉える狙いがあります。
痛みを感じる動作に近い姿勢で撮影することで、痛みの原因が特定しやすくなることがあります。
- 横向き姿勢での撮影
- 股関節を曲げた姿勢での撮影
- 脚を開脚した状態での撮影
特殊アングル
先天的な障害や外傷が疑われる場合、通常とは異なるアングルを試すことが有効です。撮影技師と医師が連携して、骨盤や大腿骨頭を多角的に映し出しながら問題を探ります。
一般的な方法で確認しきれないような小さな変形や骨棘を洗い出すのに活用します。
特殊アングルで注目するポイント
| ポイント | 具体例 | 期待できる利点 |
|---|---|---|
| 骨盤の深部の確認 | 通常のX線では重なって見えにくい構造を把握 | 小さな骨棘や軟骨の損傷箇所を詳細に把握 |
| 足を開いた状態の撮影 | 股関節が外転したときの関節空間や骨の当たり具合 | 動きが大きい姿勢に伴う痛みの原因を推測しやすい |
代表的な疾患とレントゲン画像
レントゲン股間撮影によって確認できる代表的な疾患には、変形性股関節症、大腿骨頭壊死、先天性股関節脱臼などがあります。
症状によっては複数の疾患が併発していることもあるので、画像だけでなく問診や触診も合わせて総合的に診断します。
変形性股関節症
股関節の軟骨がすり減り、骨どうしが擦れ合って痛みを生じる病気です。加齢や日常動作の負担が大きい場合に起こることが多いです。
レントゲン画像では関節裂隙の狭小化や骨棘形成が見られることがあり、進行度に応じて痛みや可動域の制限が変化します。
進行度の目安
| 進行段階 | 主な画像所見 | 日常生活への影響 |
|---|---|---|
| 初期 | わずかな関節裂隙の狭小化 | 長時間歩くと痛みを感じる場合がある |
| 中期 | 骨棘がはっきり現れ、関節空間がさらに狭くなる | 立ち上がりや歩行に痛みが強まる |
| 進行期 | 骨の変形が顕著になり股関節が変わってしまう | 日常動作全般に支障をきたす |
大腿骨頭壊死
大腿骨頭に血流が行きにくくなり、骨組織が壊死を起こす疾患です。進行すると骨頭が潰れるように変形し、強い痛みが生じます。
レントゲン股間画像では、骨頭の輪郭が変化して見えたり、骨の内部の変性が写ったりします。早期の段階で発見すると、治療方針を幅広く選ぶ余地があります。
先天性股関節脱臼
出生時から股関節の発育がうまく進まなかった場合にみられる疾患です。適切な時期に治療しないと、大人になってから股関節痛や変形性股関節症のリスクが高まります。
レントゲン画像では大腿骨頭が正常な位置より外側にずれて写ることが多いです。幼少期から定期的な検査を行い、成長過程を把握する必要があります。
異常が疑われる症状の特徴
股間部の異常を抱える場合、痛みや違和感のパターンに特徴があります。痛みの種類や発生タイミングを手掛かりにすると、レントゲン股間検査を検討する段階を早めることができます。
歩行時の痛み
普通に歩いているだけで股関節周辺が痛むときは、関節面がなめらかに動いていない可能性があります。
初期は疲れやすい程度の感覚でも、原因が変形性股関節症や骨棘形成の場合は放置すると悪化することが多いです。脚を少し引きずるように歩き始めたら、変形が進行している恐れがあります。
歩行時に意識したいポイント
| ポイント | 具体的な例 |
|---|---|
| 痛む場所 | 股の付け根、太ももの外側、臀部 |
| 痛みの強さ | 歩き始めだけ痛む、長い距離を歩くと痛むなどのパターン |
| 足の運び方 | 引きずるように歩く、足を大きく外に振る |
立ち上がりの困難
椅子から立ち上がる動作は、股関節に大きな負荷がかかる瞬間です。痛みがあると上半身を前に倒して重心をずらすなど、変則的な動きで乗り切ろうとする場合があります。
その影響で腰や膝に余計なストレスをかけることも多いです。スムーズに立ち上がれなくなったときは、股間部に問題があると考えて検査を行う選択が効果的です。
- 立ち上がるときにズキッとした痛みを感じる
- 上半身を過度に前傾して重心を逃がす動作が習慣化する
- 立ち上がり後もしばらく脚がうまく動かない
夜間の違和感
夜間、横になっている状態でも股間部がうずくような痛みを覚えるときは、骨や関節の炎症が進んでいるかもしれません。
痛みで寝返りが打てないときや、特定の姿勢でしか安眠できなくなった場合も要注意です。安静にしている状況であっても痛みが続くなら、レントゲン股間撮影を含む精査が欠かせません。
レントゲン以外の検査との併用
股間部の痛みが複雑な要因によって生じているときは、レントゲン画像だけでは診断が難しいこともあります。
超音波やCT、MRIなど、ほかの画像検査を組み合わせるとより詳細な情報を得られます。
MRIとの違い
MRIは骨だけでなく軟骨や筋肉、靭帯といった軟部組織を高い解像度で映し出す特長があります。一方、レントゲン股間写真は骨の状態を把握するのに適しています。
骨折や変形性股関節症の進行度を判断するときはレントゲンを優先し、軟骨や筋肉の損傷度を調べるときにMRIを加えると相互補完がしやすいです。
検査選択の比較
| 検査名 | 得意とする領域 | 弱点・制限 |
|---|---|---|
| レントゲン股間 | 骨の変形、骨棘、関節裂隙など | 軟部組織の状態はわかりにくい |
| MRI | 軟骨、筋肉、靭帯、血管の状態など | 金属が体内にある場合は撮影が制限される |
| CT | 骨の断面像、3D再構築など | 被ばく量がレントゲンより多くなることがある |
CTとの違い
CTはレントゲンの透過を多角的にとらえ、断層画像として再構成する方法です。
骨の立体構造を把握するのに役立ちますが、被ばく量が増える面があるため、必要性を見極めたうえで行うことが多いです。複雑骨折や腫瘍疑いなどのケースで有用性が高まります。
超音波との使い分け
超音波検査は動きのある筋肉や血流の状態をリアルタイムで観察できる利点があります。レントゲン股間写真では写りにくい軟部組織や関節内の液体の様子を確認できる場合があります。
痛みの原因が滑液包炎や腱炎などに由来するときは、超音波によって正確な患部位置を捉えやすいです。
- 超音波は生きた動きを見られる
- レントゲンは骨格中心の評価が得意
- 症状に応じて組み合わせると、診断精度を高めやすい
適切な診断と治療への流れ
股間部の異常は初期段階で対処すると、将来的な合併症を減らせる可能性があります。特に変形性股関節症などは、早期発見によって保存的治療を選択できる機会が広がります。
医師と相談しながら、自分の症状に合う治療計画を進めることが大切です。
医師の診察
問診と視診を行い、痛みの強さや範囲、日常生活での支障度を確認します。そのうえで、レントゲン股間撮影や他の画像検査を組み合わせて総合的に判断します。
検査結果だけでなく、患者が感じる痛みの種類や生活背景を踏まえたうえで治療方針を決める流れになります。
診察時に確認しておきたい項目
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 痛みの性質 | ずきずきとした痛み、鋭い痛み、重苦しい痛みなど |
| 発生時の姿勢や動作 | 立ち上がり時、階段昇降時、就寝中の体勢など |
| 既往歴 | 骨折や脱臼の経験、先天性疾患など |
初期治療と保存療法
痛みがまだ軽度であれば、リハビリテーションや生活習慣の見直しなどで進行を食い止める方法を検討します。体重管理や歩き方の指導、股間部を安定させる筋力トレーニングなどが含まれます。
痛み止めの服用や注射などの薬物療法を適宜組み合わせる場合もあります。レントゲン画像と比較しながら、効果の程度を観察して治療内容を調整します。
- 骨や関節に負担をかけすぎない運動メニュー
- 体重減少を目指した生活習慣調整
- 痛み止めや消炎鎮痛薬の活用
手術療法の検討
重度の変形や壊死が進んでいるケースでは、手術によるアプローチを考えることがあります。
骨や関節面を人工物に置き換える人工股関節置換術が代表的ですが、患者の年齢や活動量、骨の状態などを総合的に判断したうえで選択します。
術前術後のリハビリテーション計画も重要で、股関節の可動域と機能回復をめざしたトレーニングを行います。
手術方法の主な種類
| 方法 | 特徴 |
|---|---|
| 人工股関節置換術 | 関節そのものを人工パーツに置き換え、痛みを軽減する |
| 骨切り術 | 骨盤や大腿骨の配列を調整し、関節面の接触を改善する |
| 骨頭回転骨切り術 | 大腿骨頭を回転させ、まだ壊死が少ない部分を関節面にあてる技法 |
まとめ
レントゲン股間撮影は骨盤と大腿骨頭の位置関係や変形の度合いなど、股間部の状態を総合的に評価する有用な方法です。
歩行時や立ち上がり時に違和感や痛みを覚えた場合、早めに整形外科で撮影を行うことが症状の進行を抑えるカギになります。
MRIやCT、超音波と組み合わせて診断の精度を上げると、原因を的確に突き止めやすくなります。症状の初期段階であれば、保存的治療による改善も期待できます。
一方で重症度が高いケースでは手術が選択肢になる場合もあり、患者の生活スタイルや希望に合わせた治療計画が必要です。
痛みを見過ごさず、レントゲン股間検査を軸に医師と相談しながら対策を進めましょう。
以上
参考文献
RUIZ SANTIAGO, Fernando, et al. Imaging of Hip Pain: From Radiography to Cross‐Sectional Imaging Techniques. Radiology research and practice, 2016, 2016.1: 6369237.
MARTIN, Harold E. Geometrical-anatomical factors and their significance in the early X-ray diagnosis of hip-joint disease in children. Radiology, 1951, 56.6: 842-849.
BLUM, A.; RAYMOND, A.; TEIXEIRA, P. Strategy and optimization of diagnostic imaging in painful hip in adults. Orthopaedics & Traumatology: Surgery & Research, 2015, 101.1: S85-S99.
SELTZER, Steven E., et al. Improved diagnostic imaging in joint diseases. In: Seminars in Arthritis and Rheumatism. WB Saunders, 1982. p. 315-330.
WEBER, M.-A., et al. Modern radiological imaging of osteoarthritis of the hip joint with consideration of predisposing conditions. In: RöFo-Fortschritte auf dem Gebiet der Röntgenstrahlen und der bildgebenden Verfahren. © Georg Thieme Verlag KG, 2016. p. 635-651.
KIM, Young-Jo, et al. Imaging structural abnormalities in the hip joint: instability and impingement as a cause of osteoarthritis. In: Seminars in musculoskeletal radiology. © Thieme Medical Publishers, 2008. p. 334-345.
CHIAMIL, Sara Muñoz; ABARCA, Claudia Astudillo. Imaging of the hip: a systematic approach to the young adult hip. Muscles, Ligaments and Tendons Journal, 2016, 6.3: 265.
LEQUESNE, M.; MALGHEM, Jacques; DION, E. The normal hip joint space: variations in width, shape, and architecture on 223 pelvic radiographs. Annals of the rheumatic diseases, 2004, 63.9: 1145-1151.
KLOTH, Jost Karsten, et al. Pelvic X-ray examinations in follow-up of hip arthroplasty or femoral osteosynthesis–Dose reduction and quality criteria. European Journal of Radiology, 2015, 84.5: 915-920.
ALZYOUD, Kholoud, et al. Optimum positioning for anteroposterior pelvis radiography: a literature review. Journal of Medical Imaging and Radiation Sciences, 2018, 49.3: 316-324. e3.
Symptoms 症状から探す