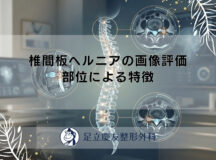股関節のすべり症に対する治療とリハビリ
股関節や膝の周りに原因不明の痛みが続く、歩き方がぎこちない、といった症状でお悩みではありませんか。
特に成長期のお子さんに見られるこれらのサインは、「大腿骨頭すべり症」という股関節の病気が原因かもしれません。
この病気は、大腿骨の成長に関わる部分がずれてしまうもので、早期に適切な対応をすることがとても重要です。放置すると、将来的に股関節の機能に大きな影響を及ぼす可能性もあります。
この記事では、股関節すべり症がどのような病気であるか、その原因、症状、そして診断後の治療法や回復に向けたリハビリテーションについて、専門的な知見に基づき、分かりやすく解説していきます。
ご自身の、またはお子さんの症状を理解し、向き合うための一助となれば幸いです。
目次
股関節すべり症とはどのような病気か
股関節に生じる病気の一つである「大腿骨頭すべり症」、通称「股関節すべり症」について、まずはその基本的な知識から掘り下げていきましょう。
あまり聞き慣れない名前かもしれませんが、成長期の子どもたちにとっては決して珍しくない病気です。
ここでは、この病気の定義や、なぜ「すべる」という現象が起きるのか、どのような子どもに発症しやすいのか、そして他の股関節の病気とどう違うのかを具体的に説明します。
大腿骨頭すべり症の基本
股関節すべり症は、正式には「大腿骨頭すべり症(だいたいこっとうすべりしょう)」と呼びます。
これは、太ももの骨である大腿骨の、股関節側にあるボール状の先端部分(大腿骨頭)が、成長軟骨板(骨端線)という部分を境にして、首の部分(大腿骨頚部)からずれてしまう病気です。
骨が成長する過程で重要な役割を持つ骨端線は、成人になると固い骨に変わりますが、成長期には軟骨でできているため、構造的に弱い部分です。
この弱い部分で、骨頭が後方や下方に「すべる」ように位置がずれてしまうのが、この病気の本質です。
なぜ「すべり」が起きるのか
「すべり」という言葉から、関節が脱臼するように大きく外れてしまうイメージを持つかもしれませんが、実際には骨の内部での位置関係のずれを指します。
成長期の子どもの骨端線は、成人の骨に比べてせん断力(ずれようとする力)に弱い特徴があります。
この骨端線に、体重による負荷や、スポーツ活動などによる捻りの力が繰り返し加わることで、軟骨部分が耐えきれなくなり、徐々に、あるいは急激に骨頭がずれていきます。
この現象が、まるで骨がすべっているように見えることから「すべり症」と呼ばれています。
主な発症年齢と性差
股関節すべり症は、骨の成長が活発になる思春期に発症しやすいことが知られています。具体的には、10歳から16歳くらいの年代に多く見られます。
一般的に、男子のほうが女子よりも2倍から3倍ほど発症しやすい傾向があります。
また、肥満傾向にあるお子さんは、股関節にかかる負担が大きくなるため、発症のリスクが高まることが指摘されています。
発症年齢と思春期の関係
急激に身長が伸びる時期は、骨の成長も活発である一方、骨端線の強度が一時的に低下します。
この時期にホルモンバランスの変化も加わり、すべり症が発症しやすい環境が整うと考えられています。
他の股関節疾患との違い
成長期に股関節の痛みを引き起こす病気は、股関節すべり症だけではありません。似たような症状を示す他の病気と区別することが、適切な治療のためには重要です。
代表的な成長期股関節疾患との比較
| 疾患名 | 主な発症年齢 | 主な特徴 |
|---|---|---|
| 大腿骨頭すべり症 | 10歳~16歳(思春期) | 骨端線での骨頭のずれ。肥満傾向の子に多い。 |
| ペルテス病 | 4歳~10歳(幼少期) | 大腿骨頭への血流障害による骨の壊死。 |
| 単純性股関節炎 | 3歳~10歳(幼児期~学童期) | 風邪などの感染後に一時的に起こる股関節の炎症。 |
これらの病気は発症年齢や原因が異なるため、専門医による正確な診断が求められます。
股関節すべり症の主な原因
股関節すべり症がなぜ特定の子どもに発症するのか、その原因は一つだけではありません。複数の要因が複雑に絡み合って発症に至ると考えられています。
ここでは、発症の背景にある主な要因を、「成長期の骨の特性」「体重の影響」「ホルモンの関与」「物理的な負荷」という4つの観点から詳しく解説します。
成長期の骨端線の脆弱性
最も基本的な原因は、成長期特有の骨の構造にあります。子どもの骨には、骨が長軸方向に成長するための「骨端線(成長軟骨板)」が存在します。
この部分は軟骨細胞で構成されており、成人の硬い骨と比べて物理的な強度、特にねじれやずれに対する抵抗力が弱いという性質を持っています。
思春期に身長が急激に伸びる時期には、この骨端線も活発に活動し、一時的にさらに弱くなることがあります。この構造的な弱点が、すべり症が起こる土台となります。
体重増加や肥満の影響
股関節は、立ったり歩いたりする際に体重を支える重要な役割を担っています。体重が増えれば、それだけ股関節にかかる力学的な負荷も増大します。
特に、肥満傾向にあるお子さんの場合、標準体重のお子さんと比較して、歩行時や走行時に骨端線にかかるせん断力が常に大きい状態にあります。
この過剰な負荷が、構造的に弱い骨端線に継続的にかかることで、骨頭がすべるリスクを有意に高めることが多くの研究で示されています。
発症に関わる要因の概要
| 要因の分類 | 具体的な内容 | 影響 |
|---|---|---|
| 力学的要因 | 肥満、過度なスポーツ | 骨端線へのせん断力増大 |
| 内分泌的要因 | 成長ホルモン、性ホルモン | 骨端線の強度低下 |
| 遺伝的要因 | 家族歴 | 発症しやすい体質の可能性 |
内分泌系(ホルモン)の関与
思春期は、成長ホルモンや性ホルモンなど、様々なホルモンの分泌が活発になる時期です。
これらのホルモンは骨の成長に必要ですが、そのバランスの変化が骨端線の強度に影響を与えると考えられています。
例えば、成長ホルモンは骨端線の活動を促進しますが、これが過剰になると骨端線が厚くなり、かえって強度が低下することがあります。
一方で、性ホルモンは骨端線の閉鎖を促し、骨を成熟させる働きがあります。このホルモンバランスの乱れが、骨端線を脆弱にし、すべりを引き起こす一因となる可能性があります。
外傷や過度な運動による負荷
明らかな原因が特定できない場合が多い一方で、転倒などの軽い外傷や、特定のスポーツ活動が発症の引き金になることもあります。
ジャンプや急な方向転換を繰り返すスポーツ(バスケットボール、サッカーなど)は、股関節に大きなせん断力や捻転力を加えます。
このような力が、もともと脆弱な骨端線に繰り返し、あるいは急激に作用することで、すべりが生じたり、もともとあった軽度のすべりが悪化したりすることがあります。
ただし、多くの場合、単一の外傷だけが原因ではなく、素因があるところに特定の負荷が加わって発症すると考えられています。
見逃せない股関節すべり症の症状
股関節すべり症の発見が遅れると、治療が難しくなったり、後遺症が残りやすくなったりします。そのため、初期のサインを見逃さず、早期に医療機関を受診することが非常に重要です。
この病気の症状は、痛みの現れ方や歩行の変化など、多岐にわたります。ここでは、注意すべき具体的な症状について詳しく解説します。
股関節や膝に現れる痛み
最も一般的な症状は痛みです。しかし、痛みの現れ方には特徴があります。多くの患者さんは、股関節の付け根(鼠径部)に痛みを訴えます。
しかし、それと同じくらい、あるいはそれ以上に多いのが、「膝の痛み」を最初に訴えるケースです。
これは、股関節の異常を伝える神経と、膝の感覚を伝える神経が一部共通しているために起こる「関連痛」と呼ばれる現象です。
股関節自体には痛みをあまり感じず、膝や太ももの内側だけが痛いと感じるため、膝の問題だと勘違いされ、発見が遅れる原因となることがあります。
- 鼠径部(足の付け根)の痛み
- 太ももの前面から内側の痛み
- 膝の痛み
歩行時の異常(足を引きずるなど)
痛みを避けるため、あるいは股関節の動きが悪くなるために、歩き方に変化が現れます。無意識に患側の足をかばうようになり、足を引きずるような歩き方(跛行:はこう)が見られます。
また、すべりが生じた側の足先が、自然と外側を向くようになるのも特徴的なサインです。
本人は気づいていないことも多いため、周囲の家族が「最近、歩き方がおかしい」と気づいて受診につながるケースも少なくありません。
股関節の可動域制限
股関節の動きが悪くなるのも重要な症状です。特に、股関節を内側にひねる動き(内旋)と、深く曲げる動き(屈曲)が制限されます。
仰向けに寝た状態で膝を胸に近づけるように曲げていくと、自然と股関節が外側に開いてしまう(外旋してしまう)という現象が見られます。
これは、すべった骨頭が骨盤の骨と衝突するために起こるもので、この病気に非常に特徴的な所見です。
あぐらをかくのは楽なのに、内股の姿勢がとりにくい、という自覚症状があるかもしれません。
症状の進行度による分類(急性・慢性)
症状の現れ方によって、股関節すべり症はいくつかのタイプに分類されます。この分類は、治療方針を決定する上で重要です。
症状の経過による分類
| 分類 | 症状の期間 | 特徴 |
|---|---|---|
| 急性型 | 3週間未満 | 急激な強い痛みで歩行が困難になる。転倒などがきっかけになることも。 |
| 慢性型 | 3週間以上 | 軽度から中等度の痛みが持続。歩行時の跛行が主な症状。最も多いタイプ。 |
| 慢性急性増悪型 | 3週間以上 | 慢性的な痛みが続いていた中で、急に痛みが強くなり歩けなくなる。 |
また、痛みがありながらも松葉杖などを使えば歩ける状態を「安定型」、痛みで完全に体重をかけることができない状態を「不安定型」と分類することもあります。
不安定型は、骨頭への血流が途絶える合併症のリスクが高く、より緊急性の高い状態と判断します。
股関節すべり症の診断方法
股関節すべり症が疑われる症状がある場合、医療機関では正確な診断を下すために系統的な診察と検査を行います。
特に成長期のお子さんの股関節痛や膝痛では、この病気の可能性を常に念頭に置くことが重要です。診断は、主に医師による診察と画像検査を組み合わせて行われます。
ここでは、診断に至るまでの具体的な流れを解説します。
医師による問診と身体所見
まず、医師は患者さんやご家族から詳しい話を聞きます(問診)。
いつから、どこが、どのように痛むのか、痛みが強くなる動作はあるか、スポーツ活動の有無、最近の体重の変化、過去のケガの経験などを詳細に確認します。
特に「膝の痛み」を訴えている場合でも、股関節すべり症の可能性を考えて股関節の状態を注意深く聞きます。 続いて、身体所見をとります。
ベッドに仰向けに寝てもらい、股関節の動きを評価します。特徴的な所見は、股関節の可動域制限です。
特に股関節の内旋(内ひねり)が制限されているか、股関節を曲げていくと自然に足が外を向いてしまうか(外旋変形)を確認します。これらの所見は、診断の手がかりとして非常に有益です。
レントゲン(X線)検査の重要性
身体所見で股関節すべり症が強く疑われた場合、診断を確定するためにレントゲン検査を行います。これは最も重要で基本的な画像検査です。
通常、股関節を正面から撮影する像と、側面(軸位)から撮影する像の2方向から撮影します。 正面像では、骨端線が通常より広く見えたり、骨頭の高さが低く見えたりすることがあります。
より診断に有用なのは側面像で、大腿骨頚部に対して骨頭が後方にずれている様子を明確に捉えることができます。
ごく初期の軽微なすべりでは正面像で異常が見られないこともあるため、側面像の撮影は必須です。このレントゲン画像を用いて、すべりの程度を角度で評価し、重症度を判断します。
MRIやCT検査が必要なケース
ほとんどのケースではレントゲン検査で診断がつきますが、追加の情報が必要な場合にMRIやCT検査を行うことがあります。
各種画像検査の役割
| 検査方法 | 主な目的 | 利点 |
|---|---|---|
| レントゲン検査 | 診断の確定、重症度の評価 | 基本的で必須の検査。簡便で侵襲が少ない。 |
| CT検査 | すべりの三次元的な評価 | 骨の形状を詳細に把握でき、手術計画に有用。 |
| MRI検査 | 合併症の評価、超早期診断 | 骨頭壊死の有無や骨端線の炎症状態がわかる。 |
MRI検査は、レントゲンでは判断が難しいごく初期の「すべる前の段階(pre-slip)」の骨端線の炎症を描出したり、重篤な合併症である大腿骨頭壊死(骨への血流が悪くなる状態)の有無を評価したりするのに非常に役立ちます。
CT検査は、骨の立体的なずれ方を詳細に把握できるため、複雑な骨切り術などを行う際の手術計画の立案に有用です。
診断における注意点
前述の通り、この病気は膝の痛みとして現れることが多いため、膝の診察や検査のみで終わってしまうと、診断が見逃される危険性があります。
成長期のお子さんが原因不明の膝痛を訴える場合は、必ず股関節の評価を行うことが鉄則です。
また、片側の股関節すべり症と診断された場合、高い確率(20~40%程度)で反対側の股関節も将来的にすべりを起こす可能性があるため、症状がない反対側の股関節も注意深く観察していくことが重要です。
股関節すべり症の治療法
股関節すべり症の診断が確定したら、速やかに治療を開始します。
治療の主な目的は、①これ以上すべりを進行させないこと、②痛みを和らげ股関節の機能を回復させること、③将来的な変形性股関節症への進行を防ぐこと、の3点です。
治療法は、すべりの程度(重症度)や症状の安定性(安定型か不安定型か)に基づいて決定します。
治療方針の決定要因
治療法を決定する上で考慮する主な要因は以下の通りです。
- すべりの角度(軽度、中等度、重度)
- 症状の安定性(安定型、不安定型)
- 症状の持続期間(急性、慢性)
- 患者の年齢(骨の成熟度)
これらの要因を総合的に評価し、患者さん一人ひとりに合った治療計画を立てます。
一般的に、少しでもすべりが確認された場合は、進行を防ぐために手術的治療が選択されることがほとんどです。
保存的治療(免荷、安静)
保存的治療は、手術を行わない治療法です。
ごくまれに、レントゲンでは明らかなすべりはないもののMRIで骨端線の炎症が確認される「すべり前段階」と診断された場合に選択されることがあります。
その内容は、松葉杖を使用して患側の足に体重をかけないようにする「免荷(めんか)」と、運動を中止して安静を保つことです。
しかし、この方法ではすべりの進行を確実に防ぐことは難しく、長期間の免荷と安静が必要になるため、現在では主要な治療法とは考えられていません。
多くの場合、手術までの待機期間や、診断直後にさらなるすべりを防ぐための応急処置として行われます。
手術的治療の目的と種類
現在の股関節すべり症治療の基本は、手術による固定です。手術の最大の目的は、骨端線を固定して、それ以上のすべりの進行を永久に停止させることです。
すべりが軽度であれば、将来的な機能障害を残さずに済む可能性が高まります。手術方法は主に、すべりの程度に応じて選択されます。
スクリュー固定術
これは、最も一般的に行われる手術方法で、「in situ pinning」とも呼ばれます。すべりの程度が軽度から中等度の場合に選択されます。
皮膚を小さく切開し、レントゲンで確認しながら、大腿骨の側面から骨端線を貫くように金属製のスクリュー(ネジ)を1本または2本挿入して、骨頭と骨頚部を固定します。
現在のずれた位置のままで固定する手術ですが、これにより骨端線が安定し、将来的に骨が成熟して閉鎖するまでの間の進行を防ぎます。比較的、体への負担が少ない手術です。
骨切り術
すべりの角度が大きい重症例では、ずれた骨頭をそのままの位置で固定するだけでは、股関節の動きの制限が残ったり、将来的に大腿骨と骨盤が衝突して痛みや変形性股関節症の原因になったりするリスクがあります。
このような場合に、ずれを矯正して股関節の形を正常に近づける目的で行われるのが骨切り術です。大腿骨の骨頭の下あたりで骨を切り、骨頭を正しい位置に戻してからプレートやスクリューで再固定します。
スクリュー固定術に比べて体への負担は大きくなりますが、股関節の機能をより良く再建することが期待できます。
手術方法の概要比較
| 手術方法 | 主な対象 | 目的 |
|---|---|---|
| スクリュー固定術 | 軽度~中等度のすべり | すべりの進行防止(現状での固定) |
| 骨切り術 | 重度のすべり | すべりの矯正と進行防止 |
治療における合併症のリスク
股関節すべり症の治療、特に手術においては、いくつかの合併症のリスクが存在します。
最も注意すべき合併症は、「大腿骨頭壊死症」と「軟骨融解症」です。大腿骨頭壊死症は、骨頭へ栄養を送る血管が損傷し、骨頭が死んでしまう病気です。
特に、急激に発症した不安定型のすべり症でリスクが高くなります。軟骨融解症は、原因不明ですが股関節の軟骨が急激にすり減ってしまう状態です。
これらの合併症は、股関節の機能に深刻な後遺症を残す可能性があるため、治療中は細心の注意を払って経過を観察します。
治療後のリハビリテーション
股関節すべり症の治療において、手術と同じくらい重要なのが、その後のリハビリテーションです。
リハビリは、低下した筋力や関節の動きを回復させ、痛みをなくし、最終的に学業やスポーツを含む元の生活へ円滑に戻るために行います。
手術方法や患者さんの状態に合わせて、専門家の指導のもとで段階的に進めていくことが大切です。
リハビリテーションの目的
治療後のリハビリの主な目的は、単に「歩けるようにする」だけではありません。質の高い生活を取り戻すために、以下のような多角的な目標を設定します。
- 疼痛の管理と軽減
- 関節可動域の改善
- 筋力の回復とバランス能力の向上
- 正しい歩行パターンの再学習
- スポーツや日常生活への安全な復帰
手術直後から開始するリハビリ
リハビリは手術の翌日など、非常に早い段階から開始します。この時期は、手術で固定した部分に過度な負担をかけないことが最優先です。
主な内容は、ベッドの上で行える運動が中心です。足首を動かす運動で血流を促進し、血栓(エコノミークラス症候群)を防ぎます。
また、膝の曲げ伸ばしや、患側以外の足の筋力トレーニングも行います。
理学療法士の指導のもと、股関節に体重をかけずに動かす練習(他動運動や自動介助運動)を開始し、関節が硬くなるのを防ぎます。
体重をかける時期のリハビリ
骨の固定性が良好であることをレントゲンで確認した後、医師の許可が出たら、徐々に体重をかける練習(荷重訓練)を開始します。
通常は、まず体重の一部(1/3など)から始め、松葉杖を使いながら慎重に進めます。この時期は、正しい歩き方を再学習することが重要です。
痛みをかばう歩き方が癖になっていることが多いため、理学療法士が歩行フォームを細かくチェックし、修正していきます。
並行して、股関節周囲の筋力(特にお尻の筋肉である中殿筋)を強化するトレーニングを本格化させていきます。
リハビリの段階的な目標
| 時期 | 主な目標 | リハビリ内容の例 |
|---|---|---|
| 手術直後~荷重開始前 | 疼痛管理、関節拘縮予防 | ベッド上での関節可動域訓練、筋力維持訓練 |
| 部分荷重期 | 正しい歩行の基礎学習 | 松葉杖での歩行訓練、股関節周囲の筋力強化 |
| 全荷重期~復帰準備期 | 筋力・持久力・バランス能力の向上 | 杖なし歩行、水中運動、ジョギング、競技特性に応じた訓練 |
スポーツや日常生活への復帰に向けた取り組み
痛みなく杖なしで歩けるようになり、筋力も十分に回復してきたら、最終段階のリハビリに移ります。日常生活の様々な動作(階段昇降、しゃがみ込みなど)をスムーズに行えるように練習します。
スポーツへの復帰を目指す場合は、ジョギングから開始し、徐々にランニング、ジャンプ、方向転換など、競技特有の動きを取り入れたトレーニングへと移行していきます。
復帰のタイミングは、筋力や関節機能が十分に回復し、医師や理学療法士が安全だと判断してからになります。焦らず、専門家の指導に従うことが再発や新たな怪我を防ぐ鍵です。
股関節すべり症の予後と長期的な注意点
股関節すべり症の治療を終えた後、多くの患者さんは元の生活に戻ることができます。しかし、長期的に見ると、いくつか注意すべき点があります。
治療後の経過(予後)は、発見されたときの重症度や治療の適切さに大きく左右されます。ここでは、長期的な健康を維持するために知っておくべきことについて解説します。
早期発見・早期治療の重要性
股関節すべり症の予後を決定づける最大の要因は、いかに早く発見し、治療を開始できたか、という点に尽きます。
すべりの角度が軽微なうちに手術で進行を止められれば、股関節の形状はほぼ正常に保たれ、長期的な機能も良好に維持できる可能性が非常に高くなります。
発見が遅れて重度のすべりになってしまうと、たとえ矯正手術を行ったとしても、完全な正常形態に戻すことは難しく、将来的に何らかの症状が残るリスクが高まります。
将来的な変形性股関節症への移行リスク
股関節すべり症の最も懸念される長期的な合併症は、「変形性股関節症」への移行です。
大腿骨頭のすべりによって股関節の形状が正常でなくなると、関節軟骨の特定の部分に負担が集中しやすくなります。
この状態が長年続くと、軟骨がすり減り、骨が変形して、痛みや可動域制限を引き起こす変形性股関節症を発症するリスクが高まります。
このリスクは、治療開始時のすべりの程度が重度であったほど高くなります。適切な治療によって、そのリスクを最小限に抑えることが治療の大きな目標の一つです。
日常生活で心がけるべきこと
治療後、特に成長が止まって骨端線が閉鎖した後は、日常生活に大きな制限はありません。
しかし、股関節への負担を減らし、良好な状態を長く維持するために、いくつか心がけると良い点があります。
日常生活での注意点
| 項目 | 具体的な内容 | 目的 |
|---|---|---|
| 体重管理 | 適正体重を維持する | 股関節への力学的負担を軽減する |
| 運動習慣 | 水泳や自転車など股関節に優しい運動を続ける | 股関節周囲の筋力を維持し、関節を安定させる |
| 動作の工夫 | 重い物を持ち上げる際などに無理な姿勢を避ける | 股関節への急激な負荷を避ける |
定期的な検診の必要性
症状がなくなったとしても、自己判断で通院をやめてしまうのは禁物です。治療後も、医師の指示に従って定期的にレントゲン検査などを受けることが重要です。
特に、成長が完了するまでは、固定したスクリューの状態や、反対側の股関節にすべりが起きていないかなどをチェックする必要があります。
成長が完了した後も、数年に一度は検診を受け、変形性股関節症の兆候がないかなどを確認していくことが、長期的な股関節の健康維持につながります。
よくある質問
股関節すべり症に関して、患者さんやご家族から寄せられることの多い質問とその回答をまとめました。治療やその後の生活に関する疑問や不安の解消にお役立てください。
Q. 成長が止まれば自然に治りますか?
A. いいえ、自然に治ることはありません。一度ずれてしまった骨の位置が、成長の停止とともに自然に元に戻ることはありません。
成長が止まれば、骨端線が閉鎖して硬い骨になるため、それ以上すべりが進行することはなくなります。しかし、ずれた状態のまま骨が固まってしまうため、関節の機能障害や将来の変形性股関節症のリスクは残ります。
そのため、成長が止まるのを待つのではなく、診断された時点ですべりの進行を止める治療を行うことが原則です。
Q. スポーツはいつから再開できますか?
A. スポーツへの復帰時期は、行った手術の種類、回復の程度、そして競技の内容によって大きく異なります。
医師がレントゲンで骨の癒合状態が良好であることを確認し、理学療法士が筋力や関節の機能、バランス能力などが競技に耐えうるレベルまで回復したと判断してから、段階的に復帰を許可します。
一般的には、手術後6ヶ月から1年程度が一つの目安となりますが、個人差が大きいため、必ず専門家の許可を得てください。自己判断での早期復帰は、再受傷や後遺症のリスクを高めるため危険です。
Q. 反対側の股関節もすべり症になりますか?
A. その可能性は十分にあります。片側の股関節すべり症と診断された患者さんのうち、約20~40%が、後に反対側の股関節にも発症すると報告されています。
これを「両側性」と呼びます。発症には体質的な要因(ホルモンバランスや骨端線の脆弱性)が関わっているため、片側に発症したということは、反対側にも同様のリスクがあると考えられます。
そのため、治療中や治療後も、症状のない反対側の股関節の状態を定期的にレントゲンでチェックしていくことが非常に重要です。
Q. 大人になってから発症することはありますか?
A. 大腿骨頭すべり症は、成長期に骨端線が開いている時期に特有の病気です。したがって、骨の成長が完全に終了し、骨端線が閉鎖した成人になってから新たに発症することはありません。
ただし、思春期に軽度のすべり症を発症したものの、症状が軽かったために気づかずに過ごし、成人になってから股関節の痛みや変形性股関節症として発見されるケースはあります。
この場合、原因は子どもの頃のすべり症であった、ということになります。
以上
参考文献
AMARA, S. Abu; LEROUX, J.; LECHEVALLIER, J. Surgery for slipped capital femoral epiphysis in adolescents. Orthopaedics & Traumatology: Surgery & Research, 2014, 100.1: S157-S167.
BENCHOT, Rosalie. The adolescent with slipped capital femoral epiphysis. Journal of pediatric nursing, 1996, 11.3: 175-182.
NEGRU, Marius, et al. The role of physical exercise in the rehabilitation of children with surgically treated unilateral slipped capital femoral epiphysis. Balneo & PRM Research Journal, 2025, 16.1.
GIOVANOULIS, Vasileios, et al. Slipped Capital Femoral Epiphysis in Adolescents: Functional Outcomes and Return to Physical Activity after Surgical Treatment. Maedica, 2023, 18.3: 420.
ARONSSON, David D.; LODER, Randall T. Treatment of the unstable (acute) slipped capital femoral epiphysis. Clinical Orthopaedics and Related Research®, 1996, 322: 99-110.
ARONSSON, David D., et al. Slipped capital femoral epiphysis: current concepts. JAAOS-Journal of the American Academy of Orthopaedic Surgeons, 2006, 14.12: 666-679.
ARONSSON, David D.; KAROL, Lori A. Stable slipped capital femoral epiphysis: evaluation and management. JAAOS-Journal of the American Academy of Orthopaedic Surgeons, 1996, 4.4: 173-181.
PECK, David M.; VOSS, Lisa M.; VOSS, Tyler T. Slipped capital femoral epiphysis: diagnosis and management. American Family Physician, 2017, 95.12: 779-784.
CRAWFORD, Alvin H. Slipped capital femoral epiphysis. JBJS, 1988, 70.9: 1422-1427.
GEORGIADIS, Andrew G.; ZALTZ, Ira. Slipped capital femoral epiphysis: how to evaluate with a review and update of treatment. Pediatric Clinics, 2014, 61.6: 1119-1135.
Symptoms 症状から探す