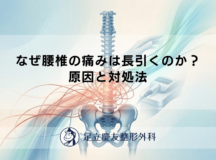椎間板の変性による症状と機能障害について
長引く腰痛や足のしびれに悩んでいませんか。その不調の原因は、背骨の間でクッションの役割を担う「椎間板」の性質が変化する「変性」にあるかもしれません。
椎間板は年齢とともに少しずつ水分を失い、本来の弾力性が低下します。この変化が、痛みやしびれといった様々な症状、さらには日常生活における機能障害につながることがあります。
この記事では、椎間板の変性がなぜ起こるのか、それによってどのような症状が現れるのか、そして日常生活でどのような点に気をつければ良いのかを詳しく解説します。
目次
椎間板の役割と構造の基本
はじめに、私たちの体を支える背骨の重要な構成要素である椎間板について、その基本的な働きと構造を理解することから始めましょう。
椎間板がどのようなもので、なぜこれほど大切なのかを知ることは、変性によって生じる問題を理解する上で基礎となります。
背骨を支えるクッション「椎間板」とは
椎間板は、一つ一つの背骨(椎骨)の間に存在する、軟骨組織の一種です。
中央にはゼリー状の「髄核」があり、その周りをコラーゲン線維でできた「線維輪」が何層にもなって取り囲む二重構造をしています。
この構造により、歩行や運動の際に背骨にかかる衝撃を吸収し、分散させるクッションとしての重要な役割を果たします。
また、背骨が滑らかに動くための土台となり、体を曲げたりひねったりする動作を可能にしています。
椎間板を構成する主な成分
椎間板の機能は、その構成成分によって支えられています。中心部の髄核は、約80%が水分で、その他にプロテオグリカンという保水性の高い物質を豊富に含んでいます。
この水分とプロテオグリカンが、椎間板の弾力性と衝撃吸収能力の源です。
一方、外側の線維輪は、丈夫なコラーゲン線維が層状に重なってできており、髄核を正しい位置に保持し、ねじれや過度な動きに耐える強度を持っています。
年齢と椎間板の水分含有率
| 年代 | 髄核の水分含有率(目安) | 特徴 |
|---|---|---|
| 若年期(10〜20代) | 約80〜85% | 最も弾力性が高く、衝撃吸収能力に優れる。 |
| 中年期(30〜50代) | 約70〜75% | 徐々に水分が減少し始め、弾力性が低下してくる。 |
| 高年期(60代以降) | 70%未満 | 水分量が大きく減少し、線維輪に亀裂が入りやすくなる。 |
健康な椎間板が持つ弾力性とその重要性
健康な椎間板が持つ高い弾力性は、日常生活を送る上で極めて重要です。ジャンプした時や重い物を持った時に背骨にかかる大きな力を和らげ、骨や神経を守ります。
もし椎間板がなければ、骨同士が直接ぶつかり合い、少しの動作でも強い痛みを感じたり、骨がすり減ってしまったりするでしょう。
この弾力性があるからこそ、私たちは痛みを感じることなく、自由に体を動かすことができるのです。
椎間板への栄養供給の仕組み
椎間板の大きな特徴として、内部に血管が存在しない点が挙げられます。そのため、血液から直接栄養を受け取ることができません。
椎間板の栄養は、上下にある椎骨の端の軟骨部分(椎体終板)を通して、ゆっくりと染み込むようにして供給されます。
この栄養供給は、体を動かすことで椎間板の内圧が変化し、ポンプのように水分や栄養素が出入りすることで促進されます。適度な運動が椎間板の健康維持に大切なのは、このためです。
椎間板の変性が起こる原因
椎間板はなぜ時間とともにその性質を変えてしまうのでしょうか。ここでは、椎間板の変性を引き起こす主な要因について掘り下げていきます。
加齢だけでなく、日々の生活習慣や遺伝的な要素も関わっていることを理解しましょう。
主な原因としての加齢変化
椎間板の変性を引き起こす最も大きな原因は、加齢に伴う自然な変化です。年齢を重ねると、髄核の水分やプロテオグリカンが減少し、クッションとしての機能が低下します。
同時に、線維輪にも小さな亀裂が入りやすくなり、耐久性が落ちてきます。これらの変化により、椎間板全体の高さが低くなり、衝撃をうまく吸収できなくなります。
これは誰にでも起こりうる生理的な変化ですが、その進行度には個人差があります。
日常生活に潜む負担と影響
日々の生活習慣も、椎間板の変性を促進する大きな要因です。特に、長時間同じ姿勢を取り続けることは、椎間板内の圧力を持続的に高め、栄養供給を妨げます。
デスクワークや長距離運転、あるいは中腰での作業などは、椎間板に大きな負担をかけます。
また、姿勢の悪さ、例えば猫背の状態で座り続けると、特定の椎間板に圧力が集中し、変性が進みやすくなります。
姿勢による椎間板内圧の変化
| 姿勢 | 椎間板への負荷(立位を100として) | 解説 |
|---|---|---|
| 仰向け | 約25 | 最も負荷が少ない姿勢。 |
| 直立 | 100 | 基準となる負荷。 |
| 椅子に座る(背筋を伸ばす) | 約140 | 立っている時よりも負荷が大きい。 |
| 前かがみで座る | 約185 | 椎間板への圧力が非常に高くなる。 |
遺伝的要因と生活習慣の関連
椎間板の変性のしやすさには、遺伝的な要因も関与していると考えられています。
生まれつき椎間板の組織が弱い、あるいは変性を起こしやすい体質がある場合、若いうちから症状が現れることもあります。
また、喫煙は椎間板周囲の毛細血管の血流を悪化させ、栄養供給を妨げるため、変性を助長する要因として知られています。
運動不足による体幹の筋力低下も、背骨を支える力が弱まり、結果的に椎間板への負担を増やすことにつながります。
外傷や特定の疾患による影響
交通事故やスポーツ中の激しい衝突、高所からの転落など、背骨に強い外力が加わることで、椎間板が損傷し、変性が一気に進むことがあります。
また、まれではありますが、背骨の感染症(化膿性脊椎炎)や炎症性の疾患が、椎間板組織を破壊し、変性の原因となることもあります。
生まれつきの背骨の形態異常、例えば側弯症なども、背骨のバランスが崩れることで特定の椎間板に負担が集中し、変性を早める可能性があります。
椎間板の変性によって現れる主な症状
椎間板の変性が進行すると、体にどのようなサインが現れるのでしょうか。痛みやしびれといった代表的な症状から、感覚の異常や筋力低下まで、具体的な症状を詳しく見ていきます。
これらの症状がなぜ起こるのか、その背景も解説します。
腰部に現れる痛み(腰痛)
最も一般的な症状は腰痛です。椎間板の変性による腰痛は、「ズキズキ」「ジンジン」といった鈍い痛みが持続することが多いのが特徴です。
特に、朝起きた時や、長時間座った後など、同じ姿勢を続けた後に動き始めると痛みが強く出ることがあります。
これは、変性した椎間板が炎症を起こしたり、椎間板の周りにある痛みを感知する神経が刺激されたりすることで生じます。
痛みは腰の中心部だけでなく、お尻のあたりに感じることもあります。
下半身に広がる痛みやしびれ(坐骨神経痛)
椎間板の変性が進み、線維輪に亀裂が入って髄核が後方に飛び出すと、背骨の中を通る神経を圧迫することがあります。この状態が「椎間板ヘルニア」です。
圧迫された神経が支配する領域、主にお尻から太ももの裏、ふくらはぎ、足先にかけて、電気が走るような鋭い痛みや、「ビリビリ」「ジンジン」としたしびれが生じます。
これは一般的に「坐骨神経痛」と呼ばれる症状の代表的な原因の一つです。
圧迫される神経根と症状が現れる部位
| 圧迫されやすい神経根 | 主な症状が現れる範囲 | 伴いやすい筋力低下 |
|---|---|---|
| 第4腰神経根 (L4) | 太ももの前側から膝、すねの内側 | 膝を伸ばす力の低下 |
| 第5腰神経根 (L5) | お尻から太ももの外側、すね、足の甲、親指 | 足首や足の親指を反らす力の低下 |
| 第1仙骨神経根 (S1) | お尻から太ももの裏、ふくらはぎ、足の裏、小指側 | つま先立ちをする力の低下 |
感覚障害と筋力の低下
神経への圧迫が強くなると、痛みやしびれだけでなく、感覚が鈍くなる「感覚障害」や、筋肉に力が入らなくなる「筋力低下」が現れることがあります。
例えば、「足の裏の感覚がおかしい」「皮膚を触っても感じにくい」といった症状や、「スリッパが意図せず脱げてしまう」「何もないところでつまずきやすい」といったサインが見られます。
特に、足首を上に反らす力や、足の指を曲げ伸ばしする力が弱くなることが多いです。
日常生活における動作の制限
痛みやしびれ、筋力低下は、日常生活の様々な動作に支障をきたします。長時間椅子に座っているのが辛くなったり、立っているだけで腰や足が痛くなったりします。
特に、前かがみの姿勢(洗顔、靴下を履く動作など)や、重い物を持つ動作で痛みが強くなる傾向があります。
歩行中に症状が悪化することもありますが、少し休むとまた歩けるようになる「間欠性跛行」は、後述する腰部脊柱管狭窄症でより典型的な症状です。
椎間板の変性が引き起こす代表的な疾患
椎間板の変性は、それ自体が問題であると同時に、様々な背骨の疾患を引き起こす出発点にもなります。
ここでは、変性した椎間板が原因となって発症する代表的な疾患について、それぞれの特徴と症状を解説します。
椎間板症
椎間板症は、椎間板ヘルニアのように髄核が飛び出しているわけではないものの、椎間板自体の変性によって慢性的な腰痛が生じている状態を指します。
椎間板の水分が失われてクッション機能が低下し、内部に亀裂が入ることで、椎間板自体が痛みの発生源となります。
レントゲン検査では明らかな異常が見つかりにくく、診断が難しいこともあります。主に前かがみや座位で悪化する腰痛が特徴です。
腰椎椎間板ヘルニア
腰椎椎間板ヘルニアは、変性によって弱くなった線維輪が断裂し、中の髄核が後方に脱出して神経根を圧迫する疾患です。
これにより、腰痛に加えて、お尻から足にかけての激しい痛みやしびれ(坐骨神経痛)を引き起こします。
20代から40代の比較的若い世代に多く見られ、重い物を持ち上げたり、体をひねったりした際に急に発症することもあります。
ヘルニアのタイプと特徴
| ヘルニアのタイプ | 状態 | 主な特徴 |
|---|---|---|
| 膨隆型 | 線維輪は保たれているが、全体的に後方へ膨らむ。 | 比較的軽度の症状が多い。 |
| 突出型 | 線維輪の一部が破れ、髄核が押し出される。 | 典型的なヘルニアで、強い神経症状が出やすい。 |
| 脱出型 | 髄核が完全に線維輪を突き破り、外に漏れ出す。 | 激しい痛みを伴うことが多いが、自然に吸収されることもある。 |
変形性脊椎症
椎間板の変性が長期間続くと、椎間板の高さが減少し、隣り合う椎骨同士が不安定になります。
この不安定性を補うために、体の防御反応として椎骨の縁に「骨棘」と呼ばれる骨のトゲが形成されることがあります。
この状態が変形性脊椎症です。骨棘が形成されると、背骨の動きが悪くなり、可動域が制限されたり、動かした時に痛みを感じたりします。
加齢とともに誰にでも起こりうる変化の一つです。
腰部脊柱管狭窄症との関連
椎間板の変性は、腰部脊柱管狭窄症の発症にも深く関わっています。脊柱管とは、背骨の中にある神経の通り道のことです。
変性によって椎間板が後方に膨らんだり(膨隆)、変形性脊椎症でできた骨棘が形成されたり、さらには背骨の後方にある黄色靭帯が分厚くなったりすることで、この神経の通り道が狭くなります。
このことにより、神経が圧迫され、歩行時に足の痛みやしびれが悪化し、少し休むと楽になるという特徴的な症状(間欠性跛行)が現れます。
医療機関で行う検査と診断
腰痛やしびれの原因を正確に特定するためには、医療機関での適切な検査が重要です。
問診から始まり、体の状態を詳しく調べるための画像検査まで、どのような手順で診断が行われるのかを具体的に説明します。
診断の第一歩となる問診と身体所見
診断は、まず患者さんの話を詳しく聞くことから始まります。いつから、どのような症状があるのか、どんな時に痛みが強くなるか、日常生活で困っていることなどを具体的に伝えます。
その後、医師が実際に体を動かしたり、感覚や筋力を調べたりする身体所見を行います。
例えば、仰向けで寝て膝を伸ばしたまま足を上げるSLRテストは、椎間板ヘルニアを疑う際によく行われる検査です。
- 症状(痛み、しびれ、脱力など)の具体的な内容と場所
- 症状が始まった時期やきっかけ
- 症状が強くなる、あるいは和らぐ動作や姿勢
- 日常生活への支障の程度
レントゲン(X線)検査でわかること
レントゲン検査は、主に骨の状態を評価するために行います。椎骨の変形(骨棘の有無)、骨折の有無、背骨全体の並び(アライメント)などを確認できます。
椎間板自体の変性によって椎間板の高さが低くなっている(椎間腔狭小化)様子も観察できます。
ただし、レントゲンには椎間板や神経そのものは写らないため、これらの組織の状態を直接見ることはできません。
MRI検査による詳細な評価
MRI検査は、椎間板の変性を診断する上で非常に有用な検査です。
磁気を利用して体の断面を撮影するため、レントゲンでは見えない椎間板、神経、筋肉、靭帯といった軟部組織の状態を鮮明に映し出すことができます。
椎間板の水分がどの程度失われているか(変性の程度)、椎間板ヘルニアがどこにどの程度飛び出しているか、神経がどれくらい圧迫されているかを正確に評価することが可能です。
レントゲンとMRIの比較
| 検査項目 | レントゲン検査 | MRI検査 |
|---|---|---|
| 得意な領域 | 骨の形状、骨折、アライメント | 椎間板、神経、筋肉などの軟部組織 |
| 椎間板の状態 | 間接的に推測(高さの減少など) | 直接的に評価(変性の程度、ヘルニアの有無) |
| 放射線被ばく | あり | なし |
その他の検査(CT検査、椎間板造影など)
場合によっては、さらに詳しい検査を行うこともあります。
CT検査は、レントゲンと同様に放射線を使いますが、体を輪切りにしたような詳細な画像が得られるため、骨の細かい構造や骨棘の状態をより詳しく評価するのに適しています。
椎間板造影検査は、痛みの原因となっている椎間板を特定するために、椎間板に直接造影剤を注入してレントゲン撮影を行う検査です。
痛みの再現性を見ることで、診断を確定させる目的で行われます。
自宅でできるセルフケアと予防法
椎間板への負担を減らし、症状の悪化を防ぐためには、日々の生活の中での工夫が大切です。
ここでは、専門家の指導のもとで行うことを前提に、自宅で取り組めるセルフケアや予防のためのポイントを紹介します。
日常生活での姿勢の見直し
椎間板への負担を減らす基本は、正しい姿勢を保つことです。座る時は、椅子に深く腰掛け、背もたれを利用して骨盤を立てるように意識します。
必要であれば、腰にクッションや丸めたタオルを当てるのも良い方法です。立つ時は、片足に体重をかける「休め」の姿勢を長時間続けないようにし、両足に均等に体重を乗せましょう。
寝る姿勢は、仰向けで膝の下にクッションを入れるか、横向きで膝を軽く曲げると腰への負担が和らぎます。
良い姿勢と悪い姿勢のポイント
| 動作 | 良い例 | 悪い例 |
|---|---|---|
| 座り方 | 深く腰掛け、骨盤を立てる。 | 浅く腰掛け、背中を丸める(猫背)。 |
| 立ち方 | 両足に均等に体重を乗せる。 | 片足に重心をかけ続ける。 |
| 寝方 | 仰向けで膝下にクッション、または横向き。 | うつ伏せ(腰が反りやすい)。 |
椎間板に優しい動作の心がけ
日常の何気ない動作にも注意が必要です。床の物を拾う時は、腰を曲げるのではなく、股関節と膝をしっかりと曲げて腰を落とすようにします。
洗顔や歯磨きの際も、少し膝を曲げて前かがみの角度を浅くすると良いでしょう。最も重要なのは、長時間同じ姿勢を続けないことです。
デスクワークの合間には、少なくとも1時間に1回は立ち上がって軽く体を動かし、椎間板への圧力を解放してあげましょう。
- 物を持ち上げる
- 掃除機をかける
- 靴下を履く
- 長時間の運転
体幹を支える筋力トレーニング
背骨を安定させるためには、腹筋や背筋といった体幹の筋肉(インナーマッスル)をバランス良く鍛えることが重要です。
これらの筋肉が天然のコルセットのように働き、椎間板への負担を軽減してくれます。ただし、やみくもに腹筋運動などを行うと、かえって腰を痛める可能性があります。
ドローイン(お腹をへこませる運動)など、腰に負担の少ない運動から始め、専門家の指導を受けながら行うことが望ましいです。
ストレッチによる柔軟性の維持
腰や股関節周りの筋肉が硬くなっていると、背骨の動きが悪くなり、椎間板への負担が増加します。
特に、お尻の筋肉や太ももの裏側(ハムストリングス)の柔軟性を保つことは、腰痛の予防・改善に効果的です。
お風呂上がりなど、体が温まっている時に、気持ち良いと感じる範囲でゆっくりとストレッチを行いましょう。強い痛みを感じる場合は、無理に行わないでください。
症状が悪化した場合の対処法
セルフケアを続けていても、症状が改善しない、あるいは悪化してしまうこともあります。そのような時には、どのような選択肢があるのでしょうか。
保存療法から、場合によっては手術療法まで、一般的な治療法について解説します。
専門医への相談のタイミング
セルフケアだけでは対応が難しいと感じたら、我慢せずに整形外科などの専門医に相談することが大切です。
特に、痛みがどんどん強くなる、足のしびれや筋力低下が明らかに進行している、といった場合は早めの受診が必要です。
また、非常にまれですが、尿が出にくい、便意を感じないといった「膀胱直腸障害」の症状が現れた場合は、緊急の対応が必要なサインですので、すぐに医療機関を受診してください。
- 安静にしていても痛みが治まらない
- 足の麻痺が進行し、歩行が困難になる
- 排尿や排便のコントロールができない
保存療法の主な内容
多くの場合、治療はまず手術以外の「保存療法」から開始します。
薬物療法では、痛みを抑えるための消炎鎮痛薬や、筋肉の緊張を和らげる筋弛緩薬、神経の痛みに特化した薬などが用いられます。
物理療法として、患部を温めたり、電気を流したりして血行を改善し、痛みを和らげることもあります。
痛みが特に強い場合には、痛みの原因となっている神経の周りに局所麻酔薬などを注射する「ブロック注射」が有効な場合があります。
保存療法の種類と目的
| 治療法 | 主な目的 | 内容の例 |
|---|---|---|
| 薬物療法 | 痛みや炎症を抑える | 消炎鎮痛薬、筋弛緩薬、神経障害性疼痛治療薬 |
| 理学療法 | 痛みの緩和、機能回復 | 物理療法(温熱、電気)、運動療法、ストレッチ |
| ブロック注射 | 強い痛みを取り除く | 神経根ブロック、硬膜外ブロック |
運動療法の役割と進め方
運動療法は、保存療法の中でも中心的な役割を担います。理学療法士などの専門家の指導のもと、個々の症状や体の状態に合わせた運動プログラムを実施します。
痛みを悪化させない範囲で、体幹の安定性を高めるトレーニングや、硬くなった筋肉のストレッチを行い、背骨の正しい動きを取り戻し、症状の再発を防ぐことを目指します。
自分だけで判断せず、専門家と一緒に進めることが重要です。
手術療法が検討されるケース
数ヶ月間、保存療法を続けても症状の改善が見られない場合や、日常生活への支障が非常に大きい場合には、手術療法が検討されます。
また、足の麻痺が進行している場合や、排尿・排便障害が出現した場合は、早期の手術が必要となることがあります。
手術の方法には、ヘルニアを取り除くものや、不安定になった背骨を固定するものなど、様々な種類があり、病状に応じて最適な方法が選択されます。
椎間板の変性に関するよくある質問
最後に、椎間板の変性やそれに伴う症状について、多くの方が抱く疑問にお答えします。ご自身の状態をより深く理解し、不安を解消するためにお役立てください。
一度変性した椎間板は元に戻りますか
残念ながら、加齢変化である椎間板の変性を完全に元の若い状態に戻すことは、現在の医療では困難です。
しかし、変性したこと自体が問題なのではなく、それによって引き起こされる症状や機能障害が問題となります。
適切な治療やセルフケアを行うことで、症状をコントロールし、変性の進行を緩やかにすることは十分に可能です。
変性と上手く付き合いながら、腰への負担を管理していくという考え方が大切です。
温めるのと冷やすのはどちらが良いですか
痛みの性質や時期によって使い分けるのが一般的です。
ぎっくり腰のように急に強い痛みが出た場合(急性期)は、炎症が起きている可能性が高いため、冷やして炎症を鎮めるのが良いとされています。
一方で、慢性的に続く鈍い痛みや筋肉のこわばりに対しては、温めて血行を促進することで症状が和らぐことが多いです。どちらが良いか迷う場合は、自己判断せず専門家に相談しましょう。
温罨法と冷罨法の使い分け
| 時期 | 推奨される方法 | 目的 |
|---|---|---|
| 急性期(発症直後) | 冷やす(冷罨法) | 炎症や腫れを抑える。 |
| 慢性期(痛みが続く) | 温める(温罨法) | 血行を促進し、筋肉の緊張を和らげる。 |
どのような運動を避けるべきですか
症状がある時には、腰に大きな負担がかかる運動は避けるべきです。
具体的には、腰を強くひねる動作(ゴルフのスイングなど)、急激に体を反らす動作、ジャンプを繰り返す運動などが挙げられます。
また、重いウェイトを使った筋力トレーニングも、正しいフォームで行わないと腰を痛めるリスクがあります。
どのような運動が安全で効果的かは、個人の状態によって大きく異なるため、医師や理学療法士に相談することが重要です。
サポーターやコルセットは有効ですか
痛みが非常に強い急性期に、一時的に腰の動きを制限して安定させる目的でサポーターやコルセットを使用することは有効です。
しかし、長期間にわたって常に装着していると、本来腰を支えるべき自分自身の筋肉(腹筋や背筋)が弱ってしまい、かえって腰痛を悪化させる原因にもなりかねません。
あくまで一時的な補助具として考え、頼りすぎないことが大切です。使用する期間やタイミングについては、医師の指示に従いましょう。
以上
参考文献
LUOMA, Katariina, et al. Low back pain in relation to lumbar disc degeneration. Spine, 2000, 25.4: 487-492.
PETERSON, Cynthia K.; BOLTON, Jennifer E.; WOOD, Angela R. A cross-sectional study correlating lumbar spine degeneration with disability and pain. Spine, 2000, 25.2: 218.
DE SCHEPPER, Evelien IT, et al. The association between lumbar disc degeneration and low back pain: the influence of age, gender, and individual radiographic features. Spine, 2010, 35.5: 531-536.
SALEEM, Shafaq, et al. Lumbar disc degenerative disease: disc degeneration symptoms and magnetic resonance image findings. Asian spine journal, 2013, 7.4: 322.
MÖLLER, Hans; SUNDIN, Agneta; HEDLUND, Rune. Symptoms, signs, and functional disability in adult spondylolisthesis. Spine, 2000, 25.6: 683-690.
ZHENG, Chang-Jiang; CHEN, James. Disc degeneration implies low back pain. Theoretical Biology and Medical Modelling, 2015, 12.1: 24.
SAMARTZIS, Dino, et al. A population-based study of juvenile disc degeneration and its association with overweight and obesity, low back pain, and diminished functional status. JBJS, 2011, 93.7: 662-670.
CHEUNG, Kenneth MC, et al. Are “patterns” of lumbar disc degeneration associated with low back pain?: new insights based on skipped level disc pathology. Spine, 2012, 37.7: E430-E438.
BRINJIKJI, W., et al. MRI findings of disc degeneration are more prevalent in adults with low back pain than in asymptomatic controls: a systematic review and meta-analysis. American Journal of Neuroradiology, 2015, 36.12: 2394-2399.
PHILLIPS, Frank M., et al. Lumbar spine fusion for chronic low back pain due to degenerative disc disease: a systematic review. Spine, 2013, 38.7: E409-E422.
Symptoms 症状から探す