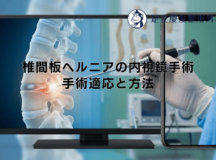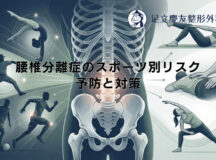整形外科で行う股関節の骨折治療とリハビリ
股関節は、立つ、歩く、座るといった私たちの基本的な日常動作を支える体の重要な部分です。この股関節を骨折すると、激しい痛みを伴い、多くの場合、自力で動くことが困難になります。
特に高齢の方に多く見られ、骨折をきっかけに寝たきりになってしまう危険性も指摘されています。
しかし、適切な治療とリハビリテーションを早期に開始することで、再び歩けるようになる可能性は十分にあります。
この記事では、整形外科でどのような診断や治療を行うのか、そして回復にむけてどのようなリハビリが必要になるのかを、順を追って詳しく解説します。
目次
股関節骨折とは?基本的な知識
私たちの体を支え、活動的な生活を送る上で中心的な役割を担う股関節。この部分の骨折は、生活の質に直接的な影響を及ぼす重大な怪我です。
ここでは、まず股関節の構造と、どのような骨折が起こるのかについて、基本的な知識から解説します。
股関節の構造と役割
股関節は、骨盤の寛骨臼(かんこつきゅう)というくぼみに、太ももの骨である大腿骨(だいたいこつ)の先端にある球状の大腿骨頭(だいたいこつとう)がはまり込む形をしています。
この構造は「球関節」と呼ばれ、脚を様々な方向に自由に動かすことを可能にしています。関節の表面は滑らかな軟骨で覆われており、衝撃を吸収し、動きをスムーズにする役割を果たします。
また、関節の周りは強靭な靭帯や筋肉で補強されており、体重を支えながら安定性を保っています。
骨折が起こりやすい部位
股関節の骨折は、正確には「大腿骨近位部骨折(だいたいこつきんいぶこっせつ)」を指します。これは大腿骨の付け根に近い部分の骨折で、主に二つの種類に分けられます。
一つは大腿骨頭の下の「くび」の部分で折れる「大腿骨頸部骨折(だいたいこつけいぶこっせつ)」、もう一つはそれより少し外側の部分で折れる「大腿骨転子部骨折(だいたいこつてんしぶこっせつ)」です。
どちらの骨折かによって、治療方針が異なる場合があります。
骨折部位による分類
| 骨折の種類 | 特徴 | 血流への影響 |
|---|---|---|
| 大腿骨頸部骨折 | 関節包の内側で骨折する。骨がつきにくい傾向がある。 | 骨頭への血流が途絶えやすく、骨が壊死するリスクがある。 |
| 大腿骨転子部骨折 | 関節包の外側で骨折する。骨がつきやすい傾向がある。 | 血流が豊富なため、骨は比較的癒合しやすいが出血量が多くなる。 |
高齢者に多い理由
股関節骨折は、若い世代では交通事故や高所からの転落など、非常に大きなエネルギーが加わった場合に起こりますが、高齢者の場合は、転倒などの比較的軽い衝撃で発生することがほとんどです。
その背景には、加齢に伴う骨密度の低下、いわゆる「骨粗しょう症」が大きく関係しています。
骨がもろくなっているため、健常な人では問題にならないようなわずかな力でも骨折に至ってしまうのです。
また、筋力やバランス能力の低下も転倒のリスクを高め、骨折の引き金となります。
股関節骨折の主な原因と危険因子
股関節骨折は、なぜ起こってしまうのでしょうか。
そのほとんどは「転倒」が直接的なきっかけですが、転倒しやすくなる、あるいは骨が折れやすくなる背景には、いくつかの危険因子が存在します。
これらの要因を理解することは、予防にもつながる大切な知識です。
最大の原因は「転倒」
高齢者の股関節骨折の9割以上は、自宅や屋外での転倒によって発生します。特に、つまずきや滑りによるものが多く、立った高さから転ぶだけでも骨折に至ることがあります。
加齢による視力、聴力、バランス感覚の低下は、転倒のリスクを著しく高めます。屋内であっても、段差や滑りやすい床、整理されていないコード類などが転倒の原因になり得ます。
骨の強度を低下させる「骨粗しょう症」
骨粗しょう症は、骨の量が減って質が劣化し、骨がスカスカになってもろくなる病気です。自覚症状がほとんどないまま進行するため、「静かなる病気」とも呼ばれます。
骨粗しょう症があると、骨の強度が著しく低下するため、わずかな衝撃でも骨折しやすくなります。
特に閉経後の女性は、骨の健康を保つ女性ホルモン(エストロゲン)の分泌が急激に減少するため、骨粗しょう症になりやすい傾向があります。
骨粗しょう症の主な危険因子
| 因子カテゴリー | 具体的な内容 | 対策 |
|---|---|---|
| 生活習慣 | カルシウム・ビタミンD不足、運動不足、喫煙、過度の飲酒 | バランスの取れた食事、適度な運動、禁煙、節酒 |
| 遺伝的要因 | 家族に骨折歴がある | 定期的な骨密度検査 |
| 身体的特徴 | 痩せ型、閉経後の女性 | 体重管理、ホルモン補充療法の検討 |
その他の危険因子
骨粗しょう症以外にも、股関節骨折のリスクを高める要因はいくつか存在します。
例えば、特定の病気(関節リウマチ、糖尿病、慢性腎臓病など)や、治療のために使用する薬剤(ステロイドなど)が骨の強度に影響を与えることがあります。
また、認知機能の低下や、睡眠薬の服用によるふらつきなども、転倒のリスクを増加させる要因として注意が必要です。
股関節骨折で見られる特徴的な症状
股関節を骨折すると、体に様々なサインが現れます。これらの症状に早く気づき、速やかに医療機関を受診することが、その後の回復に大きく影響します。
ここでは、股関節骨折の際に現れる典型的な症状について解説します。
骨折直後の激しい痛み
最も特徴的な症状は、股関節の付け根部分に生じる激しい痛みです。転倒した直後から強い痛みを感じ、ほとんどの場合、痛みで立ち上がったり、歩いたりすることができなくなります。
痛みのために脚を少し動かすことさえ困難になることも少なくありません。
脚の変形と可動域の制限
骨折によって脚の位置に異常が見られることがあります。典型的なのは、骨折した側の脚が健康な側と比べて短くなり、つま先が外側を向いてしまう変形です。
これは、骨折した部分で骨がずれてしまうために起こります。また、痛みと骨のずれによって、股関節を自力で曲げたり伸ばしたりすることができなくなります。
骨折による脚の外観の変化
- 脚が短く見える(短縮)
- つま先が外側を向く(外旋)
- 股関節の付け根の腫れや皮下出血
起立・歩行が困難になる
股関節は体重を支える重要な関節であるため、骨折するとその機能が失われます。このことにより、体重をかけると激痛が走るため、自力で立つことや歩くことはほぼ不可能になります。
まれに、骨折のずれが少ない場合には、なんとか歩けることもありますが、後でずれが大きくなり、症状が悪化する危険性があるため注意が必要です。
全身に及ぶ影響
股関節骨折は、局所的な痛みや機能障害だけでなく、全身状態にも影響を及ぼすことがあります。
骨折によるストレスや痛み、動けないことによる精神的な落ち込み、食欲不振などが起こり得ます。
また、高齢者の場合、骨折をきっかけに持病が悪化したり、認知症が進行したりすることもあります。
整形外科で行う股関節骨折の診断方法
「股関節を骨折したかもしれない」と感じた場合、速やかに整形外科を受診することが大切です。
病院では、医師が問診や診察を行い、必要な検査を進めて骨折の有無や状態を正確に把握します。ここでは、整形外科で行われる一連の診断の流れを説明します。
問診と身体診察
まず、医師が患者さんや付き添いの方から、いつ、どこで、どのようにして怪我をしたのかを詳しく聞き取ります。持病や普段飲んでいる薬、アレルギーの有無なども重要な情報です。
次に、痛みの場所や程度、脚の変形の有無、腫れや皮下出血の状態などを目で見て確認します。
医師が慎重に脚を動かし、どの範囲まで動かせるか、動かしたときに特有の痛みが出るかなども調べます。
画像検査による骨折の確定
身体診察で骨折が強く疑われる場合、次に画像検査を行って骨の状態を詳しく調べ、診断を確定します。最も基本となる検査はレントゲン(X線)検査です。
レントゲン(X線)検査
レントゲン検査は、骨折の診断において基本となる検査です。股関節を正面と側面の二方向から撮影することで、ほとんどの骨折を発見できます。
骨折の場所、骨のずれの程度などを詳細に評価し、治療方針を決定するための重要な情報を得ます。
CT検査やMRI検査
レントゲン検査で骨折線がはっきりと確認できない場合や、骨折の状態をより立体的に詳しく評価する必要がある場合には、追加でCT検査やMRI検査を行うことがあります。
CTは骨の細かい形状を、MRIは骨以外の軟部組織(筋肉や靭帯など)の状態を描出するのに優れています。
画像検査の使い分け
| 検査方法 | 主な目的 | 特徴 |
|---|---|---|
| レントゲン検査 | 骨折の有無と種類の確認 | 最も基本的で迅速な検査。 |
| CT検査 | 骨折の複雑さや骨片の評価 | 骨の3D画像を構築でき、詳細な骨折形態を把握できる。 |
| MRI検査 | レントゲンで不明瞭な骨折の検出 | 骨挫傷(骨の内部の損傷)や軟部組織の損傷も評価できる。 |
全身状態の評価
股関節骨折の治療、特に手術を行う前には、全身の状態を評価することが重要です。
心臓や肺の機能、腎臓の働き、栄養状態などを把握するために、血液検査、尿検査、心電図、胸部レントゲンなどの検査を行います。
これらの検査結果を基に、手術に耐えられる状態かどうかを総合的に判断し、安全な治療計画を立てます。
股関節骨折の主な治療法 手術と保存療法
股関節骨折の治療目標は、痛みを和らげ、骨を正しい位置で癒合させ、できるだけ早く元の歩行能力を取り戻すことです。
治療法には、手術を行わない「保存療法」と、手術によって骨を固定する「手術療法」がありますが、多くの場合で手術療法を選択します。
手術療法が第一選択となる理由
股関節骨折の治療では、多くの場合、手術が推奨されます。その最大の理由は、長期間ベッドの上で安静にしていること(臥床)による様々な合併症を防ぐためです。
動けない状態が続くと、筋力が低下し、関節が硬くなるだけでなく、床ずれ(褥瘡)、肺炎、血栓症(エコノミークラス症候群)、認知症の進行といった、生命に関わるリスクが高まります。
手術によって骨を安定させ、早期にリハビリを開始することが、これらの合併症を予防し、早期の社会復帰につながります。
長期臥床による主な合併症
| 合併症 | 内容 |
|---|---|
| 筋力低下・関節拘縮 | 筋肉がやせ細り、関節が硬くなって動かなくなる。 |
| 深部静脈血栓症 | 脚の静脈に血の塊ができ、肺に飛ぶと肺塞栓症を引き起こす。 |
| 肺炎(誤嚥性肺炎) | 寝たきりによる抵抗力の低下や、飲み込み機能の低下で発症する。 |
代表的な手術方法
手術方法は、骨折の部位やずれの程度、患者さんの年齢や活動レベルなどを考慮して決定します。主な手術には「骨接合術」と「人工関節置換術」の二つがあります。
骨接合術
骨接合術は、ずれた骨を元の位置に戻し、金属製のスクリューやプレート、髄内釘(ずいないてい)などを使って内側から固定する方法です。
自分の骨を温存できるのが最大の利点です。主に、骨のずれが少ない場合や、血流が保たれていて骨癒合が期待できる転子部骨折などで行います。
人工関節置換術
人工関節置換術は、損傷した大腿骨頭を金属やセラミックなどでできた人工の骨頭(人工骨頭)や、寛骨臼側も含めた人工関節に置き換える手術です。
主に、骨頭への血流が絶たれやすく骨癒合が期待しにくい頸部骨折や、すでに関節の変形がある場合などに行います。
手術後、比較的早期から体重をかけて歩く練習を開始できる利点があります。
手術方法の選択
| 手術方法 | 主な対象となる骨折 | メリット |
|---|---|---|
| 骨接合術 | 大腿骨転子部骨折、ずれの少ない頸部骨折 | 自分の骨・関節を温存できる。 |
| 人工関節置換術 | ずれの大きい大腿骨頸部骨折 | 早期から体重をかけたリハビリが可能。 |
保存療法を選択する場合
保存療法は、手術を行わずに、ベッド上での安静や脚の牽引(けんいん)によって骨の癒合を待つ方法です。
しかし、前述の通り、長期間の安静は多くの合併症リスクを伴うため、選択されるケースは限定的です。
全身状態が非常に悪く手術のリスクが極めて高い場合や、骨折のずれがほとんどなく安定しているごく一部の症例、あるいは患者さん自身が手術を希望しない場合などに限られます。
手術後の回復を支えるリハビリテーション
股関節骨折の治療は、手術が成功すれば終わりではありません。むしろ、手術後から始まるリハビリテーションこそが、再び自分の足で歩き、元の生活を取り戻すための鍵となります。
理学療法士や作業療法士などの専門スタッフの指導のもと、計画的に進めていきます。
リハビリテーションの目的
手術後のリハビリの最大の目的は、できるだけ早く安全に離床し、歩行能力を再獲得することです。
また、筋力や関節の動きを回復させ、着替えや入浴、トイレといった日常生活に必要な動作(ADL)を再び自立して行えるように支援することも重要な目的です。
リハビリを通じて、自信を取り戻し、退院後の生活にスムーズに移行できるようにします。
リハビリの段階的な進め方
リハビリは、患者さんの状態に合わせて、段階的に負荷を上げていきます。通常、手術の翌日や翌々日といった早い段階から開始します。
手術直後(急性期)
この時期は、まずベッドから起き上がり、車椅子に移る練習から始めます。関節が硬くなるのを防ぐために、理学療法士が股関節や膝関節を動かす訓練を行います。
また、脚の筋力が落ちないように、ベッド上で行える簡単な筋力トレーニングも開始します。
手術した脚に体重をかけられない時期でも、平行棒などにつかまって立つ練習や、松葉杖を使った歩行練習を始めることもあります。
回復期
骨の状態が安定してきたら、より本格的なリハビリに移行します。平行棒内での歩行練習から始め、徐々に杖を使った歩行へと進めていきます。
筋力強化訓練や、関節の可動域を広げる訓練も継続して行います。さらに、階段の上り下りや、床からの立ち上がりなど、より実践的な動作の練習も行い、退院後の生活に備えます。
リハビリの進行スケジュールの目安
| 時期 | 主なリハビリ内容 | 目標 |
|---|---|---|
| 手術後1日~1週 | ベッド上での運動、車椅子への移乗、座位保持訓練 | 早期離床、合併症予防 |
| 手術後1週~4週 | 平行棒内歩行、筋力強化訓練、関節可動域訓練 | 安定した立位、杖歩行の準備 |
| 手術後4週以降 | 杖歩行、階段昇降訓練、日常生活動作訓練 | 自宅退院、社会復帰 |
痛みの管理と精神的なサポート
リハビリは、時に痛みを伴うことがあります。痛みを我慢しすぎると、かえって回復を妨げてしまうこともあるため、痛み止めを適切に使いながら、無理のない範囲で進めていくことが大切です。
また、思うように体が動かないことへの不安や焦りを感じることも少なくありません。
医師や看護師、療法士、ソーシャルワーカーなどがチームとなり、身体的な回復だけでなく、精神的なサポートも行います。
退院後の生活と社会復帰に向けた準備
入院中の治療とリハビリを経て、歩行能力がある程度回復すれば、いよいよ退院です。しかし、退院はゴールではなく、自宅での生活を安全に、そして安心して送るための新たなスタートです。
退院後も継続したリハビリや、生活環境の調整が重要になります。
退院の目安と判断基準
退院の時期は、患者さん一人ひとりの回復状況によって異なりますが、一般的には、杖などを使って自宅内を安全に移動でき、トイレや着替えなどの身の回りのことが自分でできるようになった時点が目安となります。
医師、理学療法士、看護師、ソーシャルワーカーなどが連携し、本人の状態や介護者の状況、自宅の環境などを総合的に評価して、最適な退院時期を判断します。
自宅での生活で注意すべき点
退院後、最も注意すべきことは「再転倒」の予防です。
一度骨折を経験すると、転倒への恐怖心から活動性が低下しがちですが、動かないでいると筋力はさらに低下し、再び転倒しやすくなるという悪循環に陥ります。
自宅の環境を見直し、転倒のリスクを減らす工夫が大切です。
住宅改修のポイント
- 手すりの設置(廊下、トイレ、浴室)
- 段差の解消(スロープの設置)
- 床材の変更(滑りにくい素材へ)
- 照明の確保(足元を明るくする)
継続的なリハビリと骨粗しょう症の治療
退院後も、筋力やバランス能力を維持・向上させるために、リハビリを継続することが重要です。
外来リハビリテーションや、介護保険サービスを利用した通所リハビリ(デイケア)、訪問リハビリなどを活用する方法があります。
また、股関節骨折の大きな原因である骨粗しょう症の治療も並行して行います。薬物療法や食事療法、運動療法を継続し、次の骨折を防ぐことが極めて大切です。
退院後の選択肢
| 選択肢 | 内容 | 対象となる方 |
|---|---|---|
| 自宅へ退院 | 家族の支援を受けながら自宅で生活する。 | 身の回りのことが概ね自立している方。 |
| 回復期リハビリテーション病院へ転院 | 集中的なリハビリを継続するために転院する。 | より集中的なリハビリが必要な方。 |
| 介護施設へ入所 | 介護サービスを受けながら施設で生活する。 | 常時介護が必要で自宅での生活が困難な方。 |
股関節骨折の治療とリハビリに関するよくある質問
最後に、股関節骨折の治療やリハビリに関して、患者さんやご家族からよく寄せられる質問とその回答をまとめました。疑問や不安の解消にお役立てください。
手術時間はどのくらいかかりますか?
手術時間は、骨折の種類や手術方法、患者さんの状態によって異なりますが、一般的には1時間から2時間程度です。これに麻酔をかけたり、手術の準備をしたりする時間が加わります。
手術中は、麻酔科医が全身の状態を厳重に管理するので、安心して治療を受けていただけます。
入院期間はどのくらいになりますか?
入院期間も回復の進み具合によって個人差が大きいですが、手術後のリハビリを含めて、急性期病院での入院は3週間から1ヶ月程度が一般的です。
その後、自宅へ退院する方もいれば、より集中的なリハビリを行うために回復期リハビリテーション病院へ転院する方もいます。
転院した場合は、さらに1〜2ヶ月程度のリハビリ期間を見込むことが多いです。
手術後の痛みは続きますか?
手術直後は、手術による痛みがありますが、痛み止めの薬を使ってコントロールします。痛みは日数とともに徐々に和らいでいきます。
リハビリの際に多少の痛みを感じることはありますが、無理のない範囲で動かすことが回復につながります。痛みが強い場合は、我慢せずに医師や看護師に相談してください。
痛みが長引くことはまれですが、その場合は原因を詳しく調べます。
痛みの種類と対処法
| 痛みの種類 | 主な原因 | 対処法 |
|---|---|---|
| 急性期の痛み | 手術による傷や炎症 | 鎮痛薬の使用、アイシング |
| リハビリ中の痛み | 硬くなった筋肉や関節を動かすこと | 運動前のストレッチ、無理のない範囲での運動 |
| 慢性的な痛み | インプラントの問題、筋肉のアンバランス | 医師による診察、追加のリハビリ |
再び歩けるようになりますか?
多くの方が、適切な手術とリハビリテーションによって、再び歩行能力を回復することができます。
ただし、回復の程度は、骨折前の歩行能力、年齢、全身の健康状態、そしてリハビリへの取り組み意欲などに大きく影響されます。
目標は、骨折前の生活レベルにできるだけ近づけることです。杖などの補助具が必要になることもありますが、多くの患者さんが自立した生活を取り戻しています。
焦らず、ご自身のペースでリハビリに取り組むことが大切です。
参考文献
LYONS, Anthony R. Clinical outcomes and treatment of hip fractures. The American journal of medicine, 1997, 103.2: S51-S64.
JOHNSON, Marie F., et al. Outcomes of older persons receiving rehabilitation for medical and surgical conditions compared with hip fracture and stroke. Journal of the American Geriatrics Society, 2000, 48.11: 1389-1397.
MCGILTON, Katherine S., et al. Outcomes for older adults in an inpatient rehabilitation facility following hip fracture (HF) surgery. Archives of gerontology and geriatrics, 2009, 49.1: e23-e31.
MCGILTON, Katherine S., et al. Factors influencing outcomes of older adults after undergoing rehabilitation for hip fracture. Journal of the American Geriatrics Society, 2016, 64.8: 1601-1609.
ROLLAND, Yves, et al. Rehabilitation outcome of elderly patients with hip fracture and cognitive impairment. Disability and rehabilitation, 2004, 26.7: 425-431.
BUTLER, Mary, et al. Evidence summary: systematic review of surgical treatments for geriatric hip fractures. JBJS, 2011, 93.12: 1104-1115.
CHUDYK, Anna M., et al. Systematic review of hip fracture rehabilitation practices in the elderly. Archives of physical medicine and rehabilitation, 2009, 90.2: 246-262.
BINDER, Ellen F., et al. Effects of extended outpatient rehabilitation after hip fracture: a randomized controlled trial. Jama, 2004, 292.7: 837-846.
MAK, Jenson CS; CAMERON, Ian D.; MARCH, Lyn M. Evidence‐based guidelines for the management of hip fractures in older persons: an update. Medical Journal of Australia, 2010, 192.1: 37-41.
HUNG, William W., et al. Hip fracture management: tailoring care for the older patient. Jama, 2012, 307.20: 2185-2194.
Symptoms 症状から探す