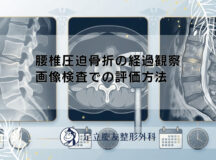変形性膝関節症の左右別症状と進行度 – 治療の選択肢
膝の痛み、特に「右膝だけ」「左膝だけ」が痛むという症状にお悩みではありませんか?その痛みは、加齢や体重、生活習慣などが原因で起こる変形性膝関節症かもしれません。
この病気は、左右どちらかの膝に症状が出ることが多く、その原因や進行度によって適切な対処法が異なります。
この記事では、変形性膝関節症がなぜ片膝に発症しやすいのか、右膝と左膝それぞれの症状の特徴、進行度による変化、そしてどのような治療の選択肢があるのかを詳しく解説します。
目次
変形性膝関節症とは 膝の痛みの基本的な知識
まずは、変形性膝関節症がどのような病気なのか、基本的な点から理解を深めましょう。膝の構造や痛みの原因を知ることは、ご自身の状態を把握するための第一歩です。
膝関節の仕組みと軟骨の役割
膝関節は、太ももの骨である「大腿骨(だいたいこつ)」、すねの骨である「脛骨(けいこつ)」、そしてお皿の骨である「膝蓋骨(しつがいこつ)」の3つの骨で構成されています。
これらの骨の表面は、「関節軟骨」と呼ばれる弾力性のある滑らかな組織で覆われています。関節軟骨は、衝撃を吸収するクッションの役割と、関節の動きを滑らかにする役割を担っています。
また、関節は「関節包(かんせつほう)」という袋に包まれており、その内側は滑膜(かつまく)で覆われています。
滑膜からは関節液が分泌され、軟骨に栄養を与えたり、潤滑油のように関節の動きを助けたりしています。
なぜ関節軟骨がすり減るのか
変形性膝関節症は、この大切な関節軟骨が、長年の負担の蓄積によってすり減ったり、変性したりすることで発症します。
軟骨には血管や神経が通っていないため、一度すり減ると自然に元に戻ることは困難です。軟骨がすり減ると、骨同士が直接こすれ合うようになり、痛みや炎症を引き起こします。
また、関節の縁に「骨棘(こつきょく)」と呼ばれる骨のとげができることもあります。これらの変化が、膝の痛み、腫れ、動かしにくさといった症状につながるのです。
主な原因
- 加齢
- 肥満
- 過去の膝の怪我
- 遺伝的な要因
変形性膝関節症の主な原因
変形性膝関節症の発症には、複数の要因が関わっています。最も大きな要因は加齢です。年齢とともに軟骨の弾力性が失われ、すり減りやすくなります。
次に重要なのが肥満です。体重が増えると、歩行時に膝にかかる負担が何倍にもなり、軟骨の摩耗を早めます。
その他、骨折や半月板損傷、靭帯損傷といった過去の膝の怪我も、将来的に変形性膝関節症を発症するリスクを高めます。
また、もともとの骨の形やO脚・X脚、遺伝的な要因も発症に関係することが知られています。
変形性膝関節症の主な要因
| 要因 | 内容 | 膝への影響 |
|---|---|---|
| 加齢 | 年齢とともに軟骨の水分量が減少し、弾力性が低下する。 | 軟骨がすり減りやすくなる。 |
| 肥満 | 体重の増加により、膝への物理的な負荷が増大する。 | 軟骨の摩耗を加速させる。 |
| 外傷歴 | 骨折や靭帯損傷、半月板損傷など。 | 関節の安定性が損なわれ、負担が偏る。 |
なぜ左右どちらかの膝が痛むのか 片膝発症の背景
変形性膝関節症は、両膝同時に進行するよりも、右膝や左膝など片方から症状が現れることが少なくありません。ここでは、その背景にある日常生活に潜む要因を探ります。
利き足と体重のかかり方の偏り
多くの人には利き足があり、無意識のうちに体重をかける足や、踏み出す足が偏っています。例えば、ボールを蹴るときや、階段を上り始めるときに使う足が利き足です。
このように、日常的に片方の足に重心をかける癖があると、そちら側の膝関節に持続的な負担がかかり、軟骨のすり減りが早く進むことがあります。
長年の習慣の積み重ねが、左右の膝の健康状態に差を生じさせる一因となります。
日常生活の癖や習慣の影響
利き足以外にも、日常生活の中の些細な癖が膝への負担の偏りを生みます。
例えば、いつも同じ側で荷物を持つ、椅子に座るときに決まって同じ側の脚を組む、横座りをするときにどちらかの脚を下に敷く、といった習慣です。
これらの動作は、体の重心を左右非対称にし、片方の膝に過剰なストレスをかけ続けることになります。このことにより、特定の膝だけに変形性膝関節症の症状が現れやすくなるのです。
膝への負担を偏らせる生活習慣の例
| 習慣 | 膝への影響 |
|---|---|
| いつも同じ側で鞄を持つ | 体のバランスを取るため、反対側の膝に負担がかかる。 |
| 脚を組んで座る | 骨盤が歪み、上になる脚側の膝や股関節に負担がかかる。 |
| 片足に体重をかけて立つ | 体重を支えている側の膝に集中的に負荷がかかる。 |
過去の怪我やスポーツによる負荷
過去に経験した膝の怪我も、左右差を生む大きな要因です。例えば、学生時代に右膝の前十字靭帯を損傷した経験があれば、将来的には右膝に変形性膝関節症を発症するリスクが高まります。
怪我によって関節の安定性が損なわれたり、軟骨や半月板が傷ついたりすると、その部分の負担が増大するためです。
特定のスポーツを長年続けている場合も同様で、競技の特性によって片方の膝に集中的な負荷がかかり、左右差の原因となることがあります。
O脚やX脚と膝への負担
脚の形も膝への負担のかかり方に大きく影響します。O脚(内反膝)は、両膝が外側に湾曲し、膝の内側に体重が集中しやすい状態です。このため、膝の内側の軟骨がすり減りやすくなります。
逆にX脚(外反膝)は、両膝が内側に寄り、膝の外側に負担がかかりやすい状態です。
多くの日本人はO脚の傾向があると言われており、変形性膝関節症も膝の内側に発症するケースが多く見られます。
O脚やX脚の度合いに左右差があれば、より負担の大きい方の膝から症状が現れることになります。
右膝に症状が現れる場合の特徴と原因
右膝に痛みや違和感がある場合、どのような特徴や原因が考えられるのでしょうか。右利きの人の動作や、特定のスポーツとの関連性について見ていきましょう。
右利きの人に多い動作の癖
日本人は右利きの割合が高く、日常生活の多くの動作で右半身を主導的に使います。例えば、物を拾うためにかがむとき、右足を一歩前に出して体を支えることが多いでしょう。
また、車の運転では、右足でアクセルとブレーキを操作するため、右足は常に緊張状態にあり、細かい動きを繰り返します。
これらの動作の積み重ねが、右膝への負担を増やし、「右 変形性膝関節症」の発症につながることがあります。
軸足としての右膝の役割
スポーツの世界では、体を回転させたり、踏み込んだりする際の「軸足」が重要になります。右利きの選手の場合、多くの競技で左足で踏み込み、右半身でボールを投げたり打ったりします。
しかし、競技によっては右足を軸足として使う場面も多くあります。例えば、野球の右打者がスイングする際、右足は体を支える軸となります。
このような軸足としての役割は、膝に大きなねじれの力や圧迫力を加え、軟骨の損傷を引き起こす原因となり得ます。
右膝に負担がかかりやすいスポーツの例
| スポーツ | 右膝への負担要因(右利きの場合) |
|---|---|
| ゴルフ | スイングの際、フォロースルーで右膝に体重が残りやすい。 |
| 野球(右打ち) | スイング時に体を回転させるための軸となり、ねじれの力がかかる。 |
| サッカー(右足で蹴る) | キックの瞬間に軸足となる左膝だけでなく、蹴り足の右膝にも着地時などに負担がかかる。 |
特定の職業やスポーツとの関連性
職業によっても、特定の膝に負担がかかることがあります。
例えば、長時間運転するドライバーや、農作業で頻繁にかがんだり立ち上がったりする動作が多い場合、特定の脚に負担が偏ることがあります。
右膝を酷使する動作が多い職業や、前述のような特定のスポーツを長年続けてきた人は、右膝の軟骨がすり減りやすく、注意が必要です。
左膝に症状が現れる場合の特徴と原因
左膝に症状が出る場合も、右膝とは異なる特徴や原因が考えられます。体のバランスや、利き足とは逆の足にかかる負担について解説します。
体のバランスを保つ左膝の負担
右利きの人が右手で何か作業をする際、体は無意識に左側に重心を移してバランスを取っています。
例えば、重い荷物を右手で持つと、左足でしっかりと踏ん張り、体が傾かないように支えます。この「バランスを取る」という役割は、持続的な負荷を左膝にかけることになります。
一回一回の負荷は小さくても、長年にわたって繰り返されることで、左膝の軟骨が徐々にすり減り、「左 変形性膝関節症」を発症することがあります。
右膝をかばうことによる影響
すでに右膝に何らかの痛みや違和感がある場合、人は無意識のうちに右膝をかばい、左膝に頼って歩いたり、立ち上がったりするようになります。
この「かばう動作」は、本来であれば左右均等にかかるはずの負担を、健康な左膝に集中させてしまいます。
右膝の軽微な問題が、結果的に左膝の変形性膝関節症を引き起こすというケースは少なくありません。左右どちらかの膝に痛みがある場合は、もう片方の膝への影響も考慮することが大切です。
かばい動作による影響の連鎖
| 段階 | 状態 | 影響 |
|---|---|---|
| 1. 右膝の不調 | 軽い痛みや違和感がある。 | 無意識に右膝への負担を避ける。 |
| 2. 左膝への過負荷 | 歩行時や階段昇降時に左足に頼る。 | 左膝の軟骨摩耗が進行する。 |
| 3. 左膝の症状発現 | 左膝に痛みや腫れが生じる。 | 両膝に問題を抱える状態になる。 |
事故や転倒による外傷の既往
交通事故やスポーツ中の衝突、日常生活での転倒など、突発的な外傷も「左 変形性膝関節症」の引き金になります。
特に、左足を地面についた状態で体に強い衝撃を受けた場合、膝関節内の半月板や靭帯、軟骨を損傷することがあります。
これらの組織が一度損傷すると、関節の安定性が低下し、将来的に変形性膝関節症へと進行するリスクが高まります。過去の怪我がどちらの足だったか、という点も重要な情報です。
症状の進行度と段階別の変化
変形性膝関節症の症状は、時間とともに変化します。ご自身の症状がどの段階にあるのかを知ることで、今後の見通しや対策を立てやすくなります。
初期症状 こわばりや軽い痛み
最も早い段階で見られるのは、朝起きたときや、長時間座った後などに感じる膝のこわばりです。少し動かすと症状が和らぐのが特徴です。
また、「立ち上がり」「歩き始め」「階段の上り下り」といった、動作の開始時に軽い痛みを感じることもあります。この段階では、痛みは一時的で、しばらく休むと治まることがほとんどです。
膝が腫れたり、熱を持ったりすることは稀で、日常生活に大きな支障はありません。
初期症状のチェック
- 朝、膝がこわばる感じがする
- 椅子から立ち上がる時に膝が痛む
- 歩き始めに違和感がある
- 長距離を歩くと膝がだるくなる
中期症状 動作時の痛みの悪化と可動域制限
病状が進行すると、痛みが慢性化し、動作時の痛みが強くなります。階段の上り下り、特に下りる動作が辛くなり、正座や深くしゃがみ込むことが困難になります。
関節軟骨のすり減りが進み、関節の隙間が狭くなることで、膝を曲げ伸ばしできる範囲(可動域)が制限されてくるためです。
炎症が強くなると、膝に関節液がたまって腫れる「水がたまる」状態になることもあります。
歩行中に膝が「ゴリゴリ」「ミシミシ」といった音(轢音:れきおん)を発することも特徴的な症状です。
末期症状 安静時痛と著しい変形
さらに進行すると、関節軟骨がほとんどなくなり、骨同士が直接ぶつかるようになります。
この段階では、歩行などの動作時だけでなく、じっとしていても膝が痛む「安静時痛」や、夜間に痛みで目が覚める「夜間痛」が現れます。
膝の変形も外見から明らかになり、O脚やX脚がさらに進行します。
膝が完全に曲がらなくなったり、伸びなくなったりするため、歩行が著しく困難になり、杖や歩行器などの補助具が必要になることもあります。日常生活の質(QOL)が大きく低下する段階です。
進行度別の主な症状
| 進行度 | 痛みの特徴 | その他の症状 |
|---|---|---|
| 初期 | 動作開始時の軽い痛み | こわばり、だるさ |
| 中期 | 動作時の痛みが慢性化 | 可動域制限、腫れ、轢音 |
| 末期 | 安静時痛、夜間痛 | 著しい変形、歩行困難 |
専門機関での診断と検査方法
膝の痛みが続く場合、自己判断せずに専門機関を受診することが重要です。ここでは、どのような診察や検査が行われるのか、その目的と内容を説明します。
問診と視診・触診
診察では、まず問診が行われます。いつから、どのような時に、膝のどのあたりが痛むのか、過去の怪我の有無、職業やスポーツ歴、日常生活での困りごとなどを詳しく伝えます。
次に、視診で膝の腫れや変形の有無、歩き方などを観察します。
そして触診では、医師が直接膝に触れ、圧痛(押して痛む場所)の有無、関節の動く範囲、関節液の貯留(水がたまっているか)、ぐらつきなどを確認します。
これらの情報は、診断を下すための重要な手がかりとなります。
レントゲン(X線)検査でわかること
変形性膝関節症の診断において、レントゲン検査は基本的な検査です。立った状態で撮影し、膝に体重がかかったときの関節の状態を評価します。
レントゲン画像からは、関節の隙間の広さ(軟骨の厚さを間接的に示す)、骨棘の有無、骨の変形の程度などを確認できます。これらの所見を基に、病気の進行度を分類します。
レントゲン検査による進行度分類(Kellgren-Lawrence分類)
| グレード | レントゲン所見 |
|---|---|
| 0 | 正常。 |
| 1 | 骨棘の疑いがある。 |
| 2 | 明らかな骨棘があるが、関節裂隙は保たれている。 |
| 3 | 中等度の関節裂隙狭小化がある。 |
| 4 | 高度な関節裂隙狭小化と骨硬化がある。 |
必要に応じて行われる追加検査
レントゲン検査だけでは診断が難しい場合や、半月板損傷や靭帯損傷など他の病気が疑われる場合には、追加の検査を行います。
MRI検査は、レントゲンでは写らない軟骨や半月板、靭帯などの軟部組織の状態を詳しく調べることができます。
関節液がたまっている場合は、注射器で関節液を抜いてその性状を調べる関節穿刺を行うこともあります。これらの検査結果を総合的に判断して、最終的な診断を下します。
変形性膝関節症の治療の選択肢
治療法は、病気の進行度や症状、ライフスタイルによって異なります。ここでは、主な治療法である「保存療法」と「手術療法」について、その具体的な内容を紹介します。
痛みを和らげる保存療法
多くの変形性膝関節症は、まず保存療法から開始します。保存療法は、手術以外の方法で症状の緩和と進行の抑制を目指す治療法です。複数の方法を組み合わせて行います。
運動療法
膝周りの筋力、特に太ももの前の筋肉(大腿四頭筋)を鍛えることは、膝の安定性を高め、負担を軽減するために非常に重要です。
また、関節の動きを良くするためのストレッチも行います。専門家の指導のもと、無理のない範囲で継続することが大切です。
物理療法
温熱療法で膝を温めて血行を良くしたり、電気刺激で痛みを和らげたりします。痛みの緩和や筋肉のこわばりの改善を目的とします。
薬物療法
痛みが強い場合には、消炎鎮痛剤の飲み薬や貼り薬、塗り薬を使用します。また、ヒアルロン酸を関節内に注射し、関節の滑りを良くして痛みを軽減する方法もあります。
装具療法
膝にかかる負担を減らすために、サポーターや足底板(インソール)を使用します。O脚の人には、靴の外側を高くした足底板が有効な場合があります。
膝の機能を再建する手術療法
保存療法で十分な効果が得られない場合や、病状が進行して日常生活に大きな支障が出ている場合には、手術療法を検討します。
手術法にはいくつかの種類があり、年齢や活動レベル、変形の程度に応じて選択します。
主な手術療法
| 手術名 | 内容 | 主な対象 |
|---|---|---|
| 関節鏡視下手術 | 小さなカメラで関節内を観察し、損傷した半月板の切除や軟骨の掃除を行う。 | 比較的若年で、半月板損傷などが痛みの主因の場合。 |
| 高位脛骨骨切り術 | すねの骨を切って角度を変え、O脚を矯正することで膝の内側にかかる負担を軽減する。 | 比較的活動性の高い60歳代くらいまでの人。 |
| 人工膝関節置換術 | 損傷した関節の表面を削り、金属やポリエチレンでできた人工の関節に置き換える。 | 進行期・末期で痛みが強く、日常生活に支障がある高齢者。 |
日常生活でできるセルフケア
治療と並行して、日常生活の中で膝への負担を減らす工夫をすることも大切です。
まず、肥満気味の人は減量に取り組みましょう。体重を1kg減らすだけで、歩行時の膝への負担は約3〜4kg減ると言われています。
また、床での生活(正座、あぐら)を避け、椅子やベッドを使う洋式の生活スタイルに切り替えることも有効です。
杖を使用することに抵抗がある人もいますが、杖は痛い膝と反対側の手で使うことで、膝への負担を大幅に軽減できます。
日常生活での注意点
- 適正体重を維持する
- 床に座る生活を避ける
- クッション性の良い靴を選ぶ
- 長時間の歩行や立ち仕事を避ける
- 膝を冷やさない
変形性膝関節症に関するよくある質問
ここでは、変形性膝関節症について多くの方が疑問に思う点にお答えします。正しい知識を持つことで、不安の軽減につなげてください。
右膝の痛みと左膝の痛みで治療法は変わりますか
基本的に、変形性膝関節症の治療方針が右膝か左膝かによって大きく変わることはありません。
治療法は、どちらの膝であっても、進行度、症状の強さ、年齢、活動量、ライフスタイルなどを総合的に考慮して決定します。
ただし、原因となった生活習慣や体の使い方の癖が左右で異なる可能性があるため、リハビリテーションや生活指導においては、その点を考慮した個別のアプローチが必要になる場合があります。
サプリメントは症状の改善に役立ちますか
グルコサミンやコンドロイチンなどのサプリメントが、変形性膝関節症の症状改善に効果があるという科学的な証拠は、現在のところ十分ではありません。
一部の人で痛みの軽減効果が報告されることもありますが、医薬品のような効果を期待するものではなく、あくまで健康食品として補助的に利用するものと考えるのが良いでしょう。
サプリメントに頼るよりも、まずは専門機関で診断を受け、確立された治療法(運動療法や薬物療法など)に取り組むことが重要です。
一度すり減った軟骨は元に戻らないのでしょうか
残念ながら、現在の医療では、すり減ってしまった関節軟骨を完全に元の状態に再生させることは困難です。軟骨には血管がなく、自己修復能力が非常に低いためです。
しかし、治療の目的は軟骨を元に戻すことだけではありません。
運動療法で膝周りの筋力をつけたり、体重を減らしたりすることで、残っている軟骨への負担を減らし、痛みを和らげ、病気の進行を遅らせることは十分に可能です。
また、手術療法によって、痛みなく歩ける機能を取り戻すこともできます。
どのような運動をすれば良いですか
膝に負担をかけずに筋力を強化できる運動が推奨されます。
代表的なのは、椅子に座ったまま膝を伸ばす運動(大腿四頭筋セッティング)や、仰向けに寝て膝を伸ばしたまま脚を上げる運動(SLR)などです。
水中ウォーキングやエアロバイクも、膝への負担が少なく、全身の持久力向上にもつながるため良い運動です。ただし、痛みがあるときに無理に行うのは逆効果です。
どのような運動が適しているかは個人の状態によって異なるため、医師や理学療法士に相談し、指導を受けながら行うようにしてください。
参考文献
MILLS, Kathryn, et al. Between-limb kinematic asymmetry during gait in unilateral and bilateral mild to moderate knee osteoarthritis. Archives of physical medicine and rehabilitation, 2013, 94.11: 2241-2247.
CREABY, Mark W.; BENNELL, Kim L.; HUNT, Michael A. Gait differs between unilateral and bilateral knee osteoarthritis. Archives of physical medicine and rehabilitation, 2012, 93.5: 822-827.
MESSIER, Stephen P., et al. Are unilateral and bilateral knee osteoarthritis patients unique subsets of knee osteoarthritis? A biomechanical perspective. Osteoarthritis and cartilage, 2016, 24.5: 807-813.
METCALFE, Andrew J., et al. Is knee osteoarthritis a symmetrical disease? Analysis of a 12 year prospective cohort study. BMC musculoskeletal disorders, 2012, 13.1: 153.
KOMATSU, Daigo, et al. Laterality of radiographic osteoarthritis of the knee. Laterality: Asymmetries of Body, Brain and Cognition, 2017, 22.3: 340-353.
KIM, Si-hyun; PARK, Kyue-nam. Lateral symmetry of center of pressure during walking in patients with unilateral knee osteoarthritis. Physical Therapy Korea, 2021, 28.1: 77-83.
PATERSON, Kade L., et al. Longitudinal association between foot and ankle symptoms and worsening of symptomatic radiographic knee osteoarthritis: data from the osteoarthritis initiative. Osteoarthritis and cartilage, 2017, 25.9: 1407-1413.
CAWLEY, Derek T., et al. The significance of hand dominance in hip osteoarthritis. In: Seminars in Arthritis and Rheumatism. WB Saunders, 2015. p. 527-530.
SHAKOOR, Najia, et al. Nonrandom evolution of end‐stage osteoarthritis of the lower limbs. Arthritis & Rheumatism, 2002, 46.12: 3185-3189.
UMEDA, Naoya, et al. Progression of osteoarthritis of the knee after unilateral total hip arthroplasty: minimum 10-year follow-up study. Archives of orthopaedic and trauma surgery, 2009, 129.2: 149-154.
Symptoms 症状から探す