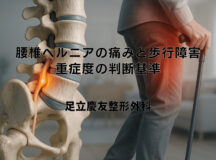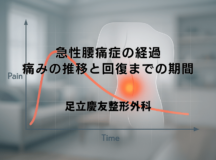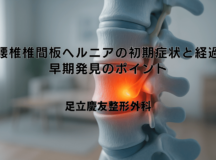膝が曲がってる状態における原因と改善方法
ふとした時に「膝が完全に伸びきらない」「膝が曲がったままになっている」と感じたことはありませんか。
このような膝が曲がってる状態は、単なる癖や加齢によるものと軽視されがちですが、身体からの重要なサインかもしれません。
この記事では、膝がまっすぐ伸びない状態がなぜ起こるのか、その原因を日常生活の習慣から考えられる病気の可能性まで、幅広く掘り下げて解説します。
さらに、ご自身で状態を確認する方法や、今日から始められる改善に向けたセルフケア、専門的なアプローチについても詳しく紹介します。
膝の不調の背景を正しく理解し、健やかな毎日を取り戻すための一歩として、ぜひお役立てください。
目次
膝が曲がってる状態とは?まずはセルフチェック
膝が曲がってる、あるいは伸びきらないと感じる時、それがどの程度の状態なのかを客観的に把握することが大切です。
まずは正常な膝の動きと比較し、ご自身の膝がどのような状態にあるのかを確認する方法から見ていきましょう。
簡単なセルフチェックを通じて、現状を正しく認識することが、適切な対策への第一歩となります。
正常な膝の可動域
膝関節は、太ももの骨(大腿骨)とすねの骨(脛骨)から構成される、人体で最も大きな関節の一つです。主に曲げる(屈曲)と伸ばす(伸展)という動きを担っています。
健康な膝であれば、痛みなくスムーズに動かすことができます。一般的に、完全に伸ばした状態を0度として、そこから正座をするように深く曲げるところまでが正常な可動域と考えられています。
可動域の目安
| 動き | 正常な角度の目安 | 説明 |
|---|---|---|
| 伸展(伸ばす) | 0度~-5度 | 脚をまっすぐ伸ばした状態。人によっては少し反ることもあります。 |
| 屈曲(曲げる) | 約130度~150度 | 深く曲げ、かかとがお尻につく、あるいはそれに近い状態です。 |
膝が伸びない「伸展制限」と曲がらない「屈曲制限」
膝が曲がってる状態は、専門的には「伸展制限」と表現することが多いです。これは、膝をまっすぐ伸ばそうとしても、何らかの原因で0度まで到達しない状態を指します。
わずかな伸展制限でも、歩行時のバランスが崩れたり、膝への負担が増加したりする原因となります。一方で、膝を深く曲げられない状態を「屈曲制限」と呼びます。
しゃがむ動作や階段の上り下り、正座などが困難になるのが特徴です。どちらの制限も、生活の質に大きく影響を与える可能性があります。
自宅でできる簡単チェック方法
ご自身の膝の状態を手軽に確認する方法をいくつか紹介します。痛みがある場合は無理に行わないでください。
仰向けでの伸展チェック
床やベッドに仰向けになり、力を抜いて脚をまっすぐ伸ばします。この時、膝の裏側が床にぴったりとつくか確認します。
もし膝裏と床の間に隙間ができてしまう場合、伸展制限が起きている可能性があります。指が何本入るかで、その程度を把握できます。
壁を使った屈曲チェック
壁から15cmほど離れて立ち、壁に手をついて体を支えながらゆっくりとしゃがんでいきます。
かかとを床につけたまま、無理なくしゃがむことができれば、屈曲の可動域は比較的保たれていると考えられます。
途中で痛みが出たり、かかとが浮いてしまったりする場合は、屈曲制限のサインかもしれません。
どんな時に注意が必要か
セルフチェックで可動域の制限が見られた場合、特に以下のような症状を伴う際は注意が必要です。
これらのサインは、単なる筋肉の硬さだけでなく、関節内部に何らかの問題が起きている可能性を示唆しています。
- 膝を動かすと痛みやひっかかりを感じる
- 膝が腫れている、熱を持っている
- 歩き始めや特定の動作で痛みが強くなる
- 安静にしていても痛む
これらの症状が一つでも当てはまる場合は、自己判断で放置せず、一度専門の医療機関に相談することを推奨します。
日常生活に潜む膝が曲がる原因
膝が曲がってしまう原因は、必ずしも病気だけではありません。
実は、普段何気なく行っている生活習慣や身体の使い方の癖が、少しずつ膝に影響を与え、可動域を狭めているケースが多く見られます。
ここでは、日常生活の中に潜む主な原因について解説します。
長時間の同じ姿勢(デスクワーク・立ち仕事)
デスクワークで長時間座りっぱなし、あるいは接客業などで立ちっぱなしというように、同じ姿勢をとり続けることは膝にとって大きな負担となります。
特に座った状態では膝が常に曲がったまま固定されるため、膝の裏側にある筋肉や靭帯が硬くなり、いざ立って伸ばそうとした時にスムーズに伸びなくなります。
この状態が慢性化すると、伸展制限が定着してしまうことがあります。
姿勢の悪さ(猫背・反り腰)と歩き方の癖
猫背や反り腰といった不良姿勢は、身体全体のバランスを崩し、結果として膝に過剰なストレスをかけます。
例えば、猫背になると身体の重心が前に傾き、バランスをとるために無意識に膝を少し曲げた「膝曲げ歩行」になりがちです。
また、O脚やX脚、足を引きずるような歩き方も、膝関節の特定の部分に負担を集中させ、痛みや変形、可動域制限の原因となります。
姿勢と膝への影響
| 姿勢のタイプ | 膝への影響 | 特徴 |
|---|---|---|
| 猫背 | 重心が前方に偏り、膝を曲げてバランスをとる傾向がある。 | 背中が丸まり、頭が前に出ている。 |
| 反り腰 | 骨盤が前傾し、太ももの前側の筋肉が緊張しやすくなる。 | 腰が過度に反り、お腹が前に突き出ている。 |
| O脚・X脚 | 膝の内側または外側に負担が集中し、軟骨のすり減りを助長する。 | 両膝の間に隙間ができる(O脚)、両膝が内側に接触する(X脚)。 |
筋力低下と柔軟性の欠如
膝関節は、その周りにある多くの筋肉によって支えられ、安定しています。
特に太ももの前側にある大腿四頭筋や、裏側にあるハムストリングスは、膝の曲げ伸ばしにおいて中心的な役割を果たします。
運動不足などによってこれらの筋力が低下すると、関節をしっかりと支えきれなくなり、安定性が低下します。
また、筋肉の柔軟性が失われると、関節の動きそのものが硬くなり、可動域が狭まる直接的な原因となります。
体重増加による膝への負担
体重が重ければ重いほど、膝関節にかかる負担は大きくなります。通常、歩いているだけでも体重の約3倍、階段の上り下りでは約7倍もの負荷が膝にかかると言われています。
体重が1kg増えるだけで、膝にはその数倍の圧力が加わる計算になります。
この過剰な負荷が長期間続くと、関節の軟骨がすり減りやすくなり、炎症や痛みを引き起こし、結果として膝が曲がった状態につながることがあります。
膝の痛みを伴う場合に考えられる病気
膝が曲がってる状態に加えて、痛みや腫れ、動かしにくさなどの症状がある場合、関節やその周辺組織に何らかの病気が隠れている可能性があります。
放置すると症状が進行してしまうこともあるため、どのような病気が考えられるのかを知っておくことは重要です。ここでは代表的な病気について解説します。
変形性膝関節症
加齢や体重増加、過去の怪我などを背景に、膝関節のクッションの役割をしている軟骨がすり減り、骨が変形していく病気です。
日本の高齢者において最も一般的な膝の痛みの原因とされています。
初期段階では、立ち上がりや歩き始めに痛む程度ですが、進行すると膝に水がたまったり、安静時にも痛むようになったりします。
さらに進行すると、骨の変形によってO脚が目立つようになり、膝が完全に伸びない、曲がらないといった可動域制限が顕著になります。
変形性膝関節症の主な症状
| 進行度 | 主な症状 | 特徴 |
|---|---|---|
| 初期 | 立ち上がり、歩き始めの痛み | 休むと痛みが和らぐことが多い。 |
| 中期 | 階段昇降時の痛み、正座が困難になる | 膝の腫れや水がたまることがある。 |
| 末期 | 安静時痛、夜間痛、歩行困難 | O脚などの変形が著しくなり、可動域が大きく制限される。 |
関節リウマチ
関節リウマチは、自己免疫疾患の一つで、免疫システムが誤って自分自身の関節を攻撃してしまうことで炎症が起こる病気です。
膝だけでなく、手足の指など複数の関節で症状が出ることが特徴です。
朝起きた時に関節がこわばる「朝のこわばり」が代表的な症状で、炎症が続くと関節の軟骨や骨が破壊され、変形や機能障害を引き起こします。
膝に関節リウマチが発症すると、強い痛みや腫れと共に、可動域が著しく制限されることがあります。
半月板損傷や靭帯損傷
スポーツ活動中や交通事故などで膝に大きな力が加わった際に起こる怪我です。
半月板は膝関節の中でクッションの役割を果たすC字型の軟骨組織で、これが損傷すると膝の曲げ伸ばしの際にひっかかり感や痛みが生じ、「ロッキング」といって膝が動かなくなることもあります。
また、膝の安定性を保つ前十字靭帯や後十字靭帯などが損傷すると、膝がぐらつく不安定感と共に、痛みや腫れを引き起こし、正常な動きが妨げられます。
これらの外傷後、適切な処置をしないと、将来的に変形性膝関節症へ移行するリスクも高まります。
その他の関節炎
痛風や偽痛風のように、関節内に尿酸やピロリン酸カルシウムの結晶が沈着することで、突然激しい痛みと腫れを引き起こす関節炎もあります。これを「結晶誘発性関節炎」と呼びます。
多くの場合、膝関節に発症し、歩けないほどの激痛を伴うことも少なくありません。
また、細菌が関節内に侵入して起こる「化膿性関節炎」も、急激な痛み、腫れ、発熱を伴い、迅速な治療が必要な状態です。
これらの炎症が治まった後も、関節の組織がダメージを受け、動きにくさが残ることがあります。
医療機関での検査と診断
膝の曲がってる状態や痛みが続く場合、正確な原因を特定するために医療機関での診断が重要になります。
医師は、患者さんからの話を聞き、身体を診察し、必要に応じて画像検査などを行うことで、総合的に状態を判断します。ここでは、一般的な検査と診断の流れについて説明します。
どのような場合に受診するべきか
日常生活に支障をきたすような症状がある場合は、早めに整形外科を受診しましょう。特に以下のような症状が見られる場合は、専門家による診断が必要です。
- 痛みが強く、歩くのがつらい
- 膝が急に腫れてきた、熱を持っている
- 怪我をしてから、膝の調子がおかしい
- 膝がガクッと崩れるような感覚がある
問診と身体診察の内容
診察では、まず医師が患者さんから詳しい話を聞きます(問診)。
いつから、どのような時に、どのあたりが痛むのか、きっかけになった出来事はあるか、といった情報が診断の手がかりとなります。
その後、医師が実際に膝の状態を観察し、触って確認します(身体診察)。膝の腫れや熱感の有無、押して痛む場所、関節の可動域、ぐらつきがないかなどを丁寧にチェックし、原因の見当をつけます。
問診でよく聞かれること
| 質問項目 | 確認する目的 |
|---|---|
| 症状の始まりと経過 | 急性の怪我か、慢性の病気かなどを判断します。 |
| 痛みの性質 | どのような痛み(ズキズキ、ジンジンなど)が、いつ出るかを確認します。 |
| 日常生活への影響 | 症状の重症度や治療の必要性を判断します。 |
| 過去の病歴や怪我 | 現在の症状との関連性を探ります。 |
レントゲン(X線)検査でわかること
レントゲン検査は、骨の状態を評価するための基本的な画像検査です。関節の隙間の広さ(軟骨の厚みを反映)、骨の変形の有無、骨折などを確認することができます。
変形性膝関節症の診断や進行度の評価において、非常に重要な情報を提供します。
ただし、レントゲンには軟骨や半月板、靭帯そのものは写らないため、これらの組織に問題が疑われる場合は、さらに詳しい検査が必要となります。
MRI検査や関節液検査の役割
MRI検査は、磁気を利用して体の断面を撮影する検査です。レントゲンでは見ることのできない軟骨、半月板、靭帯、筋肉といった軟部組織の状態を詳細に描出することが可能です。
半月板損傷や靭帯損傷が疑われる場合や、レントゲンで異常がないにもかかわらず症状が強い場合に、非常に有用な検査となります。
また、膝に水(関節液)がたまっている場合は、注射器で関節液を抜いて調べる「関節液検査」を行うことがあります。
関節液の色や濁り、含まれる成分を調べることで、関節リウマチや痛風、化膿性関節炎などの診断に役立ちます。
自宅でできるセルフケアとストレッチ
医療機関での診断と並行して、あるいは症状が軽い場合には、自宅でのセルフケアが症状の緩和と進行予防に役立ちます。
特に膝周りの筋肉の柔軟性を高め、筋力を維持することは、膝関節の負担を減らす上でとても大切です。ここでは、自宅で安全に行えるケアや運動を紹介します。
ただし、痛みが強い時は無理をせず、医師に相談してください。
膝周りの筋肉をほぐすストレッチ
硬くなった筋肉をゆっくりと伸ばし、柔軟性を取り戻すことで、膝の動きがスムーズになります。特に太ももの前後、お尻の筋肉を入念に行いましょう。
反動をつけず、「痛いけど気持ちいい」と感じる程度で20〜30秒ほど静かに伸ばすのがポイントです。
おすすめのストレッチ
| ストレッチ対象の筋肉 | 簡単な方法 | ポイント |
|---|---|---|
| ハムストリングス(太もも裏) | 椅子に浅く座り、片脚を前に伸ばす。背筋を伸ばしたまま上体を前に倒す。 | 膝が曲がらないように注意する。 |
| 大腿四頭筋(太もも前) | 壁などに手をついて立ち、片方の足首を持ってかかとをお尻に近づける。 | 膝が体より前に出ないようにする。 |
| お尻の筋肉 | 仰向けに寝て、片膝を両手で抱えて胸に引き寄せる。 | 腰が浮かないように気をつける。 |
膝に負担をかけない筋力トレーニング
膝を支える筋力を強化することは、関節の安定性を高め、痛みの軽減につながります。重要なのは、膝に体重をかけすぎない方法でトレーニングを行うことです。
急に激しい運動を始めるのではなく、簡単な運動から少しずつ慣らしていきましょう。
椅子に座ってできる筋トレ
椅子に深く座り、背筋を伸ばします。片方の脚をゆっくりと持ち上げ、床と水平になるまで膝を伸ばします。その状態で5秒ほど静止し、ゆっくりと下ろします。
この動作を左右それぞれ10回程度繰り返します。太ももの前側の筋肉(大腿四頭筋)を効果的に鍛えることができます。
日常生活での注意点と工夫
普段の生活の中での少しの工夫が、膝への負担を大きく減らすことにつながります。
- 床からの立ち座りを避け、椅子やベッド中心の生活にする
- 階段の上り下りを減らす、手すりを利用する
- クッション性の高い靴を選ぶ
- 正座やあぐらなど、膝を深く曲げる姿勢を避ける
アイシングと温熱療法の使い分け
膝のケアとして、冷やすべきか温めるべきか迷うことがあるかもしれません。この二つは、状況に応じて使い分けることが重要です。
急な痛みや腫れ、熱感がある場合、つまり「急性期」の炎症が起きている時は、アイシング(冷却)が有効です。氷のうなどで15〜20分程度冷やすことで、炎症と痛みを和らげます。
一方で、慢性的な痛みや筋肉のこわばりがある場合は、温熱療法(温めること)が効果的です。蒸しタオルや入浴で血行を促進し、筋肉の緊張をほぐすことで、痛みが緩和され動きやすくなります。
冷却と温熱の使い分け
| アイシング(冷却) | 温熱療法(温める) | |
|---|---|---|
| 適用する状況 | 怪我の直後、急な痛み、腫れ、熱感がある時 | 慢性的な痛み、筋肉のこわばり、運動前 |
| 主な目的 | 炎症を抑え、痛みを鎮める | 血行を促進し、筋肉の緊張を和らげる |
専門家による改善アプローチ
セルフケアだけでは症状が改善しない場合や、痛みが強い場合には、医療機関での専門的なアプローチが必要となります。
治療法は、患者さん一人ひとりの年齢、活動レベル、症状の原因や進行度によって異なります。医師と相談しながら、自分に合った方法を選択していくことが大切です。
薬物療法(内服薬・外用薬・注射)
痛みを和らげ、炎症を抑えることを目的に薬物療法が行われます。
まずは炎症を抑える効果のある非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)の飲み薬や貼り薬、塗り薬などが用いられることが一般的です。
これらの薬で効果が不十分な場合や、痛みが強い場合には、関節内に直接薬剤を注入する関節内注射が行われることもあります。
ヒアルロン酸注射は、関節の滑りを良くし、痛みを和らげる効果が期待できます。また、炎症が非常に強い場合には、ステロイド注射が選択されることもあります。
物理療法と運動療法
物理療法は、電気や温熱、超音波などの物理的なエネルギーを利用して、痛みの緩和や血行改善を図る治療法です。
医療機関やリハビリテーション施設で、理学療法士などの専門家の指導のもとに行われます。
運動療法もリハビリテーションの柱であり、患者さん個々の状態に合わせたストレッチや筋力トレーニングの指導を受けることができます。
正しい身体の使い方を学び、膝に負担の少ない動作を習得することも、運動療法の重要な目的です。
代表的な物理療法
| 治療法 | 内容 | 期待される効果 |
|---|---|---|
| 温熱療法 | ホットパックやマイクロ波などで患部を温める。 | 血行促進、痛みの緩和、筋肉の弛緩。 |
| 電気刺激療法 | 低周波や干渉波などの電気で筋肉や神経を刺激する。 | 鎮痛効果、筋力低下の予防。 |
| 超音波療法 | 超音波の振動により、深部組織を温め、マッサージする。 | 組織の修復促進、痛みの緩和。 |
装具療法(サポーターやインソール)
膝の状態を安定させ、負担を軽減するために装具を用いることがあります。代表的なものに膝サポーターがあります。
サポーターには、保温効果のあるシンプルなものから、関節の動きを制限して安定性を高める支柱付きのものまで様々な種類があります。
また、O脚や扁平足など、足のアライメント(骨の配列)に問題がある場合は、靴の中に入れる足底板(インソール)が有効なことがあります。
インソールによって足裏からの衝撃を吸収し、膝にかかる負担のバランスを整えることができます。
手術療法という選択肢
薬物療法やリハビリテーションなどの保存的治療を続けても症状が改善せず、日常生活に大きな支障が出ている場合には、手術療法が検討されます。
手術にはいくつかの種類があり、関節の状態や年齢などを考慮して最適な方法が選択されます。
代表的な手術には、関節鏡を使って損傷した半月板などを処置する「関節鏡視下手術」や、O脚を矯正する「高位脛骨骨切り術」、そして傷んだ関節の表面を人工の関節に置き換える「人工膝関節置換術」などがあります。
手術は最終的な選択肢の一つですが、多くの患者さんの痛みを取り除き、生活の質を大きく改善する可能性があります。
よくある質問
ここでは、膝が曲がってる状態やそれに伴う症状に関して、患者さんからよく寄せられる質問とその回答をまとめました。
膝を動かすとポキポキと音が鳴ります。これは異常でしょうか?
回答:膝の音には、あまり心配のいらないものと、注意が必要なものがあります。
痛みや腫れを伴わず、たまに鳴る程度の音であれば、関節内の気泡が弾ける音などの生理的な現象であることが多く、過度に心配する必要はありません。
しかし、音が鳴るたびに痛みやひっかかりを感じる、頻繁に鳴る、音が大きくなってきた、といった場合は、軟骨がすり減っていたり、半月板が傷ついていたりする可能性がありますので、一度整形外科で相談することをお勧めします。
膝に良いとされるサプリメントは効果がありますか?
回答:グルコサミンやコンドロイチン、ヒアルロン酸など、関節に良いとされる成分を含んだサプリメントは数多く市販されています。
これらの成分はもともと体内に存在する軟骨の構成成分ですが、サプリメントとして摂取した場合の効果については、医学的に明確な結論が出ていないのが現状です。
一部の方で痛みが和らいだという報告もありますが、効果には個人差が大きいと考えられます。
サプリメントはあくまで健康食品であり、治療の基本は適切な運動、体重管理、そして必要に応じた医療機関での治療です。
使用する場合は、補助的なものと位置づけ、過度な期待はせずに試してみるのが良いでしょう。
正座が全くできません。改善することは可能でしょうか?
正座ができない原因は様々です。太ももの前の筋肉(大腿四頭筋)が硬い、膝関節そのものの動きが悪い(屈曲制限)、あるいは半月板などの組織に問題がある、といったことが考えられます。
筋肉の硬さが原因であれば、ストレッチを継続することで少しずつ改善する可能性があります。
しかし、変形性膝関節症などが進行して骨の形が変わってしまっている場合は、正座ができるようになるのは難しいこともあります。
無理に正座をしようとするとかえって膝を痛める原因にもなりますので、まずはなぜ正座ができないのか、原因をはっきりさせることが重要です。
原因に応じた対処法(ストレッチ、リハビリ、生活習慣の改善など)を行うことで、症状の緩和を目指します。
治療やセルフケアを始めたら、どのくらいの期間で改善が見込めますか?
回答:改善にかかる期間は、膝が曲がってる原因、症状の重さ、年齢、そして取り組む内容によって大きく異なります。
例えば、軽度の筋肉の緊張が原因であれば、数週間のストレッチや生活習慣の見直しで変化を感じられるかもしれません。
一方、変形性膝関節症が進行しているような場合は、症状の緩和や進行抑制を目的とした長期的な取り組みが必要になります。
大切なのは、焦らずに根気強くケアを続けることです。数日で劇的に変わるものではありませんが、適切なケアを継続することで、少しずつ痛みが和らいだり、動きがスムーズになったりといった変化が期待できます。
定期的に専門家のチェックを受けながら、自分に合ったペースで続けていきましょう。
参考文献
MARTIN, Jean-Noël, et al. Treatment of knee flexion contracture due to central nervous system disorders in adults. JBJS, 2006, 88.4: 840-845.
TEMELLI, Yener; AKALAN, Nazif. Treatment approaches to flexion contractures of the knee. Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica, 2009, 43.2: 113-120.
RODRIGUEZ-MERCHAN, E. C., et al. Articular contracture of the knee. Musculoskeletal aspects of haemophilia, 2000, 112-120.
HERZENBERG, John E., et al. Mechanical distraction for treatment of severe knee flexion contractures. Clinical Orthopaedics and Related Research (1976-2007), 1994, 301: 80-88.
STEFFEN, Teresa M.; MOLLINGER, Louise A.; HARADA, Nancy. Low-load, prolonged stretch in the treatment of knee flexion contractures in nursing home residents. Physical Therapy, 1995, 75.10: 40-52.
JAMES, SE Farmer, M. Contractures in orthopaedic and neurological conditions: a review of causes and treatment. Disability and rehabilitation, 2001, 23.13: 549-558.
KULOWSKI, Jacob. THE CLASSIC: Flexion Contracture of the Knee: The Mechanics of the Muscular Contracture and the Turnbuckle Cast Method of Treatment; with a Review of Fifty-Five Cases*. Clinical Orthopaedics and Related Research (1976-2007), 2007, 464: 4-10.
FEHRING, Thomas K., et al. Surgical treatment of flexion contractures after total knee arthroplasty. The Journal of arthroplasty, 2007, 22.6: 62-66.
HEIJNEN, L.; DE KLEIJN, P. Physiotherapy for the treatment of articular contractures in haemophilia. Haemophilia, 1999, 5: 16-19.
CAMPBELL, T. Mark, et al. Stretching, bracing, and devices for the treatment of osteoarthritis-associated joint contractures in nonoperated joints: a systematic review and meta-analysis. Sports health, 2023, 15.6: 867-877.
Symptoms 症状から探す