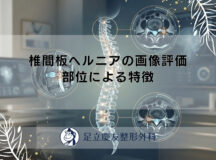股関節痛における整形外科での治療の選択肢
股関節に痛みや違和感があると、「歩けなくなったらどうしよう」と不安になるかもしれません。
足の付け根が痛む、靴下が履きにくい、あぐらがかけないといった症状は、股関節からのサインです。
この記事では、「股関節 症状」でお悩みの方が、整形外科を受診した際にどのような検査を行い、どのような治療の選択肢があるのかを分かりやすく解説します。
ご自身の状態を理解し、医師と相談しながら納得のいく治療法を見つけるための一助となれば幸いです。
ここでは、保存療法から手術療法まで、股関節痛に対する標準的な整形外科での対応を順序立てて紹介します。
目次
股関節の症状 気づきのサイン
股関節の不調は、日常生活のささいな動作で現れることがあります。初期の症状を見逃さず、自分の体の変化に気づくことが大切です。
ここでは、股関節に問題があるときに感じやすい代表的な症状を紹介します。
痛みの出る場所と特徴
股関節の痛みは、必ずしも「足の付け根」だけとは限りません。
「お尻が痛い」「太ももの外側が張る」「膝の上あたりが痛む」といった場合も、原因が股関節にあることは少なくありません。
痛み方にも特徴があり、ズキズキとうずくような痛み、歩くときに体重がかかると響くような痛み、関節がこすれるような鈍い痛みなど、人によって感じ方が異なります。
どのあたりが、どのように痛むのかを把握することは、診断の重要な手がかりとなります。
痛みの出るタイミング
痛みがいつ出るかにも注目しましょう。代表的なのは「歩き始め」の痛みです。座っていて立ち上がる時や、歩き出す最初の一歩、二歩が痛むものの、歩いているうちに和らぐことがあります。
また、長時間歩いた後や、階段の上り下りで痛みが強くなることもあります。
症状が進行すると、夜寝ている時に痛む(夜間痛)や、安静にしていても痛む(安静時痛)といった状態になることもあり、注意が必要です。
可動域の制限
痛みだけでなく、「関節の動きが悪くなる」ことも股関節の重要な症状です。具体的には、以下のような動作がやりにくくなります。
- 靴下を履く動作
- 足の爪を切る動作
- あぐらをかく動作
- 正座(股関節が曲がりにくくなる)
これらの動作は股関節を深く曲げたり、外側に開いたりする動きを必要とします。関節の変形や炎症によって、この動きが制限されるのです。
左右の足でやりにくさに差があるかどうかも確認してみましょう。
その他の気になるサイン
痛みや動きの制限以外にも、いくつかのサインがあります。
歩いているときに「体が左右に揺れる」(跛行:はこう)のは、痛みから逃れるためであったり、股関節周囲の筋力が低下していたりするためです。
また、股関節を動かしたときに「ゴリゴリ」「ポキポキ」といった音が鳴る(クリック音)こともあります。すぐに問題となることは少ないですが、痛みを伴う場合は注意が必要です。
症状から考える主な股関節の病気
股関節に症状が出る背景には、いくつかの代表的な病気が考えられます。症状の原因を特定することが、適切な治療への第一歩です。
ここでは、整形外科でよく見られる股関節の病気を紹介します。
変形性股関節症
股関節の病気の中で最も多いとされるのが、変形性股関節症です。これは、関節のクッションである「軟骨」がすり減り、骨が変形していく病気です。
初期は歩き始めや立ち上がりの痛みですが、進行すると持続的な痛みや可動域の制限が強くなります。
日本では、生まれつき股関節の骨盤側の受け皿(臼蓋)が浅い「臼蓋形成不全」が背景にある場合が多いとされています。
臼蓋形成不全
前述の通り、骨盤側の屋根(臼蓋)の発育が不十分で、大腿骨頭(太ももの骨の先端)を十分に覆えていない状態を指します。
若い頃は症状がなくても、年齢とともに股関節に負担がかかり、軟骨がすり減りやすくなるため、将来的に変形性股関節症に移行しやすい特徴があります。
股関節インピンジメント症候群(FAI)
FAI(Femoroacetabular Impingement)とも呼ばれ、股関節を深く曲げた時などに、大腿骨と臼蓋の骨同士が衝突(インピンジメント)し、痛みや軟骨、関節唇(軟骨の縁にある組織)の損傷を引き起こす状態です。
比較的若い世代やスポーツ選手に見られることがあり、特定の動作で足の付け根に詰まるような痛みが出ることが特徴です。
股関節の主な病気の比較
| 病名 | 主な特徴 | 症状が出やすい年代 |
|---|---|---|
| 変形性股関節症 | 関節軟骨のすり減りと骨の変形 | 中高年以降(特に女性) |
| 臼蓋形成不全 | 臼蓋(受け皿)の発育不全 | 若年期から症状が出る場合もある |
| 股関節インピンジメント(FAI) | 骨同士の衝突による痛みや損傷 | 比較的若い世代、スポーツ選手 |
整形外科での最初のステップ 診断までの流れ
股関節の症状で整形外科を受診すると、まずは症状の原因を正確に把握するための診察と検査を行います。
どのような流れで診断がつくのかを知っておくと、安心して受診できるでしょう。
問診 症状を詳しく伝える
医師はまず、患者さんの話を詳しく聞きます。これは診断において非常に重要です。
いつから症状があるのか、どこが痛むのか、どんな時に痛むのか、これまでにかかった病気やケガ、現在飲んでいる薬などについて質問します。
自分の症状を具体的に(例えば「1ヶ月前から、歩き始めに右足の付け根が痛む」のように)伝えられるよう、少し整理しておくと良いでしょう。
視診と触診 股関節の状態を確認
次に、医師が股関節の状態を直接確認します。立った姿勢や歩き方(視診)を観察し、ベッドに横になって股関節を動かしながら痛みが出る角度や動きの制限(可動域)を調べます(触診)。
また、股関節の周囲を押して、圧痛点(押して痛む場所)を探します。これにより、股関節のどの部分に問題がありそうか、おおよその見当をつけます。
画像検査による詳細な評価
問診や触診で得た情報をもとに、画像検査で股関節の状態を客観的に評価します。股関節は体の深い部分にあるため、画像検査は正確な診断に必要です。
画像検査の種類と目的
| 検査方法 | 主な目的 | 分かること |
|---|---|---|
| レントゲン(単純X線)検査 | 骨の状態の確認 | 骨の変形、関節の隙間(軟骨の厚さ)、臼蓋形成不全の有無 |
| MRI検査 | 軟骨や筋肉、靭帯などの確認 | 軟骨の損傷、関節唇損傷、炎症、大腿骨頭壊死の早期発見 |
| CT検査 | 骨の立体的な形状の確認 | 骨の変形や骨折の詳しい状態、骨棘(こつきょく)の様子 |
これらの検査結果を総合的に判断し、医師は股関節の症状の原因を診断します。そして、その診断に基づいて治療の方針を立てていきます。
保存療法 痛みを和らげ機能を守る
診断がついた後、多くの股関節痛の治療は「保存療法」から始めます。保存療法とは、手術以外の方法で症状の改善と病気の進行予防を目指す治療法です。
股関節にかかる負担を減らし、痛みを管理しながら、できるだけ長く自分の関節機能を維持することが目的です。
薬物療法 炎症と痛みの管理
痛みが強い時期には、薬物療法を行います。主に、炎症を抑えて痛みを和らげる目的で使用します。
ただし、薬は根本的に病気を治すものではなく、あくまで症状を緩和するため、あるいはリハビリテーションをスムーズに進めるために用いるものです。
主な薬物療法の種類
| 種類 | 形態 | 主な役割 |
|---|---|---|
| 非ステロイド性抗炎症薬 (NSAIDs) | 内服薬(飲み薬) | 炎症と痛みを抑える |
| 非ステロイド性抗炎症薬 (NSAIDs) | 外用薬(湿布・塗り薬) | 局所の炎症と痛みを抑える |
| アセトアミノフェン | 内服薬(飲み薬) | 鎮痛作用(炎症を抑える作用は弱い) |
このほか、痛みが非常に強い場合には、股関節に直接注射(関節内注射)を行うこともあります。
運動療法(リハビリテーション)
保存療法の中心となるのが運動療法、すなわちリハビリテーションです。理学療法士などの専門家の指導のもと、股関節周囲の筋力を強化したり、関節の柔軟性を高めたりします。
痛いからといって動かさないでいると、筋力が低下し、関節が硬くなり、かえって症状が悪化することがあります。
適切な運動は、股関節を安定させ、負担を減らすためにとても重要です。
日常生活の工夫
股関節への負担を減らすためには、日々の生活習慣を見直すことも大切です。体重が重いと、歩行時に股関節にかかる負担は何倍にもなります。
適正体重を維持することは、股関節を守る上で非常に有効です。また、股関節に負担のかかる動作を避ける工夫も必要です。
日常生活での注意点
| 場面 | 推奨される工夫 | 避けた方がよい動作 |
|---|---|---|
| 動作全般 | 杖を使用する(痛い方と反対の手で持つ) | 重い物を持つ、長時間の歩行 |
| 住環境 | 洋式の生活(椅子、ベッドの使用) | 床からの立ち座り、正座、あぐら |
| 入浴 | 浴槽内に椅子を置く、手すりをつける | 深い浴槽をまたぐ動作 |
これらの工夫は、痛みを誘発する動作を減らし、股関節の炎症を悪化させないために役立ちます。
運動療法(リハビリテーション)の具体的な内容
保存療法の核となる運動療法(リハビリテーション)は、股関節の機能を維持・改善するために行います。
医師の診断に基づき、理学療法士が個々の状態に合わせたプログラムを作成します。
自己流で行うと逆に痛めてしまう可能性もあるため、専門家の指導のもとで正しく行うことが大切です。
筋力トレーニング 股関節の安定化
股関節を支える筋肉を鍛えることは、関節の安定性を高め、軟骨への負担を減らすのに役立ちます。
特に重要なのが、お尻の筋肉(中殿筋など)や太ももの筋肉(大腿四頭筋など)です。
股関節周囲の主な筋肉と役割
| 筋肉名 | 主な役割 | 機能低下による影響 |
|---|---|---|
| 中殿筋(お尻の横) | 歩行時に骨盤を支える | 歩行時の体の揺れ(跛行) |
| 大殿筋(お尻の後ろ) | 体を起こす、階段を上る | 立ち上がりや歩行の推進力低下 |
| 大腿四頭筋(太ももの前) | 膝を伸ばす、体重を支える | 膝折れ、歩行時の不安定感 |
トレーニングは、ベッドで横になったまま行う負荷の軽いものから始め、状態に合わせて徐々に強度を調整します。
例えば、仰向けに寝てお尻を持ち上げる「ヒップリフト」や、横向きに寝て上の脚を持ち上げる「側臥位外転」などがあります。
ストレッチ 柔軟性の改善
痛みがあると、股関節周囲の筋肉が緊張して硬くなり、血流が悪化し、さらに痛みを感じやすくなるという悪循環に陥ることがあります。
また、筋肉が硬いと関節の動きも制限されます。
お尻や太ももの裏側(ハムストリングス)、股関節の付け根(腸腰筋)などを中心に、無理のない範囲でゆっくりと筋肉を伸ばすストレッチを行い、柔軟性を取り戻します。
可動域訓練 関節の動きを保つ
股関節が硬くなる(拘縮:こうしゅく)のを防ぐため、関節を動かす訓練も行います。痛みが出ない範囲で、股関節を曲げる、伸ばす、開く、閉じるといった動きをゆっくりと行います。
自分で行うだけでなく、理学療法士が補助しながら動かすこともあります。これにより、現在の関節の動きを維持し、日常生活での動作をスムーズにします。
動作指導 日常生活での負担軽減
リハビリテーションでは、運動機能の改善だけでなく、日常生活での動作の仕方を指導することも重要な役割です。
前述した「日常生活の工夫」とも関連しますが、立ち上がり方、歩き方、階段の上り下りの仕方など、股関節に負担をかけにくい体の使い方を学びます。
例えば、杖の正しい使い方や、物を拾うときに股関節を深く曲げずに膝を使う方法などを習得します。
手術療法 高度な変形や痛みに対する選択
保存療法を数ヶ月続けても痛みが改善しない場合や、日常生活に大きな支障が出ている場合、あるいは画像検査で変形が高度に進行している場合には、手術療法を検討します。
手術の目的は、痛みの原因を取り除き、股関節の機能(歩く、座るなど)を改善することです。
関節鏡視下手術(股関節鏡)
比較的小さな切開からカメラ(関節鏡)と器具を関節内に挿入し、損傷した組織の修復や、衝突の原因となる骨の隆起を切除する手術です。
主に、股関節インピンジメント症候群(FAI)や関節唇損傷など、軟骨のすり減りが軽度な場合が対象となります。体への負担が比較的少ないことが利点です。
骨切り術 自分の関節を温存する
臼蓋形成不全などで骨盤側の被りが浅い場合に、骨盤の骨を切って移動させ、大腿骨頭をより深く覆うようにする手術です(寛骨臼回転骨切り術など)。
自分の関節を温存できるため、比較的若い世代で、軟骨のすり減りがまだそれほど進んでいない場合に選択されます。長期的に変形性股関節症への進行を予防する目的もあります。
人工股関節置換術 関節機能の再建
変形性股関節症が進行し、軟骨がすり減り、骨が著しく変形してしまった場合に選択される手術です。
損傷した股関節の表面(臼蓋側と大腿骨頭側)を取り除き、金属やポリエチレン、セラミックなどでできた人工の関節(インプラント)に入れ替えます。
股関節の痛みを大きく改善し、関節の動きを取り戻す効果が期待できます。
主な手術療法の比較
| 手術方法 | 主な対象 | 主な目的 |
|---|---|---|
| 関節鏡視下手術 | FAI、関節唇損傷(変形が軽度) | 痛みの原因除去、組織の修復 |
| 骨切り術 | 臼蓋形成不全(変形が軽度~中等度) | 関節の安定化、変形の進行予防 |
| 人工股関節置換術 | 変形性股関節症(変形が高度) | 除痛(痛みの除去)、関節機能の再建 |
人工股関節置換術について
手術療法の中でも、変形性股関節症が進行した場合の治療法として広く行われているのが「人工股関節置換術」です。
この手術は、股関節の機能を取り戻す上で大きな効果が期待できますが、どのような手術なのか、術後はどうなるのか、不安に思う方も多いでしょう。
手術の概要と目的
人工股関節置換術は、すり減った軟骨と変形した骨を取り除き、代わりとなる人工の関節部品(インプラント)を設置する手術です。
インプラントは、骨盤側に設置する「カップ」と、大腿骨側に設置する「ステム」、そしてその間ではまる「骨頭ボール」と「ライナー」から構成されます。
この手術の最大の目的は、変形した関節による「痛みを取り除く」ことです。痛みがなくなることで、歩行能力が改善し、日常生活の動作が楽になり、生活の質(QOL)の向上が期待できます。
術後のリハビリテーション計画
手術が終わればすぐに元通りに歩けるわけではなく、術後のリハビリテーションが非常に重要です。
手術で関節の機能は再建されますが、その関節を支え、動かすための筋力を取り戻し、正しい歩き方を再学習する必要があります。
術後リハビリの一般的な流れ(一例)
| 時期(目安) | 主な内容 | 目標 |
|---|---|---|
| 手術翌日~数日 | ベッド上での運動、車椅子への移乗 | 関節を動かす、離床する |
| 手術後数日~1週 | 平行棒や歩行器を使った歩行訓練 | 体重をかけて歩く練習 |
| 手術後1週~退院 | 杖を使った歩行訓練、階段昇降 | 安定した歩行、日常生活動作の獲得 |
この流れは医療機関や患者さんの状態によって異なります。退院後も、筋力トレーニングや可動域訓練を継続し、定期的に診察を受けて股関節の状態を確認します。
人工関節の耐久性
かつては人工関節の耐久年数(耐用年数)が課題とされることもありましたが、近年はインプラントの材質やデザインが改良され、長期的な成績は非常に安定しています。
ただし、人工関節は永久に機能するわけではなく、体重や活動量、骨の状態によっては、将来的に入れ替え(再置換)の手術が必要になる可能性もあります。
そのため、術後は体重管理に努め、激しいスポーツや股関節に過度な負担がかかる動作は避けるよう指導されることが一般的です。
股関節痛における整形外科での治療に関するよくある質問
最後に、股関節の症状や治療に関して、患者さんからよく寄せられる質問とその回答をまとめます。
Q. 症状が出たらすぐに病院に行くべきですか?
A. 痛みが軽い場合や、一時的なものであれば様子を見ることもありますが、痛みが続く場合や、だんだん強くなる場合、日常生活の動作(靴下を履く、歩くなど)に支障が出始めた場合は、早めに整形外科を受診することをお勧めします。
特に「股関節 症状」が気になる場合は、一度専門医に相談し、現在の状態を正確に把握することが大切です。
早期に原因が分かれば、それだけ早く適切な対策(リハビリや生活指導)を始めることができます。
Q. 保存療法でどのくらい良くなりますか?
A. 保存療法の効果は、病気の進行度や個人の筋力、生活習慣によって異なります。
初期の変形性股関節症であれば、保存療法によって痛みが和らぎ、日常生活を問題なく送れるようになることも少なくありません。
運動療法や体重管理を継続することで、病気の進行を緩やかにする効果も期待できます。
ただし、保存療法は変形した骨や減った軟骨を元に戻すものではないため、症状の管理と機能の維持が主な目的となります。
Q. 手術を勧められましたが、決断できません。
A. 手術、特に人工股関節置換術は大きな決断です。不安を感じるのは当然のことです。
大切なのは、医師から手術の必要性、手術によって期待できる効果、そして手術に伴うリスクや術後の生活について、十分に説明を受けることです。
その上で、現在の痛みの強さや日常生活での困りごと(例えば、痛みのために外出できない、趣味を諦めているなど)と、手術によって得たいものを天秤にかけ、ご自身が納得して治療法を選択することが重要です。
Q. 治療法の選択はどのように行いますか?
A. 治療法の選択は、医師が一方的に決めるものではありません。
医師は、診断結果(病名、進行度)、患者さんの年齢、活動レベル(仕事や趣味)、全身の状態、そして患者さん自身の希望を総合的に考慮して、いくつかの治療の選択肢を提示します。
それぞれの治療法のメリットとデメリットについてよく話し合い、患者さん自身が主体的に治療方針の決定に関わっていくことが、満足のいく結果につながります。
参考文献
HUNT, Devyani, et al. Clinical outcomes analysis of conservative and surgical treatment of patients with clinical indications of prearthritic, intra-articular hip disorders. PM&R, 2012, 4.7: 479-487.
KELLY, Bryan T.; WILLIAMS, Riley J.; PHILIPPON, Marc J. Hip arthroscopy: current indications, treatment options, and management issues. The American journal of sports medicine, 2003, 31.6: 1020-1037.
DE L’ESCALOPIER, Nicolas; ANRACT, Philippe; BIAU, David. Surgical treatments for osteoarthritis. Annals of physical and rehabilitation medicine, 2016, 59.3: 227-233.
CEBALLOS-LAITA, Luis, et al. Effects of non-pharmacological conservative treatment on pain, range of motion and physical function in patients with mild to moderate hip osteoarthritis. A systematic review. Complementary therapies in medicine, 2019, 42: 214-222.
ANZILLOTTI, Giuseppe, et al. Conservative vs. surgical management for femoro-acetabular impingement: a systematic review of clinical evidence. Journal of clinical medicine, 2022, 11.19: 5852.
SINATRA, Raymond S.; TORRES, Jaime; BUSTOS, Arsenio M. Pain management after major orthopaedic surgery: current strategies and new concepts. JAAOS-Journal of the American Academy of Orthopaedic Surgeons, 2002, 10.2: 117-129.
SNIJDERS, G. F., et al. Evidence-based tailored conservative treatment of knee and hip osteoarthritis: between knowing and doing. Scandinavian journal of rheumatology, 2011, 40.3: 225-231.
AWEID, Osama, et al. Treatment modalities for hip and knee osteoarthritis: A systematic review of safety. Journal of Orthopaedic Surgery, 2018, 26.3: 2309499018808669.
MCGOVERN, Ryan P., et al. Non-operative management of individuals with non-arthritic hip pain: a literature review. International journal of sports physical therapy, 2019, 14.1: 135.
COOK, Kyle M.; HEIDERSCHEIT, Bryan C. Conservative management of a young adult with hip arthrosis. journal of orthopaedic & sports physical therapy, 2009, 39.12: 858-866.
Symptoms 症状から探す