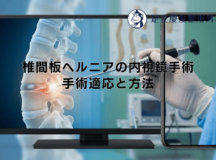膝の脱臼が起きたときの緊急対応と治療方針
膝に強い衝撃が加わったり、無理な体勢で力を入れたりすると、膝脱臼という状態に陥ることがあります。
急に膝が外れたような痛みや見た目の変形が生じると、多くの方が戸惑うのではないでしょうか。適切な初動で膝の安定を保ち、専門医の診察を受けるまでの対応を知っておくことは大切です。
本記事では膝脱臼に関する基礎知識や応急処置、治療に至るまでの考え方を詳しく解説いたします。
目次
膝脱臼とは何か
急激な外力や捻転によって膝の骨同士の連結が崩れ、正常な位置から外れた状態を指します。健やかな膝の働きを維持するためにも、原因や基本的な特徴を知ることが重要です。
膝関節には骨や靭帯、軟骨など多様な組織が集まっており、関節全体がうまく噛み合うことで足を曲げ伸ばしできます。
膝脱臼が起こる背景を理解すると、緊急対応と治療方針への意識が高まります。
膝脱臼の基本構造
膝は大腿骨、脛骨、膝蓋骨と呼ばれる骨が相互に連結している部分です。靭帯がこれらの骨同士を強固につなぎ、半月板や軟骨が衝撃を吸収しながら滑らかな動きをサポートします。
ところが強い力で膝を外側や内側にひねるなどの動作が加わると、骨同士の位置関係がずれて膝脱臼となる可能性があります。
膝脱臼が起こるメカニズム
膝の安定性は大腿四頭筋やハムストリングスなどの筋肉、そして複数の靭帯によって保たれています。これらがうまく働かない状態で膝に過剰な負荷をかけると、膝脱臼のリスクが高まります。
特に急激な加速や減速、方向転換などに伴う衝撃が直接膝へ伝わると、脱臼まで発展することがあります。
間違えやすい症状との違い
激しい膝の痛みと変形があるとき、多くの人は骨折や靭帯損傷を疑うかもしれません。しかし膝脱臼は文字どおり骨の位置が外れている状態です。
強い痛みに加えて膝がぐらぐらしたり、足が変な方向を向いたりする点が大きな特徴です。自己判断で患部を動かすと悪化する危険性があるので、慎重に動きを控えて医療機関を受診しましょう。
参考データと膝の構造要素
膝脱臼は全体の関節脱臼の中ではそれほど頻度が高いものではありません。しかし体格や筋肉量、普段の運動習慣などによっても発生リスクは異なります。
膝が担う役割と複雑な構造を示すデータを確認すると、日頃のケアがどれほど大切かを改めて実感するはずです。
膝まわりの組織と主な役割
| 名称 | 役割 |
|---|---|
| 大腿骨 | 太ももの骨で膝の上部を構成する |
| 脛骨 | すねの骨で膝の下部を構成する |
| 膝蓋骨 | いわゆるお皿の骨 |
| 半月板 | 膝の衝撃を和らげる軟骨組織 |
| 前十字靭帯 | 膝の前後方向の安定を保つ |
| 後十字靭帯 | 膝の後ろ側の安定を維持する |
| 内側側副靭帯 | 膝の内側方向の安定を保つ |
| 外側側副靭帯 | 膝の外側方向の安定を支える |
発生頻度と原因
膝脱臼は他の関節脱臼と比較すると少ないといわれていますが、発生すると重症化しやすい特徴があります。
膝は体重を支える部位であるだけに、怪我が起こった際のダメージも大きくなりがちです。運動や日常生活の動きが引き金となるケースを知っておくと、リスク回避に役立ちます。
日常生活での要因
普段の生活の中でも、ちょっとした転倒や段差の踏み外しなどで膝脱臼を引き起こす場合があります。膝に急激な衝撃が加わると、そのまま骨がずれてしまうことがあります。
特に体力が低下している方や筋力不足の方は、ちょっとした段差でも踏ん張りが利かずに怪我へつながることがあります。
スポーツ中に多い動作
サッカーやバスケットボールなど、素早い方向転換やストップ動作を繰り返すスポーツは膝脱臼の原因になりやすいです。
捻りの強い動作やジャンプ後の着地など、膝に大きな負荷がかかる場面が多いためです。コンタクトスポーツで相手選手と接触した際にも、強い外力が膝へ伝わり、脱臼が生じる可能性があります。
スポーツにおける負荷の比較
| スポーツ種目 | 膝への衝撃の特徴 | 膝脱臼リスク要因 |
|---|---|---|
| サッカー | 方向転換や急停止が多い | 斜めからの衝撃、踏み込みの誤差 |
| バスケット | ジャンプや着地が頻繁 | 着地で体重が片膝に集中する場面 |
| ラグビー | タックルなど直接的な接触が多い | 強い外力が横から加わる |
| テニス | 急な方向転換と短いダッシュ | コートサーフェスによる滑り |
| バレーボール | ジャンプやアタック時の着地動作 | 無理な姿勢での着地 |
加齢や基礎疾患との関係
年齢を重ねると筋肉や靭帯が弱くなり、骨の強度も低下する可能性があります。その結果、わずかな転倒や膝への衝撃でも脱臼につながるリスクが上昇します。
またリウマチや骨粗しょう症など、骨や関節に影響を与える基礎疾患を持つ場合も膝脱臼のリスクが高まります。
医療機関での統計結果
整形外科を含めた医療施設での集計データによると、膝脱臼の多くがスポーツ中の外傷や転倒事故によって生じています。
また、発生時の年齢層を見ると若年層だけでなく、中高年以降も一定数発生している点が特徴的です。筋力低下やバランス感覚の衰えが関係すると考えられています。
膝脱臼の症状と応急処置
脱臼に至ると、激しい痛みとともに膝の形が明らかに変形する場合があります。動かそうとすると激痛を伴い、無理に元に戻そうとするとさらに関節や靭帯を傷める恐れがあります。
まずは安静を保ち、早めに医療機関へつなげる対応が不可欠です。早期の的確な処置で膝の状態を悪化させない工夫が必要です。
痛みや変形の特徴
膝脱臼は大きな痛みとともに、明らかに膝周辺の形が異常に見えるケースがあります。具体的には膝蓋骨や脛骨が外側にずれてしまい、肉眼でも曲がった状態がわかることがあります。
痛みだけでなく、皮膚の色変化や腫れ、内出血などが起こることもあり、歩行が困難になることが多いです。
膝脱臼による変形パターン
| パターン | 具体的な様子 | 考えられる要因 |
|---|---|---|
| 前方脱臼 | 膝が前に突き出たように見える | 前十字靭帯周辺の損傷 |
| 後方脱臼 | 膝が後ろへ押し込まれたように見える | 後十字靭帯や外力の影響 |
| 外側脱臼 | 膝が外側へ向けてずれたように見える | 外側側副靭帯の損傷や内側からの衝撃 |
| 内側脱臼 | 膝が内側へ向けてずれたように見える | 内側側副靭帯の損傷や外側からの衝撃 |
自宅での応急手当
膝脱臼が疑われる場合、自分で膝を強く引っ張ったり無理に動かしたりしないほうが無難です。患部を固定し、安静を保ち、可能であれば氷や冷却ジェルなどで痛みを和らげる方法が有効です。
また、足を少し高く保ち、血流が鬱滞しないように意識すると腫れを軽減できます。自己判断で激しく動かすと関節内部の傷を拡大させる恐れがあります。
時間経過によるリスク
膝脱臼を放置すると、血管や神経が圧迫されて二次的な障害が起こるリスクがあります。
時間が経過するほど周囲組織のダメージが進行しやすく、最終的な回復までに長期間を要する可能性が高くなります。
応急処置と早期受診が重要になる理由は、この二次損傷を最小限に抑えるためです。
初動対応の重要性
受傷直後に安静を保つか、あるいは無理に動かしてしまうかで回復の程度が変わることがあります。医療機関へ向かう前の段階で適切に膝を冷やし、足を動かさないようにすることが大切です。
やむを得ず移動する場合は添え木などで固定してから動かすと関節への負担が減らせます。
膝脱臼後の初期対応手順
- 患部を固定して安静を保つ
- 冷却ジェルや氷を使って患部を冷やす
- 心臓より高い位置に足を置き、腫れを軽減する
- できる限り早く医療機関を受診する
受診のタイミングと診断方法
膝脱臼が疑われるときは、痛みの強弱にかかわらず整形外科などの専門医を早めに訪れることが大切です。専門医による診断を受けることで、的確な治療方針を立てることができます。
医療機関では画像検査や身体所見を組み合わせ、膝の状態を多角的に確認します。
専門医を受診する目安
激しい痛みがある、膝の変形がはっきりしている、歩行が困難などの症状が少しでも見られる場合は受診を急ぎましょう。
痛みが軽度に感じられても、内部で靭帯や血管が損傷している可能性があります。放置すると回復に時間がかかるばかりか、慢性的な痛みに悩まされる恐れもあります。
画像検査と身体所見
膝脱臼の診断にはエックス線撮影やCT、MRIなど複数の画像検査を活用します。骨のずれ方だけでなく、靭帯や軟骨の損傷も確認し、最終的に診断を下します。
また医師が膝をわずかに動かしてゆるみやぐらつきを触診することもあります。痛みを伴う操作になりやすいため、医師が患者の状態を見極めて行います。
主な画像検査の特徴
| 検査方法 | 特徴 | 目的 |
|---|---|---|
| エックス線 | 骨の位置関係や骨折の有無を把握しやすい | 骨がどれだけずれているかを素早く確認できる |
| CT | 断面撮影によって骨や関節の形状を詳細に見る | エックス線では見えにくい部位の構造を把握する |
| MRI | 軟骨や靭帯など軟部組織の状態を把握する | 靭帯断裂や半月板損傷の有無を確認する |
診察時に確認するポイント
医師は患者の痛みの程度や怪我が発生した状況、既往歴などを詳しく尋ねながら診断を進めます。靭帯や血管、神経などの状態も確認して、必要に応じて追加検査を実施します。
また、痛み止めの処方やサポーターの使用を検討することも多いです。
誤診を防ぐために
時に膝脱臼が外見上そこまで大きな変形を伴わず、靭帯損傷や半月板損傷などと混同される場合があります。
誤診を防ぐためには患者側も「どのような動作で痛みを感じたか」「いつからどんな経過をたどっているか」を具体的に医師に伝えることが大切です。
膝脱臼の治療選択肢
膝脱臼の治療には大きく分けて保存療法と手術療法があり、いずれもリハビリテーションを組み合わせる場合が多いです。
医師は骨のずれ具合、靭帯や軟骨の損傷度、患者さんの年齢や生活スタイルなどを総合的に考慮し、治療方針を決めます。回復状況を観察しながら治療内容を微調整する場合もあります。
保存療法
膝脱臼の程度が比較的軽い場合や、靭帯に大きな損傷がない場合はギプス固定や装具による安定化を図り、自然回復を促します。
固定期間の目安は数週間から数カ月で、痛みが落ち着いてきた段階でリハビリテーションを始めます。固定による筋力低下を予防するため、周辺筋肉を軽く動かす練習を行うことも大切です。
保存療法で使用する装具の例
| 装具の名称 | 特徴 | 目的 |
|---|---|---|
| ハードタイプ固定具 | 金属や硬いプラスチックで作られる | 骨の位置を強固に固定し、動きを制限する |
| ソフトタイプ固定具 | 布や弾性素材を用いた軽量タイプ | 動きを適度に制限しながら日常生活を支える |
| 包帯固定 | 弾力のある包帯で簡易的に固定する | 応急的な処置や短期間の固定に使用する |
手術療法
靭帯の断裂や骨片のずれが大きい場合、手術によって構造を整復する必要があります。一般的には関節鏡を用いた手術や開放手術など、損傷部位の状態によって術式が選択されます。
術後もリハビリテーションが欠かせないため、手術のメリットとともにリハビリに要する期間や負担についても医師とよく相談しましょう。
リハビリテーション
治療全般を通してリハビリテーションが重要です。膝脱臼によって衰えた筋力や関節可動域を回復させるため、理学療法士や作業療法士と連携しながら段階的にメニューをこなします。
筋力トレーニングやストレッチ、バランス練習を中心に、再発を防ぐための正しい動き方を体得することが求められます。
治療経過のモニタリング
保存療法でも手術療法でも、定期的に専門医の診察を受けることが推奨されます。エックス線撮影やMRIなどで骨や靭帯の状態を再確認し、必要に応じて治療計画を修正します。
痛みの程度や可動域、歩行に問題がないかなどを総合的にチェックして、段階的に日常生活へ復帰できるよう準備を進めます。
日常生活での注意点とサポート方法
膝脱臼の治療後、あるいは予防の観点からも、日常生活での気遣いが大切です。再発を防ぐには膝への負担を軽減する習慣づくりや、適切な運動を行うことが重要になります。
さらにサポーターや装具を使った補助、栄養バランスに配慮した食生活なども視野に入れて管理することが望ましいです。
生活習慣の見直し
肥満体型は膝に負担をかけやすいため、適度な運動やバランスの良い食事で体重をコントロールすることが勧められます。
長時間の立ち仕事や座り仕事も膝に負荷がかかりやすいので、定期的にストレッチや歩行を挟むなどの工夫が求められます。
靴選びも重要なポイントで、かかとに余分な衝撃が加わらないようにクッション性のあるものを選ぶと安心です。
膝に優しい生活習慣チェック項目
| 項目 | 意識したい内容 |
|---|---|
| 体重コントロール | BMIの管理、食事バランスの見直し |
| 適度な運動 | ジョギングよりウォーキング、軽い筋トレ |
| 定期的な休憩 | 同じ姿勢を続けず、こまめに足を伸ばす |
| 正しい靴選び | クッション性、安定性のある靴を選択 |
| 栄養バランス | タンパク質やカルシウム、ビタミンDの摂取 |
サポーターや装具の活用
膝脱臼の治療後や不安があるときにはサポーターや装具が役立ちます。膝の側方動揺を抑えるタイプや、膝蓋骨を安定化させるタイプなど、多様な製品があります。
膝の不安定感を軽減し、日常動作を安心して行えるようにサポートしてくれます。ただし長時間の装着で筋力が衰える可能性もあるため、医師やリハビリ担当と相談しながら使い方を決めましょう。
運動やストレッチのポイント
リハビリテーションが一段落した後も、膝周辺の筋肉を強化し、柔軟性を高める運動を継続することが再発防止に役立ちます。
スクワットやレッグプレスなどで大腿四頭筋やハムストリングスを鍛え、ストレッチで関節の可動域を保つことが効果的です。痛みを感じたら無理をせず休息を挟み、適度な負荷で続けることが大切です。
- 太ももの前面を鍛える運動を週2~3回
- ふくらはぎをほぐすストレッチを毎日の習慣に
- 自重スクワットを行う場合は正しいフォームを意識
- ウォーキング時には膝の動きを確かめながら歩く
自己管理の心構え
治療やリハビリが終了しても、今後の生活の中で再び膝に大きな負荷がかかると再発する可能性があります。膝の違和感や痛みを早期に察知し、無理をしない心構えが大切です。
痛みが軽くても長引く場合は早めの受診を心掛け、膝脱臼の予防に努めましょう。
他の膝トラブルとの違い
膝脱臼以外にも膝にはさまざまなトラブルが生じます。中には似たような症状を示すものもありますが、治療内容や回復プロセスは異なることが多いです。
誤解や混同を防ぐためにも、他の代表的な膝のトラブルとの違いを把握しておきましょう。
半月板損傷や靭帯損傷との比較
半月板損傷や靭帯損傷は膝脱臼と同様に強い痛みが出る場合がありますが、骨の位置が明らかにずれる膝脱臼とは区別可能です。
エックス線撮影では骨のずれがないのに痛みが強い場合、軟部組織の損傷が疑われます。
半月板や靭帯は膝の安定性と動作を支える要であり、損傷度によっては手術が必要になる点は脱臼と共通する部分があります。
変形性膝関節症との違い
変形性膝関節症は長期間の負担や加齢などによって軟骨がすり減り、膝が変形していく疾患です。一方、膝脱臼は急性的な外傷であり、症状の発生様式が異なります。
変形性膝関節症は徐々に痛みやこわばりが進行するのに対し、膝脱臼は急激な痛みと変形が目立ちます。
膝の主なトラブルの特徴
| トラブル名 | 発生様式 | 痛みの特徴 | 共通点 |
|---|---|---|---|
| 膝脱臼 | 急激な衝撃や捻転 | 急な激痛と変形 | リハビリに筋力強化が大切 |
| 半月板損傷 | ひねりや衝撃による損傷 | ロッキングや鋭い痛み | MRIで状態を確認 |
| 前十字靭帯・後十字靭帯損傷 | 急停止や衝突など外力 | 動作時に不安定感が強い | スポーツ時にリスクが高い |
| 変形性膝関節症 | 長年の負担と加齢 | 初期は鈍い痛み、徐々に増す | 日常生活の改善が重要 |
外部衝撃と転倒リスクの相違点
膝脱臼は瞬間的に強い衝撃が加わるケースで起こりやすく、転倒や衝突の一瞬が大きな分岐点になります。
一方、膝周辺の慢性的な疾患は姿勢の崩れや運動不足が原因となり、少しずつ進行する場合が多いです。患者さんの年齢や生活習慣、運動歴などからトラブルの原因を推測することが必要です。
適切な受診先の考え方
膝のトラブルが疑われる場合、まず整形外科の受診が基本となります。スポーツ中の怪我であればスポーツ整形外科に特化した医療機関を選ぶのも方法のひとつです。
日常生活による慢性的な膝の痛みがある場合も、早めに専門医の診察を受けると正しい治療法を提案してもらえます。
よくある質問
膝脱臼に関する不安や疑問は多岐にわたります。治療期間や再発のリスク、サポーターの使用などについては患者さんから頻繁に問い合わせがあります。
症状や治療内容によって回答は変わることもありますが、参考になる一般的な情報をまとめました。
膝脱臼と再発リスク
膝脱臼を一度起こすと関節や靭帯にダメージが残り、再発しやすくなると言われています。
特に筋力が不十分な状態でスポーツに復帰したり、日常生活に支障が出ているのに無理を重ねたりすると、再脱臼の危険が高まります。
適切なリハビリと筋力強化、膝の状態に合った装具の使用などでリスクを下げることができます。
リハビリの期間
膝脱臼のリハビリ期間は程度や個人差によって変わります。保存療法なら数カ月、手術を行った場合は半年以上かかる場合もあります。
大切なのは医師や理学療法士の指導のもと、痛みや腫れの具合に応じたメニューをこなしながら段階的に運動量を増やすことです。
サポーターの使用期限
サポーターは膝の安定感を高めて日常生活やスポーツを支える反面、装着に頼りすぎると筋力維持が疎かになりやすい面があります。
医師やリハビリ担当と相談しながら外すタイミングを決めるとよいでしょう。外す時期の目安は痛みの軽減や可動域の回復、筋力評価などを考慮することが多いです。
病院の選び方
膝脱臼の治療では整形外科全般を扱う医療機関で診てもらうのが基本ですが、スポーツでの受傷が多い方や重度の靭帯損傷が疑われる方はスポーツ整形外科を標榜している施設を選ぶと専門的なリハビリや手術が受けやすいです。
通いやすさや治療実績、スタッフとの相性も含めて検討すると安心です。
以上
参考文献
HOWELLS, Nick R., et al. Acute knee dislocation: an evidence based approach to the management of the multiligament injured knee. Injury, 2011, 42.11: 1198-1204.
HARNER, Christopher D., et al. Surgical management of knee dislocations. JBJS, 2004, 86.2: 262-273.
MASLARIS, Alexander, et al. Management of knee dislocation prior to ligament reconstruction: what is the current evidence? Update of a universal treatment algorithm. European Journal of Orthopaedic Surgery & Traumatology, 2018, 28: 1001-1015.
PESKUN, Christopher J., et al. Diagnosis and management of knee dislocations. The Physician and Sportsmedicine, 2010, 38.4: 101-111.
GOTTLIEB, Michael; KOYFMAN, Alex; LONG, Brit. Evaluation and management of knee dislocation in the emergency department. The Journal of Emergency Medicine, 2020, 58.1: 34-42.
ERANKI, Vivek; BEGG, Collie; WALLACE, Brian. Outcomes of operatively treated acute knee dislocations. The open orthopaedics journal, 2010, 4: 22.
D’AMBROSI, Riccardo, et al. Management of the first episode of traumatic patellar dislocation: an international survey. Knee surgery, sports traumatology, arthroscopy, 2023, 31.6: 2257-2265.
ROBERTS, Daniel M.; STALLARD, Timothy C. Emergency department evaluation and treatment of knee and leg injuries. Emergency medicine clinics of North America, 2000, 18.1: 67-84.
Symptoms 症状から探す