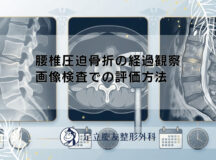股関節の横の痛みが続くときの症状と対策
歩き始めや階段の上り下り、あるいは夜寝ているときに、股関節の「横」にズキッとした痛みを感じることはありませんか。
その痛み、年のせいだと諦めたり、そのうち治るだろうと放置したりしていないでしょうか。股関節の横の痛みが続く場合、その裏には特定の原因が隠れている可能性があります。
この記事では、股関節の横に痛みが生じる理由から、考えられる代表的な疾患、ご自身でできる症状のチェック方法、そして今日から始められる具体的な対策までを詳しく解説します。
痛みの正体を知り、適切な対処法を見つけることで、つらい症状の緩和と快適な毎日を取り戻すための一歩を踏み出しましょう。
目次
股関節の横の痛み、その原因はどこにある?
股関節の横に痛みが生じると、多くの方が「骨に異常があるのでは?」と心配します。
しかし、原因は骨だけでなく、その周辺にある筋肉や腱、滑液包といった軟部組織にあることも少なくありません。なぜ股関節の、特に「横側」に痛みが集中しやすいのか。
その理由を理解するために、まずは股関節の基本的な構造と、痛みを引き起こす日常生活の要因について見ていきましょう。
股関節の構造と役割
股関節は、太ももの骨である大腿骨の先端にある球状の「大腿骨頭」が、骨盤の「寛骨臼」というお椀のようなソケットにはまり込む形をしています。
この構造は「球関節」と呼ばれ、脚を前後左右、そして回すといった非常に自由度の高い動きを可能にします。
関節の表面は滑らかな軟骨で覆われ、衝撃を吸収し、動きをスムーズにする役割を担っています。
さらに、股関節の周りは、強靭な靭帯や多くの筋肉によって支えられ、体重を支えながら歩く、立つ、座るといった基本的な動作を安定させています。
なぜ「横」が痛くなるのか
股関節の横側、出っ張った骨の部分を「大転子」と呼びます。この大転子には、お尻の筋肉(中殿筋や小殿筋など)の腱が付着しています。
これらの筋肉は、歩行時に骨盤を安定させるために極めて重要な働きをします。
歩くたびに、片足で体重を支える瞬間がありますが、このときに骨盤が傾かないように制御しているのが、まさにお尻の筋肉群なのです。
このため、歩行や階段の上り下りなどで繰り返し負担がかかりやすく、筋肉の腱や、その間にある滑液包(動きを滑らかにするための袋)に炎症が起こり、痛みとして感じられることが多くなります。
日常生活に潜む痛みの引き金
股関節の横の痛みは、特別な原因がなくても、日々の何気ない動作の積み重ねによって引き起こされることがあります。特に、股関節に偏った負担をかける習慣は、痛みのリスクを高めます。
例えば、いつも同じ側でバッグを持つ、足を組んで座る、片足に体重をかけて立つといった癖は、骨盤の歪みや左右の筋肉のアンバランスを生み、結果として股関節への負担を増大させます。
股関節への負担を増やす生活習慣
| 習慣・行動 | 股関節への影響 | 対策のポイント |
|---|---|---|
| 足を組んで座る | 骨盤の歪みを助長し、左右の筋肉バランスを崩す。 | 膝を揃えて深く座ることを意識する。 |
| 片足重心で立つ | 体重を支える側の股関節に過度な負担がかかる。 | 両足に均等に体重をかけるように立つ。 |
| 合わない靴を履く | 衝撃吸収が不十分で、歩行時の負担が増える。 | クッション性の高い靴を選ぶ。 |
年齢や性別による痛みの傾向
股関節の横の痛みは、幅広い年代で見られますが、特に中高年の女性に多い傾向があります。
女性は男性に比べて骨盤が広く、股関節にかかる力学的な負担が大きくなりやすいことが一因と考えられます。
また、加齢に伴う筋力の低下やホルモンバランスの変化も、腱や関節の柔軟性を低下させ、痛みを引き起こす要因となり得ます。
若い世代でも、スポーツによるオーバーユース(使いすぎ)や、長時間のデスクワークによる姿勢の悪化が原因で痛みを発症することがあります。
股関節の横の痛みを引き起こす代表的な疾患
「股関節の横が痛い」という症状が現れたとき、いくつかの疾患が考えられます。痛みの原因を正しく理解することは、適切な対策への第一歩です。
ここでは、股関節の横の痛みを引き起こす代表的な疾患について、その特徴と症状を解説します。自己判断は禁物ですが、知識として知っておくことで、専門家への相談がスムーズになります。
大転子部痛症候群(GTPS)とは
大転子部痛症候群(Greater Trochanteric Pain Syndrome, GTPS)は、股関節の横、大転子周辺に痛みが生じる状態の総称です。
以前は「転子部滑液包炎」と診断されることが多かったのですが、近年の研究で、痛みの原因は滑液包の炎症だけでなく、中殿筋や小殿筋といったお尻の筋肉の腱の損傷が大きく関わっていることが分かってきました。
歩行時や、痛い方を下にして横になったときに痛みが増すのが特徴です。
中殿筋・小殿筋腱付着部炎
中殿筋や小殿筋は、骨盤の安定に不可欠な筋肉で、その腱は大転子に付着しています。
長時間の歩行やランニング、階段の上り下りなどで繰り返し負担がかかることで、この腱の付着部に微細な損傷や炎症が起こり、痛みを生じます。
これが腱付着部炎です。安静にしていても鈍い痛みを感じることがあり、押すと強い痛み(圧痛)があるのが特徴です。
弾発股(だんぱつこ)
弾発股は、股関節を動かしたときに「ポキポキ」「ゴリゴリ」といった音や引っかかり感が生じる状態です。多くの場合、痛みは伴いませんが、炎症を伴うと痛みを感じるようになります。
股関節の外側で起こるタイプは、大転子の上を腸脛靭帯という硬い組織が乗り越えるときに起こり、これがGTPSの一因となることがあります。
変形性股関節症の可能性
変形性股関節症は、股関節の軟骨がすり減り、骨の変形が生じる疾患です。
初期症状としては、立ち上がりや歩き始めに股関節の付け根(鼠径部)に痛みを感じることが多いですが、進行するとお尻や太もも、そして股関節の横にも痛みが広がることがあります。
特に、関節の動きが悪くなる(可動域制限)や、歩行時に脚を引きずるような歩き方(跛行)が見られる場合は、この疾患を疑う必要があります。
腰椎由来の痛み(関連痛)
意外に思われるかもしれませんが、股関節の横の痛みは、腰に原因がある場合もあります。
腰の骨(腰椎)に問題があり、そこから出ている神経が圧迫されると、その神経が支配する領域であるお尻や股関節の横に痛みやしびれを感じることがあります。
これを「関連痛」と呼びます。腰痛を伴うこともあれば、腰の症状はほとんどなく、股関節周辺の痛みだけを感じることもあり、診断が難しい場合があります。
代表的な疾患の比較
| 疾患名 | 主な痛みの場所 | 特徴的な症状 |
|---|---|---|
| 大転子部痛症候群 | 股関節の横(大転子) | 横向きで寝ると痛い、押すと痛い |
| 変形性股関節症 | 股関節の付け根、お尻、横側 | 動き始めの痛み、関節の動きの制限 |
| 腰椎由来の関連痛 | お尻から太ももの外側 | しびれを伴うことがある、腰の動きで痛みが変化 |
その他の考えられる原因
上記の疾患以外にも、股関節の横の痛みを引き起こす原因はいくつか存在します。頻度は低いものの、見逃してはならない状態もあります。
- 大腿骨頭壊死症
- 関節リウマチ
- 疲労骨折
- 腫瘍
これらの疾患は、早期の専門的な診断と治療が重要です。痛みが長引く、急に悪化する、安静にしていても痛みが強いなどの場合は、速やかに医療機関を受診してください。
こんな症状に要注意!セルフチェックリスト
股関節の横の痛みが気になるとき、自分の症状を客観的に把握することは、原因を探り、適切な対処法を見つける上で非常に重要です。
どのようなときに、どのような痛みを感じるのか。痛み以外に気になるサインはないか。ここでは、ご自身で症状を確認するためのチェックリストを用意しました。
これらの項目を確認し、専門家に相談する際の参考にしてください。
痛みの種類と特徴
痛みの感じ方は人それぞれですが、その性質によって原因を推測する手がかりになることがあります。
「ズキズキ」「ジンジン」「ピリピリ」など、ご自身の痛みがどのタイプに近いか、またどのような状況でその痛みが出るかを確認してみましょう。
痛みの性質と関連する可能性
| 痛みの種類 | 考えられる状態 | 主な特徴 |
|---|---|---|
| 鋭い痛み(ズキッ) | 腱や筋肉の損傷、炎症 | 特定の動きをした瞬間に生じやすい。 |
| 鈍い痛み(ジンジン) | 慢性的な炎症、関節の変形 | 安静時にも持続することがある。 |
| しびれるような痛み | 神経の圧迫(腰椎由来など) | 電気が走るような感覚を伴うことがある。 |
痛み以外のサイン
痛みだけでなく、股関節周りに現れる他のサインにも注意を払いましょう。これらの症状は、痛みの原因を特定するための重要な情報となります。
- 股関節の動かしにくさ(靴下が履きにくい、爪が切りにくいなど)
- 歩行時の引っかかり感や音(ポキポキ、ゴリゴリ)
- 痛みのある側の脚の筋力低下
- 痛みのある場所の熱感や腫れ
どのような動きで痛みが出やすいか
日常生活の特定の動作で痛みが誘発される、あるいは強くなることが多いです。ご自身の生活を振り返り、どの動きが痛みの引き金になっているかを確認しましょう。
歩行時の痛み
歩き始めの数歩が特に痛むのか、それとも長く歩くと痛くなるのか。平坦な道は問題ないが、坂道や階段で痛むのか。
歩行中に体が左右に揺れるような歩き方になっていないかもチェックポイントです。中殿筋などの股関節外側の筋肉に問題があると、体重を支える際に痛みが出やすくなります。
立ち上がり時の痛み
椅子や床から立ち上がる瞬間に、股関節の横に鋭い痛みが走る場合は注意が必要です。これは、安静状態から急に股関節に負荷がかかることで起こります。
変形性股関節症の初期症状としてもよく見られます。
就寝時の痛み
夜、寝ているときに痛みで目が覚めることはありませんか。特に、痛い方を下にして横向きに寝ると、体重で大転子部が圧迫されて痛みが強くなることがあります。
これは大転子部痛症候群(GTPS)の典型的な症状の一つです。寝返りを打つときに痛みを感じることもあります。
専門医の受診を検討すべきサイン
セルフケアで様子を見ても良い場合もありますが、中には速やかに専門医の診察を受けるべきケースもあります。
以下の項目に一つでも当てはまる場合は、自己判断で放置せず、整形外科などを受診することを強く推奨します。
- 痛みがどんどん強くなっている
- 安静にしていても痛みが治まらない
- 痛みに加えて、しびれや熱感、腫れがある
- 転倒などのきっかけがあってから痛みが始まった
- 歩くのが困難になってきた
自宅でできる!股関節の横の痛みへの対策
専門医の診断を受けることはもちろん重要ですが、痛みが比較的軽い場合や、日常生活に大きな支障がない段階では、ご自身でできる対策もたくさんあります。
ここでは、痛みを悪化させず、症状を和らげるために今日から実践できるセルフケアの方法を紹介します。これらの対策は、治療と並行して行うことで、より高い効果を期待できます。
まずは安静とアイシング
痛みが強いとき、特に運動後などに熱っぽさを感じる場合は、炎症が起きているサインです。
このような急性期には、無理に動かしたり温めたりせず、まずは安静を保つことが第一です。
痛む部分にタオルで包んだ保冷剤などを15分から20分程度当てて冷やす(アイシング)と、炎症を抑え、痛みを和らげる助けになります。
ただし、冷やしすぎには注意し、1日に数回に分けて行いましょう。
日常生活での注意点
日々の無意識な動作が、股関節への負担を増やしている可能性があります。痛みを悪化させないために、座り方や立ち方、寝方などを見直してみましょう。
正しい座り方と立ち方
椅子に座るときは、深く腰掛け、背筋を伸ばしましょう。膝と股関節が同じくらいの高さになるように椅子の高さを調整すると、股関節への負担が軽減します。
足を組む癖は、骨盤の歪みを招くため避けるべきです。立ち上がるときは、勢いをつけず、テーブルなどに手をついてゆっくりと立ち上がるように心がけます。
痛みを悪化させない寝方
横向きで寝る場合は、痛い方を上にして、膝の間にクッションや枕を挟むと、股関節が安定し、痛みが和らぐことがあります。
仰向けで寝る場合は、膝の下にクッションを入れて膝を軽く曲げた状態にすると、股関節周りの筋肉の緊張がほぐれ、楽になることがあります。
良い姿勢と悪い姿勢の比較
| 動作 | 負担の少ない姿勢(推奨) | 負担の大きい姿勢(注意) |
|---|---|---|
| 座る | 深く腰掛け、背筋を伸ばす。膝は90度。 | 浅く腰掛け、背中が丸まる。足を組む。 |
| 立つ | 両足に均等に体重を乗せ、お腹を軽く引き締める。 | 片足に体重をかけ、腰が反っている。 |
| 寝る | 痛い方を上にし、膝の間にクッションを挟む。 | 痛い方を下にして寝る。 |
体重管理の重要性
股関節には、歩行時に体重の3倍から5倍もの負荷がかかると言われています。つまり、体重が1kg増えるだけで、股関節には3kgから5kgもの追加の負担がかかる計算になります。
体重を適正な範囲にコントロールすることは、股関節への負担を直接的に減らし、痛みの軽減と進行予防に非常に効果的です。
食事内容の見直しや、水泳や自転車など、股関節に負担の少ない運動を取り入れることを検討しましょう。
靴選びのポイント
毎日履く靴も、股関節の健康に大きく影響します。硬い地面からの衝撃は、足、膝、そして股関節へと伝わります。衝撃を和らげ、足を安定させる靴を選ぶことが大切です。
- クッション性が高く、衝撃を吸収してくれる靴底
- かかとをしっかりと支える構造の靴
- 足指が自由に動かせる、つま先にゆとりのあるデザイン
- ヒールは低く、安定感のあるもの
靴を選ぶ際は、夕方の足がむくんだ時間帯に、実際に試し履きをしてから購入することをお勧めします。
痛みの緩和を目指すストレッチとエクササイズ
痛みが少し落ち着いてきたら、股関節周りの筋肉の柔軟性を高め、筋力を強化するための運動を少しずつ取り入れていきましょう。
硬くなった筋肉をほぐし、股関節を支える力をつけることは、痛みの再発予防に繋がります。ただし、無理は禁物です。
痛みを感じる場合はすぐに中止し、専門家の指導のもとで行うことが最も安全です。
ストレッチの前に確認すること
運動を始める前には、いくつかの注意点があります。まず、痛みが強いときや、熱を持っているとき(急性期)は、ストレッチやエクササイズは避けましょう。
症状を悪化させる可能性があります。また、運動はリラックスした状態で行い、呼吸を止めないように意識します。
「痛いけれど気持ちいい」と感じる範囲で、ゆっくりと筋肉を伸ばすことがポイントです。
股関節周りの筋肉をほぐすストレッチ
股関節の横の痛みには、特にお尻周りの筋肉(中殿筋、大殿筋)や、太ももの外側にある腸脛靭帯の柔軟性が関係しています。これらの部位を重点的にストレッチしましょう。
お尻のストレッチ
椅子に座った状態で行える簡単なストレッチです。まず、椅子に深く腰掛け、背筋を伸ばします。次に、痛む側の足首を、反対側の膝の上に乗せます。
その状態から、ゆっくりと体を前に倒していきます。お尻の筋肉が伸びているのを感じながら、20秒から30秒キープします。これを数回繰り返します。
太ももの外側のストレッチ
立った状態で、壁などに手をついて体を支えます。痛む側の脚を、反対側の脚の後ろで交差させます。その体勢から、ゆっくりと体を脚を交差させた方向の横に倒していきます。
太ももの外側から腰にかけての部分が伸びるのを感じましょう。この姿勢も20秒から30秒キープし、数回繰り返します。
股関節を支える筋力トレーニング
股関節を安定させるためには、お尻の筋肉(特に中殿筋)を鍛えることが重要です。横向きに寝た状態で行うエクササイズが効果的です。
運動の種類と目的
| 運動名 | 主な目的 | 注意点 |
|---|---|---|
| お尻のストレッチ | 殿部筋群の柔軟性向上 | 背中が丸まらないように注意する。 |
| 太もも外側のストレッチ | 腸脛靭帯の柔軟性向上 | 体を倒しすぎず、心地よい伸びを感じる程度に。 |
| サイドレッグレイズ | 中殿筋の筋力強化 | 体を一直線に保ち、反動を使わない。 |
サイドレッグレイズは、まず横向きに寝て、下側の腕で頭を支えます。体は一直線になるように意識し、上側の脚をゆっくりと天井方向へ持ち上げます。
このとき、体が前後に倒れないように注意してください。10回程度を1セットとし、無理のない範囲で数セット行います。
運動を行う上での注意点
運動療法は正しく行えば非常に効果的ですが、やり方を間違えると逆効果になることもあります。
運動中に強い痛みを感じたり、運動後に痛みが悪化したりするようであれば、その運動は中止してください。
どのような運動が自分に適しているか分からない場合は、自己流で行わず、理学療法士などの専門家に相談し、適切な指導を受けることが大切です。
専門家による診断と治療法
セルフケアを続けても症状が改善しない場合や、痛みが強く日常生活に支障をきたしている場合は、専門家である医師の診断を仰ぐことが重要です。
医療機関では、問診や身体所見に加えて、さまざまな検査を用いて痛みの原因を正確に特定し、一人ひとりの状態に合わせた治療計画を立てます。
ここでは、整形外科などで行われる一般的な検査と治療法について解説します。
医療機関で行う検査
医師はまず、いつから、どこが、どのように痛むのかといった詳しい問診を行い、股関節の動きや圧痛点(押して痛い場所)などを確認する身体診察を行います。
この所見に基づいて、より詳細な情報を得るために画像検査などを実施します。
主な検査方法とその目的
| 検査方法 | 目的 | この検査で分かること |
|---|---|---|
| レントゲン(X線)検査 | 骨の状態を確認する | 骨の変形、骨折、関節の隙間の広さなど |
| 超音波(エコー)検査 | 筋肉や腱、滑液包の状態をリアルタイムで見る | 腱の損傷、滑液包の炎症、血流の状態など |
| MRI検査 | 軟部組織や骨の内部を詳細に描出する | 軟骨のすり減り、腱の断裂、骨頭壊死など |
保存療法のアプローチ
多くの場合、股関節の横の痛みは、手術をしない「保存療法」で治療を開始します。
保存療法には、痛みを和らげるための薬物療法、身体機能の改善を目指す物理療法や運動療法など、さまざまなアプローチがあります。
薬物療法
痛みの原因が炎症である場合、まずは炎症を抑えることが優先されます。非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)の飲み薬や貼り薬、塗り薬などが処方され、痛みと炎症の軽減を図ります。
物理療法
温熱療法や電気刺激療法、超音波療法などを用いて、血行を促進し、筋肉の緊張を和らげ、痛みを軽減させる治療法です。
リハビリテーションの一環として、運動療法と組み合わせて行われることが多くあります。
注射療法
痛みが強い場合や、他の保存療法で十分な効果が得られない場合には、注射療法を検討します。
痛みの原因となっている部位(滑液包や腱の周辺)に、局所麻酔薬やステロイドを注射することで、強力に炎症と痛みを抑える効果が期待できます。
手術療法が選択される場合
保存療法を数ヶ月間続けても症状の改善が見られない場合や、腱の断裂が大きい場合、あるいは変形性股関節症が進行して日常生活に著しい支障が出ている場合には、手術療法が選択肢となります。
手術には、内視鏡(関節鏡)を用いて損傷した組織を修復する方法や、変形した関節を人工の関節に置き換える人工股関節置換術などがあります。
手術を行うかどうかは、年齢、活動レベル、症状の程度などを総合的に判断して決定します。
リハビリテーションの役割
保存療法、手術療法のいずれにおいても、リハビリテーションは治療の重要な柱です。
理学療法士などの専門家が、個々の状態に合わせて、股関節の可動域を改善する訓練や、筋力を強化する運動プログラムを作成し、指導します。
正しい体の使い方を再学習し、股関節への負担を減らすことで、痛みの根本的な解決と再発予防を目指します。
保存療法の選択肢
| 治療法 | 内容 | 期待される効果 |
|---|---|---|
| 薬物療法 | 消炎鎮痛薬(内服、外用)の使用 | 痛みと炎症の軽減 |
| 物理療法 | 温熱、電気刺激など | 血行促進、疼痛緩和 |
| 運動療法 | ストレッチ、筋力トレーニング | 柔軟性・筋力の向上、機能改善 |
よくある質問
股関節の横の痛みに関して、多くの方が抱く疑問についてお答えします。ただし、ここでの回答は一般的なものであり、個々の症状については必ず専門医にご相談ください。
Q. 痛みはどれくらいで治まりますか?
A. 痛みが治まるまでの期間は、原因や症状の程度、そして治療への取り組み方によって大きく異なります。
使いすぎによる一時的な炎症であれば、安静とセルフケアで数週間以内に改善することが多いです。しかし、腱の損傷や変形性股関節症などが背景にある場合は、治療に数ヶ月以上を要することもあります。
大切なのは、焦らずに専門家の指導のもとで治療を継続することです。痛みが長引く場合は、原因の再評価や治療法の見直しが必要になることもあります。
Q. 温めるのと冷やすのはどちらが良いですか?
A. 温める(温熱療法)か冷やす(冷却療法)かは、痛みの時期や状態によって使い分けるのが基本です。
急な痛みや、運動後で熱感があるような「急性期」には、炎症を抑えるために冷やすのが適しています。
一方、慢性的な鈍い痛みや、筋肉のこわばりを感じる「慢性期」には、血行を促進して筋肉をリラックスさせるために温めるのが効果的です。
温める?冷やす?判断の目安
| 状況 | 推奨される対応 | 目的 |
|---|---|---|
| 急な痛み、腫れ、熱感がある | 冷やす(アイシング) | 炎症を抑える、痛みを鎮める |
| 慢性的な鈍い痛み、こわばり | 温める(入浴、ホットパック) | 血行促進、筋肉をほぐす |
Q. サポーターは効果がありますか?
A. 股関節用のサポーターは、関節の安定性を高め、筋肉の働きを補助することで、痛みを一時的に和らげる効果が期待できます。
特に、歩行時や運動時に不安を感じる場合には、安心感にも繋がります。ただし、サポーターはあくまで補助的なものであり、根本的な原因を治療するものではありません。
長期間の使用は、かえって自身の筋力を低下させてしまう可能性も指摘されています。使用については、医師や理学療法士に相談し、適切なタイプを選び、必要な場面でのみ使用するようにしましょう。
Q. どのような病院を受診すれば良いですか?
A. 股関節の痛みや足の症状を専門とする「整形外科」を受診するのが一般的です。
整形外科では、骨、関節、筋肉、神経といった運動器の専門家が、問診、診察、そして必要な検査を通じて正確な診断を行います。
特に、股関節疾患を専門とする医師や、スポーツ整形外科の経験が豊富な医師がいる医療機関を選ぶと、より専門的な治療やアドバイスを受けられる可能性があります。
まずはかかりつけの整形外科に相談し、必要に応じて専門の医療機関を紹介してもらうのも良いでしょう。
以上
参考文献
WILLIAMS, Bryan S.; COHEN, Steven P. Greater trochanteric pain syndrome: a review of anatomy, diagnosis and treatment. Anesthesia & Analgesia, 2009, 108.5: 1662-1670.
KLAUSER, Andrea S., et al. Greater trochanteric pain syndrome. In: Seminars in musculoskeletal radiology. Thieme Medical Publishers, 2013. p. 043-048.
REID, Diane. The management of greater trochanteric pain syndrome: a systematic literature review. Journal of orthopaedics, 2016, 13.1: 15-28.
TORRES, Ana; FERNÁNDEZ-FAIREN, Mariano; SUEIRO-FERNÁNDEZ, José. Greater trochanteric pain syndrome and gluteus medius and minimus tendinosis: nonsurgical treatment. Pain Management, 2018, 8.1: 45-55.
CHOWDHURY, Rajat, et al. Imaging and management of greater trochanteric pain syndrome. Postgraduate medical journal, 2014, 90.1068: 576-581.
LEQUESNE, M., et al. Gluteal tendinopathy in refractory greater trochanter pain syndrome: diagnostic value of two clinical tests. Arthritis Care & Research, 2008, 59.2: 241-246.
MULLIGAN, Edward P.; MIDDLETON, Emily F.; BRUNETTE, Meredith. Evaluation and management of greater trochanter pain syndrome. Physical Therapy in Sport, 2015, 16.3: 205-214.
GRIMALDI, Alison, et al. Gluteal tendinopathy: a review of mechanisms, assessment and management. Sports Medicine, 2015, 45.8: 1107-1119.
SPEERS, Christopher JB; BHOGAL, Gurjit S. Greater trochanteric pain syndrome: a review of diagnosis and management in general practice. The British Journal of General Practice, 2017, 67.663: 479.
GUEMARA, Romain; NISSEN, Michael John. The Greater Trochanteric Pain Syndrome: Clinical Presentation, Diagnosis, and Management. Current Treatment Options in Rheumatology, 2023, 9.4: 192-203.
Symptoms 症状から探す