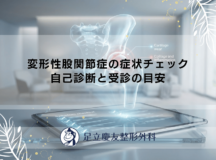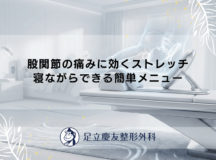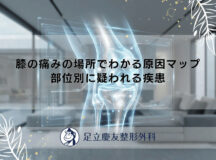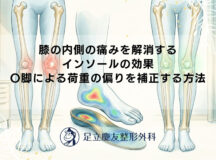膝をぶつけた後の腫れと痛み – 経過観察のポイント
タンスの角に膝をぶつけた、スポーツ中に転倒したなど、日常生活や運動中に膝を強く打ってしまう経験は誰にでもあるでしょう。
打った直後からズキズキと痛み出し、時間とともに腫れてくると、「このまま様子を見ていて大丈夫だろうか」「何か重大な怪我につながっていないか」と不安になるものです。
多くの場合、膝の打撲は適切な応急処置と安静で回復に向かいます。しかし、中には骨折や靭帯損傷といった専門的な治療を必要とするケースも隠れています。
この記事では、膝を打った後の痛みと腫れの原因から、ご自身でできる応急処置、経過を観察する上での重要な視点、そして医療機関を受診すべき危険なサインまでを詳しく解説します。
目次
膝を打った直後に確認すべきこと
膝を強く打った直後は、気が動転していることもあり、冷静な判断が難しいかもしれません。しかし、まず落ち着いて膝の状態を確認することが、その後の適切な対応につながります。
痛みや腫れだけでなく、膝が正常に機能するかどうかを慎重に見極めましょう。
体重をかけられるか
まず、打った方の足に体重をかけられるかどうかを試してください。
激しい痛みで全く立てない、体重をかけると膝が崩れるような感覚がある場合は、単なる打撲ではなく骨折や靭帯の深刻な損傷の可能性があります。
無理に立とうとせず、座るか横になるなど、安静な姿勢をとりましょう。少し痛みはあっても、ゆっくりと体重をかけて歩けるようであれば、重篤な怪我の可能性は低いと考えられます。
歩行時のチェックポイント
| 状態 | 考えられること | 対応 |
|---|---|---|
| 全く立てない、激痛が走る | 骨折、重度の靭帯損傷 | 動かずに安静にし、救急車を呼ぶか周囲に助けを求める |
| 痛みはあるが、なんとか歩ける | 打撲、軽度の靭帯・半月板損傷 | 無理せず活動を中止し、応急処置を行う |
| 痛みは軽微で、普通に歩ける | 軽度の打撲 | 念のため経過を観察し、必要に応じて応急処置を行う |
膝の曲げ伸ばしはできるか
次に、膝の曲げ伸ばしがスムーズにできるかを確認します。座った状態や寝た状態で、ゆっくりと膝を曲げたり伸ばしたりしてみてください。
このとき、「ゴリゴリ」という音がしたり、何かが引っかかるような感覚があったり、特定の角度で激痛が走ったりする場合は注意が必要です。
また、膝が固まってしまって動かせる範囲が極端に狭くなっている(これを「可動域制限」と呼びます)場合も、関節内部に問題が起きているサインかもしれません。
目に見える異常はないか
膝を注意深く観察し、見た目に異常がないかを確認することも大切です。
打撲による腫れは一般的ですが、短時間でパンパンに腫れ上がる、明らかに形が変形している、お皿(膝蓋骨)の位置がずれているように見えるといった場合は、骨折や脱臼を疑います。
皮膚の色も確認しましょう。打撲による内出血で青紫色になることはよくありますが、その範囲が広すぎたり、皮膚が不自然にへこんでいたりしないかを見てください。
なぜ膝を打つと腫れて痛むのか
膝を打ったときに生じる「痛み」と「腫れ」は、体が傷ついたことに対する正常な反応です。
なぜこのような症状が現れるのか、その背景にある体の働きを知ることで、ご自身の状態への理解が深まります。ここでは、打撲後に起こる体内の変化を解説します。
打撲による組織の損傷
打撲とは、外部からの強い衝撃によって、皮膚やその下にある皮下脂肪、筋肉、血管などの軟部組織が損傷することです。
特に膝は、皮膚のすぐ下に骨(大腿骨、脛骨、膝蓋骨)があるため、衝撃が直接骨や関節に伝わりやすい部位です。
この衝撃により、細かい血管が破れて出血したり、筋肉の繊維が傷ついたりすることで、痛みを感じる神経が刺激され、ズキズキとした痛みが生じます。
炎症反応の発生
体が損傷を受けると、その部分を修復しようとする「炎症反応」が起こります。これは、体を守るための大切な防御反応です。
損傷した組織からは、痛みを引き起こす物質(発痛物質)や、血管を広げる物質が放出されます。
血管が広がると、傷ついた場所の修復に必要な細胞や栄養素を運ぶために、血液の流れ(血流)が増加します。この血流の増加が、患部の熱感や赤みの原因となります。
炎症の主な兆候
| 兆候 | 原因 |
|---|---|
| 痛み(疼痛) | 発痛物質による神経の刺激 |
| 腫れ(腫脹) | 血管から漏れ出た血液成分(血漿) |
| 熱感 | 血流の増加 |
| 赤み(発赤) | 毛細血管の拡張と血流の増加 |
関節内の出血(関節内血腫)
膝関節は、関節包という袋に覆われています。打撲の衝撃が強く、関節内部の組織や骨まで損傷が及ぶと、この関節包の中で出血が起こることがあります。
関節内に血液が溜まった状態を「関節内血腫」と呼び、これが強い腫れと痛みを引き起こします。膝がパンパンに腫れて曲げ伸ばしが困難になる場合は、この関節内血腫の可能性があります。
溜まった血液が膝の動きを妨げ、強い圧迫感や激しい痛みの原因となるのです。
自宅でできる応急処置「RICE処置」の基本
膝を打った直後の適切な応急処置は、その後の回復を大きく左右します。医療現場で基本とされるのが「RICE処置」です。
これは、Rest(安静)、Icing(冷却)、Compression(圧迫)、Elevation(挙上)の4つの処置の頭文字をとったものです。
これらの処置を正しく行うことで、痛みや腫れを最小限に抑える効果が期待できます。
安静(Rest)
最も重要なのが安静です。膝を打ったら、すぐに運動や作業を中止し、体重をかけないようにしましょう。
歩き回ったり、無理に膝を動かしたりすると、損傷が悪化し、内出血や腫れがひどくなる可能性があります。椅子に座るか、可能であれば横になって、膝をリラックスさせてください。
冷却(Icing)
次に、患部を冷やします。冷却は、血管を収縮させて内出血を抑え、腫れや痛みを和らげる効果があります。
氷をビニール袋に入れてタオルで包んだものや、市販のアイスパックなどを使い、痛みや熱感が最も強い部分に当ててください。
直接氷を皮膚に当てると凍傷になる恐れがあるため、必ずタオルなどを一枚挟むようにしましょう。
冷却のポイント
| 項目 | 内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| 時間 | 1回15〜20分が目安 | 長時間冷やしすぎない |
| 頻度 | 48時間程度は1〜2時間おきに繰り返す | 感覚がなくなったら一度中断する |
| 方法 | 氷嚢やアイスパックをタオルで包む | 凍傷を防ぐため直接当てない |
圧迫(Compression)
患部を適度に圧迫することも、内出血や腫れを抑えるのに有効です。弾性包帯やサポーター、テーピングなどを使って、腫れている部分を中心に少し圧力をかけるように巻きます。
ただし、強く巻きすぎると血行が悪くなり、逆効果になることもあります。圧迫した部分の先(足先など)がしびれたり、皮膚の色が変色したりした場合は、すぐに緩めてください。
挙上(Elevation)
最後に、患部を心臓より高い位置に保ちます。横になった状態で、膝の下にクッションや座布団、丸めたタオルなどを入れて、足を高く上げてください。
このことにより、重力を利用して患部に血液や体液が溜まるのを防ぎ、腫れの軽減を助けます。
座っている場合でも、足を別の椅子に乗せるなどして、できるだけ高い位置に保つよう心がけましょう。
経過観察中の注意点とセルフケア
応急処置を行った後は、数日間、症状の変化を注意深く観察することが大切です。多くの打撲は時間とともに回復に向かいますが、過ごし方によっては回復を遅らせてしまうこともあります。
ここでは、回復を促すためのセルフケアと、注意すべき点について解説します。
急性期(受傷後〜48時間)の過ごし方
受傷後2〜3日間は「急性期」と呼ばれ、炎症が最も強い時期です。この期間は、RICE処置を継続することが基本となります。
特に、痛みや腫れが強い間は、無理に動かず安静を心がけてください。入浴はシャワー程度にとどめ、湯船で体を温めることは避けましょう。
体を温めると血行が良くなり、炎症や腫れを悪化させてしまう可能性があります。同様に、アルコールの摂取も血管を拡張させる作用があるため、控えるのが賢明です。
急性期に避けるべきこと
- 患部を温めること(長時間の入浴など)
- アルコールの摂取
- マッサージ
- 無理な運動やストレッチ
回復期(受傷後3日目以降)の過ごし方
受傷から3日ほど経過し、ズキズキとした強い痛みや熱感が和らいできたら、「回復期」に入ります。この時期からは、少しずつ膝を動かしていくことが回復を促します。
血行を良くして硬くなった筋肉をほぐすために、今度は逆に温めるケア(温熱療法)が有効になる場合があります。
ぬるめのお湯にゆっくり浸かったり、蒸しタオルで膝を温めたりするのも良いでしょう。
ただし、温めて痛みがぶり返すようなら、まだ炎症が残っているサインなので、すぐに中止して冷却に戻してください。
温熱療法への切り替えタイミング
| 症状 | 推奨されるケア |
|---|---|
| 強い痛み、熱感、腫れがある(急性期) | 冷却(アイシング) |
| 痛みが和らぎ、腫れが引いてきた(回復期) | 温熱療法(温める) |
| 温めると痛みが強くなる | 冷却に戻す |
痛みのない範囲での運動
回復期に入ったら、痛みのない範囲で意識的に膝を動かすことが大切です。
長時間動かさないでいると、関節が固まってしまい(これを「拘縮」と言います)、その後の動きに支障が出ることがあります。
まずは体重をかけずに、座ったままでゆっくりと膝を曲げ伸ばしする運動から始めましょう。痛みを感じる場合は無理をせず、動かせる範囲で少しずつ可動域を広げていくことを目指してください。
この症状が出たら要注意!医療機関を受診する目安
ほとんどの膝の打撲はセルフケアで改善しますが、中には専門的な診断と治療が必要な重大な怪我が隠れていることもあります。
様子を見ていて良いケースと、すぐに整形外科などを受診すべきケースを見分けることが重要です。以下に示すようなサインが見られる場合は、自己判断で済ませず、医療機関に相談してください。
痛みの特徴で判断する
痛みの強さや種類は、受診を判断する上での重要な手がかりです。
安静にしていてもズキズキとした痛みが続く、夜も眠れないほどの激しい痛みがある、といった場合は、単なる打撲以上の損傷が考えられます。
また、打撲してから数日経っても痛みが全く引かない、あるいはむしろ強くなっている場合も、炎症が続いていたり、別の問題が起きていたりする可能性を示唆します。
受診を強く推奨する痛みのサイン
| 痛みの種類 | 考えられる状態 |
|---|---|
| 安静時でも続く激しい痛み | 骨折、重度の靭帯損傷、関節内血腫 |
| 日に日に痛みが強くなる | 炎症の悪化、感染症の併発(まれ) |
| 膝の内部からの痛み、特定の動作での鋭い痛み | 半月板損傷、軟骨損傷 |
腫れや見た目の異常で判断する
見た目の変化も重要な判断材料です。打撲した直後からみるみるうちに膝がパンパンに腫れ上がり、左右の足で太さが全く違う場合は、関節内での大量の出血が疑われます。
また、膝のお皿が割れているように見える、明らかに膝が変な方向に曲がっているなど、形に異常がある場合は骨折や脱臼の可能性が非常に高いです。
このような場合は、ためらわずに医療機関を受診してください。
膝の機能で判断する
膝の機能に異常がある場合も、受診が必要です。
「体重をかけると膝がガクッと崩れる」「膝が不安定で力が入らない」といった症状は、膝の安定性を保つ靭帯が損傷している典型的なサインです。
また、「膝の曲げ伸ばしの際に何かが引っかかって、それ以上動かせなくなる(ロッキング)」という症状は、半月板損傷に特徴的です。
これらの機能的な問題は、放置すると日常生活に大きな支障をきたすため、専門家による正確な診断が求められます。
医療機関で行われる検査と診断
「この症状は病院に行くべきかもしれない」と判断した場合、主に整形外科を受診することになります。
医療機関では、医師が専門的な知識と検査機器を用いて、膝の状態を正確に評価し、適切な診断を下します。ここでは、整形外科で行われる一般的な診察や検査の流れを紹介します。
問診と視診・触診
まず、医師による問診が行われます。
「いつ、どこで、どのように膝を打ったのか」「どのような痛みがあるのか」「どのような時に痛みが強くなるのか」などを詳しく伝えてください。
正確な情報が、診断の大きな助けとなります。
その後、医師が膝を直接見て、腫れや変形、皮膚の色などを確認(視診)し、手で触れて圧痛点(押して痛い場所)や熱感、関節の緩みなどを評価(触診)します。
医師に伝えるべき情報
- 受傷した日時と状況
- 痛みの場所、強さ、種類(ズキズキ、ジンジンなど)
- 歩けるか、膝の曲げ伸ばしはできるか
- 過去の膝の怪我や病気の有無
- 現在行っているスポーツや仕事の内容
画像検査
問診や診察の結果、骨や関節内部の状態を詳しく調べる必要があると判断された場合、画像検査を行います。最も一般的に行われるのがレントゲン(X線)検査です。
レントゲン検査は、骨折や脱臼の有無を確認するのに非常に有効です。
骨に異常が見られない場合でも、靭帯や半月板、軟骨などの損傷が疑われるときには、さらに詳しい検査としてMRI検査や超音波(エコー)検査が行われることがあります。
主な画像検査とその目的
| 検査方法 | 主な目的 | 特徴 |
|---|---|---|
| レントゲン検査 | 骨折、脱臼、骨の変形の確認 | 基本的な検査で、迅速に骨の状態を評価できる |
| MRI検査 | 靭帯、半月板、軟骨、筋肉などの軟部組織の評価 | 軟部組織の損傷を詳細に描出できるが、検査に時間がかかる |
| 超音波(エコー)検査 | 軟部組織の評価、関節内血腫の確認 | 手軽に関節の状態をリアルタイムで観察できる |
関節穿刺(かんせつせんし)
膝の腫れが非常に強く、関節内血腫が強く疑われる場合には、関節穿刺が行われることがあります。これは、注射器で関節内に溜まった血液や液体を抜き取る処置です。
抜き取った液体の性状(血液か、黄色い関節液かなど)を確認することで診断の助けになるだけでなく、関節内の圧力を下げることで、痛みを和らげる治療的な効果もあります。
膝の打撲で考えられる怪我の種類
「膝の打撲」と一言で言っても、その衝撃によって引き起こされる可能性のある怪我は様々です。軽度の打ち身から、手術が必要となるような重度の損傷まで多岐にわたります。
ご自身の症状がどの程度のものなのかを理解するために、打撲をきっかけに起こりうる代表的な怪我の種類を知っておきましょう。
単純な打撲(打ち身)
最も多いのが、骨や靭帯、半月板には大きな損傷がなく、皮膚や筋肉などの軟部組織だけが傷ついた状態です。
いわゆる「打ち身」と呼ばれるもので、痛みや腫れ、内出血は見られますが、歩行や膝の曲げ伸ばしは可能です。通常、RICE処置と安静によって1〜2週間程度で自然に回復します。
靭帯損傷
膝関節の安定性を保っている靭帯が、強い衝撃によって伸びたり、部分的に切れたり、完全に断裂したりする怪我です。
膝の前後方向の安定性を担う前十字靭帯や後十字靭帯、左右の安定性を担う内側側副靭帯や外側側副靭帯などがあります。
損傷すると、「膝がグラグラする」「力が抜ける」といった不安定感が生じるのが特徴です。
半月板損傷
膝関節の中でクッションの役割を果たしているC型をした軟骨組織「半月板」が、強い衝撃によって傷ついたり、断裂したりする怪我です。
膝の曲げ伸ばしの際に引っかかり感や痛みを感じたり、急に膝が動かなくなる「ロッキング」という症状が起こったりすることがあります。
打撲で起こりうる主な怪我
| 怪我の種類 | 特徴的な症状 | 注意すべきサイン |
|---|---|---|
| 単純な打撲 | 痛み、腫れ、内出血 | 症状が徐々に軽快する |
| 靭帯損傷 | 膝の不安定感(グラつき)、痛み、腫れ | 体重をかけると膝が崩れる |
| 半月板損傷 | 引っかかり感、曲げ伸ばし時の痛み、ロッキング | 特定の角度で激痛が走る |
| 骨折 | 激しい痛み、強い腫れ、変形、歩行不能 | 見た目に明らかな異常がある |
骨折
強い衝撃が加わった場合、膝関節を構成する骨が折れてしまうことがあります。
膝のお皿である膝蓋骨(しつがいこつ)の骨折や、すねの骨の上部である脛骨高原(けいこつこうげん)骨折などが代表的です。
骨折した場合は、激しい痛みと腫れ、明らかな変形、起立や歩行が不可能になるなど、重篤な症状が現れます。この場合は、直ちに医療機関での治療が必要です。
膝の打撲に関するよくある質問
最後に、膝を打った方からよく寄せられる質問とその回答をまとめました。セルフケアや回復過程での疑問解消の参考にしてください。
Q. 湿布は温湿布と冷湿布のどちらが良いですか?
A. 受傷直後の炎症が強い時期(急性期:〜48時間程度)は、血管を収縮させて炎症を抑える効果のある「冷湿布」を使用してください。
ズキズキする痛みや熱感が和らいできた回復期には、血行を促進して回復を助ける「温湿布」に切り替えるのが一般的です。
ただし、温めて痛みが強くなるようであれば、冷湿布に戻しましょう。
Q. お風呂で温めても良いですか?
A. 受傷後2〜3日の急性期は、温めると炎症が悪化する可能性があるため、長時間の入浴は避け、シャワー程度にするのが望ましいです。
痛みや腫れが引いてきた回復期であれば、ぬるめのお湯にゆっくり浸かることで血行が改善し、筋肉の緊張が和らぐため、回復を助ける効果が期待できます。
Q. 痛みが引いても運動は控えるべきですか?
A. 痛みが引いたからといって、すぐに元のレベルの運動に復帰するのは危険です。損傷した組織が完全に修復されるには時間がかかります。
まずはウォーキングや軽いジョギングなど、負荷の低い運動から再開し、膝に違和感や痛みが出ないかを確認しながら、段階的に運動強度を上げていくことが大切です。
本格的なスポーツへの復帰時期は、自己判断せず、医師に相談することをお勧めします。
Q. サポーターは着けた方が良いですか?
A. サポーターには、膝を保温する効果、関節を安定させる効果、動きをサポートする効果などがあります。
痛みが残っている時期や、運動を再開する際の不安感がある場合には、サポーターの着用は有効です。ただし、サポーターに頼りすぎると膝周りの筋力が低下する可能性もあります。
日常生活では外し、運動時や負担がかかる場面で補助的に使用するなど、目的に応じて使い分けるのが良いでしょう。どのようなサポーターが適しているかについては、医師や理学療法士に相談してください。
以上
参考文献
BUNT, Christopher W.; JONAS, Christopher E.; CHANG, Jennifer G. Knee pain in adults and adolescents: the initial evaluation. American family physician, 2018, 98.9: 576-585.
HUNT, P. A.; GREAVES, Ian. Presentation, examination, investigation and early treatment of acute knee injuries. Trauma, 2004, 6.1: 53-66.
GUPTE, Chinmay; ST MART, Jean-Pierre. The acute swollen knee: diagnosis and management. Journal of the Royal Society of Medicine, 2013, 106.7: 259-268.
JACKSON, Jeffrey L.; O'MALLEY, Patrick G.; KROENKE, Kurt. Evaluation of acute knee pain in primary care. Annals of internal medicine, 2003, 139.7: 575-588.
LANDEWÉ, R. B. M., et al. EULAR/EFORT recommendations for the diagnosis and initial management of patients with acute or recent onset swelling of the knee. Annals of the rheumatic diseases, 2010, 69.1: 12-19.
DUONG, Vicky, et al. Evaluation and treatment of knee pain: a review. Jama, 2023, 330.16: 1568-1580.
HSU, Joseph R., et al. Clinical practice guidelines for pain management in acute musculoskeletal injury. Journal of orthopaedic trauma, 2019, 33.5: e158-e182.
HOWELLS, Nick R., et al. Acute knee dislocation: an evidence based approach to the management of the multiligament injured knee. Injury, 2011, 42.11: 1198-1204.
KARY, Joel M. Diagnosis and management of quadriceps strains and contusions. Current reviews in musculoskeletal medicine, 2010, 3.1: 26-31.
PATEL, Dilip R.; VILLALOBOS, Ana. Evaluation and management of knee pain in young athletes: overuse injuries of the knee. Translational pediatrics, 2017, 6.3: 190.
Symptoms 症状から探す