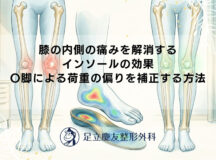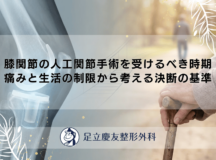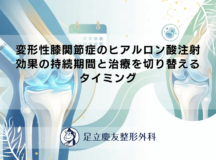腰痛で整形外科を受診する目安|診断と検査の流れ
多くの人が経験する腰痛。一時的なものだろうと様子を見ているうちに、痛みが長引いたり、悪化したりすることもあります。
「この腰痛、病院に行くべき?」「整形外科ではどんなことをするの?」といった疑問や不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。
この記事では、腰痛で整形外科を受診する具体的な目安、そして病院で行う診断や検査の基本的な流れを詳しく解説します。
危険な腰痛を見分けるサインや、診察時に医師へ的確に症状を伝えるための準備についても触れていきます。ご自身の腰痛と向き合い、適切な一歩を踏み出すための参考にしてください。
目次
こんな腰痛は要注意!すぐに整形外科を受診すべき危険なサイン
ほとんどの腰痛は、筋肉の疲労などが原因で、安静にすることで自然と和らいでいきます。しかし、中には重大な病気が隠れており、早急な対応が必要なケースも存在します。
ここでは、見逃してはいけない「危険な腰痛」のサインを具体的に解説します。
これらの症状に当てはまる場合は、自己判断で様子を見ずに、速やかに整形外科を受診してください。
安静にしていても痛みが続く、夜間に痛みが強くなる
体を動かしたときだけでなく、楽な姿勢で安静にしていても腰の痛みが軽減しない、あるいは横になっていても痛くて眠れない、夜中に痛みで目が覚める、といった症状は注意が必要です。
通常の筋肉性の腰痛は、安静にすることで痛みが和らぐことが多いです。安静時にも痛みが続く場合は、腰椎の感染症や腫瘍など、筋肉以外の原因を考える必要があります。
足のしびれや麻痺、力が入らないといった症状がある
腰痛に加えて、お尻から太ももの裏、すね、足先にかけて広がるしびれや痛みがある場合、神経が圧迫されている可能性があります。
特に、「足に力が入らない」「スリッパが脱げやすい」「つま先立ちができない」といった筋力の低下を伴う症状は、神経障害が進行しているサインかもしれません。
これらの症状は、腰部脊柱管狭窄症や腰椎椎間板ヘルニアなどで見られます。
排尿や排便の異常を伴う
腰痛とともに、「尿が出にくい」「頻尿になった」「残尿感がある」「便秘がひどくなった」「便失禁や尿失禁がある」といった排尿・排便に関する異常が現れた場合、緊急性の高い状態と考えられます。
これは、馬尾(ばび)神経と呼ばれる脊髄の下部にある神経の束が強く圧迫されることで起こる「馬尾症候群」の可能性があります。速やかな医療機関の受診が重要です。
原因不明の発熱や体重減少が見られる
腰痛に加えて、37.5度以上の発熱が続く、安静にしていても汗をかく、ここ数ヶ月で急に体重が減った、といった全身の症状が見られる場合も注意が必要です。
これらの症状は、脊椎の感染症(化膿性脊椎炎)や、がんの骨転移など、全身的な病気の一症状として腰痛が現れている可能性を示唆します。
医師による詳しい検査で原因を特定することが大切です。
危険な腰痛のサインと関連疾患の可能性
| 症状 | 考えられる原因・疾患 | 対応 |
|---|---|---|
| 安静時痛・夜間痛 | 脊椎の感染症、腫瘍など | 早急に整形外科を受診 |
| 足の麻痺・筋力低下 | 腰椎椎間板ヘルニア、腰部脊柱管狭窄症など | 早めに整形外科を受診 |
| 排尿・排便障害 | 馬尾症候群など | 緊急で医療機関を受診 |
日常生活に支障が出る腰痛|受診を検討するタイミング
先に述べたような危険なサインはなくても、痛みが続くことで生活の質(QOL)が低下している場合は、我慢せずに整形外科の受診を考えましょう。
ここでは、日常生活への影響を基準に、受診を検討すべき具体的な状況を説明します。ご自身の状態と照らし合わせてみてください。
痛みが1週間以上続いている
ぎっくり腰のような急性の腰痛でも、通常は数日から1週間程度で徐々に痛みは和らいでいきます。
もし、痛みが1週間以上たっても改善する気配がない、あるいは徐々に悪化しているように感じる場合は、一度専門家である医師の診察を受けることをお勧めします。
長引く痛みは、慢性化する前に原因を特定し、適切な対応を始めることが重要です。
市販の湿布薬や鎮痛薬で改善しない
腰痛を感じたとき、まずは市販の湿布薬や飲み薬で対処する方も多いでしょう。これらのセルフケアで痛みが和らぐのであれば、しばらく様子を見ても良いかもしれません。
しかし、数日間試しても効果が感じられない、薬を使っている間は良いがやめるとすぐに痛みが戻る、といった場合は、痛みの原因がセルフケアで対応できる範囲を超えている可能性があります。
朝起き上がるときに特に痛みが強い
「朝、ベッドから起き上がる一連の動作が一番つらい」という方は少なくありません。
起床時の強い痛みは、睡眠中の姿勢や寝具の問題も考えられますが、腰椎の変形や炎症が原因となっていることもあります。
毎日繰り返される朝の苦痛は、一日のはじまりを憂鬱にさせます。原因を調べることで、痛みを和らげるヒントが見つかるかもしれません。
仕事や家事など特定の動作で痛みが悪化する
デスクワークで座り続けていると痛む、立ち仕事で夕方になるとつらくなる、掃除機をかけるときや子供を抱き上げるときに痛みが走るなど、特定の動作や状況で痛みが強くなる場合も受診の目安です。
日常生活や仕事に支障が出ている状態を放置すると、無意識に痛みをかばう動作をとることで、他の部位に負担がかかり、新たな不調を招くこともあります。
腰痛の期間による分類
| 分類 | 期間 | 特徴 |
|---|---|---|
| 急性腰痛 | 発症から4週間未満 | いわゆる「ぎっくり腰」など。多くは自然に改善する。 |
| 亜急性腰痛 | 発症から4週間以上3ヶ月未満 | 痛みが長引いている状態。慢性化への移行期。 |
| 慢性腰痛 | 発症から3ヶ月以上 | 痛みが継続している状態。多角的な対応が必要になる。 |
整形外科での腰痛診断|問診で医師に伝えるべきこと
整形外科を受診すると、まず医師による問診が行われます。
正確な診断を下すためには、患者さんから得られる情報が非常に重要です。ご自身の症状を的確に、そして具体的に伝えることで、その後の診察や検査がスムーズに進みます。
ここでは、問診でよく聞かれる項目や、事前に整理しておくと良いポイントを解説します。
痛みの性質を具体的に伝える
「腰が痛い」という訴えだけでは、医師は原因を絞り込むことが困難です。痛みの性質を、ご自身の感覚で構わないので具体的に表現してみましょう。
「ズキズキと脈打つように痛い」「電気が走るようにピリッと痛む」「ジンジンとしびれるような痛み」「重だるい感じがする」など、オノマトペ(擬音語・擬態語)を使うと伝わりやすいです。
また、痛みの範囲も「腰のこの辺りがピンポイントで痛い」「お尻から足にかけて痛みが広がっている」のように、指で示しながら説明すると良いでしょう。
いつから、どのようなきっかけで痛み始めたか
痛みが始まった時期と、そのきっかけを思い出してみましょう。
「昨日の朝、重いものを持ち上げたときから急に痛くなった」「1ヶ月くらい前から、はっきりした原因はないが徐々に痛くなってきた」など、具体的な情報が診断の手がかりになります。
もし、過去にも同じような腰痛を繰り返している場合は、その頻度や状況も伝えると、より多くの情報を提供できます。
痛みが楽になる姿勢や動作、悪化する状況
どのようなときに痛みが変化するかも重要な情報です。
「座っていると痛いが、歩くと楽になる」「前かがみになると痛みが強まる」「お風呂で温まると少し和らぐ」など、日常生活の中での変化を医師に伝えてください。
これらの情報は、痛みの原因がどこにあるのか(筋肉、関節、神経など)を推測する上で役立ちます。
例えば、腰部脊柱管狭窄症では、歩くと痛みが増し、少し休むと楽になる「間欠性跛行(かんけつせいはこう)」という特徴的な症状が見られます。
これまでの病歴や現在服用中の薬
腰痛とは直接関係ないように思えることでも、診断や治療方針を決める上で重要な情報となる場合があります。
過去にかかった大きな病気や手術の経験、現在治療中の病気(高血圧、糖尿病、骨粗しょう症など)は必ず伝えましょう。
また、現在服用している薬(他の病院から処方された薬、市販薬、サプリメントなど)があれば、お薬手帳を持参すると正確に情報を伝えることができます。
医師に伝えるべき腰痛の情報のまとめ
| 項目 | 伝える内容の例 |
|---|---|
| 痛みの性質・場所 | ズキズキする、しびれる、重だるい。腰の中心、お尻、足など。 |
| 発症の時期・きっかけ | いつから痛むか。重い物を持ち上げた、転倒した、など。 |
| 痛みが変化する状況 | 楽になる姿勢(座る、立つ)、悪化する動作(前屈、歩行)。 |
| 既往歴・内服薬 | 過去の病気や手術。現在服用中のすべての薬。 |
身体診察でわかること|医師が行う基本的な確認
問診で詳しくお話を聞いた後は、医師が患者さんの体に直接触れたり、動かしたりして状態を確認する「身体診察」を行います。
この診察は、レントゲンなどの画像検査ではわからない情報を得るためにとても重要です。痛みの原因となっている場所や神経の状態をある程度推測することができます。
姿勢や歩き方の確認
診察室に入るところから、医師は患者さんの様子を観察しています。
無意識に腰をかばうような歩き方をしていないか、体が左右どちらかに傾いていないか、背骨の自然なカーブが失われていないかなどを確認します。
これらの視覚的な情報は、痛みの原因や体の歪みを把握するための第一歩となります。
痛む場所の圧痛や熱感の有無
医師が腰や背中、お尻などを直接触診し、押してみて特に痛みが強く出る場所(圧痛点)を探します。圧痛の場所から、どの筋肉や関節、骨に問題があるのかを推測します。
また、患部が熱を持っていないか(熱感)、腫れていないかなども確認し、炎症の有無を判断します。
関節の動く範囲の測定
患者さんに、体を前に倒したり(前屈)、後ろに反らしたり(後屈)、左右にひねったり(回旋)してもらい、腰椎や股関節がどのくらい動くかを確認します。
これを関節可動域の評価といいます。特定の動きで痛みが出たり、動きが制限されたりする場合、その情報が診断の大きな手がかりとなります。
例えば、前屈で痛みが強まる場合は椎間板ヘルニア、後屈で強まる場合は脊柱管狭窄症や椎間関節障害などを疑います。
神経学的検査
腰痛の原因として神経の圧迫が疑われる場合、神経学的検査を行います。
これには、ハンマーのような道具で膝などを軽く叩いて反射を見る腱反射テストや、感覚が鈍くなっていないかを調べる知覚検査、特定の筋肉が弱っていないかを確認する筋力テストなどがあります。
また、仰向けに寝て、膝を伸ばしたまま足をゆっくりと持ち上げていくSLRテスト(下肢伸展挙上試験)は、坐骨神経の圧迫を調べる代表的な検査です。
主な神経学的検査の種類と目的
| 検査名 | 方法 | 目的 |
|---|---|---|
| SLRテスト | 仰向けで膝を伸ばしたまま足を上げる | 坐骨神経の圧迫(椎間板ヘルニアなど)を調べる |
| 腱反射テスト | 打腱器で膝蓋腱などを叩く | 神経の伝達に異常がないかを調べる |
| 徒手筋力テスト | 足首や足の指などに抵抗をかけて動かす | 特定の神経が支配する筋肉の力が弱っていないかを調べる |
腰痛の原因を特定する画像検査の種類と特徴
問診や身体診察で得られた情報から、医師が「より詳しく腰の状態を調べる必要がある」と判断した場合に、画像検査を行います。
画像検査にはいくつかの種類があり、それぞれ見えるものや目的が異なります。ここでは、整形外科で腰痛の診断によく用いられる代表的な画像検査について、その特徴を解説します。
レントゲン(X線)検査
レントゲン検査は、放射線の一種であるX線を体に照射し、体を通り抜けたX線の量の差を画像にする検査です。
骨のような硬い組織はX線を通しにくいため白く写り、逆に筋肉や脂肪などの軟部組織はX線を通しやすいため黒く写ります。
レントゲン検査でわかること
レントゲン検査の主な目的は、骨の状態を確認することです。
具体的には、腰椎の骨折、脱臼、骨の変形(変形性脊椎症)、腰椎の並び方の異常(腰椎すべり症、側弯症)、骨がもろくなっていないか(骨粗しょう症の評価)、また、まれに骨にできる腫瘍などを確認することができます。
多くの整形外科で最初に行われる基本的な画像検査です。
レントゲン検査の限界
レントゲンは骨の異常を描出することに優れていますが、神経や椎間板、筋肉、靭帯といった軟部組織はほとんど写りません。
そのため、腰椎椎間板ヘルニアや腰部脊柱管狭窄症のように、神経や椎間板が主な原因である病気の確定診断はレントゲンだけでは困難です。
レントゲンで異常が見つからなくても、痛みの原因が隠れていることは少なくありません。
MRI検査
MRI検査は、強力な磁石と電波を使って体内の状態を画像にする検査です。放射線を使用しないため、被ばくの心配がありません。
体の断面をさまざまな角度から撮影することができ、特に軟部組織の描出に優れています。
MRI検査でわかること
レントゲンでは見えない椎間板、神経、脊髄、筋肉、靭帯などの状態を鮮明に映し出すことができます。
椎間板が飛び出して神経を圧迫している様子(腰椎椎間板ヘルニア)や、神経の通り道である脊柱管が狭くなっている状態(腰部脊柱管狭窄症)を詳しく評価できます。
また、脊椎の感染症や腫瘍の診断においても非常に有用です。
MRI検査が必要になる場合
足のしびれや筋力低下といった神経症状が強い場合、レントゲンで異常がないにもかかわらず痛みが長引く場合、あるいは感染症や腫瘍などが疑われる場合にMRI検査を検討します。
腰痛の原因を特定するための、非常に重要な検査と言えます。
CT検査
CT検査は、レントゲンと同じX線を使いながら、体を輪切りにしたような断層写真を撮影する検査です。
体を360度方向から連続的に撮影し、そのデータをコンピュータで処理することで、体の内部をより詳細に立体的に見ることができます。
CT検査でわかること
CT検査は、特に骨の細かい構造を観察するのに優れています。レントゲンでは分かりにくい、複雑な骨折や骨の変形、骨にできた腫瘍などを詳しく評価するのに役立ちます。
また、椎間板ヘルニアや脊柱管狭窄症の診断にも用いられますが、神経そのものの描出能はMRIに劣ります。
レントゲンやMRIとの違い
CTはレントゲンよりも骨の情報をはるかに詳しく得ることができ、MRIよりも検査時間が短いという利点があります。
一方で、軟部組織の描出能力はMRIの方が高く、放射線被ばくがあるという点がMRIとの違いです。それぞれの検査の長所と短所を考慮し、医師が目的に応じて使い分けます。
画像検査の比較
| 検査種類 | 得意なこと | 不得意なこと |
|---|---|---|
| レントゲン | 骨全体の構造、骨折、変形の把握 | 神経、椎間板、筋肉などの軟部組織の描出 |
| MRI | 神経、椎間板、筋肉などの軟部組織の描出 | 骨の微細な構造の評価、検査時間が長い |
| CT | 骨の微細な構造、複雑な骨折の評価 | 神経そのものの描出、放射線被ばくがある |
その他の検査|血液検査や骨密度検査
腰痛の原因は、腰椎やその周辺の組織の問題だけとは限りません。
画像検査だけでは原因が特定できない場合や、全身性の病気が疑われる場合には、診断の補助として、あるいは別の角度から原因を探るために、追加で他の検査を行うことがあります。
ここでは、腰痛の診断で用いられることがあるその他の検査について解説します。
感染症や炎症を調べる血液検査
腰痛の原因として、細菌などが背骨に感染して炎症を起こす「化膿性脊椎炎」や、関節リウマチなどの膠原病、あるいは内臓の病気などが疑われる場合に血液検査を行います。
血液検査では、体内に炎症反応があるかを示すCRP(C反応性タンパク)や赤沈(血沈)、白血球数などを調べます。
これらの数値が高い場合、体内のどこかで炎症や感染が起きている可能性を示唆します。
- 白血球数
- CRP(C反応性タンパク)
- 赤沈(ESR)
骨粗しょう症を評価する骨密度検査
特に高齢の女性や、些細なきっかけで腰痛が生じた場合に、骨粗しょう症が背景にないかを調べるために骨密度検査を行うことがあります。
骨粗しょう症は、骨がもろくなり、軽い衝撃でも骨折しやすくなる病気です。
背骨が体の重みで潰れてしまう「圧迫骨折」は、骨粗しょう症による代表的な骨折であり、強い腰痛の原因となります。
検査は、DXA(デキサ)法と呼ばれる微量のX線を用いて、腰椎や大腿骨の骨密度を正確に測定する方法が標準的です。
血液検査で確認する主な炎症項目
| 検査項目 | 基準値の目安 | 項目が示すこと |
|---|---|---|
| 白血球数 (WBC) | 3,300~8,600 /μL | 細菌感染などで増加する。体の防御反応を示す。 |
| CRP | 0.30 mg/dL 以下 | 体内で炎症が起きると急激に増加するタンパク質。 |
| 赤沈 (ESR) | 男性: 10mm/時 以下 女性: 15mm/時 以下 | 炎症や組織破壊があると亢進する。慢性的な炎症の指標。 |
神経の伝わる速さを調べる筋電図検査
足のしびれや筋力低下の原因が、腰の神経にあるのか、あるいは足先の末梢神経にあるのかを判断するのが難しい場合に、筋電図検査を行うことがあります。
この検査では、神経に電気的な刺激を与え、その信号が筋肉に伝わる速さや強さを測定します。
これにより、神経がどの部位で、どの程度障害されているのかを客観的に評価することができます。
診断結果の説明と今後の見通し
問診、身体診察、そして必要な各種検査が終わると、医師はそれらの結果を総合的に判断し、診断を確定します。そして、患者さんに対して診断結果と今後の治療方針などについて説明します。
ご自身の腰の状態を正しく理解し、今後の対応について納得することが、腰痛と向き合っていく上でとても大切です。
診断名の告知
まず、一連の診察・検査から導き出された診断名が伝えられます。「腰椎椎間板ヘルニア」や「腰部脊柱管狭窄症」、「変形性脊椎症」など、具体的な病名が告げられます。
場合によっては、画像検査などではっきりとした原因が見つからない「非特異的腰痛」と診断されることもあります。
これは、日本の腰痛診療ガイドラインでも、腰痛の約85%を占めるとされています。
病状と原因についての説明
次に、医師はレントゲンやMRIなどの画像を見せながら、なぜ痛みやしびれが出ているのか、体の内部で何が起きているのかを具体的に説明します。
例えば、「この部分で椎間板が飛び出して、足へ行く神経に触っていますね」といったように、専門的な内容を分かりやすく解説します。
疑問に思った点があれば、遠慮せずに質問しましょう。
今後の治療方針の提案
診断と病状の説明に基づき、今後の治療方針が提案されます。
治療には、薬物療法(飲み薬、湿布薬)、リハビリテーション(運動療法、物理療法)、神経ブロック注射など、さまざまな選択肢があります。
医師は、患者さんの症状の程度やライフスタイルを考慮して、最も適していると考えられる治療法をいくつか提示し、それぞれの利点や注意点について説明します。
最終的な治療法は、医師と患者さんが相談して決定します。
日常生活での注意点
治療と並行して、日常生活で気をつけるべき点についても指導があります。
腰に負担のかからない姿勢や動作の工夫、推奨される運動や避けるべき運動、体重管理の重要性など、内容は多岐にわたります。
これらのアドバイスを実践することが、症状の改善や再発予防につながります。
代表的な腰痛の原因となる疾患
| 疾患名 | 主な原因 | 特徴的な症状 |
|---|---|---|
| 腰椎椎間板ヘルニア | 椎間板が後方に突出し神経を圧迫 | 急性の激しい腰痛、お尻から足にかけての痛み・しびれ |
| 腰部脊柱管狭窄症 | 加齢などにより神経の通り道が狭くなる | 歩行で悪化する足の痛み・しびれ(間欠性跛行) |
| 変形性脊椎症 | 加齢による腰椎の変形 | 動作開始時の痛み、慢性的な鈍い痛み |
腰痛の診断と検査に関するよくある質問
最後に、腰痛で整形外科を受診する際に多くの方が抱く疑問や不安について、質問と回答の形式でまとめました。
受診前の不安を少しでも解消し、安心して医師の診察を受けるための参考にしてください。
レントゲン検査で異常なしと言われたのに痛いのはなぜですか?
レントゲン検査は骨の状態を見るのに優れた検査ですが、神経や椎間板、筋肉といった軟部組織は写りません。
そのため、痛みの原因が椎間板ヘルニアや筋肉の炎症などにある場合、レントゲンでは「異常なし」と診断されることがあります。
痛みが続く場合は、MRI検査など、さらに詳しい検査で原因を調べることがあります。また、明らかな原因が見つからない「非特異的腰痛」である可能性も考えられます。
MRI検査はどのくらいの時間がかかりますか?また、費用はどのくらいですか?
MRI検査にかかる時間は、撮影する範囲や目的によって異なりますが、一般的には20分から40分程度です。
検査中は大きな音がする狭いトンネル状の装置の中で、体を動かさずにじっとしている必要があります。
費用は、保険適用の3割負担の場合で、おおよそ7,000円から10,000円程度が目安となりますが、医療機関や使用する薬剤によって変動します。詳しくは検査を受ける医療機関にご確認ください。
診断がつくまで何回くらい通院が必要ですか?
症状や検査内容によって異なります。問診と身体診察、レントゲン検査で診断がつき、治療方針が決まる場合は、初診日に診断がつくこともあります。
一方で、MRI検査などが必要になったり、治療の効果を見ながら慎重に診断を進めたりする場合は、診断確定までに数回の通院が必要になることもあります。
焦らず、医師の指示に従って通院を続けることが大切です。
整形外科以外に、何科を受診すればよいか迷います
腰痛の多くは、骨や関節、筋肉、神経などが原因であるため、まずは整形外科を受診するのが一般的です。
ただし、腹痛や血尿など内臓の症状を伴う場合や、帯状疱疹のような皮膚の異常が見られる場合は、内科や泌尿器科、皮膚科などが適切な場合もあります。
判断に迷う場合は、まずはかかりつけ医に相談するか、整形外科を受診して専門的な判断を仰ぐのが良いでしょう。
受診科目の目安
| 主な症状 | 推奨される診療科 | 考えられる原因 |
|---|---|---|
| 腰の痛み、足のしびれ、動きの制限 | 整形外科 | 骨、関節、神経、筋肉の問題 |
| 腰痛に加え腹痛や血尿がある | 内科、泌尿器科 | 尿路結石、腎臓の病気など |
| 腰痛に加え皮膚に発疹がある | 皮膚科 | 帯状疱疹など |
以上
参考文献
VERHAGEN, Arianne P., et al. Red flags presented in current low back pain guidelines: a review. European spine journal, 2016, 25.9: 2788-2802.
PARREIRA, Patricia CS, et al. Evaluation of guideline-endorsed red flags to screen for fracture in patients presenting with low back pain. British Journal of Sports Medicine, 2019, 53.10: 648-654.
COOK, Chad E.; GEORGE, Steven Z.; REIMAN, Michael P. Red flag screening for low back pain: nothing to see here, move along: a narrative review. British journal of sports medicine, 2018, 52.8: 493-496.
STORARI, Lorenzo, et al. Standardized Definition of Red Flags in Musculoskeletal Care: A Comprehensive Review of Clinical Practice Guidelines. Medicina, 2025, 61.6: 1002.
ENTHOVEN, Wendy TM, et al. Prevalence and “red flags” regarding specified causes of back pain in older adults presenting in general practice. Physical therapy, 2016, 96.3: 305-312.
LADEIRA, Carlos E. Physical therapy clinical specialization and management of red and yellow flags in patients with low back pain in the United States. Journal of Manual & Manipulative Therapy, 2018, 26.2: 66-77.
HAN, Christopher S., et al. Red flags to screen for vertebral fracture in people presenting with low back pain. Cochrane Database of Systematic Reviews, 2023, 8.
DEPALMA, Michael G. Red flags of low back pain. Jaapa, 2020, 33.8: 8-11.
STEARNS, Zachary R., et al. Screening for yellow flags in orthopaedic physical therapy: a clinical framework. journal of orthopaedic & sports physical therapy, 2021, 51.9: 459-469.
FINUCANE, Laura M., et al. International framework for red flags for potential serious spinal pathologies. journal of orthopaedic & sports physical therapy, 2020, 50.7: 350-372.
Symptoms 症状から探す