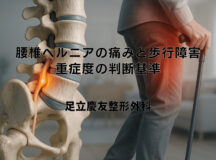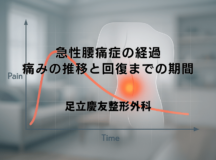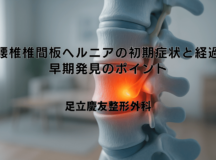膝が逆に曲がる症状の原因と対処方法
立ったときや歩いているときに、自分の膝が本来曲がるべき方向とは逆に、少し反っているように感じたことはありませんか。
「膝が逆に曲がる」というこの症状は、多くの方が不安を覚えるものです。
この状態は「反張膝(はんちょうひざ)」と呼ばれ、見た目の問題だけでなく、膝の痛みや不安定感、さらには将来的な関節の悩みにつながる可能性も秘めています。
なぜこのような状態になるのでしょうか。
この記事では、膝が逆に曲がる症状の基本的な知識から、考えられる主な原因、ご自身でできるチェック方法、そして医療機関での診断や具体的な対処法まで、網羅的に解説します。
目次
「膝が逆に曲がる」とは?反張膝の基礎知識
膝が逆に曲がるという現象について、まずはその正体と基本的な情報を理解することが大切です。
ここでは、専門的に「反張膝」と呼ばれるこの状態がどのようなものか、なぜ起こるのか、そして見た目以外にどのような問題があるのかを詳しく見ていきます。
反張膝の定義
反張膝とは、立った状態で膝を伸ばした際に、膝関節がまっすぐ(0度)以上に反ってしまう状態を指します。
正常な膝関節は、伸ばしても約0度で伸展が止まりますが、反張膝の場合は5度、10度と過剰に伸展します。この過伸展の状態が、一般的に「膝が逆に曲がる」と表現されます。
軽度の場合は自覚がないことも少なくありませんが、角度が大きくなるにつれて、見た目にも膝が「くの字」に反っているのがわかるようになります。
なぜ膝は逆に曲がってしまうのか
膝関節は、太ももの骨(大腿骨)とすねの骨(脛骨)で構成され、その周りを靭帯や筋肉が覆うことで安定性を保っています。
膝が逆に曲がるのは、これらの構造的な安定性が何らかの理由で損なわれるために起こります。
具体的には、関節を支える靭帯が生まれつき緩い、膝を支える筋肉のバランスが悪い、あるいは過去の怪我で靭帯が損傷している、といった要因が考えられます。
これらの要因により、膝を伸ばした際にストッパーが効かず、可動域を超えて伸びすぎてしまうのです。
見た目以外の問題点
反張膝は単に見た目が気になるというだけでなく、膝関節そのものに大きな負担をかけ続ける状態です。
膝が逆に曲がることで、関節の前方にある軟骨や半月板に過剰な圧力がかかり、摩耗や損傷を引き起こす可能性があります。
また、関節の後方の組織は常に引き伸ばされる状態になるため、痛みや炎症の原因にもなります。
長期間この状態が続くと、膝の不安定感や痛みが慢性化し、日常生活に支障をきたすこともあります。
反張膝に伴う主な機能的問題
| 問題点 | 内容 | 具体的な影響 |
|---|---|---|
| 関節への過剰な負荷 | 膝を伸ばし切るたびに、関節面に衝撃がかかる。 | 軟骨のすり減り、半月板損傷のリスク増加。 |
| 靭帯への伸長ストレス | 関節後方の靭帯や関節包が常に伸ばされる。 | 膝の不安定感、靭帯の緩みがさらに進行する可能性。 |
| 筋肉の非効率な使用 | 膝をロックして立つため、筋肉を正しく使えない。 | 筋力低下、疲労感、パフォーマンスの低下。 |
男女差や年齢との関連
反張膝は、一般的に女性に多く見られます。これは、女性ホルモンの影響などから、男性に比べて関節や靭帯が柔らかい傾向にあるためです。
また、バレエや新体操など、関節の柔軟性を求められる活動をしている女性にも多く見られます。
年齢との関連では、子供のうちは関節がまだ発達途中であり、一時的に反張膝傾向が見られることもありますが、多くは成長とともに改善します。
しかし、成人以降に症状が続く場合や、高齢になってから膝の変形と共に現れる場合は、注意が必要です。
膝が逆に曲がる主な原因
膝が逆に曲がる反張膝は、単一の原因で起こるわけではなく、複数の要因が絡み合っている場合が少なくありません。
ここでは、その主な原因を「先天的な要因」と「後天的な要因」に分けて、それぞれ詳しく解説していきます。ご自身の状態がどれに当てはまるか考える際の参考にしてください。
先天的な関節の緩さ
生まれつき関節が柔らかく、可動域が広い体質の方がいます。これは「全身性関節弛緩症」とも呼ばれ、膝関節だけでなく、肘や指など他の関節も過剰に曲がりやすい特徴があります。
この体質の場合、膝を支える靭帯そのものが伸びやすいため、膝をまっすぐにしようとすると、意図せずして逆に曲がってしまいます。
これは病気というよりは体質的なもので、特に痛みなどがなければ問題視されないことも多いですが、怪我をしやすい傾向があるため注意が必要です。
関節弛緩性の簡易チェック
| チェック項目 | 基準 | 備考 |
|---|---|---|
| 親指 | 手首を曲げた状態で、親指が前腕につくか。 | 左右それぞれで確認します。 |
| 小指 | 手の甲側へ小指が90度以上反るか。 | 過度な力を加えないでください。 |
| 肘 | 腕を伸ばしたときに10度以上反るか。 | 反張肘も同様の原理です。 |
筋肉のアンバランス
膝関節の安定には、太ももの前側にある「大腿四頭筋」と、裏側にある「ハムストリングス」の筋力バランスが非常に重要です。
大腿四頭筋は膝を伸ばす働きを、ハムストリングスは膝を曲げる働きと、伸びすぎないように制御する働きを担っています。
しかし、何らかの理由で大腿四頭筋が過剰に強く、ハムストリングスが弱い状態になると、膝を伸ばす力ばかりが優位になり、膝が逆に曲がりやすくなります。
このアンバランスは、特定のスポーツや日常生活の癖によって生じることが多いです。
過去の怪我や靭帯の損傷
スポーツや事故などで膝の靭帯を損傷した経験がある場合、それが原因で反張膝になることがあります。
特に、膝の前後方向の安定性を司る「前十字靭帯」や「後十字靭帯」の損傷は、膝の過伸展に直接つながります。
靭帯が機能不全に陥ると、膝関節のストッパーが効かなくなり、グラグラと不安定な状態になります。
この不安定性を補うために、無意識に膝を反らせてロックするように立つ癖がつき、反張膝が助長されるケースもあります。
特定のスポーツや生活習慣
特定の動作を繰り返すスポーツも、反張膝の原因となり得ます。
例えば、バレエ、新体操、フィギュアスケートなどでは、美しい姿勢を保つために膝を最大限に伸ばす動きが求められ、結果として反張膝になりやすい傾向があります。
また、日常生活においても、かかとの高いヒールをよく履く習慣は、体の重心が前に移動し、バランスを取るために膝が反りやすくなるため、注意が必要です。
長時間立ち仕事をする際に、無意識に膝をロックして体重を支える癖も、反張膝を悪化させる一因です。
膝が逆に曲がることで起こりうる症状とリスク
膝が逆に曲がる状態は、単に見た目の問題だけではありません。
この状態を放置すると、膝関節やその周辺組織にさまざまな悪影響を及ぼし、痛みや機能障害、さらには将来的な関節の変形につながるリスクを高めます。
ここでは、反張膝が引き起こす可能性のある具体的な症状とリスクについて解説します。
膝の痛みや不安定感
反張膝の最も一般的な症状の一つが、膝の痛みです。膝が逆に曲がるたびに、関節の後方にある靭帯や関節包、筋肉が引き伸ばされ、炎症や微小な損傷が生じることがあります。
これにより、膝の裏側や側面に鈍い痛みを感じるようになります。
また、関節を支える靭帯が緩んでいるため、歩行中や運動中に膝がガクッと崩れるような「膝崩れ」と呼ばれる不安定感を覚えることもあり、日常生活での転倒リスクにもつながります。
膝関節や軟骨への負担
膝を過度に伸展させると、大腿骨と脛骨の間のクッションの役割を果たす「関節軟骨」や「半月板」に、異常な圧力がかかります。特に、関節の前方部分に負荷が集中しやすくなります。
この状態が長期間続くと、軟骨がすり減ったり、半月板が損傷したりする原因となります。軟骨や半月板は一度損傷すると再生が難しいため、将来的な膝の機能低下に直結する深刻な問題です。
反張膝による膝関節への主な負荷
| 影響を受ける部位 | 負荷の種類 | 結果として起こりうること |
|---|---|---|
| 関節軟骨(前方) | 過剰な圧迫、衝撃 | 軟骨の摩耗、すり減り |
| 半月板(前方) | 挟み込み、圧迫 | 半月板損傷、断裂 |
| 後方関節包・靭帯 | 過剰な伸長 | 組織の微小断裂、緩み、痛み |
将来的な変形性膝関節症への影響
反張膝は、将来的に「変形性膝関節症」を発症するリスクを高める要因の一つと考えられています。
変形性膝関節症は、加齢とともに関節軟骨がすり減り、関節の変形や痛みを引き起こす病気です。
反張膝によって長年にわたり関節軟骨への異常な負荷が蓄積されることは、この病気の進行を早める可能性があります。
若いうちは症状がなくても、中年以降に膝の痛みが現れ、検査をしてみると既に関節の変形が始まっていた、というケースも少なくありません。
他の部位への影響(腰痛や足首の痛みなど)
人間の体は、全ての部位が連動してバランスを取っています。膝が逆に曲がるという異常なアライメント(配列)は、膝だけの問題に留まりません。
膝を反らせて立つ姿勢は、骨盤を前傾させ、結果として反り腰を助長し、腰痛の原因となることがあります。
また、地面からの衝撃を膝でうまく吸収できないため、その負担が足首や股関節にかかり、それらの部位に痛みや不調を引き起こすこともあります。
このように、膝の問題が全身のバランスを崩すきっかけになるのです。
自分でできる症状のチェック方法
ご自身の膝が逆に曲がっているかどうか、またどの程度なのかを客観的に把握することは、適切な対処への第一歩です。
ここでは、特別な器具を使わずに自宅で簡単にできるセルフチェックの方法を紹介します。ただし、痛みがある場合は無理に行わないでください。
見た目での簡単な確認
最も簡単な方法は、鏡の前に横向きに立ち、ご自身の膝の状態を観察することです。
リラックスして自然に立ったときに、太もものラインとすねのラインが一直線にならず、膝の部分が後ろに「くの字」に反っているように見える場合、反張膝の可能性があります。
ズボンの上からでも確認できますが、より正確に見るためには、脚のラインがわかりやすい服装で行うと良いでしょう。
可動域のセルフチェック
床に仰向けに寝て、片方の足のかかとの下に丸めたタオルやクッションを置きます。この状態で、膝の力を完全に抜いてください。
このとき、膝の裏側が床から大きく浮き上がり、手のひらが簡単に入る、あるいは拳が入るほどの隙間ができる場合、膝が過伸展している可能性が高いです。
正常な場合は、膝裏は床につくか、わずかに浮く程度です。
反張膝のセルフチェックリスト
| チェック項目 | 確認方法 | 反張膝の可能性がある状態 |
|---|---|---|
| 立位での見た目 | 鏡の前に横向きで立つ | 膝が後ろに「くの字」に反っている |
| 仰向けでの膝裏の隙間 | かかとの下にタオルを敷いて仰向けになる | 膝裏と床の間に手のひら以上の隙間がある |
| 歩行時の感覚 | 普段通りに歩く | 膝がカクンと後ろに入る感覚がある |
痛みや違和感の確認ポイント
膝が逆に曲がること自体に加えて、それに伴う症状の有無も重要なチェックポイントです。以下の点について、ご自身の状態を確認してみてください。
- 膝の裏側や側面に慢性的な鈍い痛みはないか
- 長時間立っていたり、歩いたりした後に膝が痛まないか
- 階段の上り下りや、坂道で膝に不安定感や痛みを感じるか
- 運動中に膝がガクッと崩れるような感覚(膝崩れ)はないか
これらの症状が一つでも当てはまる場合は、膝に何らかの問題が生じているサインかもしれません。
チェック時の注意点
セルフチェックはあくまで簡易的な目安です。痛みを感じる場合は、無理に膝を伸ばしたり、曲げたりしないでください。症状を悪化させる可能性があります。
また、チェックの結果だけで自己判断せず、気になる点があれば専門の医療機関に相談することが重要です。
特に、急な強い痛みや腫れ、明らかな膝崩れが起きた場合は、速やかに整形外科を受診してください。
医療機関での診断と検査
セルフチェックで反張膝の可能性が考えられたり、膝に痛みや不安定感などの症状があったりする場合には、整形外科を受診して専門家による正確な診断を受けることが大切です。
医療機関では、症状の原因や程度を特定するために、様々な診察や検査を行います。
整形外科での問診と視診・触診
診察では、まず医師による問診が行われます。
いつから症状が気になるようになったか、どのような時に痛みや不安定感を感じるか、過去の怪我の有無、スポーツ歴や生活習慣などについて詳しく伝えます。
次に、視診で立った状態や歩行時の膝のアライメントを確認し、触診で膝のどの部分に痛みがあるか、関節の緩みや不安定性がないかを慎重に評価します。
この問診と身体所見から、おおよその状態を把握します。
レントゲン(X線)検査
レントゲン検査は、骨の状態を確認するための基本的な画像検査です。
反張膝の診断においては、立った状態で撮影することで、膝関節がどの程度逆に曲がっているかを客観的な角度として測定できます。
また、骨の変形や関節の隙間の狭小化など、変形性膝関節症の進行度合いを評価するためにも重要です。骨折や骨の腫瘍など、他の病気が隠れていないかを確認する目的でも行います。
MRI検査でわかること
MRI検査は、レントゲンでは写らない軟部組織(靭帯、半月板、軟骨、筋肉など)の状態を詳しく観察できる検査です。
反張膝の原因が、前十字靭帯や後十字靭帯の損傷にあると疑われる場合や、半月板損傷、軟骨のすり減りが疑われる場合に特に有効です。
治療方針を決定する上で、これらの軟部組織の状態を正確に把握することは非常に重要です。この検査により、痛みの原因をより詳細に特定できます。
主な画像検査とその目的
| 検査方法 | 主な観察対象 | この検査でわかること |
|---|---|---|
| レントゲン検査 | 骨 | 反張膝の角度、骨の変形、関節の隙間の状態 |
| MRI検査 | 靭帯、半月板、軟骨など | 靭帯損傷の有無と程度、半月板や軟骨の状態 |
| 超音波(エコー)検査 | 靭帯、筋肉、水腫など | 関節内の水分の貯留、特定の靭帯や筋肉の状態 |
必要に応じて行うその他の検査
上記の検査に加えて、症状や状態に応じてその他の検査を行うこともあります。
例えば、関節に水が溜まっている(関節水腫)場合には、注射器で関節液を抜いてその成分を調べる関節穿刺を行うことがあります。
また、より詳細なアライメント評価のために、下肢全長を撮影する特殊なレントゲン検査を行うこともあります。
これらの検査を組み合わせることで、総合的に膝の状態を診断し、一人ひとりに合った治療計画を立てていきます。
膝が逆に曲がる症状への対処法と治療
膝が逆に曲がる反張膝の診断がついた場合、その治療や対処は、症状の程度、原因、年齢、活動レベルなどを総合的に考慮して決定します。
多くの場合、すぐに手術が必要になることは稀で、膝への負担を減らし、筋力バランスを整える保存療法が中心となります。ここでは、主な対処法と治療について解説します。
保存療法が基本
反張膝の治療の基本は、手術を行わない「保存療法」です。保存療法の目的は、痛みをコントロールし、膝関節の安定性を高め、症状の進行を防ぐことにあります。
具体的には、後述する運動療法、装具療法、そして日常生活の指導などを組み合わせて行います。すぐに結果が出るものではなく、根気強く継続することが重要です。
痛みが強い場合には、一時的に消炎鎮痛剤の内服や外用薬(湿布など)、ヒアルロン酸注射などを行うこともあります。
保存療法の主な構成要素
| 治療法 | 目的 | 具体的な内容例 |
|---|---|---|
| 運動療法 | 筋力バランスの改善、安定性の向上 | ハムストリングス強化、体幹トレーニング |
| 装具療法 | 膝の過伸展抑制、アライメント補正 | サポーター、インソール(足底板) |
| 物理療法 | 痛みの緩和、血行促進 | 温熱療法、電気刺激療法 |
運動療法(リハビリテーション)
運動療法は保存療法の中心となるものです。理学療法士などの専門家の指導のもと、個々の状態に合わせたプログラムを実施します。
主な目的は、弱っているハムストリングス(太もも裏)や殿筋(お尻)の筋力を強化し、過剰に働いている大腿四頭筋(太もも前)の緊張を和らげることです。
これにより、筋肉のアンバランスを是正し、膝が逆に曲がらないように制御する能力を高めます。
また、体幹を鍛えることで、体全体の安定性を向上させ、膝への負担を軽減することも目指します。
装具療法(サポーターやインソール)
膝の過伸展を物理的に抑制するために、装具を使用することがあります。
膝の伸展角度を制限する機能がついたサポーターや硬性装具は、膝の安定性を高め、歩行時の不安感を軽減するのに役立ちます。
ただし、装具に頼りすぎると筋力が低下する可能性もあるため、運動療法と並行して、必要な場面で適切に使用することが大切です。
また、足部の崩れ(扁平足など)が膝のアライメントに影響している場合には、靴の中に入れるインソール(足底板)を作成し、足元からバランスを整えることも有効な手段です。
手術療法が必要な場合
保存療法を長期間続けても症状が改善しない場合や、靭帯の断裂が原因で膝の不安定性が非常に高く、日常生活やスポーツ活動に大きな支障が出ている場合には、手術療法を検討することがあります。
代表的な手術には、損傷した靭帯を再建する「靭帯再建術」があります。また、骨の変形が原因で反張膝が起きている場合には、骨の角度を矯正する「骨切り術」などが行われることもあります。
手術は体への負担も大きいため、その必要性については医師と十分に相談して決定します。
日常生活で気をつけるべきポイント
反張膝の症状を改善し、悪化を防ぐためには、医療機関での治療と並行して、日常生活でのセルフケアが非常に重要です。
無意識に行っている動作や習慣が、膝に負担をかけている可能性があります。ここでは、普段の生活の中で意識したいポイントをいくつか紹介します。
正しい立ち方と歩き方
反張膝の人は、無意識に膝をピンと伸ばしきって「ロック」した状態で立つ癖があります。これは一見楽なように感じますが、関節に直接体重がかかり、大きな負担となります。
立つときは、膝をほんの少しだけ曲げ、「膝で立つ」のではなく「太ももやお尻の筋肉で立つ」という意識を持つことが大切です。
歩くときも同様に、地面を蹴り出す際に膝を伸ばしきらないように注意し、足裏全体で着地するような歩き方を心がけましょう。
立ち方の意識改革
| 良くない立ち方(反張膝を助長) | 意識したい正しい立ち方 |
|---|---|
| 膝を完全に伸ばしきってロックする | 膝をほんの少し緩める(伸ばしきらない) |
| 体重を関節で支える | 太ももとお尻の筋肉で体を支える意識 |
| 重心がつま先や前方に偏る | 足裏全体に均等に体重を乗せる |
膝に負担をかけない動作
日常生活の中の何気ない動作でも、少しの工夫で膝への負担を減らすことができます。
- 床から物を拾うとき:膝を曲げ、腰を落として拾う(膝を伸ばしたまま前かがみにならない)
- 椅子からの立ち上がり:浅く腰掛け、片足を少し後ろに引いてから、テーブルなどに手をついて立つ
- 階段の上り下り:手すりを使い、一段ずつゆっくりと行う
これらの動作を意識するだけでも、膝の過伸展を防ぎ、関節を保護することにつながります。
靴選びの重要性
履いている靴は、膝のアライメントに大きな影響を与えます。
特に、かかとの高いヒールは、重心を前方に移動させ、バランスを取るために膝が反りやすくなるため、長時間の使用は避けるのが賢明です。
靴を選ぶ際は、かかとが安定し、クッション性が高く、足指が自由に動かせるものを選びましょう。足に合った靴は、地面からの衝撃を吸収し、膝への負担を軽減してくれます。
必要であれば、インソールを入れて調整することも有効です。
適切な運動習慣
膝に痛みがあるからといって、全く動かないのは逆効果です。筋力が低下し、さらに関節が不安定になる可能性があります。
ウォーキングや水泳、エアロバイクなど、膝への負担が少ない有酸素運動を無理のない範囲で続けることは、筋力の維持や体重コントロールに役立ち、症状の改善につながります。
ただし、運動の前後には必ずストレッチを行い、痛みを感じる場合はすぐに中止して専門家に相談してください。
膝が逆に曲がる症状に関するよくある質問
最後に、膝が逆に曲がる症状に関して、患者さんからよく寄せられる質問とその回答をまとめました。ご自身の疑問や不安を解消するための一助としてください。
子供の膝が逆に曲がるのは問題ないですか?
幼児期や学童期の子供は、骨格がまだ発達途中であり、関節が柔らかいため、ある程度の反張膝が見られることは珍しくありません。
多くの場合、成長とともに筋肉や靭帯がしっかりしてくると自然に改善していきます。
ただし、左右差が著しい場合、痛みを訴える場合、頻繁に転ぶなどの症状がある場合は、一度整形外科に相談することをお勧めします。
サポーターは常に着けていた方が良いですか?
サポーターは膝の安定性を高め、過伸展を防ぐ助けになりますが、常に装着していると、その支持機能に頼ってしまい、自らの筋力が低下してしまう可能性があります。
そのため、医師や理学療法士の指示に従い、特に負担のかかる動作をする時(長時間の歩行やスポーツなど)に限定して使用するのが一般的です。
就寝中や安静にしている時は外すようにしましょう。
改善までにどれくらいの期間がかかりますか?
改善にかかる期間は、症状の原因、重症度、年齢、そしてリハビリテーションへの取り組み方によって大きく異なります。
数ヶ月で症状が軽くなる方もいれば、年単位でのケアが必要な方もいます。特に、筋力バランスの改善や正しい体の使い方を習得するには、ある程度の時間が必要です。
焦らず、専門家の指導のもとで根気強く治療やセルフケアを続けることが重要です。
改善期間に影響する主な要因
- 症状の重症度(反張膝の角度)
- 痛みの有無と強さ
- 原因(先天性か後天性か)
- リハビリテーションの継続性
放置するとどうなりますか?
軽度で痛みのない反張膝であれば、必ずしも深刻な問題に発展するとは限りません。
しかし、膝に負担をかけ続けている状態であることに変わりはなく、放置することで将来的に様々なリスクが高まる可能性があります。
具体的には、慢性的な膝の痛み、半月板や軟骨の損傷、そして変形性膝関節症への移行などが考えられます。
特に痛みや不安定感などの自覚症状がある場合は、放置せずに早期に医療機関を受診し、適切な対処を開始することが、将来の膝の健康を守る上で非常に大切です。
参考文献
LOUDON, Janice K.; GOIST, Heather L.; LOUDON, Karen L. Genu recurvatum syndrome. Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy, 1998, 27.5: 361-367.
DEAN, Robert S., et al. Treatment for symptomatic genu recurvatum: a systematic review. Orthopaedic Journal of Sports Medicine, 2020, 8.8: 2325967120944113.
BLEYENHEUFT, Corinne, et al. Treatment of genu recurvatum in hemiparetic adult patients: a systematic literature review. Annals of physical and rehabilitation medicine, 2010, 53.3: 189-199.
TEODORESCU, Matei, et al. Approach to rehabilitation treatment of gait disorders in patients with genu recurvatum. Health, Sports & Rehabilitation Medicine, 2019, 20.2.
APPASAMY, Malathy, et al. Treatment strategies for genu recurvatum in adult patients with hemiparesis: a case series. PM&R, 2015, 7.2: 105-112.
KARIMI, Mohammad Taghi, et al. Different Types of Orthoses in the Management of Genu Recurvatum: What are the Best Choices?. Muscles, Ligaments & Tendons Journal (MLTJ), 2025, 15.2.
AGHAALIKHANI, Mahdi, et al. Progressive Late-Onset Genu Recurvatum Post-Total Knee Arthroplasty: Insights from a Spinal Stenosis-Related Case Series. Archives of Bone and Joint Surgery, 2024, 12.5: 337.
LIU, Kuan-Lin, et al. A Novel Surgical Technique for the First Case of Neglected Bilateral Severe Congenital Genu Recurvatum Combined with Bilateral Talipes Equinocavovarus. Medicina, 2025, 61.3: 543.
TEODORESCU, Matei, et al. Rehabilitation treatment of post-stroke spastic and non-spastic genu recurvatum. Health, Sports & Rehabilitation Medicine, 2010, 142.
SAHOO, Pabitra Kumar, et al. Outcomes of VY Quadricepsplasty for the Management of Genu Recurvatum Deformity in Congenital Dislocation Knee. Indian Journal of Physical Medicine & Rehabilitation, 2024, 34.2: 107-111.
Symptoms 症状から探す